
更新日:2024/08/06
総合福祉団体定期保険とは?加入目的やメリットも解説!
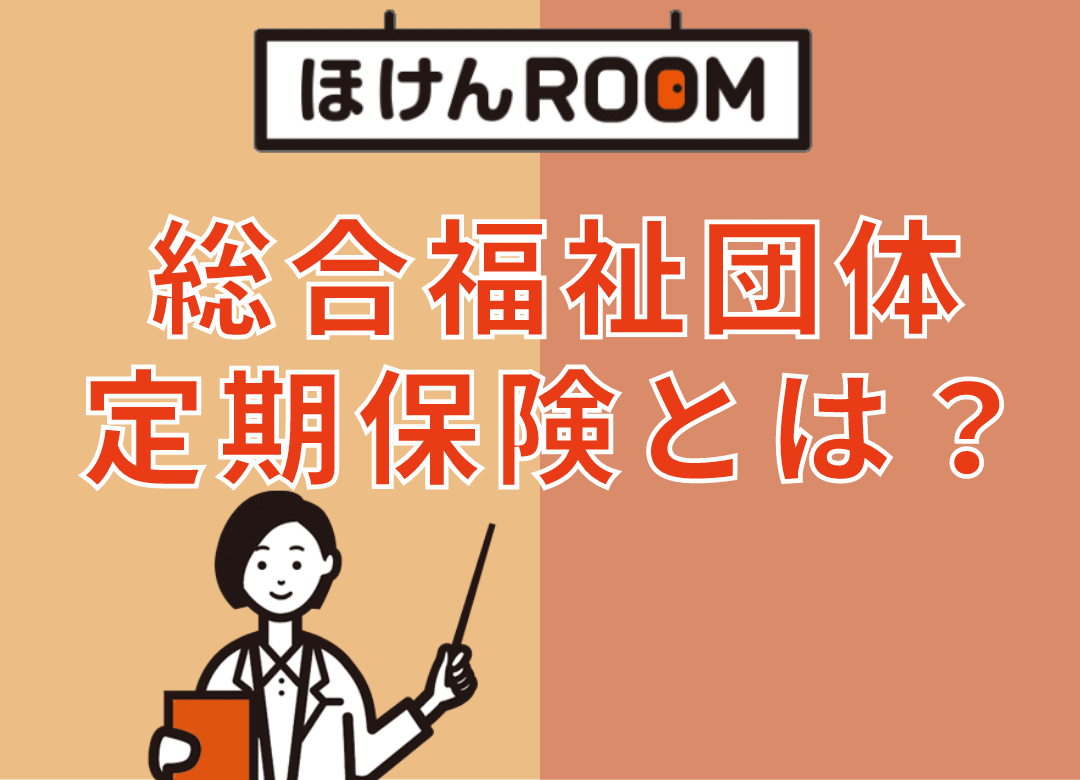
内容をまとめると
- 総合福祉団体定期保険は、従業員の福利厚生の一環として加入でき、「有配当」と「無配当」の2種類がある(前者は配当金がもらえるが保険料は割高となる)。
- 「ヒューマン・バリュー特約」で従業員死亡時の経済的損出もカバーできるうえ、対外的にも福利厚生が充実していることをPRできる。
- しかし、福利厚生のほかにも、役員や従業員へ万が一があった場合の対策や、運転資金リスクなど事業運営に活用できる保険の検討も必須である。
- そのため、総合福祉団体保険を含む保険全般の見直しに「法人保険の専門家へ無料で何度でも相談できるマネーキャリア」を使う企業が増えている。

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 総合福祉団体定期保険とは
- 総合福祉団体定期保険の種類とは
- 総合福祉団体定期保険の契約者は4種類に分かれる
- 【法人編】総合福祉団体定期保険に加入するメリットとは
- 福利厚生を充実させる
- まとまった資金を準備できる
- 保険料は全額損金になる
- 従業員の意欲向上につながる
- 求人広告を充実させられる
- 総合福祉団体定期保険の「ヒューマン・バリュー特約」とは
- 【役員・従業員編】総合福祉団体定期保険に加入するメリット
- 持病があっても加入しやすい
- 手厚い保障を受けられる
- 労災でなくても死亡保険金を受け取れる
- 団体定期保険との違いは?
- 自社のリスク対策で加入すべき保険が無料で簡単にわかる方法
- 法人保険のプロにリスク対策を無料で何度でも相談できる:マネーキャリア
- 総合福祉団体定期保険の加入目的・メリットまとめ
目次
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
総合福祉団体定期保険とは

総合福祉団体定期保険とは、全従業員の死亡・労働災害の補償金に充てる財源を確保するために加入する、企業が契約する1年更新の定期保険です。原則として全従業員が加入対象となり、企業が保険金を負担し従業者の負担はありません。
総合福祉団体定期保険の主な目的は、役員・従業員の遺族の生活保障はもちろん、亡くなってしまったときの退職金や弔慰金で遺族の生活の保証となります。
保険金の受取人は従業員の家族になるので、全ての従業員は万が一のことがあった場合に、遺族の心配をせずに済むのです。
個人の加入の生命保険よりは少ない保険金になるものの、保険契約において約束されている金額はおよそ500万円ほどとなります。
総合福祉団体定期保険の種類とは
総合福祉団体定期保険には大きく分けて、以下の2種類があります。
- 総合福祉団体定期保険(有配当)
- 無配当総合福祉団体定期保険(無配当)
有配当の生命保険は保険料が高くなりがちですが、支払った金額を損金として扱えるメリットがあります。
しかし、生命保険の配当は生命保険会社の決算事情に起因するので、必ず支払われるわけではない点に注意です。(たとえば、デフレで景気が悪いときには生命保険の配当の支払いは期待できません。)
総合福祉団体定期保険の契約者は4種類に分かれる
総合福祉団体定期保険の契約者は、従業者数の規模と団体の目的によって、それぞれ以下の4種類に分類できます。
- 第Ⅰ種団体…最低従業員数10人(同一企業に所属する者の団体など)
- 第Ⅱ種団体…最低従業員数50人(親子関係の企業体の職域による団体や共済組合の団体など)
- 第Ⅲ種団体…最低従業員数50人(商工会、協同組合、特定同業者団など)
- 第Ⅳ種団体…最低従業員数100人(宗教団体など)
【法人編】総合福祉団体定期保険に加入するメリットとは

ここでは、法人が総合福祉団体定期保険に加入するメリットを解説します。同保険に加入している事業者は、以下のメリットを正しく把握して加入しているのです。
福利厚生を充実させる
第一に福利厚生のシステムをより良くする目的です。
退職金と弔慰金のためのまとまったお金を確実に用意する目的があるため、 福利厚生が充実できるのです。さらに、企業としてのイメージが良くなる副次的効果も見込めます。
法定福利厚生と併せて加入することで、ケガや病気などで万が一従業員が働けなくなった場合でも保険金を使って従業員を守れるのです。
まとまった資金を準備できる
従業員に万が一の事態が発生したときの資金が準備できる点もメリットです。
労働基準法では、従業員が10人以上いる企業は就業規則の作成をしなければならないと定められています。上記規則に、亡くなってしまったときの退職金の記載や弔慰金の規定がある場合は、企業は従業員の家族に対し、保険金を支払わなければなりません。
また、退職金を支払わなければならないケースでも、総合福祉団体定期保険を含む保険に加入しておけば、資金準備が用意できるのです。
保険料は全額損金になる
有配当の総合福祉団体定期保険に加入すれば、企業が支払った保険料は全額損金算入されます。
保険費用は「費用」としてではなく「損金」として益金から差し引くことが可能なので、法人税を減らせます。
ただし、税制改正によって保険金が「最高解約返戻率が50%以下の場合のみ全額損金算入できる」に変更となったので、法律や税務に詳しい専門家の意見を聞きつつ加入は検討する必要があるのです。
 法人保険による節税効果
法人保険による節税効果従業員の意欲向上につながる
今日では働く環境が見直されはじめ、ブラック企業が社会問題化しています。
給与の問題だけではなく、いかに「安心して長く働けるか」が焦点になっており、従業員に負担をかけることなく手厚い福利厚生を充実させなければなりません。
総合福祉団体定期保険に加入することにより、従業員の負担なしで急逝や事故・病気の保障できます。
上記のように、従業員と家族のことを考えた福利厚生のシステムは、従業員の働く環境が整うので重要なものになります。
求人広告を充実させられる
優れた人材を確保するために魅力的な求人広告を作らなければならないなか、総合福祉団体定期保険は求人上のPRにも貢献します。
大手求人サイトであるリクナビでは「【総合福祉団体定期保険】を含む求人」というカテゴリを用意しています。
このことから、次世代の働き手が福利厚生のシステムを重要視していることがわかります。また、総合福祉団体保険は「保障」以外にも「事業面の手助け」にも活用できるのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
総合福祉団体定期保険の「ヒューマン・バリュー特約」とは
総合福祉団体定期保険のヒューマン・バリュー特約とは、従業員が死亡もしくは高度な障がいを抱えてしまった場合に、企業の損失を補償してくれる特約です。
優れた従業員が急逝してしまった場合、新たな働き手を探し出さなければなりません。
そのとき、ヒューマン・バリュー特約は新しい従業員を育成するために、企業が負担しなければならない費用など経済的損失を補償してくれるのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【役員・従業員編】総合福祉団体定期保険に加入するメリット
 ここでは、役員や従業員にとってのメリットを解説します。メリットがある総合福祉団体定期保険は、企業にも活用されやすい一方、法人側だけでなく役員や従業員のメリットも考慮する必要があります。
ここでは、役員や従業員にとってのメリットを解説します。メリットがある総合福祉団体定期保険は、企業にも活用されやすい一方、法人側だけでなく役員や従業員のメリットも考慮する必要があります。
持病があっても加入しやすい
総合福祉団体定期保険の加入条件は、ほとんどの保険会社において「直近2週間で入院していないこと」のみである点がメリットです。
保険料の負担をせずに、生命保険に加入できることもポイントです。また、保険の更新のたびに「健康状態や病歴について詳しく伝える必要がないこと」も入りやすい理由の1つです。
上記のように、持病や入院手術既往歴有がある方でも加入しやすいのが総合福祉団体定期保険です。
手厚い保障を受けられる
総合福祉団体定期保険は手厚い保障を受けられることも魅力の1つです。
高度障害保険金・死亡保険金だけではなく、不慮の事故による傷害を補償する「障害給付金」や入院費用を給付する「入院給付金」といった特約があります。
また、健康状態に関わらず保障する対象範囲が広いです。たとえば、入院給付金は保険会社によるものの、5日以上180日以内の入院をした場合に給付されます。
ほかにも、勤務していないときに亡くなってしまった場合も、一般的な生命保険と同じように保障の対象となり、遺族の生活も安心です。
上記のように保険金・給付金が支払われる、手厚い保障を受けられることがわかります。そして、商品によっては、ガンなどの病気による入院だけではなく、リハビリ施設の利用や柔道整復師の施術も給付金支払い対象となる可能性もあるのです。
労災でなくても死亡保険金を受け取れる
総合福祉団体定期保険は一般的な生命保険と同じように、被保険者の生活を24時間保障する目的があります。
勤務していないときの死亡事故や病気も保険金の支払い対象となるのが魅力です。
たとえば、被保険者が休日の交通事故によって高度の障がいを抱えてしまったとき、入院費用や治療のための費用は保障の範囲内です。
従業員の急逝や不慮の事故に対応する目的のためにも、加入しておきたい保険です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
団体定期保険との違いは?

総合福祉団体定期保険は所属している団体が保険に加入している場合は、特別な理由がない限り「全員加入」であり、保険料の負担は企業や法人となります。
しかし、団体定期保険は「任意加入」となり、保険料の負担は従業員側となります。
企業そのものが保険に加入してはいないものの、扱いは企業に委ねられるため、保険料は給与から天引きされる場合が多いです。
団体定期保険は個人の生命保険と比べると保険料が安いです。しかし、年間3〜10万円ほど支払わなければならないので、従業員にとっては団体定期保険より総合福祉団体定期保険の方が好まれます。

支払った保険料は生命保険料控除の対象となります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自社のリスク対策で加入すべき保険が無料で簡単にわかる方法
以下では、自社のリスク対策で加入すべき保険が無料で簡単にわかる方法を紹介します。
総合福祉団体定期保険は、企業側で保険料を負担しつつ従業員の福利厚生を充実させられる保険の一種ではあるものの「有配当」「無配当」の種類があるうえに、加入後どのように活かすべきかは自社で検討しなければなりません。
また、経営リスクには従業員への福利厚生だけではなく、役員や従業員に万が一があった場合の後、事業運営が滞りなく推進できるかの問題もあるのです。上記のように経営全体を通して対策できている会社が少ないのが現状です。
しかし、経営陣のみで調べられる情報には限界があることからも、法人保険のプロへの相談が必須となるのです。そこで、マネーキャリアのように、プロの専門家へ総合的なリスク対策を「無料で何度でも」相談できるサービスを使う会社も増えています。
丸紅グループ運営のマネーキャリアでは、80,000件以上の相談実績をもとに得たノウハウを活用し、経営陣のリスク対策への最適な提案が強みなので、満足度も98.6%を誇ります。
法人保険のプロにリスク対策を無料で何度でも相談できる:マネーキャリア

お金に関する全ての悩みにオンラインで相談できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、法人保険のプロのみを厳選しています。
・保険だけではなく、総合的な事業リスクへの対策を踏まえて「自社の理想の状態を叶える」提案が可能です。
・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も80,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに 「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。
総合福祉団体定期保険の加入目的・メリットまとめ
ここまで、総合福祉団体定期保険の加入目的・メリットなどを紹介しました。
総合福祉団体定期保険は、従業員の福利厚生の一環として加入できるのはもちろん、ヒューマン・バリュー特約で従業員死亡時の経済的損出もカバーできます。また、安心して働く環境が保たれ、従業員のモチベーションにもつながるうえ、求人広告を充実させられる副次的効果も見込めるのです。
 関連記事】法人向け生命保険に関する質問
関連記事】法人向け生命保険に関する質問
 【関連記事】法人保険全般に関する質問
【関連記事】法人保険全般に関する質問
 【関連記事】(法人向け)退職金に関する質問
【関連記事】(法人向け)退職金に関する質問
 【関連記事】事業承継・保障に関する質問
【関連記事】事業承継・保障に関する質問



















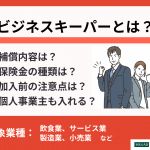
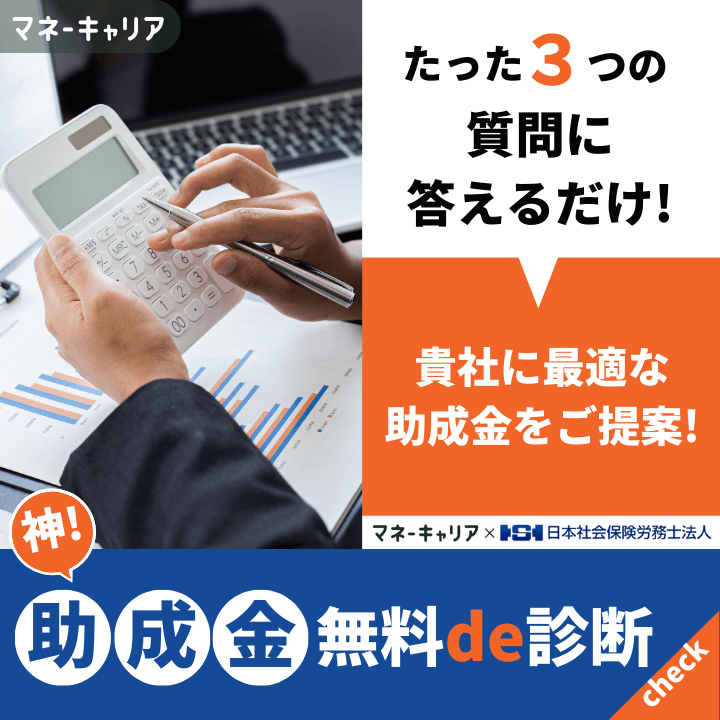
働く環境が以前よりも重要視されている今日では、より優秀な人材を獲得するためには従業員の福利厚生を充実させることが大切です。そして、福利厚生を充実させる選択肢のひとつに「総合福祉団体定期保険」があげられます。
一方、従業員の福利厚生を充実させたくても、コストをかけられず「どのように対処すべきか」悩む経営者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、低いコストで従業員の福利厚生を充実させられる「総合福祉団体定期保険」の概要や目的をわかりやすく紹介します。
・総合福祉団体定期保険の加入可否の検討をしたい
・総合福祉団体定期保険の概要は少しだけ把握しているが、当該保険への加入だけで従業員や自社のリスク対策が十分かが不安である
方は本記事を参考にすると、総合福祉団体定期保険の概要がわかることはもちろん、低予算で充実した、かつ自社にマッチするリスク対策の方法もわかります。