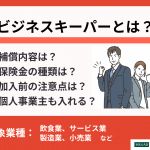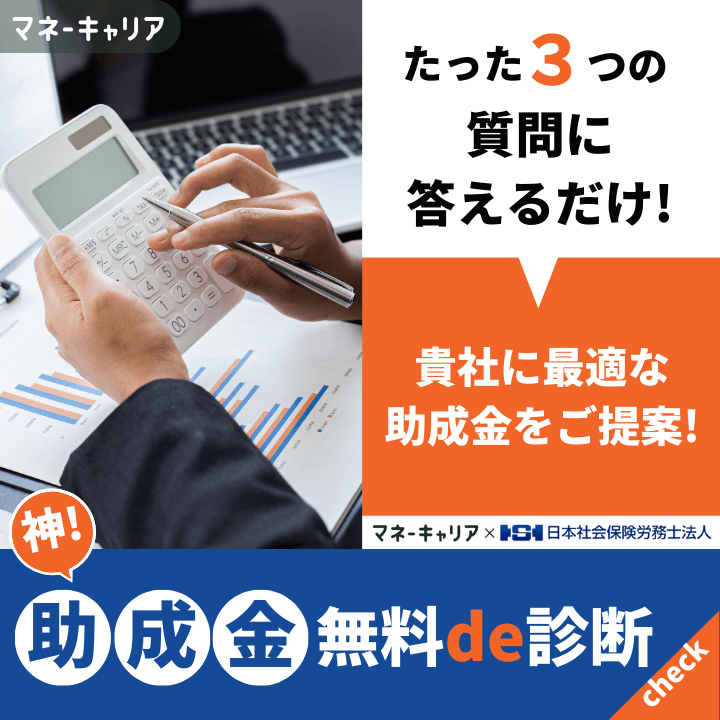更新日:2024/08/06
【必見】法人保険の経理処理や損金ルールをわかりやすく解説

内容をまとめると
- 定期保険の経理処理は最高解約返戻率で4つのパターンに分けられる。
- 第三分野保険の経理処理は全期払いと短期払いで違いがある。
- 養老保険の経理処理は死亡保険金・満期保険金の受取人の組み合わせによって異なる。
- 配当金は保険料の処理で決まり、損金ならば雑収入に計上する。 法人保険の経理処理が2019年のルール改正によって複雑化したことを機に、保険そのものを見直す会社が急増している。
- 法人保険の経理処理はもちろん、見直しに悩む会社は「法人保険のプロへ何度でも無料相談ができる「マネーキャリア」を使うのが必須

目次を使って気になるところから読みましょう!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社の最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人保険の経理処理についてわかりやすく解説

法人保険の経理処理は思った以上に複雑で分かりにくい、と感じているかもしれません。
2019年に行われた税制改正によって一層複雑なものになってしまいました。
貯蓄性の有無や受取人を見ることである程度分かりやすくなります。このような基本的な考え方は知っておきたいポイントのひとつです。
保険の種類は大きく分けると
- 定期保険
- 医療保険・がん保険
- 養老保険
- 終身保険
です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社の最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
基本的な経理処理の考え方
法人保険の基本的な経理処理のポイントとしては、
- 契約形態
- 保険の種類
- 保険料の支払い方法
です。これらの違いによって損金算入となるのか資産計上となるのかが決まってくるのです。
しかし、長期平準型定期保険や逓増定期保険のように、特別なパターンの経理処理が必要となる法人保険があることにも注意が必要です。
特に大きなポイントとなるのが「受取人」です。会社が得をしているのか、従業員が得をしているのか、誰が得をしているのかを見極めることで、経理処理がかなりスムーズになるのではないかと思います。(参考:日本生命・保険税務のしおり)
以下では基本事項として、
- 貯蓄性のある保険
- 貯蓄性のない保険
の特徴的な経理処理についてご紹介します。
1.貯蓄性のある保険商品
法人保険で貯蓄性があるものとして挙げられるのが
- 養老保険
- 個人年金保険
- 解約返戻金のある終身保険
などです。
契約形態のなかのひとつである「受取人」をポイントにすることで、経理処理の方法がわかりやすくなります。誰が得をするのかが正しく理解できるようになるのです。
| 受取人 | 経理処理 |
|---|---|
| 法人 | 資産計上 |
| 役員や従業員など個人 | 損金算入 |
2.貯蓄性のない保険商品
貯蓄性のない保険商品は、解約返戻金などの無いタイプの保険です。
- 掛け捨て型定期保険
- 掛け捨て型医療保険
などの保険です。
こちらの場合の保険料支払い時の経理処理は以下のようになります。
| 受取人 | 経理処理 |
|---|---|
| 法人 | 損金算入 |
| 役員や従業員などの個人 | 損金算入 |
- 全員:福利厚生費として損金算入
- 特定の個人:みなし給与として損金算入
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社の最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
①定期保険の経理処理
定期保険の経理処理は以下の4つのパターンです。
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 |
|---|---|---|
| 50%以下 | 全額損金算入 | 全額損金算入 |
| 50%超~70%以下 | 4割 | 4割 |
| 70%超~85%以下 | 4割 | 6割 |
| 85%超 | 開始日から終了日まで | 10年まで:9割 11年目以降:保険料×最高解約返戻率×70% |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社の最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
②医療保険・がん保険など(第三分野)の経理処理
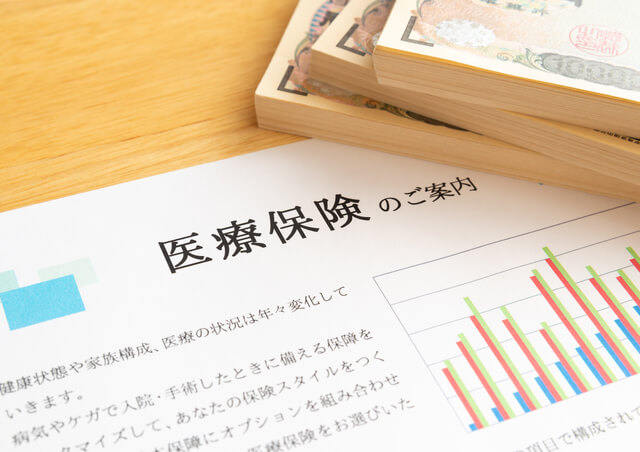
最近では法人保険を利用して医療保険やがん保険などへの加入をする会社も増えてきました。
ここで注意したいのが、第三分野の法人保険の経理処理は保険の種類や保険料支払い期間によって変わってくる、という点です。
医療保険などの場合、定期か終身か、保険期間が違うものがあります。さらに終身の場合、一生涯支払いを続ける全期払いと、補償は続きますが保険料の支払いは一定期間になる短期払いの2つのタイプに分かれるのです。
これらの違いが経理処理にどのように影響するのでしょうか?また、給付金などを受け取る際の経理処理についても解説していきます。
第三分野の保険料の経理処理
ここでのポイントは種類と支払い方法です。
| 種類 | 処理 |
|---|---|
| 定期 | 定期保険と同一 |
| 終身:全期払い | 定期保険と同一 |
| 終身:短期払い | 年間保険料によって異なる |
年間保険料×払込期間÷保険期間
116歳-契約年齢
- 年間30万円以下
第三分野の給付金受取時の経理処理
第三分野の法人保険は医療保険やがん保険となるため、被保険者が病気やケガなどで補償が適用される状態となった際には保険金が支払われることになります。
受取人が法人となっている際には保険金は会社に支払われることになりますが、その際の経理処理は「雑収入」などで益金に算入します。
受け取った保険金をかいしゃから個人へ「見舞金」などとして支給することもあります。このような場合は「福利厚生費」などで経費として処理することが可能です。
第三分野の退職金名義変更時の経理処理
名義変更時は保険料支払い時の資産計上の有無で多少違いがあります。
| 保険料の資産計上の有無 | 名義変更時の経理処理 |
|---|---|
| あり | 損金算入 前払い保険料の取り崩し |
| なし | 損金算入 |
どちらの場合も現金支給額と解約返戻金を合計したものが退職金として支給されます。この合計金額は損金算入します。差額がある場合には雑収入・雑損失などの適切な処理を行います。
保険料の資産計上があった場合、前払い保険料が資産として残っているので、これを取り崩す処理を行います。
③養老保険(福利厚生目的の保険)の経理処理
養老保険の処理方法に変更はなく、以前と同じ方法が使われています。
死亡保険金・満期保険金のそれぞれの受取人によって異なってきます。
| 死亡保険金 | 満期保険金 | 経理処理 |
|---|---|---|
| 法人 | 法人 | 全額資産計上 |
| 個人の遺族 | 個人 | 全額損金 |
| 個人の遺族 | 法人 | 1/2損金算入 1/2資産計上 |
法人保険の養老保険について、保険金受取時の処理について知りたい方は、以下の養老保険の経理処理に関する記事を参考にしてください。
④終身保険の経理処理
終身保険の保険料は全額資産計上が基本です。「保険料積立金」として資産計上しなくてはなりません。
会社の「現金・預金」は減りますが、「保険料積立金」が増えるのでプラスマイナス0の状態です。
解約返戻金受取時には、返戻率が100%を超えている場合支払保険料との差額が雑収入に、返戻率が100%を下回っている場合は支払保険料との差額が雑損失として経理処理されることになります。
しかし、法人保険で終身保険を取り扱うのはリスクが多いため、利用する際には十分注意するようにしましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社の最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
節税を目的とした法人保険の利用が制限された
今までは法人保険を利用して節税を行う会社が多くありましたが、特に死亡定期保険では節税効果が高く、「節税保険」として多くの保険会社が取り扱いをしていました。
しかし、税制改正でこれらの節税効果は低い商品となってしまったのです。バレンタインショックとも呼ばれます。
今まで節税対策として利用していた「全額損金算入」が基本的にできなくなり、医療保険でも年間30万円までと制限されることになってしまったのです。
これは死亡定期保険などの中に保険料の80%以上が解約返戻金として支払われるタイプのものもあり、お金が戻ってくるのに全額「損金」として扱うのは不自然で、資産として扱うべきだ、という意見が上がっていたのです。
このような保険に対して全額損金を制限することで過度な節税に対する対処をしていましたが、付加保険料を高く設定してより多くの節税効果を産む商品などが問題となり、とうとう2019年に税制改正となってしまったのです。
さらに2021年には「ホワイトデーショック」と呼ばれる新通達も出ており、これからその他の保険の改正も行われるのではと言われています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社の最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人保険の経理処理を含む「悩み」を解消する方法とは
以下では、「損害保険を適切に経理処理する方法」をはじめとした、法人保険全般の悩みを解消できる方法を紹介します。
法人向け損害保険の保険料や補償金の経理処理は複雑であり、正確な処理が求められます。とくに、保険料の支払いや補償金の受け取り時に適切な仕訳を行わなければ、税務上の問題が発生するリスクがあります。
さらに、経理処理の問題だけではなく、保険の見直しリスク対策が適切にできているかは担当者のみはでは判断が難しく、専門知識が必要になるのです。
そこで今日では、法人保険のプロに「無料で何度でも」法人保険に関する悩みを相談できるマネーキャリアを使うのが必須です。
丸紅グループが運営するマネーキャリアは「相談実績80,000件以上、相談満足度98.6%の高い評価」があるため、損害保険はもちろんリスク対策に関してもアドバイスができる強みを持っています。
法人保険全般やリスク対策の問題をすぐに解消可能:マネーキャリア(丸紅グループ)

法人保険に関する全ての悩みにオンラインで相談できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、法人保険のプロのみを厳選しています。
・保険だけではなく、総合的な事業リスクへの対策を踏まえて「自社の理想の状態を叶える」提案が可能です。
・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も80,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに 「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社の最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
適切な法人保険の経理処理方法まとめ

ここまで、法人保険の経理処理をそれぞれの保険種類ごとに解説しました。
定期保険は返戻率で4つのパターンに分けられ、第三分野では全期払いと短期払いで違いがあります。なかでも養老保険は死亡保険金・満期保険金の受取人の組み合わせによって異なるので注意しましょう。
また、2019年から国税庁より新ルールになったのは、過度な節税に対処するためであり、以前までのような節税はできなくなっている点には押さえておくべきポイントです。一方、ルールの改正によって経理処理はより複雑化しており、さらに多くの会社で「現在加入している保険が最適か」の見直しがされるようにもなりました。
そこで、保険の見直しをし、自社にとって最適な選択ができている会社は「マネーキャリア」のように、法人保険のプロが「無料で何度でも」リスク対策や保険の見直しができるサービスを使っているのです。
無料相談予約は30秒で完了するので、ぜひマネーキャリアを活用し、リスクに強い環境を整えましょう。