
更新日:2024/08/06
【法人の養老保険】満期保険金の経理処理は?据え置きの場合も解説
内容をまとめると
- 養老保険の「満期保険金」を受け取った際の経理処理は、受取人が「被保険者」か「法人」かによって異なる。
- 前者では給与扱いとなるので「全額損金算入」(しかし、社会保険料の負担が増える)、後者では資産計上となるので「全額資産計上」となる。
- 満期保険金の受け取りを据え置きにしても、課税の繰延をしているだけなので、以前ほどの節税は見込めない。一方、年間利息がつくことがポイント。
- 自社に最適な保険が養老保険かは、2019年の税制改正によって業態業種問わず見直しを強いられる会社が多くなり、マネーキャリアのような法人保険のプロに無料相談できるサービスを使う会社も増えている。

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 【2パターン】養老保険が満期を迎えたときの経理処理とは
- 法人契約の満期保険金を「被保険者」が受け取る場合
- 法人契約の満期保険金を「法人」が受け取る場合
- 法人が満期保険金を年金払いで受け取る「年金支払特約」の場合
- 年金支払特約を満期になる前に付加した場合
- 年金支払特約を満期保険金の受取時に付加した場合
- 満期保険金を据え置きした場合は?
- 養老保険で満期を迎える場合以外の経理処理
- 死亡保険金受け取り時の経理処理
- 解約返戻金受け取り時の経理処理
- 事業リスクへの対策が無料でわかる方法
- 事業リスク対策に最適なパートナー:マネーキャリア(丸紅グループ)
- 養老保険の満期保険金の経理処理方法や据え置き時のまとめ
目次
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【2パターン】養老保険が満期を迎えたときの経理処理とは
法人契約で養老保険に加入するときは、満期保険金の受取人を誰にするかによって経理処理が異なるので、特に節税目的で加入する場合は注意が必要です。
たとえば、養老保険の満期保険金を法人が受け取ると法人税が課税されたり、個人の被保険者が受け取ると所得税や住民税が課税されたりしてしまうのです。
そのため、養老保険の満期保険金の経理処理には受取人が法人の場合と個人の被保険者の場合の2つがあることを押さえておきましょう。
次からは養老保険について、以下の2つの異なる経理処理について解説します。
- 満期保険金の受取人が被保険者の場合
- 満期保険金の受取人が法人の場合
法人契約の満期保険金を「被保険者」が受け取る場合
法人契約の満期保険金を、従業員や役員といった個人の被保険者が受け取る場合は、「全額損金算入」されます。
理由は、被保険者が受け取る満期保険金が「給与扱い」になるからです。給与であれば法人側としては損金計上されますが、一方で、受け取る側の被保険者としては所得が増加するため、所得税や住民税の課税対象額も大きくなってしまいます。
また、もう1つ注意しなければならないのは、所得の増加に伴って労使折半の社会保険料が増加することです。
従業員は健康保険が給与の9.96%、厚生年金が18.182%、合計で「給与の28.142%」が社会保険料に充当されており、これを会社と折半しています。
したがって、所得が増えれば課税される社会保険料も増えることになるので、折半している会社側の負担も増えるのです。
法人契約の満期保険金を「法人」が受け取る場合
法人契約の満期保険金を、役員や従業員を被保険者にしながら法人を受取人にする場合は、全額資産計上されます。
法人税は資産として計上された金額に課税されるので、満期保険金の全額が資産に計上されれば、法人税の課税対象額も増えます。
そのため、満期保険金の受取人を法人にした場合、役員などの経営陣に万が一の事態が発生したときの備えになるメリットがある一方で、法人税が多く課税されてしまうデメリットがあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人が満期保険金を年金払いで受け取る「年金支払特約」の場合
ここからは法人が満期保険金を年金払いで受け取る時の経理処理について解説します。
年金支払特約とは、満期保険金をそのまま全額受け取るのではなく、年金払いで受け取る方法です。
たとえば、2億円の満期保険金をそのまま受け取ると、2億円すべてが課税対象となり、税負担が大きくなってしまいます。そこで、2億円の満期保険金を年金払いとして、年間200万円ずつ分割で受け取れば、年間200万円のみ課税対象になりません。
そのため、法人が満期保険金をそのまま受け取るよりも、年金支払特約を利用して分割で受け取った方が節税効果が高いと言えます。
年金支払特約の経理処理を以下の2つの場合に分けて解説していきます。
- 年金支払特約を満期になる前に付加した場合
- 年金支払特約を満期保険金の受け取り時に付加した場合
 法人保険の年金支払特約について
法人保険の年金支払特約について年金支払特約を満期になる前に付加した場合
契約時あるいは満期になる前に年金支払特約を付加した場合、資産計上されている保険料積立金と配当積立金の両方を、年金の原資として年金積立保険料に振替処理します。
例えば、以下のような例を考えます。
- 保険料積立金:750万円
- 積立配当金:100万円
- 支払われる年金:年額150万円
- 保険期間:10年間
- 年金受取見込み総額:1,500万円
このとき、満期日に資産計上した年金積立保険料750万円から、以下の式で計算した額を取り崩します。
取り崩し額 = 年金積立保険料 × 受取年金額/年金受取見込み総額
この式に実際の数字を当てはめると、以下のように取り崩し額が85万円と計算されます。
850万円×150万円÷1,500万円 = 85万円
このとき、年間の年金受取額、年金積立保険料、雑収入はそれぞれ以下のようになります。
- 年間の年金受取額=150万円
- 年金積立保険料=85万円
- 雑収入=65万円
年金支払特約を満期保険金の受取時に付加した場合
満期保険金の受け取り時に年金支払い特約を付加した場合、年金積立保険料と現在の保険料積立金・配当積立金の差額が雑収入となります。
例えば、以下のような例を考えます。
- 年金積立保険料=1,100万円
- 保険料積立金=750万円
- 支払われる年金=150万円
- 配当積立金=100万円
- 雑収入=250万円
満期日に資産計上した年金積立保険料の1,100万円から、以下の式で計算した額を取り崩します。
取り崩し額 = 年金積立保険料 × 受取年金額/年金受取見込み総額
この式に実際の数字を当てはめると、以下のように取り崩し額が110万円と計算されます。
1,100万円×150万円÷1,500万円=110万円
このとき、年間の年金受取額、年金積立保険料、雑収入はそれぞれ以下のようになります。
- 年間の年金受取額=150万円
- 年金積立保険料=110万円
- 雑収入=40万円
満期保険金を据え置きした場合は?

実は、満期保険金は満期になってもすぐには受け取らず、据え置きできる仕組みがあるのです。
養老保険では、満期になったらすぐに満期保険金を受け取らなければならないわけではなく、必要になるときまで保険会社に預けておけるのです。ただし、満期保険金は据え置きをしていても、受け取ったものとして法人税が課税され、節税対策になるわけではありません。
一方、赤字になりそうな年や事業拡大で資金が必要になる予定がある場合などにあわせて、満期保険金を受け取るなどの対策は可能です。
メリットとしては、養老保険を据え置きをしている間は利息がつく点です。利率は年間0.01%ほどであり、三井住友銀行や三菱UFJ銀行、みずほ銀行といった大手銀行の利率(0.001%)よりも得であるといえます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
養老保険で満期を迎える場合以外の経理処理
ここでは、「死亡保険金・解約返戻金について」や「それぞれの経理処理」受け取り時の経理処理を解説します。
養老保険で満期を迎える以外にも、資金を受け取るタイミングがあり、解約返戻金と死亡保険金の2つが挙げられます。
養老保険でお金を受け取れるのは、満期か解約返戻金、死亡保険金です。満期以外の方法で受け取った場合、経理処理の方法が少し異なります。
そのため、契約形態の例をもとに、経理処理が必要なのかを押さえておく必要があるのです。
死亡保険金受け取り時の経理処理
死亡保険金を受け取った場合の経理処理には、保険料積立金は雑損失として損金算入する必要があります。
死亡保険金は保険期間中、被保険者に万が一のことが起こった際に支払われます。金額は契約会社によってさまざまですが、満期を迎えた際に受け取れる金額と同額になります。
死亡保険金と満期保険金のいずれでも、同額受け取れる点が養老保険の魅力です。
例えば、死亡保険金10,000,000円、保険料積立金2,750,000円だった場合には、以下の表のように処理を行います。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 雑損失 2,750,000円 | 保険料積立金2,750,000円 |
解約返戻金受け取り時の経理処理
解約返戻金とは、途中で契約解除したときに受け取れる資金です。何らかの事情があり、解約した場合に、今まで支払った保険料の一部を受け取れるのです。
返金率は、以下の計算式に当てはめると抽出できます。
解約返戻金の返戻率 = 解約返戻金 ÷ 払い込んだ保険料の総額
一般的な定期保険にはない制度なので、養老保険の大きな魅力の1つといえます。
解約返戻金を受け取った際の経理処理は、解約返戻金と保険料積立金の差額を雑収入または雑損失として計算します。
例えば、解約返戻金が4,850,000円、保険料積立金が2,750,000円だった場合には、以下の表のように処理を行います。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 現金・預金 4,850,000円 | 保険料積立金 2,750,000円 雑収入 2,100,000円 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
事業リスクへの対策が無料でわかる方法
以下では、「事業リスクへの対策」が無料でわかる方法をご紹介します。
養老保険は、死亡保険金と満期保険金のいずれかを受け取れるので、従業員に万が一があった際の保障として選択肢のひとつに挙がります。しかし、2019年の税制改正によって、以前ほど損金算入による節税ができなくなったことから、事業リスクに対して正しく検討することが事業者に求められます。
しかし、普段の事業運営で忙しいなか、経営陣のみで「本当に自社の保険でリスク対策ができているか」を判断するのは至難の技です。
そこで、法人保険のプロに、自社で起こりうる事業リスクを「無料で何度でも」相談できるマネーキャリアを使うのが必須です。
丸紅グループが運営するマネーキャリアは、税務を含めた総合的な保険の活用方法の提案が無料で受けられるサービスです。数多くの保険相談を通じて得たノウハウを活用し、80,000件以上の相談実績を誇ります。
事業リスク対策に最適なパートナー:マネーキャリア(丸紅グループ)

お金に関する全ての悩みにオンラインで相談できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、法人保険のプロのみを厳選しています。
・保険だけではなく、総合的な事業リスクへの対策を踏まえて「自社の理想の状態を叶える」提案が可能です。
・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も80,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに 「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。
養老保険の満期保険金の経理処理方法や据え置き時のまとめ
ここまで、法人契約で加入する「養老保険の満期保険金の経理処理」を中心に解説しました。
養老保険では、被保険者が満期保険金を受け取ると給与扱いになり、法人が満期保険金を受け取ると全額資産に計上されます。また、年金支払特約では満期保険金を分割して受け取れるうえ、満期保険金を据え置くと利息分プラスになります。
しかし、養老保険には魅力的なメリットがある反面、受取人や被保険者が誰かによって経理処理が異なるため、扱いが難しい商品でもあります。さらに、養老保険は保障が充実している分、保険料が高額となりがちなので、自社に最適な保険かを正しく判断する必要があるのです。
そこで、法人保険に関する悩みを、自社の状況を踏まえて「何度でも無料で相談」できるマネーキャリアを使って、リスク対策を進める企業も増えているのです。
無料登録は30秒で完了するので、ぜひマネーキャリアを使い、自社と従業員を守るリスク対策を進めていきましょう。
▼この記事を見た方はこちらも見ています。
 【関連記事】法人向け生命保険に関する質問
【関連記事】法人向け生命保険に関する質問
 【関連記事】法人保険全般に関する質問
【関連記事】法人保険全般に関する質問
 【関連記事】(法人向け)退職金に関する質問
【関連記事】(法人向け)退職金に関する質問
 【関連記事】事業承継・保障に関する質問
【関連記事】事業承継・保障に関する質問



















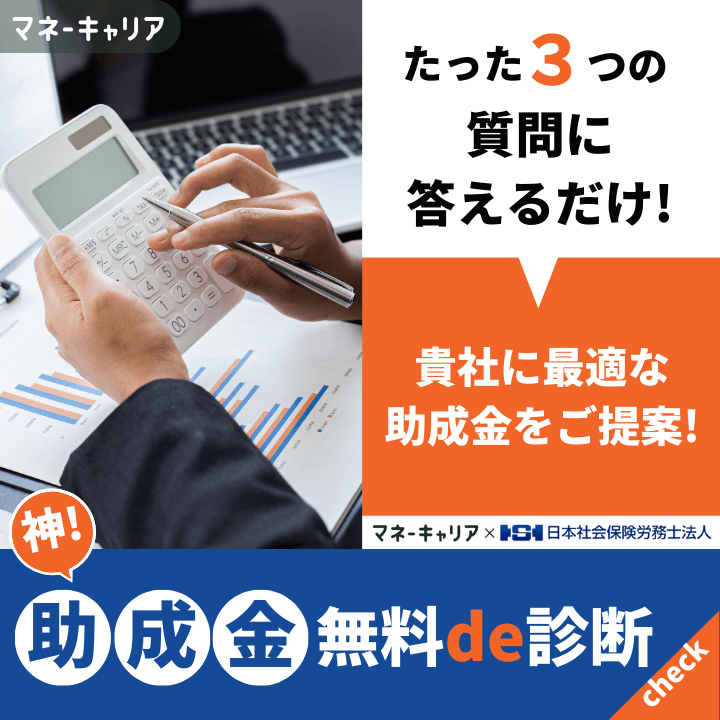
養老保険は満期を迎えても満期保険金を受け取ることができ、法人契約で養老保険に加入したいと考えている方も多いです。
しかし、養老保険の満期保険金の経理処理は受取人が法人なのか役員や従業員なのかによって異なるため、理解されていないのが現実です。また、経理処理を正しく理解していなければ、法人税を多く支払っている可能性もあるのです。
そのため、法人養老保険の満期保険金の経理処理を正しく理解し、効率的に企業経営をしていくことが重要です。そこで今回は、法人契約の養老保険の満期保険金を受け取った際の経理処理を中心にご紹介します。
・養老保険の満期保険金の経理処理にて損金算入し、資金の流出を抑えたい
・実は、養老保険による従業員の万が一のリスク対策と事業リスク対策が両立できているか不安
な方は本記事を読むと「法人契約の養老保険の満期保険金」について、被保険者や受取人のパターンごとの経理処理はもちろん、事業リスク対策への方法もわかります。