
更新日:2024/08/06
法人税の納付期限は1日遅れだけでも過ぎてはいけない?
内容をまとめると
- 法人税・消費税の支払時期は、事業年度終了の翌日から2カ月以内に支払わなければならず、金額によって中間申告の義務が発生する。
- 法人が納めるべき税金には源泉所得税・固定資産税などがあり、納付が遅れると延滞税や加算税などのペナルティが課される。
- もし、遅れる場合の申告期限は手続きをすれば延長できるケースもあるが、基本的には納付期限までに法人税を支払うことはマスト。
- しかし、法人税の支払いを含む年間の資金計画を立てていても、急な出費に焦る会社も多いので、法人保険やリスク対策へのプロへ、何度でも無料相談できるマネーキャリアを使って対策をとる会社が急増している。

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 法人税の支払時期はいつ?時期を守らないときのペナルティは?
- 法人税の支払時期は「事業年度終了日の翌日からの2カ月」
- 年間20万円を超えると中間申告が必要
- 消費税・源泉所得税・固定資産税の支払時期を解説!
- 消費税の支払時期
- 源泉所得税の支払時期
- 固定資産税の支払時期
- 支払が遅れると延滞税と加算税のペナルティがある
- 延滞税
- 加算税
- 納税申告時期を延ばすことはできるか
- 会社にかかる9種類の税金を解説
- 税金の納付方法
- 法人税を含む税負担のリスクにあらかじめ準備しておく方法とは
- 法人税のリスク対策について無料で何度でも相談可能:マネーキャリア(丸紅グループ)
- 法人税の納付期限は1日遅れだけでも過ぎてはいけない?のまとめ
目次
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人税の支払時期はいつ?時期を守らないときのペナルティは?
まず、法人税の支払時期と中間申告についてわかりやすく解説します。
中間申告が必要な場合、不要な場合を理解しておけば、余裕をもって資金準備にとりかかることができます。
法人税の支払時期は「事業年度終了日の翌日からの2カ月」
法人税は、事業年度終了日の翌日から2カ月以内に申告・納付する必要があります。
「申告」とは申告書を作成して税務署に提出すること、「納税」とは申告によって確定した税額を金融機関や税務署で納めることです。申告と納付のどちらも2カ月以内に行わなくてはなりません。
個人事業であれば自分で所得税の申告を行う経営者もいます。しかし、法人税は計算が複雑で税額も大きくなることから、申告書の作成は税理士や会計士に依頼をするのが一般的です。
決算終了後に税理士が申告書を持参し、説明を受けたうえで「紙もしくは電子」で申告書を税務署に提出します。納付書は税理士から手渡しもしくは郵送で届くものを、納付期限までに納めましょう。
届いた納付書を放置してしまうと、納付が遅れて延滞税・加算税などのペナルティの対象となる場合もあるので注意が必要です。
年間20万円を超えると中間申告が必要
事業年度の半年が経過した時点で、期末に納める税金を前倒しで納める制度を「中間申告」といいます。
中間申告は法人税が年間20万円を超えた場合に必要となり、中間申告をするかしないかを法人が選択することはできません。
中間申告の方法には、「予定申告方式」と「仮決算方式」があります。
予定申告方式とは、前期の年間の法人税額の半額を納める方法です。当期末には、年間の法人税額から中間申告で納めた金額を差し引きして納めることになります。
ただし、前期も中間申告をしていた場合、当期の中間申告で納める法人税額は、「前期の年間の法人税額の半額」です。期末に実際に納めた税金の半額ではないので注意しましょう。
一方、仮決算方式とは、決算と同様の手続きをしで半年分の申告書を作成し、添付書類等もつけて申告する方法です。事務手続きが煩雑なことから、一般的には採用されません。
前期に比べて大幅に業績が悪化し、予定申告方式で計算した法人税の納税資金を準備できない場合などに採用されることがあります。
たとえば、前期の中間申告で50万円納め、期末に計算した年間の法人税額が120万円なら、期末に実際に納める税額は70万円です。当期は前期の年間の法人税額の半額を中間申告で納めるため、中間申告は60万円です。
その後、期末に計算した年間の法人税額が170万円であれば、期末に実際に納める税額は110万円となります。中間申告の申告・納付期限は、事業年度の半年を経過した日から2カ月後です。
中間申告が必要な場合、税務署から申告書や納付書が届くものの、支払時期を過ぎるとペナルティの対象となるため注意しましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
消費税・源泉所得税・固定資産税の支払時期を解説!
次に、消費税・源泉所得税・固定資産税の支払時期についても詳しく説明します。各税の支払時期がそれぞれ異なるので、納税時期にはとくに注意を払う必要があります。
消費税の支払時期
消費税の支払時期は法人税と同様で、事業年度終了日の翌日から2カ月以内です。
ただし、中間申告の仕組みは法人とは異なるため、注意しましょう。
法人税の中間申告の基準は20万円で、前期の年間の法人税額が20万円以下であれば中間申告はなし、20万円を超えれば年に1回中間申告をするというシンプルな制度でした。
しかし、消費税は基準が「48万円以下・400万円以下・4,800万円以下・4,800万円超」の4段階に分けられており、それによって中間申告の回数が変わります。
前期の年間の消費税額が48万円以下であれば、中間申告は必要ありません。48万円超400万円以下であれば、年1回の中間申告が必要です。
中間申告の消費税の支払時期は、法人税のときと同様半年を経過した日から2カ月後になるため、事業年度開始から8カ月以内です。
中間申告の消費税の税額は、前期の年間消費税額の半額であり、400万円超4,800万円以下であれば、年3回の中間申告が必要です。この場合の支払時期は5カ月以内・8カ月以内・11カ月以内で、納める税額は前期の年間消費税額の4分の1です。
4800万円超の場合、中間申告は11回必要で、納める税額は前期の年間消費税額の12分の1です。支払時期は、決算が確定するタイミングから4カ月目に2カ月分を納め、その後は毎月納める必要があります。
消費税は個人である一般消費者が負担する税金で、会社が負担する税金ではありません。ただし、徴収した消費税を会社は個人にかわって国に納める必要があります。
通常、会社が商品やサービスを消費者に提供するときは、消費税を徴収します。同時に、会社は材料や商品の仕入などの取引で、取引先に消費税を支払います。
消費税の申告とは、売上で徴収した消費税から取引先に支払った消費税を差し引いて、その差額を申告・納付することです。会社としては、徴収した消費税を国に納めている形になるので、実際に負担が発生しているわけではありません。
源泉所得税の支払時期
源泉所得税は、従業員の所得税を会社が給与から天引きし、本人にかわって納める制度です。
そのため、会社が税金を負担しているわけではありません。源泉所得税は徴収した月の翌月10日までに納めるのが原則です。
たとえば、4月の給与を4月25日に支払った場合、4月分の給与から天引きした所得税は5月10日までに納めます。ただし、小規模事業者は「納期の特例」の制度を利用できます。
納期の特例は給与の支給人員が10人未満の小規模な事業者のみ適用できる制度で、従業員が10人以上いる場合は適用できません。
納期の特例を適用するときは、税務署に申請書を提出すると、徴収した所得税を半年ごとにまとめて納めることができます。
納期の特例を適用した場合の源泉所得税の支払時期は、7月10日と1月20日です。
1月から6月の給与から天引きした所得税を7月10日までに納め、7月から12月の給与から天引きした所得税を1月20日までに納めます。
固定資産税の支払時期
固定資産税は一括払いか年4回払いかを選択でき、納付期限は市町村ごとに定められています。固定資産税の納付書は4月から6月頃に届きます。
東京都23区であれば、6月末・9月末・12月末・2月末が納付期限です。一括払いなら、最初の納付期限である6月末にすべて納めることになります。
固定資産税と償却資産税は、毎年1月1日時点で会社が所有する資産に対して課税される税金です。土地建物などの不動産に対しては固定資産税がかかり、機械・器具・備品に対しては償却資産税がかかります。
土地建物については市役所は登記で把握していますが、機械・器具・備品は把握できないため、年末になると会社に償却資産税の申告書が送られてきます。償却資産税の申告書が届いたら、増えた資産・減った資産を記載して送り返しましょう。
固定資産税も償却資産税も、法人税や消費税とは違い、計算そのものは市役所が行ってくれます。しかし、その後納付書が届くため、納税者としては届いた金額をそのまま納めることになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
支払が遅れると延滞税と加算税のペナルティがある
続いては、支払が遅れた場合のペナルティについて詳しく説明します。ペナルティが発生しないように法人税は納めるべきですが、万が一へのリスクとして把握しておく必要があります。
延滞税
税金の支払が法定期限に間に合わなかった場合、「延滞税」が発生します。
延滞税は納付期限の翌日から実際に税金が納められるまでの間の日数をもとに計算されます。「数日なら大目に見てもらえるだろう」という甘えは税務署には通用しません。
計算上延滞税が発生する場合は必ず支払を求められるため、注意が必要です。
延滞税の税率は、法定期限から2カ月以内であれば「年率7.3%か特例基準割合に1%を足した税率」のうち、低い方が適用されます。
法定期限の2カ月を超える場合、年率14.6%か特例基準割合に7.3%を足した税率のうち、低い方が適用されます。延滞税は国税庁のホームページで試算することもできるため、万一過ぎてしまった場合はチェックしてみましょう。(国税庁:延滞税の計算)
加算税
加算税とは、適正な申告がされなかった場合に課されるペナルティです。
申告・納付を法定期限までにしなかった場合、無申告加算税が課されます。無申告加算税の税率は、納付すべき税額50万円までは15%、50万円を超えてからは20%となります。
また、税務署から指摘される前に自主的に申告した場合は5%軽減されます。
一定の要件を満たす場合は1カ月以内に申告すれば無申告加算税が課税されないケースもありますが、少なくとも納税は法定期限内に終えている必要があります。
また、申告したものの計算に誤りがあり、納めるべき法人税が足りなかった場合、過少申告加算税が課されます。
過少申告加算税の税率は10%で、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分には5%加算して課税されます。決算の準備には早めに取り掛かり、計算を誤ることがないようにしましょう。
源泉所得税を法定期限までに納付しなかった場合、不納付加算税が課されます。自主的に納付した場合の税率は5%ですが、税務署から指摘を受けると10%の税率で計算しなければなりません。
また、無申告加算税・過少申告加算税・不納付加算税が課された際に、納税する意思が認められなかったり悪質だったりすると、最も重い罰則である重加算税が課されます。
無申告加算税に代わって重加算税が課税されるときの税率は40%、過少申告加算税・不納付加算税に代わって重加算税が課税されるときの税率は35%と、重加算税の対象になると金額はかなり高額になる見込みです。
また、平成28年度の税制改正によって、過去にも無申告加算税や重加算税が課税されているなど一定の要件を満たした場合、重加算税がさらに10%割り増しされるという厳しい措置がとられました。(国税庁:加算税制度の改正のあらまし)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
納税申告時期を延ばすことはできるか
万が一申告が遅れそうな場合でも、申告期限の延長の特例を適用すれば申告を延長できる場合があります。
ポイントは、法人税の申告期限は決算後2カ月以内ですが、株主総会の開催は決算後3カ月以内とされている点です。
「株主総会を開くのが決算後3カ月目になるため、株主総会のあとに納付する」という申請を税務署に対して行うのです。ただし、この特例を適用するためには、会社の定款で株主総会の召集時期が3カ月以内と規定されている必要があります。
召集時期が2カ月以内と規定されている場合、この特例を申請する根拠がありません。また、申告を1カ月延長したとしても、納付は法定期限までに行う必要があります。
申告が間に合わず正式な税額が確定しない場合は、少し多めに納付しておきましょう。同時に、申告期限の延長を申請し、申告書が完成して税額が確定した時点で、払い過ぎた税金については還付の手続きができます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
会社にかかる9種類の税金を解説
会社が支払う税金には、下記のような種類があります。
- 法人税・法人住民税・法人事業税
- 消費税
- 源泉所得税
- 固定資産税(償却資産税)
- 印紙税・登録免許税
- 自動車関連の税
印紙税や登録免許税は、契約書に貼る印紙を購入した場合や登記の際に発生します。自動車関連の税は、自動車税や自動車重量税などです。
会社にかかる9種類の税金の中でも特に、法人税等・消費税・源泉所得税・固定資産税は金額も大きいため、支払時期には注意しましょう。年間の納税計画を立て、早めに資金準備をしておくことが大切です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
税金の納付方法
法人税・消費税・源泉所得税は国に納める税金なので、金融機関か所轄の税務署で納めます。
法人住民税は金融機関もしくは都道府県・市町村の窓口で納めます。固定資産税は金融機関か市町村の窓口で納めますが、コンビニエンスストアでも受け付けてくれる場合があります。
固定資産税の納付方法については市町村のホームページや納付書の裏側にも案内が記載されています。また、固定資産税は口座振替で納めることもできます。
一方、法人税や源泉所得税の場合も、「ダイレクト納付」の手続きをすれば口座振替で納めることができます。ダイレクト納付の手続きには時間がかかることもあるため、余裕を持って手続きをしましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人税を含む税負担のリスクにあらかじめ準備しておく方法とは
ここでは、法人税を含む税負担のリスクにあらかじめ準備しておく方法が、「無料で簡単に」わかる方法を紹介します。
法人税の支払い期限は必ず遵守しなければならず、1日でも遅れると延滞税が加算されてしまいます。しかし、法人税だけではなく事業承継時に発生する「相続税」なども同様に正しく支払わなければなりません。
また、法人税や相続税は多額となるケースが多いので、自社の資金が不足している場合は、資金がショートする可能性もあるのです。そこで、対策をあらかじめしておかなければならない一方、そもそもその対策・準備方法として何があるのかを把握するには、総合的な事業リスク対策の「専門家」への相談が必須です。
したがって、今日ではマネーキャリアのように、法人向けのリスク対策のプロへと「無料で何度でも」相談できるサービスを使う会社も急増しています。
丸紅グループ運営のマネーキャリアでは、80,000件以上の提案実績から得たノウハウを元に、自社にマッチする最適なリスク対策の提案に強みがあります。満足度も98.6%を誇るので、初めて相談する経営陣の方でも安心です。
法人税のリスク対策について無料で何度でも相談可能:マネーキャリア(丸紅グループ)

お金に関する全ての悩みにオンラインで相談できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、法人保険のプロのみを厳選しています。
・保険だけではなく、総合的な事業リスクへの対策を踏まえて「自社の理想の状態を叶える」提案が可能です。
・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も80,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに 「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。
法人税の納付期限は1日遅れだけでも過ぎてはいけない?のまとめ
ここまで、「法人税・消費税・源泉所得税など法人が納めるべき税金」の支払時期や納付が遅れた場合のペナルティ、申告期限の延長について解説しました。
法人税・消費税の支払時期は、事業年度終了の翌日から2カ月以内に支払わなければならず、金額によって中間申告の義務が発生します。
また、法人が納めるべき税金には源泉所得税・固定資産税などがあり、納付が遅れると延滞税や加算税などのペナルティが課されるので、もし遅れる場合の申告期限は手続きをすれば延長できる場合もあります。
上記のように、法人税など税金の支払時期を知っておくことで、余裕を持って資金を準備ができます。しかし、年間の資金計画を立てていても、急な出費に焦る会社も多いのです。
そこで、法人保険やリスク対策へのプロへと無料相談できるマネーキャリアを使って、あらかじめリスク対策を万全にしておくことが鉄則です。
無料登録は30秒で完了するので、ぜひマネーキャリアで法人税リスクを解消し、自社の事業運営に集中できる環境を構築しましょう。













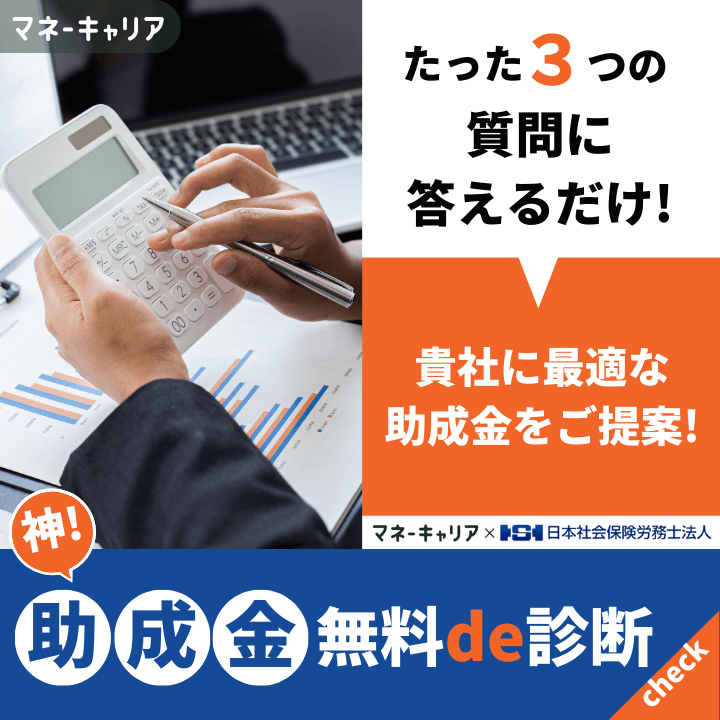
会社経営では、法人税をはじめさまざまな税金を支払う必要があります。税金には納付期限があり、時期を過ぎてしまうとペナルティがあるので注意しなければなりません。
法人税の支払時期や遅れた場合のペナルティに関して知識を身につけておけば、余裕をもって納税資金の準備ができます。しかし、ペナルティの内容やリスク対策の専門的な知識がない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「法人税の支払時期はもちろん、支払が遅れた場合のペナルティや納税申告時期を延ばす方法」を中心に解説します。
・法人税の支払時期を遅らせられるのかについて知りたい
・法人税の支払時期を遅らせられるかに加え、そもそも税負担を抑えられる方法があれば実施したい
方は本記事を参考にすると、法人にかかる税金の種類と支払時期がわかり、年間を通して納税計画を立てられます。