
更新日:2024/08/06
普遍的加入とは?法人保険の福利厚生プランも解説
内容をまとめると
- 法人保険(養老保険など)の福利厚生プランが損金算入されるには従業員・役員全員の加入(普遍的加入)が必要である。
- 一方、合理的基準により普遍的に設けられた格差であると認められる場合は、全員の加入は不要。
- 経理処理に関して、従業員側の事情によって加入できないケースであれば、損金算入が可能だが、社内規程を整備して文面に残しておく必要がある。
- また、法人保険の普遍的加入をしたとしても、自社の事業フェーズや事業形態によっては、法人保険の使い方を見直さなければならない。
- 今日では、マネーキャリアのように、専門性の高い法人保険のプロへ無料で相談しつつ、自社の事業リスクを着実に進める会社が急増している。

目次を使って気になるところから読みましょう!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人保険の福利厚生プランにおける普遍的加入は重要
法人保険の福利厚生プランに加入時は、普遍的加入に関して注意しておくことが重要です。
普遍的加入とは「会社すべての従業員や役員が加入すること」を指しており、普遍的加入がされていないと損金算入されなくなってしまうと規定されています。
しかし、法人保険の福利厚生プランでは、必ずしも「会社に在籍する全ての従業員と役員の加入」がないと普遍的加入として認められないわけではありません。
そこで、以下では「普遍的加入」を詳細に解説します。
普遍的加入とは?
法人保険の普遍的加入とは、従業員や役員全員が加入することです。
とはいえ、通達によれば「加入資格の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であっても、それが職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により普遍的に設けられた格差であると認められるときは当該役員または従業員に経済的利益はないものとする。」とされています。
たとえば、勤続5年以上で加入できる、一般社員は保険金300万円で役職者は800万円といった格差があったとしても、普遍的加入として認められるのです。
また、普遍的加入として認められる場合と認められない場合は、以下のようにまとめられます。
普遍的加入として認められる場合
- 従業員と役員が全員加入するもの
- 一部の従業員や役員が加入しており、合理的な基準により普遍的に設けられた格差であるもの
普遍的加入として認められない場合
- 従業員や役員全員が加入しておらず、かつそれが合理的な基準により設けられた格差でないもの
なぜ法人保険の福利厚生プラン加入が重要になるか
法人の養老保険の福利厚生プランは、従業員の死亡保険金の受取人を従業員の家族、満期保険金の受け取りを会社にするものです。
このとき、会社の従業員や役員全員に福利厚生が及んでいなければ、普遍的加入として認められません。福利厚生費として一般的に認められているものは、以下のとおりです。
- 従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
- 飲食等のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
- 広告宣伝費
- 会議費
- 取材費用
一方、運動会や演芸会に従業員や役員全員が参加するチャンスが与えられていなければ、福利厚生費として認められません。同じように法人保険の福利厚生プランでも、従業員や役員全員が加入していなければ普遍的加入として認められません。
普遍的加入として認められることで、従業員や役員の家族が受け取る「死亡保険金の1/2を損金算入」できます。そのため、法人保険の普遍的加入は、受取人に課税される税金を低く抑えるために重要であるといえます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人保険の普遍的加入で損金算入に関する3つのケース
会社が従業員や役員全員を法人保険の福利厚生プランに加入させようとしたとしても、会社の意思に関係ない何らかの理由で従業員が保険に加入できない場合もあります。
従業員が加入できない場合として、以下の3つが考えられます。
- 従業員の限度額のせいで加入できない場合
- 従業員の意思で法人保険の福利厚生プランに加入できない場合
- 従業員の病気で法人保険の福利厚生プランに加入できない場合
次から、この3つの場合には損金算入できるのかを詳しく解説します。
1. 従業員の限度額で加入できない場合
税法では、保険料の1/2を福利厚生費として損金算入するための要件として、生命保険などへの普遍的加入が定められています。
注意点として、生命保険には1人あたりにかけられる金額には限度額があるのです。
会社が、従業員や役員全員を保険会社Aの福利厚生プランに加入させようとしたとき、従業員の1人がすでに保険会社Aの生命保険に加入しており、その限度額に達していた場合は、その従業員のみ別の保険会社Bに加入させることで損金算入が認められます。
2. 従業員の意思で法人保険の福利厚生プランに加入できない場合
従業員が法人保険の福利厚生プランに加入することを拒否した場合を解説します。
特定の従業員のみを正当な理由もないのに福利厚生プランから外すと、普遍的加入が認められないので、損金算入されなくなってしまうのです。しかし、保険に加入するかどうかは個人の自由なので、会社としては加入を強制することはできません。
一方、上記ケースでも、本人が保険への加入を拒否したことを税務署が確認できる書類等があれば、損金算入が認められます。
3.従業員の病気で法人保険の福利厚生プランに加入できない場合
福利厚生費として損金算入するには従業員を生命保険に加入させる必要がある一方、従業員の1人に重い病気などが見つかれば、保険には加入できなくなってしまいます。
従業員の病気で法人保険の福利厚生プランに加入できないとき、1人の従業員が病気で加入できないだけで普遍的加入が認められないならば、大勢の従業員を抱える大会社は普遍的加入が難しくなるので不合理だといえます。
そこで、従業員が病気で加入できない場合でも、そのことが確認できる書類を税務署に提出すれば損金算入は認められるのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリアの公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
税務署に指摘されないように損金算入をするには
税務署に提出する「社内規程」を作成することで、損金算入が認められる可能性があがります。
従業員側の事情で法人保険に加入できない会社には責任がなく、仕方のないケースといえます。しかし、税務署に対して説明できなければ、普遍的加入ではないと指摘されてしまいます。
そこで、従業員側にこのような事情が生じた時のことを想定した「社内規定」をあらかじめ作成しておくと、税務調査のときに普遍的加入がなされていないと指摘される事態を回避しやすくできます。
また、本人が保険に加入したいと意思表示した場合や、病気が治ったなどで条件が変わったときは速やかに保険に加入させる必要があるので注意しましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人保険の効果的な活用方法が簡単にわかる方法とは
以下では、法人保険の効果的な活用方法が「無料で簡単にわかる方法」を紹介します。
法人保険を損金算入するには普遍的加入が求められますが、対象の保険である「養老保険」や「がん保険」は法定外福利厚生になるので、従業員を手厚く守れる分保険料が割高になりがちです。
また、自社に最適な保険は業態業種や事業フェーズによっても異なるので、一度加入した保険であっても保険料を過払いしている可能性もあることから、見直す必要があるのです。
しかし、重要な決断である「保険の見直し」を経営陣のみで判断するのは、加入ミスを誘発するうえに、長期的な目線で判断する必要があるのです。そこで、マネーキャリアのように法人保険のプロへ「納得できるまで何度でも相談できる」無料サービスを使うのが鉄則です。
丸紅グループ運営のマネーキャリアでは、独自のスコアリングで厳選された法人保険のプロが、自社の状況を総合的に判断しつつ「法人保険の活用方法の提案」に強みを持ち、80,000件以上の相談実績を誇ります。
費用対効果の高い「法人保険の活用方法」が無料でわかる:マネーキャリア(丸紅グループ)
お金に関する全ての悩みにオンラインで相談できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、法人保険のプロのみを厳選しています。
・保険だけではなく、総合的な事業リスクへの対策を踏まえて「自社の理想の状態を叶える」提案が可能です。
・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も80,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに 「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。
法人保険の「普遍的加入」や福利厚生プランまとめ
とはいえ、法人保険に加入していなければ、従業員に万が一のことがあった場合に、自社の預金から多額の補償金を出さなければならなくなったり、パフォーマンスの高い社員が長期間稼働できなくなったりするリスクに対応できなくなってしまうのです。
そこで、マネーキャリアのように、専門性の高い法人保険のプロとともに無料で相談しつつ、自社の事業リスクを着実に進める会社も増えているのです。
無料登録は30秒で完了するので、ぜひマネーキャリアを使い、自社の機会損失を法人保険でカバーできる環境づくりを進めましょう。

















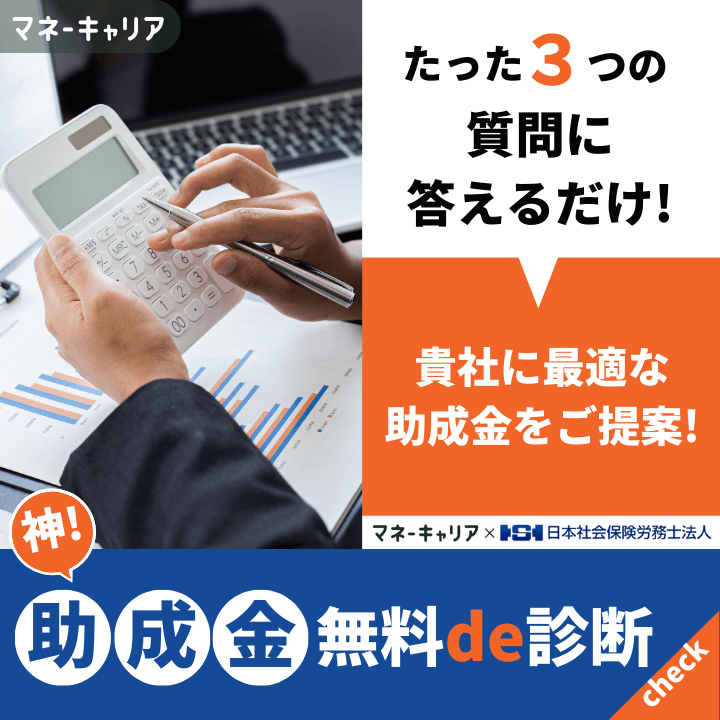
従業員や役員に支払う退職金や死亡保険金の準備として、法人保険の福利厚生プランへの加入を考える方も多いです。しかし、福利厚生プランに加入すれば、必ず損金算入が可能になるわけではありません。
法人が加入する養老保険の場合、役員や従業員が普遍的加入をしておかなければ損金に算入されず、本人に税金がかかってしまうのです。なかには、普遍的加入はもちろん、福利厚生プランにおいて自社が損をしない方法を探す方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、法人保険の普遍的加入や福利厚生プランの概要、注意すべき3つのポイントを中心にご紹介します。
・普遍的加入とはそもそも何か、自社が適切に対応できているのか知りたい
・普遍的加入のできる法人保険を見直し、費用対効果高く従業員の福利厚生も充実させたい
方は本記事を参考にすると、法人保険の福利厚生プランに加入する上で注意すべき点がわかるうえ、法人保険の活用方法を改めて見直すきっかけにもつながります。