
更新日:2024/08/06
法人保険の保険金受取人(個人と法人)をパターン別に解説
内容をまとめると
- 法人保険の保険金は、法人保険の受取人を個人にするか法人にするかで、税務処理や税金も変わってくるので正しく確認すること。
- 法人が受け取った解約返戻金・保険金は課税対象になり、法人契約・個人受取の場合は法人側での経理処理が不要となる。
- 受取人を個人のまま、契約者貸付制度を利用している場合は、被保険者が死亡したときにトラブルが発生する可能性が高い点に注意。
- 上記のように、法人保険の自社での取り扱いや見直しは専門知識を要するので、従業員とのトラブルを避けるためにも、専門家への相談が必須となる。
- そこで、法人保険のプロへ「無料で何度でも」リスク対策を相談できるマネーキャリアを使う会社が急増している。

目次を使って気になるところから読みましょう!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人保険の受取人を個人に設定することは可能?法人の保険契約の3パターンと課税対象
課税の基本的な公式は以下のようになります。
課税所得 = 益金ー(損金+特別控除)
保険料は会社の経費にできるので、上の公式のなかでは「損金」に算入できます。また、受取保険金は一時所得として益金に算入され基本的に課税対象になります。
しかし、受取人が誰かによって課税される税金の内容も変わるので、以下では法人の保険契約の3パターンと課税対象を説明します。
パターン①契約者:個人、受取人:個人
経営者が個人で生命保険に加入し、その経営者個人を受取人にする場合は、解約返戻金は一時所得として所得税の対象になります。
なお、一時所得に対する課税公式は以下になります。
一時所得 = 総収入金額ー必要経費ー特別控除(50万円)
また、一時所得による所得金額の1/2を他の所得と合計して、総合課税されることになります。総合課税の対象になる所得は計8つあります。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
パターン②契約者:法人、受取人:法人
法人が契約者として法人保険に加入し、受取人を法人にする場合に、法人が受けとった保険金は課税対象になります。
従業員に見舞金として支払う際には「社会通念上相当額」で約50,000円の支払いになってしまいます。また、仮に多額の見舞金を支払った場合は、「給与」とみなされ所得税がかされる場合があるので注意が必要です。
また、解約返戻金を法人が受け取った場合には、「雑収入」として益金に計上され、法人にお金が入るため、法人保険の課税対象となります。
このように法人が解約返戻金などを受け取った場合、法人税がかかるので個人の受取金に課税の場合と比較して支払税額が高額になるケースが多いです。
もし、法人で解約返戻金などを受け取る際は、益金と相殺できる損金計上の退職金などをあらかじめ用意しておくことが重要です。
パターン③契約者:法人、受取人:個人
法人が被保険者を従業員として養老保険に加入していて、従業員が死亡した場合
| 契約者 | 死亡保険金受取人 |
|---|---|
| 法人 | 従業員の遺族 |
このようなケースでは、保険料は給与として支払われたと処理されることになるため、法人の経理処理は必要になりません。
ただし、資産計上されている配当金積立金がある場合には、その額を取り崩し雑損失として損金処理します。そして、従業員の遺族が受け取る保険金は一時所得になるので、所得税の課税対象になります。
上記の場合、これまで給与として課税されていた支払保険料を、収入を得るために支出していた金額として控除できます。
法人が養老保険に被保険者および受取人を当該法人の社長に設定し、満期を迎えた場合
| 契約者 | 満期保険金受取人 |
|---|---|
| 法人 | 経営者 |
このようなケースでは、上記と同じく支払っていた保険料は給与として処理されるため、法人の経理処理は必要ありません。一方、社長が受け取った満期保険金は一時所得となります。
この場合も上記と同じく、これまで給与として課税されていた支払保険料を、収入を得るために支出していた金額として控除できます。
例外
被保険者に特定の役員や従業員のみが加入するのではなく、要件を満たす全役員および全従業員が加入する場合(普遍的加入)であれば、一種の福利厚生とみなされ法人の損金へ算入できます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人保険の法人契約・個人受取の場合の注意点
法人保険の法人契約・個人受取の場合の注意点としては以下の2つがあげられます。
- 法人保険の支払保険料の経理処理の精査および適切な処理が必要
- 法人保険の活用に伴って、法人が契約者貸付を受けている場合
1の「法人保険の支払保険料の経理処理の精査および適切な処理」に関しては、法人が保険を契約し受取人として保険金などを受け取るケースの場合は、保険料を経費とし、損金算入をして、受け取った保険金に一時所得として所得税が課税される仕組みです。
しかし、法人保険の法人契約・受取人が個人の場合、基本的に経費として損金算入できず「給与処理」となるので、トラブルとならないように注意しましょう。
2の「法人保険の活用に伴って法人が契約者貸付を受けている」に関しては、たとえ保険料が給与として処理されている場合であっても、契約者が法人である以上、契約継続中は会社は自由に契約者貸付制度を利用できます。
そのため、被保険者である個人の死亡による契約者貸付の精算時などにトラブルになる可能性があるので、保険金などの受け取りに支障が出る可能性がある点に注意しましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人保険を含む事業リスク対策が無料で簡単にわかる方法とは
以下では、法人保険を含む事業リスク対策が「無料かつ簡単」にわかる方法を紹介します。
法人保険の保険金受取人は個人・法人いずれでも設定可能ですが、課税対象が異なるので、経理処理には注意しなければなりません。また、法人保険は定期的に見直すべきであり、独断で決めた法人保険の保険料が、実は高額になっていたケースもあるのです。
一方、リスク対策には法人保険が必須なものの、専門知識が必要になるので、正しく活用できているのかの判断はプロと一緒に見直す必要があります。
そこで、法人保険のプロへ「無料で何度でも」相談できるマネーキャリアを使って、自社の保険の活用方法を見直す会社も急増しているのです。
丸紅グループ運営のマネーキャリアでは、借入金や事業承継対策など、事業運営に関わるあらゆる事業リスクに対して、80,000件以上の相談実績から得た「法人保険を活用するノウハウ」を自社の状況に合わせてオーダーメイドな提案が可能です。
法人保険に関するあらゆる悩みを解消できる:マネーキャリア(丸紅グループ)
法人保険契約の個人受け取りと課税についてのまとめ
ここまで、法人保険の受取人を個人・法人に設定した際の課税に関する内容や注意点を解説しました。
法人保険の保険金は、受取人の種類によって課税される税金の内容が異なります。法人が受け取った解約返戻金・保険金は課税対象になり、法人契約・個人受取の場合は法人側での経理処理が不要となります。
上記のように、法人保険の受取人を個人にするか法人にするかで、税務処理や税金も変わってくるので正しく確認することが大切です。一方、法人保険の自社での取り扱いや見直しは専門知識を要するので、従業員とのトラブルを避けるためにも、専門家への相談が必須です。
そこで、法人保険に関する情報が少ないなかでも、自社の法人保険を最大限活用するには、法人保険のプロへ「無料で何度でも」リスク対策を相談できるマネーキャリア一択です。
無料登録は30秒で完了するので、ぜひマネーキャリアを使い、万が一のリスクへも強い会社にする準備を進めましょう。





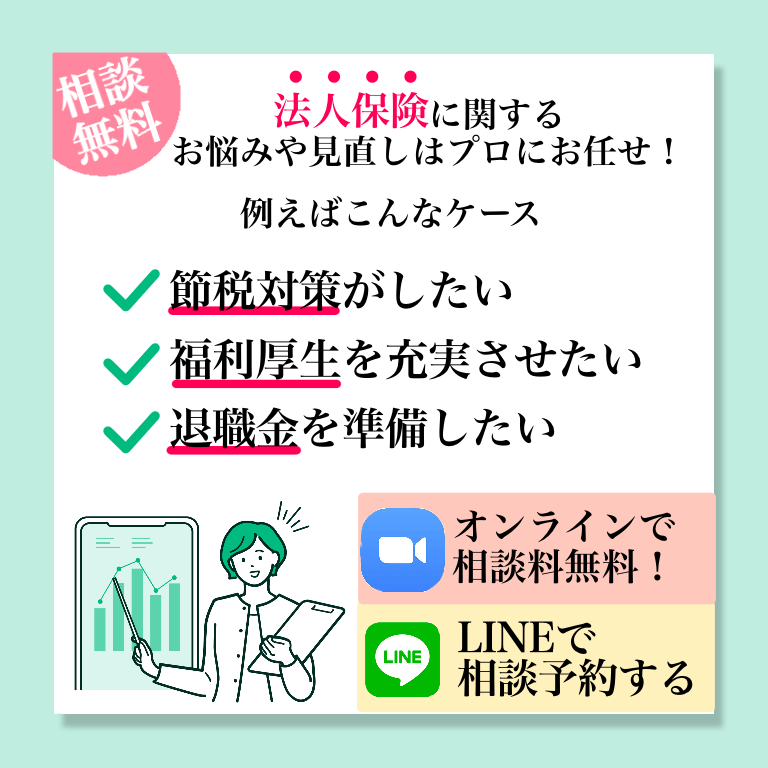
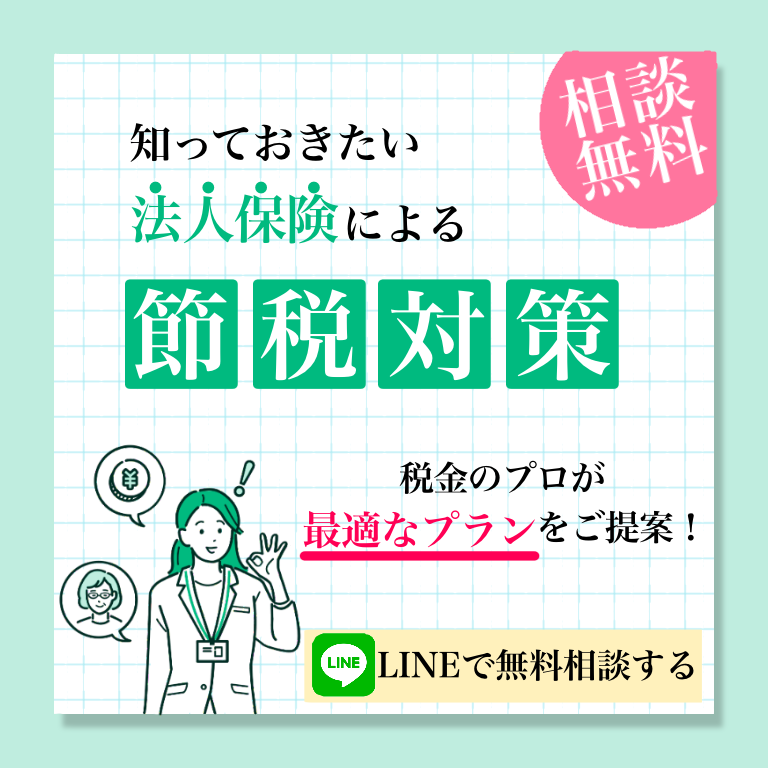














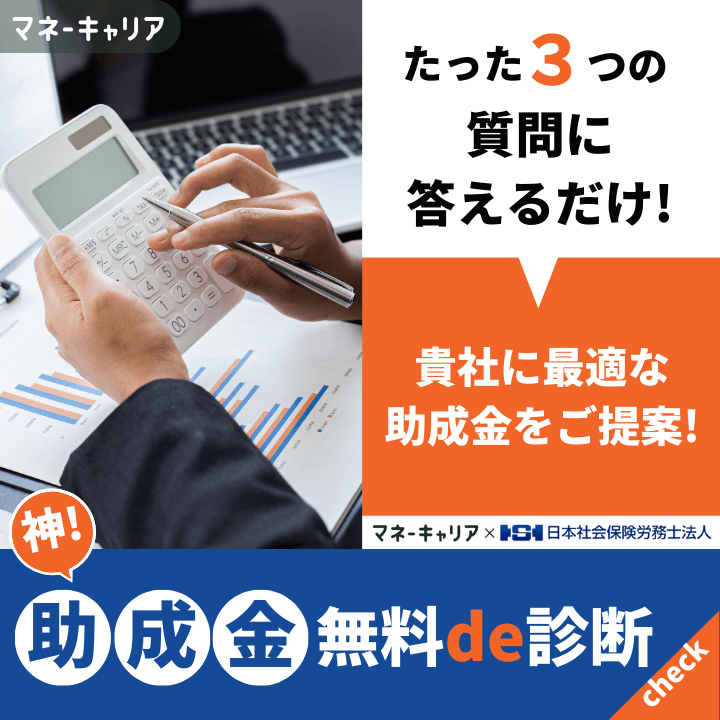
法人保険において適切な受取人は、個人なのか法人なのかできるケース、できないケースがあります。保険金の受取人によっては、支払う税額が変わるにも関わらず、自社にあった適切な受取人を設定していない法人が多いのが現実です。
一方、契約形態や注意点について確認しないままでは、渡せるはずの保険金や見舞金に対しても税金がかかってしまう可能性があるのです。そのため、法人で契約した法人保険の受取人を「個人」「法人」のいずれが良いかに悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「法人保険金の受取人と注意点」を中心に、法人の保険契約の3パターンと課税対象などを解説します。
・法人保険の保険金の受取人を個人にすべきか法人にすべきかがわからない
・税負担の軽減と自社のリスク対策を両立したい
方は本記事を参考にすると、法人保険の受取人をいずれに設定すべきかの正しい判断ができるうえ、法人保険を最大限活用する方法もわかります。