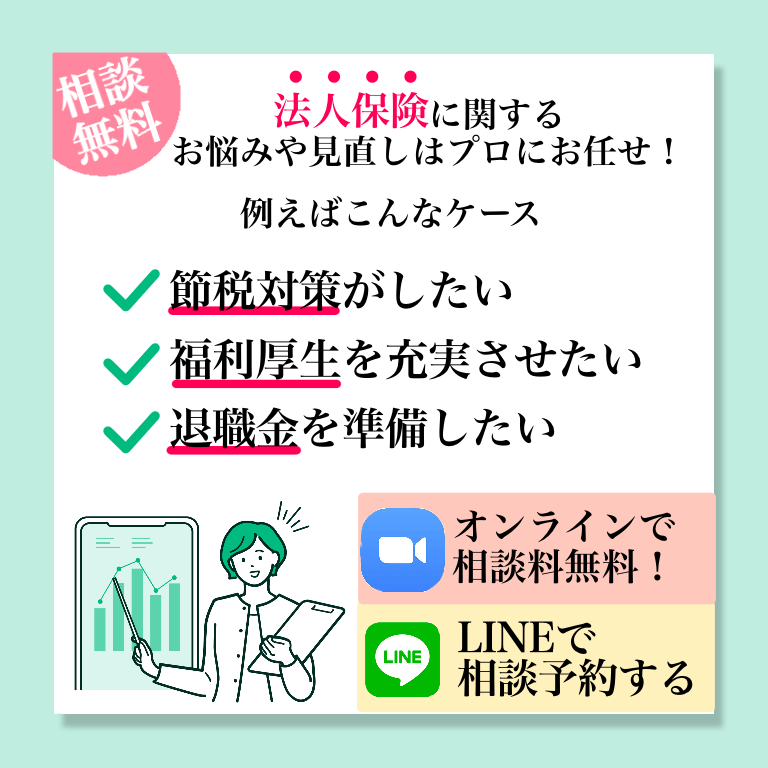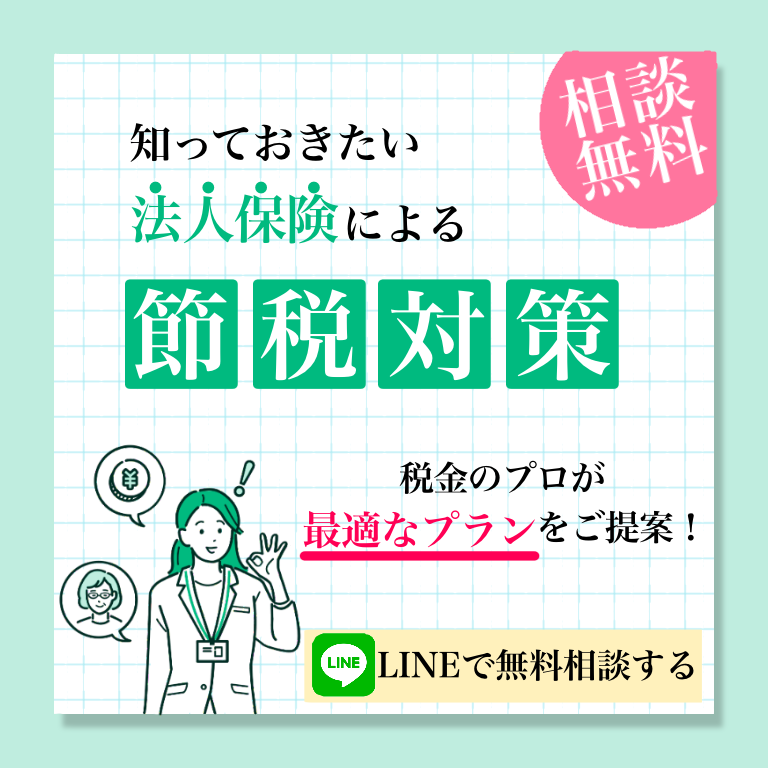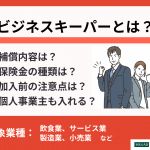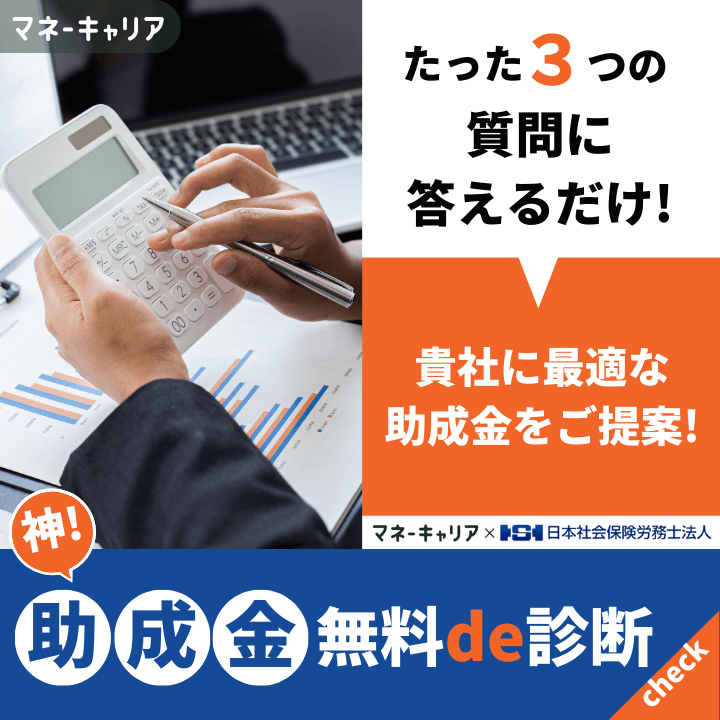更新日:2024/08/06
法人保険は節税効果なし?法人保険の本当の活用法をプロが直伝
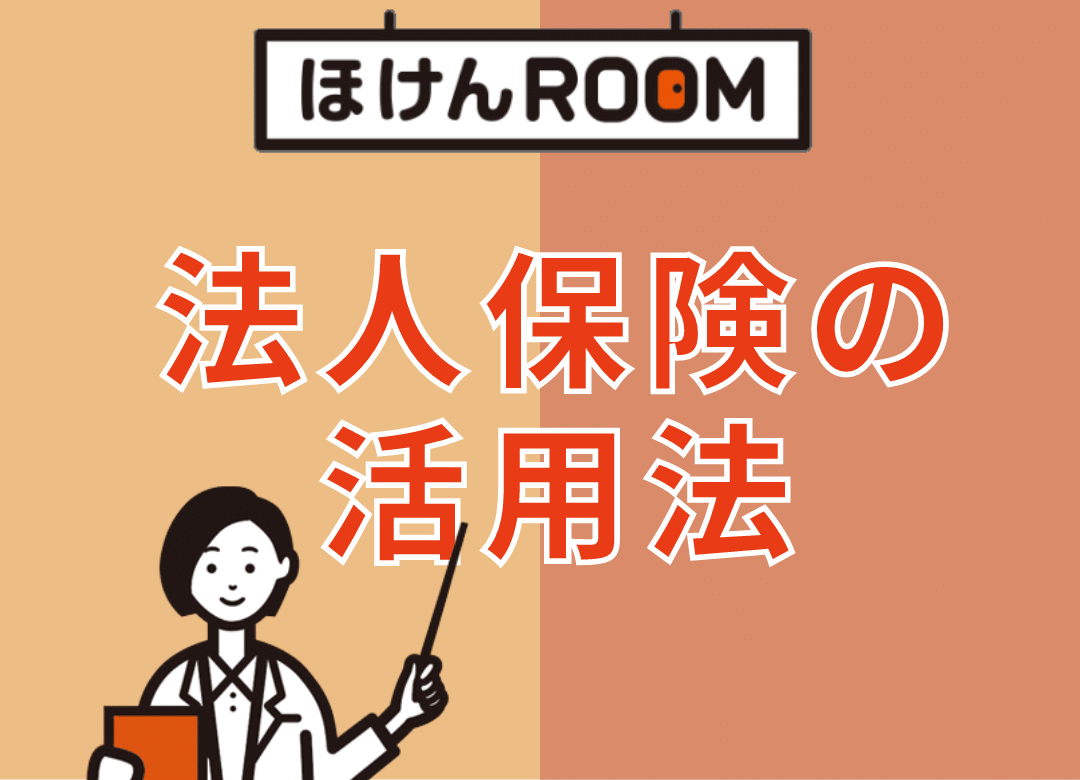
内容をまとめると
- 法人保険の保険料は損金として計上できるので理論上は減税されるが、2019年の税制改正によって保険商品を介した節税効果は無くなった。
- そのため、綿密な計画を立てて加入することが重要、かつ法人保険は保障内容や貯蓄性を重視して選ぶべきである。
- しかし、最適な法人保険を選ぶには専門知識が不可欠であり、今日では法人保険の選び方や悩みなどを法人保険のプロへ、無料で何度でも相談できるマネーキャリアを活用する会社が急増している。

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 「法人保険で節税ができる」と言われる仕組みを詳しく解説
- 「節税ができる」は課税を繰延しているだけ
- 【基礎知識】法人税の計算方法〜保険の損金算入例
- 法人保険を福利厚生費として計上した例
- 長期平準定期保険を活用した例
- 法人保険で税金対策を考えている人が知っておくべき注意点
- ①高額な保険料分のキャッシュが手元からなくなる
- ②解約返戻金で戻ってくる金額が100%未満の可能性がある
- ③保険解約時の出口戦略を考えて加入する
- ④単純返戻率と実質返戻率について
- 法人保険の税効果のシミュレーション
- 国税庁による節税目的の保険商品の規制
- 法人保険の「正しい5つ」の加入目的
- 法人保険以外の企業が検討するべき税金対策とは
- ①経営セーフティ共済〜事業保障への備え
- ②役員社宅制度〜福利厚生への備え
- ③小規模企業共済〜退職金への備え
- 個人事業主・宗教法人・学校法人の場合の法人保険での節税方法
- 個人事業主の法人保険を用いた節税
- 宗教法人・学校法人の法人保険を用いた節税
- 自社に最適な法人保険の本当の活用方法がすぐにわかる方法とは
- 法人保険やリスク対策の悩みを無料で解消:マネーキャリア(丸紅グループ)
- 法人保険の節税効果に関するまとめ
目次
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「法人保険で節税ができる」と言われる仕組みを詳しく解説
 法人保険で節税ができるといわれるのは、会社経営者や経理が「法人税」を減らすために、損金(経費)を増やして課税対象額を減らせるからです。
法人保険で節税ができるといわれるのは、会社経営者や経理が「法人税」を減らすために、損金(経費)を増やして課税対象額を減らせるからです。
2019年以前までは、「法人保険に加入すれば会社が支払う保険料は経費になるので、節税ができる」と言われます。
保険料のうち経費にできる割合は種類によって異なるものの、「全損」タイプの場合は保険料を全額「損金(経費)」に算入できます。そして、支払った保険料は将来特定のタイミングで解約すれば、高い返戻率で解約返戻金として戻ってきます。
よって法人保険に加入した結果、
- 年間の所得が減ったので、法人税も減った
- 支払った保険料も解約時に戻ってきたので、損はしていない
このようなメリットがあると考えられ節税効果があるように感じられてしまうのです。
「節税ができる」は課税を繰延しているだけ
法人保険による節税の仕組みとして、法人保険料として支払った分の金額を損金として、当該年度の所得から控除できることが大きく関わっています。
法人税の計算である「所得×法人税率」で求めたときに母数が減ることで、法人の課税金額が軽減する効果が生まれます。
また、法人保険では、全額損金タイプや1/2損金タイプといった損金算入の割合の種類を選ぶことも可能です。法人保険料を支払い続けることで解約した際に解約返戻金も得られます。
解約返戻金は契約をしたときから徐々に金額が上がり、最も高いときに解約をすれば大きな金額が返還されます。なかには支払った保険料以上の金額を最終的に払い戻してくれる保険会社もあります。
しかし、実際には「法人税は節税できません」。なぜなら、保険料を受け取る際に課税されるからです。すなわち、課税のタイミングを遅らせているだけに過ぎないのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【基礎知識】法人税の計算方法〜保険の損金算入例
ここで、法人税の計算の仕組みを把握しておきましょう。法人税の計算は、下記の計算式で求められます。
- 法人税=会社の利益×法人税率
会社の利益とは、1年間の売り上げから、給料などの経費を全額引いたものです。この利益に、「法人税率」をかけたものが、法人税になる計算です。
法人税は、「資本金の額」と「会社の利益」によって異なります。
【資本金が1億円位以下の法人】
| 利益金額 | 法人税率 |
|---|---|
| 400万円未満 | 21.43% |
| 400万以上800万円未満 | 23.21% |
| 800万円以上 | 33.58% |
【資本金が1億円以上の法人】
| 利益金額 | 法人税率 |
|---|---|
| 400万円未満 | 28.31% |
| 400万円以上800万円未満 | 29.03% |
| 800万円以上 | 29.74% |
例えば、
- 資本金2000万円
- 利益金額500万円
- 500万円×23.21%=約116万円
- 500万円×29.03%=約145万円
法人保険を福利厚生費として計上した例
法人保険の福利厚生プランでは、養老保険や年金保険に加入することで、保険料の10分の1から半分を福利厚生費にできます。
福利厚生費として認められると、法人税の課税対象外となり、支払う法人税を少なくできます。例えば、
- 資本金 2000万円
- 利益金額 500万円
- 福利厚生型養老保険200万円
上記の場合、法人税は
- (500万円ー200万円×1/2)×23.21%=約93万円
という計算になり、保険料支払時の税負担が23万円程抑えられます。
ただし、福利厚生費として認められるためには、「原則として従業員の全員が加入しなければならない」(普遍的加入)の条件があります。
また、従業員の全員が加入しなければならないのはあくまでも原則であり、例外的に全員の加入が必要でない場合があります。例外とは、職種や勤続年数、年齢といった条件に応じて合理的な基準によって設けられた普遍的な格差である場合です。
たとえば、新入社員は保険に加入してもすぐに退職してしまう可能性があるため、「勤続年数5年以上であれば保険に加入できる」といった条件は合理的な基準であると認められるのです。
長期平準定期保険を活用した例
長期平準定期保険とは、保険期間の満了時期を90歳や100歳といった長期に設定した定期保険のことです。
満期保険金は受け取れない代わりに、解約返戻率が高く、ピーク時に高額な解約返戻金を受け取れるのが長期定期保険の特徴です。ただし、長期平準定期保険の場合は「全額損金算入」ができなくなるので注意しましょう。
そのため、長期平準定期保険では、勇退時期が流動的な中小企業経営者の退職慰労金の原資に適した保険です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人保険で税金対策を考えている人が知っておくべき注意点

法人保険への加入を考えているなら、ポイントとなるのは、「最終的に損益はどうなるか」です。
節税メリットだけ考えてこのポイントを見逃すことが多いので、以下の事項を解説します。
- 保険料によるキャッシュフローへの影響
- 解約返戻金の返戻率
- 解約時の出口戦略
- 単純返戻率と実質返戻率について
- 年間保険料:300万円
- 税率:30%
- 保険期間:10年
①高額な保険料分のキャッシュが手元からなくなる
保険料を支払う場合、その分だけ現金が無くなる(=キャッシュでの資金が減る)ことです。
法人保険に加入し年間300万円の保険料を支払えば、一時的に損金算入ができたとしても、キャッシュは確実に減るため資金繰りは悪化します。
②解約返戻金で戻ってくる金額が100%未満の可能性がある
支払った保険料は、全額戻って来るとは限りません。
法人保険は支払う保険料は実質積み立てられているもので、将来的に受け取れるものです。
しかし、保険商品ごとに設定された最高解約返礼率だけ、保険料が戻ってくることからも、返戻率が100%未満の保険に加入して、税金対策のためだけに300万円もの保険料を10年間支払うメリットはありません。
また、最高解約返戻率のピークを過ぎると、解約返戻金は少なくなる点にも注意が必要です。
③保険解約時の出口戦略を考えて加入する
法人保険の解約返戻金を法人名義で受け取ると、益金に算入されるので法人税の課税対象になってしまいます。
法人税を節税するために法人保険に加入したのに、受け取った解約返戻金に法人税を課税されてしまったら本末転倒です。
そこで、受け取った解約返戻金が損金算入されるように、出口戦略を考えておく必要があります。出口戦略としては、以下のような例が挙げられます。
- 従業員や役員の退職金
- 従業員や役員のボーナス
- 事業承継時の準備資金
- 設備投資費
④単純返戻率と実質返戻率について
「単純返戻率」とは、支払った保険料の総額に対し、解約時に戻ってくる返戻金の割合を指します。
「実質返戻率は」、法人保険の加入により発生した節税金額を加味した、返戻金の割合のことであり、「法人税の軽減額」を含めた金額で返戻金が計算されるものです。
最初にあげた例にプラスして、10年後の解約時、単純返戻率が80%だった場合
- 300万円×10年間=3,000万円(=実際に支払った保険料の総額)
- 3,000万円×80%=2400万円
単純返戻率の場合、2400万円が手元に返ってくる計算です。
10年間で支払った保険料の総額は3,000万円なので、10年間以下の金額を節税できたことになります。
- 3,000万円×30%(=税率)=900万円
節税できた900万円を加味した、実質保険料の総額は、
- 3,000万円ー900万円=2,100万円
この金額を踏まえ、実質返戻率を計算すると、
- 解約返戻金額÷実質支払保険料総額(=節税を加味した金額)× 100=実質返戻率
- 2,400万円÷2,100万円×100=114%
一般的に「解約返戻率」は「単純返戻率」のことを指しますが、法人保険は、単純返礼率で見ることが重要です。解約返戻率には、「単純返戻率」と「実質返戻率」の2つがあることを把握しておく必要があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人保険の税効果のシミュレーション

以下では、節税になるのかどうかを再度シミュレートすると、益金を3,000万円として、法人保険に加入しない場合は以下のようになります。
- 3,000万円(益金) ✕ 30%(税率) = 900万円(年間税額)
- 900万円(年間法人税) ✕ 10年 = 9,000万円(総税額)
- 3,000万円(益金) ー 300万円(保険料) = 2,700万円(課税対象)
- 2,700万円(課税対象) ✕ 30%(税額) = 810万円(年間税額)
- 税金① 810万円(年間法人税) ✕ 10年(解約まで) = 8,100万円
- 税金② 3,000万円(解約返戻金) ✕ 30%(税額) = 900万円
- ① + ② = 9,000万円(総税額)
上記のように、法人保険は加入中のキャッシュフローから出口戦略まで綿密な計画を組んでから加入しなければなりません。そのため、マネーキャリアのように、保険のプロと相談しながら加入を決める会社も急増しているのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国税庁による節税目的の保険商品の規制

今までは事業保障ではなく、「節税のメリット」が打ち出されていた保険を、過去には多くの保険会社が販売していました。
しかし、それらは保険商品が持つ本来の目的を逸脱することになったため、国税庁により幾度も規制されてきました。
規制対象となった保険には、
- 長期傷害保険:損金算入可能額は4分の1
- 逓増定期保険:損金算入可能額は2分の1
- 法人向けがん保険:損金算入可能額は2分の1
 詳しい法人保険の経理処理方法はこちら
詳しい法人保険の経理処理方法はこちらーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人保険の「正しい5つ」の加入目的
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人保険以外の企業が検討するべき税金対策とは
そもそも、法人保険は「節税」のために加入すべきものではなく、事業資金や経営の保障、福利厚生などに活用されるのが本来の目的です。
しかし、「保険以外に課税金額を減額できるものはないか」のニーズがあることも事実なので、以下では法人保険以外に、会社でできるおすすめの対策をご紹介します。
①経営セーフティ共済〜事業保障への備え
経営セーフティ共済は、取引先の急な倒産によるリスクに備えた中小企業倒産防止共済制度を活用できるものです。
中小企業倒産防止共済制度とは、取引先の急な倒産による、連鎖倒産や経営難に陥るリスクを防ぐ制度です。
加入するメリットの一つに、借り入れを無担保・無保証で受け取れることが挙げられます。借入れまでのスピードも早いので、 取引先の急な倒産で経営悪化に陥った場合も安心して事業を進められます。
また、掛金は月々5,000円〜20万円までを自由に選択可能であり、掛金は「損金」として算入できるため、節税効果を期待できます。
解約しても、「解約手当金」が受け取れるもの魅力のひとつです。掛金を40ヶ月以上納めていた場合は、「掛金の全額」が手当金として返ってきます。
②役員社宅制度〜福利厚生への備え
役員社宅制度とは、企業で契約した住宅を役員へ貸し出し、役員から家賃を支払ってもらう制度のことを指します。
この制度が、「税金対策」と言われる理由は、大きく2つあります。
- 1つ目は、企業側は支払う家賃と役員が支払った家賃の差額を「地代家賃」として経費にできること。
- 2つ目は、役員の引っ越し費用や賃貸契約の手数料なども経費へ計上できること。
つまり、役員社宅制度を導入することで、社宅に関する経費が増えるのです。経費が増えると、利益減少につながるため効果が期待できる仕組みです。
また、経費を増やすだけなく、役員の手取りが増えることもメリットです。役員の社宅の使用料は、給与から差し引かれるため課税額を抑えられます。
上記のように税金がかからない分、手取り金額も増える仕組みです。企業側が負担する、社会保険料も抑えられるメリットが生まれるのです。
③小規模企業共済〜退職金への備え
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
個人事業主・宗教法人・学校法人の場合の法人保険での節税方法
ここでは下記の会社法人以外の3つの法人の場合における節税のための法人保険活用法を紹介します。
- 個人事業主
- 宗教法人
- 学校法人
個人事業主の法人保険を用いた節税
個人事業主は法人ではないので、法人契約での保険に加入できません。
しかし、個人事業主でも従業員を雇用している場合は、従業員を養老保険に加入させ、保険料の1/2を損金算入可能です。
そのとき、満期保険金の受取人は事業主でも問題ありません。しかし、死亡保険金の受取人は従業員の遺族を指定しなければなりません。
会社法人では、死亡保険金の受取人を法人にできるので、上記の点が異なっています。
宗教法人・学校法人の法人保険を用いた節税
宗教法人と学校法人は、法人税法上「公益法人」に分類され、営利を目的としない「非営利型法人」とされています。
公益法人の場合、一般的に言えば所得に対して課税されることはありません。しかし、収益を上げることを目的に行った事業によって所得が生じた場合には課税されます。
営利を目的とする会社法人の場合、公益法人とは異なり、収益事業かどうかに関係なくすべての所得に課税されます。
そのため、宗教法人と学校法人でも、収益事業から生じた所得が大きくなってしまった場合は、法人保険に加入することで節税ができます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自社に最適な法人保険の本当の活用方法がすぐにわかる方法とは
以下では、自社に最適な「法人保険の活用方法」が簡単にわかり、実践できる方法を紹介します。
2019年の税制改正により、法人保険の節税効果は大幅に減少しました。加えて、法人保険は種類が多様で、各社の事業内容に合わせた最適な保険を選ぶことが難しくなっています。
そのため、保険料のコストを抑えつつ、必要な保障を得るための「最適な法人保険の活用」には、専門的な知識が不可欠です。さらに、インターネット上における法人保険の情報は、各保険会社の保険商品がほとんどであり、情報が少ないのが現状です。
そこで、今日では「法人保険のプロに無料で何度でも」相談ができるマネーキャリアのようなサービスを使う会社が急増しているのです。
マネーキャリアの法人保険の専門家は、80,000件以上の相談実績を持ち、98.6%の高い満足度を誇ります。経営者の事業内容や予算に合わせて、最適な法人保険プランの提案に強みがあることからも、悩みをすぐに解消できます。
法人保険やリスク対策の悩みを無料で解消:マネーキャリア(丸紅グループ)
法人保険に関する全ての悩みにオンラインで相談できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、法人保険のプロのみを厳選しています。
・保険だけではなく、総合的な事業リスクへの対策を踏まえて「自社の理想の状態を叶える」提案が可能です。
・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も80,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに 「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。
法人保険の節税効果に関するまとめ

今回は法人保険に関して網羅的に紹介しました。
法人保険の保険料は損金として算入できるので理論上は減税されます。しかし、以前ほどの節税対策は見込めないので、綿密な計画を立てて加入することが重要です。
また、法人保険は保障内容や貯蓄性を重視して選ぶ活用方法もあります。一方で、自社に最適な法人保険の活用方法やリスク対策を経営陣のみで判断するのは困難であり、専門知識が必要です。
そのため、マネーキャリアのように、「法人保険のプロ」が無料で何度でも相談を受け付けている相談窓口を使うのが必須なのです。マネーキャリアを使うことで、保険に関する悩みを解消できた実績は80,000件以上にも上ります。
無料相談予約は30秒で完了するので、ぜひマネーキャリアを使い、自社に最適な法人保険の活用方法に関するアドバイスをもらいリスクに強い環境を整えましょう。