
更新日:2024/08/06
法人契約の個人年金保険とは?保障内容と経理処理も解説
内容をまとめると
- 法人向けの個人年金保険は、死亡保険金・年金の受取先によって経理処理と税務効果が変わります。
- また、保険料の一部を損金に算入できるが、2019年の税制改正によって以前ほどの節税効果は無くなっている。
- 年金受取を被保険者・死亡保険受取を法人にした場合、保険料の90%は資産計上、残り10%を損金に算入できるといった、細かな経理処理が必要になります。
- 個人年金保険は、退職金準備ができるなどのメリットがあるが、インフレ時に支払い保険料より年金額が下回る可能性がある。
- 個人年金保険が自社にとって最適な保険であるかは、専門的知識や自社の状況にもよるので、マネーキャリアのように「無料で何度でも」リスクや福利厚生対策を相談できるサービスを使う会社が急増している。

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 個人年金保険とは?
- 法人契約と個人契約との違い
- 法人契約で個人年金保険に加入するメリット・デメリットは?
- 【メリット】保険料の損金算入などで多少の税務効果が得られる
- 【デメリット】退職した従業員が増えると経理処理が大変になる
- 個人年金保険にかかる保険料の経理処理とは
- ケース①:保険金受取・年金受取を法人とした場合
- ケース②:保険金受取を被保険者・被保険者の家族にした場合
- ケース③:年金受取を被保険者・死亡保険金受取を法人にした場合
- 年金受取前に被保険者の従業員が退職した場合
- 法人が年金を受け取ったときの経理処理とは
- 「自社に最適な法人保険」の悩みを簡単に解消できる方法とは
- 法人保険のプロと「従業員を守る環境構築」を実現:マネーキャリア
- 法人契約の個人年金保険の概要や経理処理のまとめ
目次
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
個人年金保険とは?
個人年金保険は民間の保険会社が取扱し運用していることから、若干の違いがあるものの「確定年金」や「終身年金」に分類されます。
また、日本の年金制度は「公的年金」と「(公的年金の補完のための)私的年金」の2種類に分かれます。
- 公的年金:国民年金、厚生年金
- 私的年金:確定拠出年金、確定給付企業年金、個人年金保険等
国民年金の公的年金だけでは、老後資金の対策として不十分なので、私的年金を活用し、上乗せして給付の保障を行います。
保険商品それぞれが違い、任意加入となっています。そのため、個人年金保険は保険料や年金額などに違いがあることから、自由度が高く、選び方次第で将来へのリスク対策に差が出るのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人契約と個人契約との違い
法人契約と個人契約の違いは、年金の扱い方が異なる点です。
個人契約で年金を受け取った場合は所得税や贈与税がかかりますが、法人契約で受け取った場合は益金に算入し、保険積立金を一定の割合を乗じて損金に算入します。
法人契約の個人年金保険は、従業員の老後資金の対策を行えること、会社の福利厚生の充実をはかりつつ、一部税制優遇を受けることが可能といった点がメリットです。
法人契約と個人契約いずれも、年金支払い日に被保険者が生存している場合は、定められた期間にわたって年金が支払われます。同日前に死亡・または高度障害になった場合は、死亡給付金が支払われます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人契約で個人年金保険に加入するメリット・デメリットは?
ここでは、法人契約での個人年金保険に加入する場合のメリットとデメリットを解説します。
個人年金保険を企業で加入する場合、経営者のみ加入ができるものの、税制優遇を受けることができません。社員全員加入の福利厚生(普遍的加入)としていなければ、税制優遇をうけられなくなってしまいます。
そのため、正しく個人年金保険を活用できている会社は、以下のメリット・デメリットを正しく把握しているのです。
【メリット】保険料の損金算入などで多少の税務効果が得られる
法人契約で個人年金保険に加入するメリットは3つあります。
- 法人税の減税
- 社会保険料の減額
- 途中退職や死亡退職の退職金準備
 法人保険の節税効果
法人保険の節税効果【デメリット】退職した従業員が増えると経理処理が大変になる
 法人保険の経理処理方法
法人保険の経理処理方法ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
個人年金保険にかかる保険料の経理処理とは
以下では、個人年金保険にかかる保険料の経理処理のパターンを解説します。
個人年金保険を法人契約にすると、保険金受取と年金受取がどこになるかで支払い保険料の経理処理が変わります。
- 死亡保険金受取・年金受取が法人
- 死亡保険金受取・年金受取が被保険者・被保険者の家族
- 死亡保険金受取を法人、年金受取を被保険者
の3パターンで分かれ、どのパターンになるかで税務効果も変わり、法人で個人年金保険を契約する際は最適なものを選択する必要があります。
ケース①:保険金受取・年金受取を法人とした場合
保険金受取・年金受取を法人とした場合は、支払保険料は保険積立金などの「資産計上」となります。
たとえば、500万円を保険料で積み立てる場合は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 保険料積立金 500万円 | 現金・預金 500万円 |
1000万円の死亡給付金の支払いを受けた場合は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 現金・預金 1000万円 | 保険料積立金 1000万円 |
個人年金保険は貯蓄性が高いですが、法人が年金受取人になる場合は損金算入ができません。
ただし、個人年金保険は返戻率が100%を超えることも少なくなく、銀行などの定期預金より高い利息が受け取れる場合もあります。
定期預金より高い利息が欲しい場合は、個人年金保険の受け取りを法人にするのも選択肢として挙げられます。
ケース②:保険金受取を被保険者・被保険者の家族にした場合
保険金受取人・年金受取人が被保険者や被保険者の家族の場合は、「給与」として扱われます。
たとえば、500万円を保険料として支払う場合は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 給与 500万円 | 現金・預金 500万円 |
死亡給付金や年金の支払い時には、法人側での経理処理はありません。
給与扱いになる理由は、個人年金保険は貯蓄性が高く「保険料を法人が負担することは、現金を支給しているのと変わらない」と判断されるためです。
ケース③:年金受取を被保険者・死亡保険金受取を法人にした場合
年金受取を被保険者に、死亡保険金受取を法人にした場合は、保険料の10分の9を資産計上し、残りの10分の1を福利厚生費へ損金算入します。
たとえば、500万円を保険料として支払う場合は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 保険積立金 450万円 | 現金・預金 500万円 |
| 福利厚生費 50万円 |
支払った保険料の一部が損金として扱われるので、節税しながら従業員への年金対策を行うことができます。
ただし、被保険者が役員のみなど特定の者だけの場合は、支払う保険料が「全額給与」として扱われるので注意が必要です。
年金受取前に被保険者の従業員が退職した場合
年金受取前に被保険者が退職した場合、その個人年金保険を退職者へ契約者変更すると、解約返戻金相当額の退職金として取り扱います。
たとえば、解約返戻金が300万円の場合は以下になります。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 退職金 300万円 | 保険積立金 300万円 |
個人年金保険の解約返戻金は、加入年月が長いほど解約返戻率も高まりますが、加入後2年ほどは解約返戻率が著しく低くなってしまいます。
従業員や役員を被保険者にするなら、退職金についてのトラブルを避けるためにも、途中解約時の解約返戻金の変化について説明しておきましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人が年金を受け取ったときの経理処理とは
従業員の退職後、法人が年金受取人として年金を受け取った場合の経理処理は、今まで積み立ててきた保険料積立金と配当金積立金を、年金積立保険料として振り替えます。
▼支払った保険料の合計が1,000万円の場合
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 年金積立保険料 1,000万円 | 保険料積立金 1,000万円 |
年金を受け取ったときは、年金積立保険料から金額を取り崩し、受取金額との差額に配当金の額を合算し、雑収入として益金に算入します。
▼20年確定年金で、年金の年額が80万円の場合
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 普通預金 80万円 | 年金積立保険料 50万円 |
| 雑収入 30万円 |
従業員が退職し、法人が年金を受け取った場合の経理処理はこちらです。
▼年金受取額が300万円の場合
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 現金・預金 300万円 | 年金積立保険料 220万円 |
| 雑収入 80万円 |
続いて、法人が退職した従業員へ年金を支払う場合は、その金額を退職年金として損金算入が可能です。
また、源泉徴収税額分は預かり金となります。
▼年金受取額が300万円の場合
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 退職年金 300万円 | 普通預金 220万円 |
| 預かり金 80万円 |
退職した従業員数が増えると「経理処理の計算数」が増えてしまうのが、個人年金保険を法人契約した場合の問題といえます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適な法人保険」の悩みを簡単に解消できる方法とは
以下では、自社に最適な法人保険を「無料で簡単に選定できる方法」を紹介します。
個人年金保険を含む法人保険は従業員の保障や老後の生活資金を確保する目的で用いられますが、以前ほどの節税効果が見込めなくなったうえ、解約返戻金の解約時期によっては支払った保険料を下回る可能性があります。
そのため、解約返戻金や損金算入を目的に法人保険を活用するのではなく、本来の目的である「万が一のリスク対策」に重きを置いて保険の見直しをしなければならないのです。
しかし、現状の業績や事業内容、キャッシュフローの計画などは会社によって異なるので、経営陣のみで法人保険を決定するのは困難です。そこで、法人保険の専門家に「無料で何度でも」相談できるマネーキャリアを使うのが必須です。
リスク対策をはじめとした「理想の環境」を実現するマネーキャリアでは、80,000件以上の提案実績があり、満足度も98.6%を誇ります。
法人保険のプロと「従業員を守る環境構築」を実現:マネーキャリア
お金に関する全ての悩みにオンラインで相談できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、法人保険のプロのみを厳選しています。
・保険だけではなく、総合的な事業リスクへの対策を踏まえて「自社の理想の状態を叶える」提案が可能です。
・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も80,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに 「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。
法人契約の個人年金保険の概要や経理処理のまとめ
ここまで、個人年金保険の内容と経理処理について解説しました。
法人向けの個人年金保険は、保険料の一部を損金に算入できますが、死亡保険金・年金の受取先によって経理処理と税務効果が変わります。また、年金受取を被保険者・死亡保険受取を法人にした場合、保険料の90%が資産計上し、残り10%を損金に算入するなど、細かな経理処理が必要になります。
 【関連記事】法人向け生命保険に関する質問
【関連記事】法人向け生命保険に関する質問
 【関連記事】法人保険全般に関する質問
【関連記事】法人保険全般に関する質問
 【関連記事】(法人向け)退職金に関する質問
【関連記事】(法人向け)退職金に関する質問
 【関連記事】事業承継・保障に関する質問
【関連記事】事業承継・保障に関する質問





















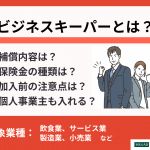
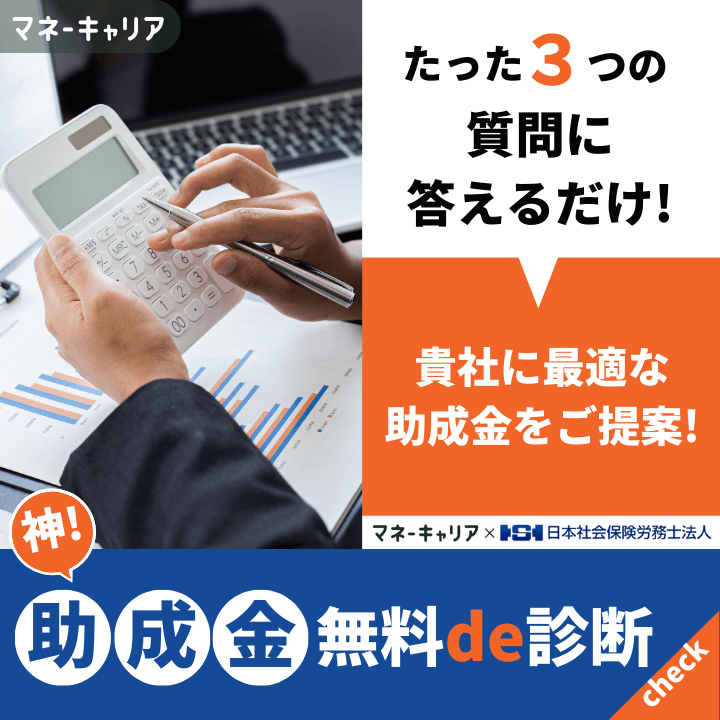
法人で従業員の老後資金の対策ができないかと考える経営者は多くいますが、選択肢のひとつとして「法人契約の個人年金保険」が挙げられます。
一方、個人年金保険は「保険金の受取人の違い」から資産・給与・損金と経理処理が変わるので、対策を検討していてもどのようにすべきかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では「個人年金保険の概要から保障内容、経理処理」を中心に解説します。
・法人向けの個人年金保険の概要を知りたい
・自社のリスク対策が個人年金保険で問題あるとすれば、ほかに費用対効果高く自社を守れる方法はないか探している
方は本記事を参考にすると、個人年金保険の内容と使い方が自社にマッチしているかの判断ができるのはもちろん、万が一のことが発生した際の対策を万全にできる方法もわかります。