
更新日:2024/08/06
法人損害保険の経理処理とは?損金算入の要件も解説

内容をまとめると
- 法人の損害保険の保険金を受け取った際の経理処理は、保険金の受取人により変化する。
- 積み立て型の法人損害保険の保険金の経理処理は満期返戻金と契約者配当金の全額が益金に算入される・
- 一方、資産計上されていた積み立て保険金の累計額が損金算入されるが、税務上の法人保険料は損金算入と資産計上の2パターンがあるので注意。
- 法人の損害保険は事業運営を推進するうえで非常に重要であるが、自社に最適な保険の見直しや環境構築に「マネーキャリア」を使う企業も増えている。

目次を使って気になるところから読みましょう!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
保険金受取人後との法人損害保険の経理処理とは
法人損害保険の経理処理は、以下の2つの場合によって異なります。
損害保険では、労災の入院や治療費、海外旅出張中の事故までカバーできるので、保険金の受取人が「従業員・役員またはその遺族」と「法人」で経理処理が異なるのです。
「保険金受取人:役員・従業員・遺族」の場合の経理処理
保険金受取人が「役員・従業員・遺族」の場合、被保険者が全従業員であることが必要である点に注意しましょう。
- 保険料の支払い=法人
- 保険金の受取人=役員、従業員、その遺族
もし、被保険者が全従業員ではなく、特定の従業員のみでは福利厚生費として認められません。福利厚生費として認められると、保険料は損金算入されます。
また、長期平準定期保険や逓増定期保険のように、前半6割と後半4割の期間で経理処理が異なる場合、保険料は期間の経過に応じて福利厚生費として損金算入されます。
保険会社から受け取った保険金は、被保険者である従業員や役員には課税されません。また、保険金を「従業員・役員・その遺族」が受け取る場合、法人の経理処理は不要です。
「保険金受取人:法人」の場合の経理処理
保険金受取人が法人である場合、福利厚生費として認められるためには被保険者が全従業員である必要があります。
福利厚生費として認められるのは以下のような事例です。
- 社員旅行、忘年会、新年会などの社内行事
- 通勤費
- 社宅
- 健康診断費用
- 慶弔見舞金
ここでは以下の場合の経理処理について考えます。
- 保険料の支払い=法人
- 保険金受取人=法人
従業員が死亡し、保険金を法人が受け取ると、全額が益金に算入されます。
受け取った保険金全額を死亡した従業員の遺族に支払った場合は、法人が受け取った死亡保険金が全額が損金算入されます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
積み立て型の法人損害保険の経理処理

積み立て型の法人損害保険とは、満期になると満期保険金を受け取れるタイプの保険のことです。また、支払保険料の積み立て部分が満期や解約時まで資産計上されます。
そして、満期になったときに受け取れる満期返戻金と契約者配当金の全額が益金に算入されます。一方で、資産計上されていた積み立て保険金の累計額が損金算入されます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリアの公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
税務上の法人保険料は損金算入と資産計上の2パターンがある

ここでは、損金算入、資産計上のメリット・デメリットに関して紹介します。
保険料がどのような割合で損金算入されるのかは保険の種類によって、保険料の1/2、1/3、1/4が損金算入できるものもあれば、全額損金算入できるものもあります。
そして、全額損金算入できる保険として、例えば以下のような商品があります。
- 定期保険(ただし、解約返戻率が50%以下の商品などに限られる)
- 医療保険
- 自動車保険
また、損金算入されるには保険会社に保険料が着金することが重要なので、損金算入にかかる日数についての把握も大切です。
損金算入するメリット・デメリット
資産計上するメリット・デメリット
損金算入するまでにかかる日数
保険料を支払うと損金算入できる保険商品の場合、支払ったらすぐに損金算入できるわけではありません。
保険料の損金算入が納税申告の際に認められるためには、支払った保険料が保険会社に着金していることが必要です。
そのため、事業年度の決算日の直前に保険料を支払っても、銀行の送金処理にに時間がかかると間に合わなくなってしまうことにも注意しましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
損害保険全体のリスク対策がすぐにわかる方法とは
以下では、損害保険全体のリスク対策が「無料で簡単に」わかる方法を紹介します。
損害保険の経理処理は、被保険者によって経理処理が異なるうえ、保険商品によって仕訳の方法が異なります。さらに、自社の事業フェーズによって最適な損害保険も異なることから、定期的な見直しが求められます。
しかし、保険の加入・見直しは経営陣が判断しなければならず、保険の専門知識がないまま独断で保険加入を判断してしまうと「保障に対して不釣り合いな保険料を払っていた」となる事態になりかねないのです。
そこで、損害保険はもちろん、事業成長のための福利厚生を含めた総合的な対策を検討するには、法人保険のプロに「無料で何度でも」相談ができるマネーキャリア一択です。
丸紅グループが運営するマネーキャリアは、税務を含めた法人保険の活用方法に関して「提案実績80,000件以上」から培ったノウハウをもとに、自社の理想を実現できる満足度の高い提案に強みがあります。
損害保険を含むリスク対策を進めるなら:マネーキャリア(丸紅グループ)

お金に関する全ての悩みにオンラインで相談できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、法人保険のプロのみを厳選しています。
・保険だけではなく、総合的な事業リスクへの対策を踏まえて「自社の理想の状態を叶える」提案が可能です。
・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も80,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに 「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。
法人損害保険の経理処理や損金算入の要件まとめ
ここまで、法人損害保険の経理処理からメリット・デメリットを中心に解説しました。
損害保険では、保険金受取人が「従業員・役員・その遺族」の場合、法人が経理処理を行う必要はありません。一方、保険金受取人が「法人」の場合、保険金の全額が益金計上されるが、福利厚生費として支払うと全額が損金算入になる特徴があります。
また、損金算入は節税効果があるが、貯蓄性がなく受け取れる保険金は少なくなり、資産計上は会社の価値を上げるが、相続の際に相続税が高くなってしまう点に注意しましょう。
法人損害保険は法人に損害が生じた場合や損害賠償責任が生じた場合に備えられるので、業態業種問わず加入すべき保険であるといえます。
しかし、保険商品は多岐に渡るうえ、専門的な知識がなければ自社に最適な保険を選ぶのは非常に困難です。そこで、マネーキャリアのように、法人保険のプロに相談しつつ自社のリスク対策を進める会社も多いのです。
無料登録は30秒で完了するので、ぜひマネーキャリアを活用しつつ、万が一のリスクへといつでも対応できる環境を構築しましょう。
▼この記事を見た方はこちらも見ています。
 【関連記事】法人向け損害保険に関する質問
【関連記事】法人向け損害保険に関する質問





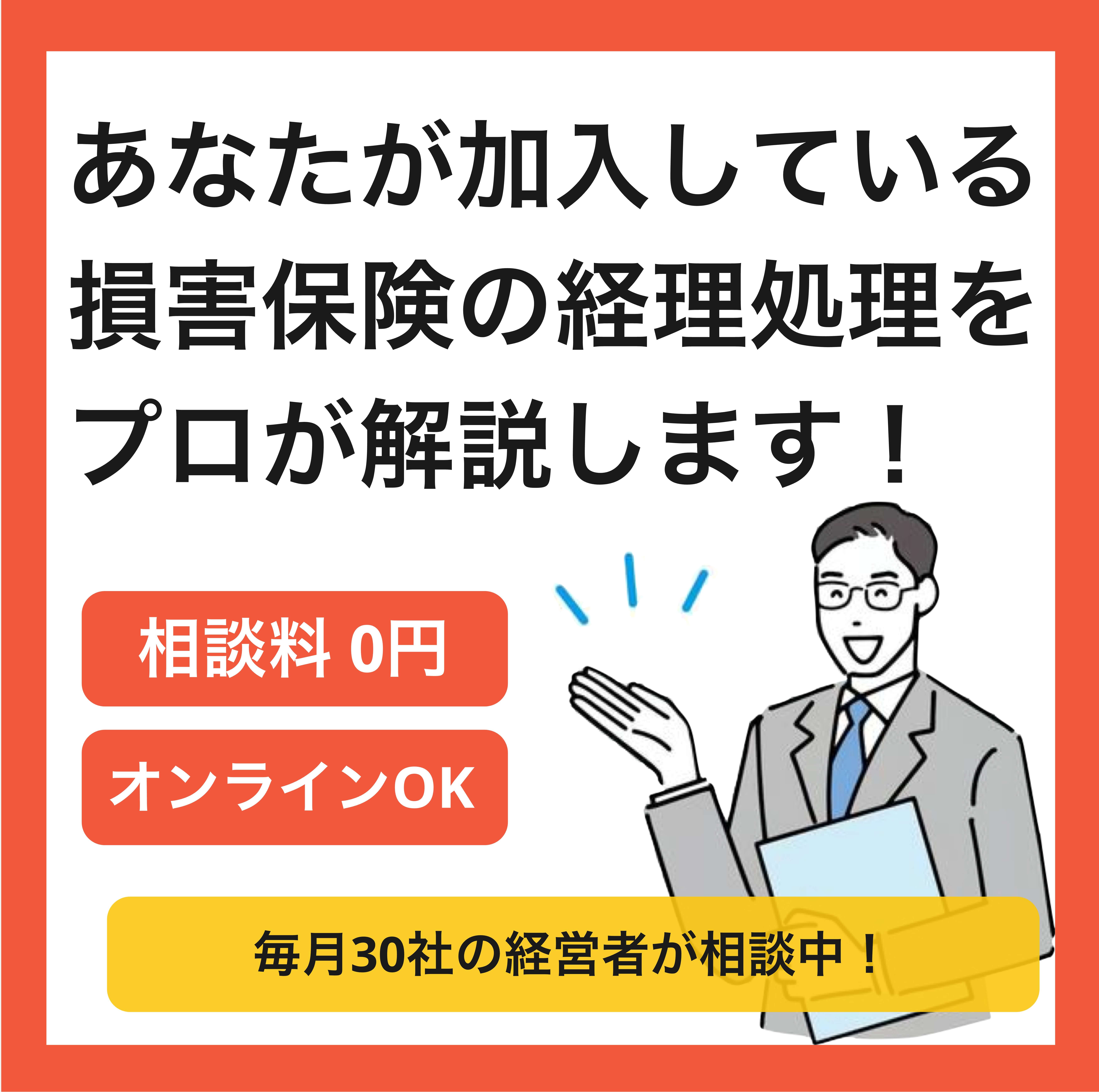












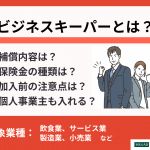
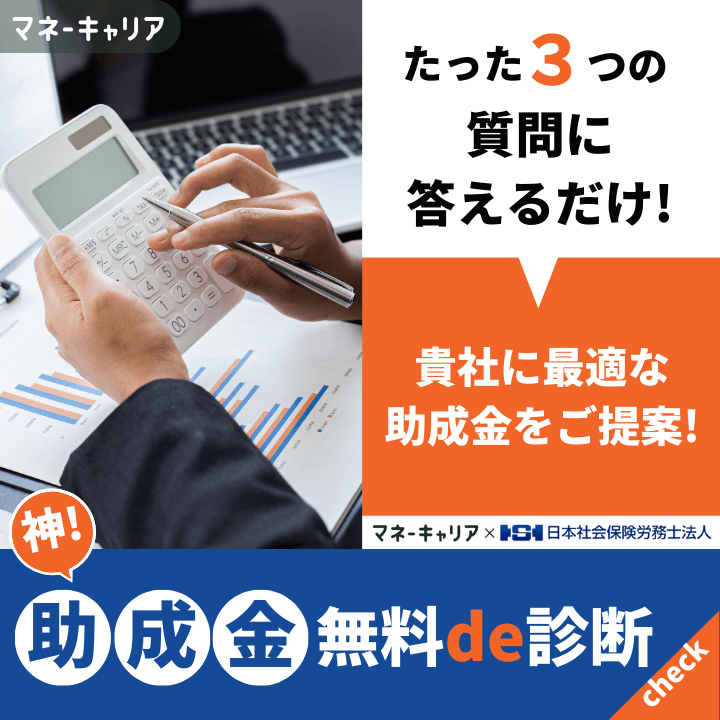
偶発的な事故や他人に損害を与えたときに備えて、法人契約で「損害保険」に加入している会社は少なくありません。万が一の事態が生じた時に保険金を受け取れる一方、保険金を受け取った際には正しく経理処理をしなければなりません。
また、法人向けの損害保険は、保険金の受取人を誰にするかによって経理処理が異なる点を把握する必要があります。しかし、定型業務があり忙しいなかでも、現場の混乱を避けたい経営者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「受取人・積立型ともに異なる法人向け損害保険の経理処理」を中心に、損金算入や資産計上におけるメリット・デメリットなども解説します。
・損害保険の経理処理を把握したい
・税務署などから指摘を受けない経理処理の対策と、より効果的な保険の種類があれば検討したい
方は本記事を参考にすると、法人損害保険の経理処理や税制上のメリットとデメリットがわかるのはもちろん、自社のリスク対策を強化する方法や損害保険の見直しが簡単にできる方法もわかります。