
更新日:2024/08/06
法人名義の自動車保険は社員以外にも適用される?補償範囲も解説

内容をまとめると
- 契約者等はすべて法人で加入することが必須。
- 加入時に制限される年齢を決められる。
- 運転者の範囲は従業員から家族まで範囲が広く、法人名義なら自動車保険料も経費で計上できる。
- 契約する自動車台数によってフリート契約と、ノンフリート契約を選択できる。
- 社員以外の人が自動車を使う場合は、一層自動車保険の重要性が高まることに加え、自社の包括的なリスク対策に関する悩みは「無料で何度でも」法人保険のプロへ相談できるマネーキャリアを使って解消する会社が急増している。

目次を使って気になるところから読みましょう!
 法人向けの自動車保険について
法人向けの自動車保険についてーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自動車保険が法人名義なら社員以外の家族など誰でも補償対象

自動車保険に限らず、保険に加入するときには必ず契約者が必要です。
個人で契約するとき
- 契約者:○○さん
- 記名被保険者:○○さん
- 自動車所有者:○○さんの夫(同居家族)
のように、契約者と自動車の所有者が同居家族であれば、加入ができます。
一方の法人契約の場合
- 契約者:法人
- 記名被保険者:法人
- 自動車所有者:法人
のように、原則として同じ法人名義で契約が必須です。また、契約者が法人の場合でも、社員以外の家族が私用で使っても、補償の対象になります。
法人契約の補償の対象は「自動車」であり「誰が」は関係ない
法人契約の自動車保険において、使用者の範囲は不特定多数になるため、契約の対象は自動車そのものとなります。
自動車の台数によって「ノンフリート契約」「フリート契約」の種別以下のように異なります。
- ノンフリート契約(9台以下)
- フリート契約(10台以上)
上記のように台数ごとで契約や補償が変わるので、法人契約の補償対象は「自動車」であり「誰が」は関係ないのです。
法人名義の自動車保険は利用者を限定して契約できない
個人契約での使用範囲
- 本人限定
- 本人と配偶者限定(ただし夫婦の場合に限る)
- 家族限定
- 限定なし
のように、この中から選択することができます。
しかし、法人契約した社用車の場合は、使用車を限定できません。社用車の場合、だれが使用するかを限定することはできないからです。
一つの車を社員全員で使用することもあるため、法人で自動車保険に加入するときは、使用者を限定しません。そのため、従業員の家族が社用車をプライベートで使用したとしても、補償の対象となるのです。
- 不特定多数の人が使用している
- そのため従業員に限らず従業員の家族も使用できる
この2点が、法人の自動車保険の対象者となるため、不特定多数の人が補償対象者となるともいえます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法人名義の自動車保険の補償対象について知っておくべきポイント

法人名義の自動車保険では、不特定多数の人が利用できますが、加入条件に注意点があります。
- 使用する人の年齢
- 契約した車種によっても年齢の条件は変わってくる
- 保険料の決め方が個人契約と異なる
- 特約の内容によっては付けないほうがいいものもある
①年齢に補償範囲の制限がないかチェック
法人契約にも個人の自動車保険のように運転者の年齢の範囲があり、それぞれ以下のように分類されます。
- 補償の年齢制限なし
- 21歳以上から
- 26歳以上から
- 30歳以上から
多くの従業員を抱えている会社であれば、年齢制限を設けないで契約する場合も少なくありません。そのため、「会社の規模や従業員の年齢層」を考慮して、運転者の範囲を設定するようにしましょう。
その他にも、法人で自動車保険加入で保険料を経費として計上できるため、節税効果も期待できます。しかし、法人税節約目的で加入する場合は、制限が付く可能性もあるので注意しましょう。
②1人でも事故を起こせば保険料が高くなる
自動車保険料の仕組みについて、個人契約は以下の通りです。
- 20等級から1等級のノンフリート契約
- 記名被保険者が26歳以上もしくは35歳以上で保険料率が変わる
- 事故情報などでも保険料率が変動
- 免許証(ゴールド)割引有
個人契約では事故を起こさなけれは、保険料が上がることはありません。次に法人契約ですがノンフリート契約とフリート契約の2つがあります。
ノンフリート契約は以下のとおりです。
- 1台か2台以上のミニフリート契約(こちらは台数割引あり)
- 保険料は1台ずつノンフリート制で決まる
- 事故を起こした車は、等級が下がり次の年から保険料が増加する
このようにノンフリート契約では、事故を起こした車ごとで保険料が変わってきます。一方、フリート契約は以下のとおりです。
- 車両一括契約は割引有、分割契約はない
- 契約する車に割増引が適用
- 1人でも事故を起こしてしまうと、全車両の保険料が次の年から増額
フリート契約では、1人でも事故を起こすとすべて保険料が増額するように、それぞれで違いがあります。
 フリート契約について
フリート契約について③他車運転特約(他車運転危険補償特約)は加入しないようにする
他車運転特約(他車運転危険補償特約)は加入しないこともポイントです。
自動車保険とは、車に保険をかけるので、他人の車を運転中に事故を起こしても自社で加入している保険は使えず、事故を起こした車の保険を利用することになります。しかし、その車の契約次第では補償が十分とは言えないケースもあります。
上記事態を避けるために、他者運転特約があります。この特約に加入さえしていれば、自分の保険が使えるようになります。
一方、法人契約の場合は運転する人の範囲に制限がないことから、保険の対象になるため、この特約を付ける意味はありません。したがって、勧められても加入しないようにしましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
リスク対策に強い環境を整備するために必須の方法とは
以下では、自社のリスク対策を簡単に整備するために必須の方法を解説します。
企業が所有する自動車を業務で使用する際、社員以外の方が運転することによる事故のリスクは経営リスクのひとつとなるため、適切な法人向け自動車保険への加入が不可欠です。
しかし、社員以外の方が運転する場合の補償内容や条件は保険会社によって異なったり、事故発生時の対応方法や手続きについても理解する必要があったりするため、経営陣の独断で保険加入やリスク対策を判断するのは得策ではありません。
そこで、リスク対策に関する悩みは法人保険の専門家に相談しながら、自社の事業内容に合った最適な法人向け自動車保険を選ぶ必要があるのです。
実際に、法人向け自動車保険の選定に悩む経営者の間では、リスク対策のプロによる相談が無料で何度でも受けられるマネーキャリアを活用する会社が急増しています。
丸紅グループが運営するマネーキャリアの専門家は、80,000件以上の相談実績を持ち、98.6%の高い満足度を誇ります。法人保険のプロが最適な事業リスク対策に関して何度でも無料で対応してくれるので、企業経営者の方々の自動車保険の悩みや包括的なリスク対策に合わせて、保険選びの悩みを解消できます。
自動車保険を含む法人保険の悩みを無料相談で解消:マネーキャリア(丸紅グループ)

法人保険に関する全ての悩みにオンラインで相談できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、法人保険のプロのみを厳選しています。
・保険だけではなく、総合的な事業リスクへの対策を踏まえて「自社の理想の状態を叶える」提案が可能です。
・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も80,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに 「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。
法人名義の自動車保険の補償対象の条件まとめ

ここまで法人契約の自動車保険や補償対象で知っておくべきポイントを紹介しました。
- 契約者等はすべて法人で加入すること
- 加入時に制限される年齢を決められる
- 運転者の範囲は従業員から家族まで範囲が広い
- 法人名義なら自動車保険料も経費で計上できる
- 契約する自動車台数によってフリート契約と、ノンフリート契約を選択できる
このように補償条件などの範囲は広いですが、その反面契約内容によって、事故を起こした翌年の自動車保険料に差が出てくることもあるため、加入の際はリスクも考慮しましょう。
一方、法人向け自動車保険の加入検討や比較には専門知識が必要不可欠です。加えて、事故発生時の対応方法や手続きについても、自社だけで対処するには限界がある問題点もあります。
また、会社におけるリスクは自動車だけではないので、事業運営に集中できる環境を強くするためにも、マネーキャリアのように、法人保険の専門家へ「無料で何度でも」リスク対策に関して相談できるサービスの利用が必須です。
無料相談予約は30秒で完了するので、ぜひマネーキャリアを使い、万が一の事態に備えた体制を整えましょう。





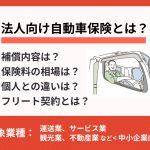
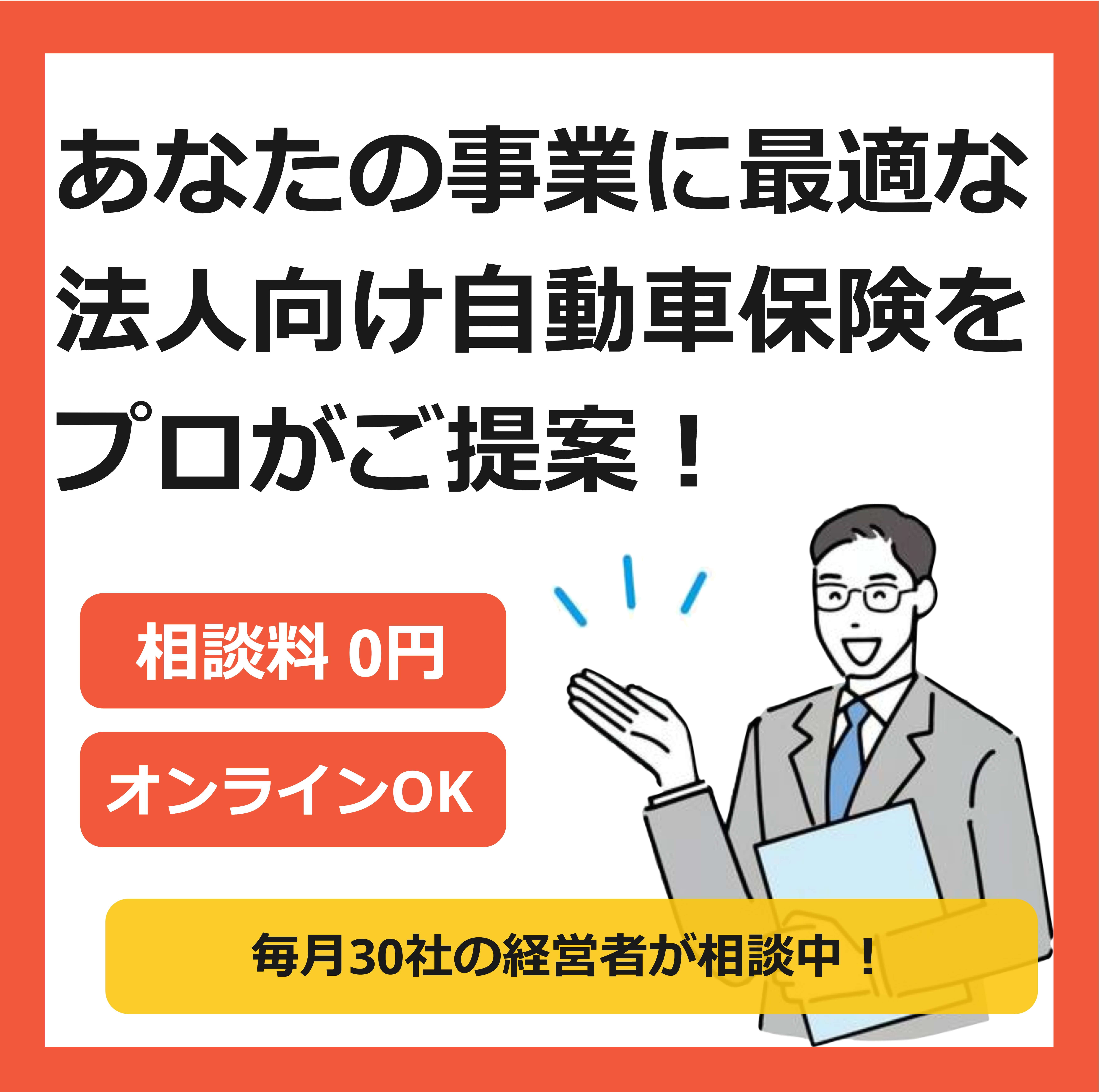













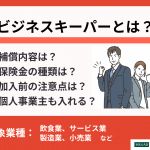
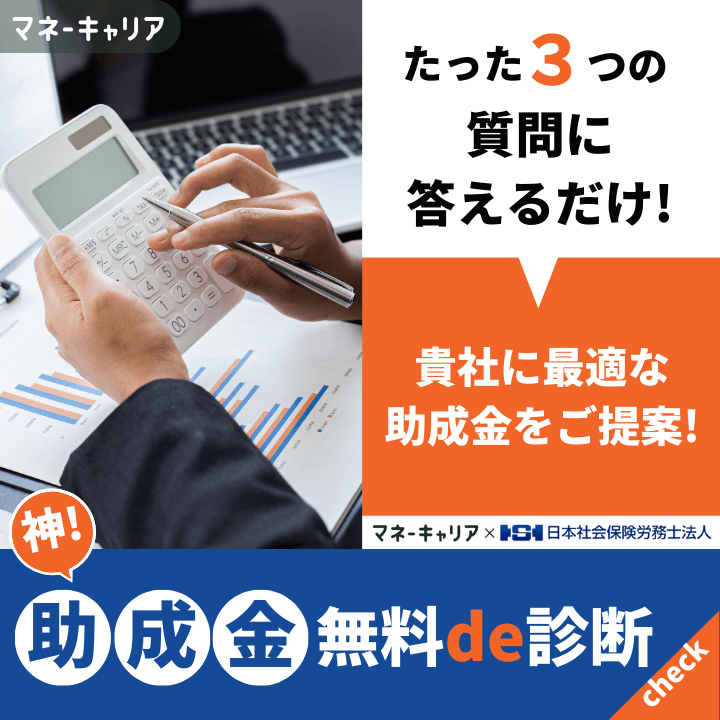
企業が所有する自動車を業務で使用する際、社員以外の方が運転する場合の事故による損害や賠償責任に備えるために、法人向けの自動車保険への加入が重要です。
しかし、社員以外の方が運転する場合の補償内容や条件について、自社の保険で十分なのか判断に迷う経営者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、企業経営者の方々に向けて、社員以外の方が企業の自動車を運転する場合の法人向け自動車保険の注意点や、補償内容の確認方法などを詳しく解説します。
・自動車を業務で使用しており、社員以外の方にも運転を任せている経営者で、自動車保険の補償内容に不安を感じている方
・社員以外の方にも運転を任せる予定の経営者で、リスク対策に関して不安な経営者の方
この記事を読むことで、社員以外の方が企業の自動車を運転する場合の法人向け自動車保険の留意点を理解し、自社に適した補償内容を確認することができるようになります。