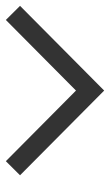 ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
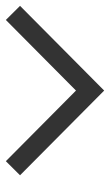
ほけんROOMのサービス一覧

ほけんROOM相談室
自由な時間で自由な場所で、納得感のある保険の無料相談を
保険は人生で三番目の大きな支出、大事だとわかっていても小難しくてわかりにくいもの。ほけんROOM相談室では、お金の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー:国家資格)が、人生設計から将来のリスクや必要なお金を考え、納得感のある保険の設計をします。相談料は一切かかりません。

ライフプラン相談
あなたの家計の見直し、将来に向けた貯蓄や投資に関するご相談
保険や資産運用だけでなく、結婚や出産、車や住宅ローンなど人生で必要なお金にのことを考えると不安になります。そこで、ライフプラン相談ではお金の専門家であるFPが、あなたの家計状況や悩みに合わせたライフプランを無料で提案します。家計管理の見直しなどにも役立ちます。
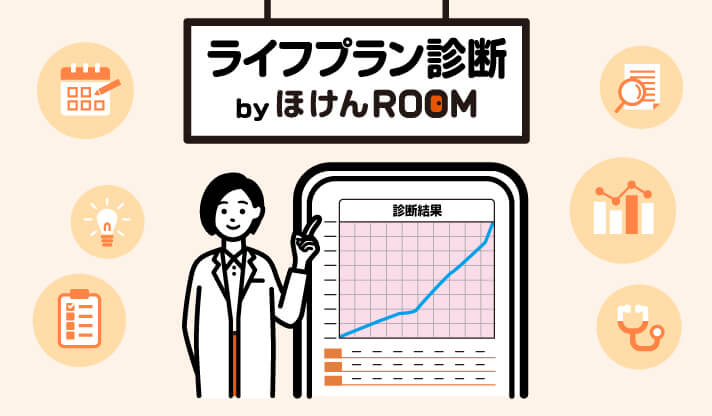
ライフプラン診断
あなたの収入・支出から、ライフプランをシミュレーション
将来のために貯金はしているが、実際いくら必要なのか具体的にはわからないもの。そこでライフプラン診断では、あなたや配偶者の年収、支出などから家計の安心度や貯金・収入・支出が年齢別グラフで表示。これからのお金の動きが一目でわかります。パターンを変えて何回でも無料で診断可能です。
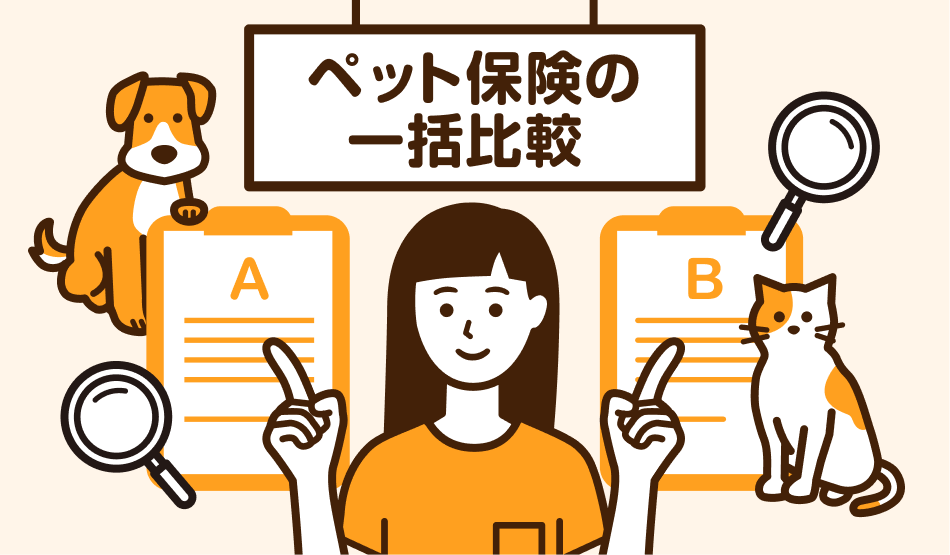
ペット保険の一括比較
簡単5秒でペット保険を一括でお見積り
今や家族として受けれられている犬や猫などのペットたち。医療の進歩により平均寿命も伸びている中、いざ病気になったときの備えはできていますか?ほけんROOMのペット保険の一括比較では、5秒で簡単にあなたの家族のためのペット保険を提案します。

ほけんROOMマガジン
保険や家計、税金などについてわかりやすく解説する
WEBメディア
ちょっとしたお金の疑問って誰に聞いたら良いか分からない、自分で解決するのは難しい。ほけんROOMマガジンではあなたのお金に関する悩みになんでも答え、知っておきたいお金の知識をお届けします。あなたが知りたいお金の知識について、気になる記事をチェックしましょう。

マネーキャリアのマネーセミナー
投資、節約、金融の制度などについて専門家がオンラインで解説するマネーセミナー
お金に関して勉強をしたことがない方でも、ライフプランの方法、資産形成のいろはなど、初心者の方向けセミナーを通して学べます。
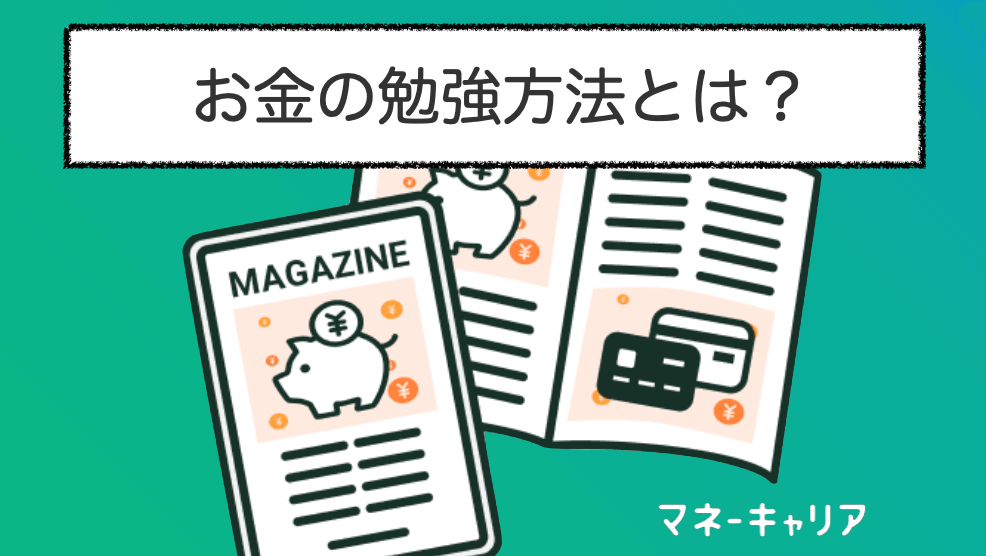
マネーキャリアマガジン
保険に限らず投資や貯蓄などお金全般についてわかりやすく解説するWEBメディア
人生が豊かになるお金の知識について解説するWEBメディアです。全記事FP監修で保険に限らず投資や貯蓄、金融の制度などをお届けします。
カテゴリ一覧
CSR活動
Wizleapでは、豊かな社会作りのため、以下の社会貢献活動を推進しています。



 保険 見直し
ポイント
保険 見直し
ポイント











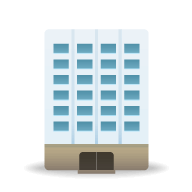
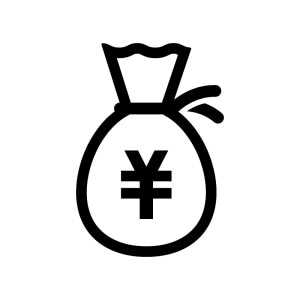
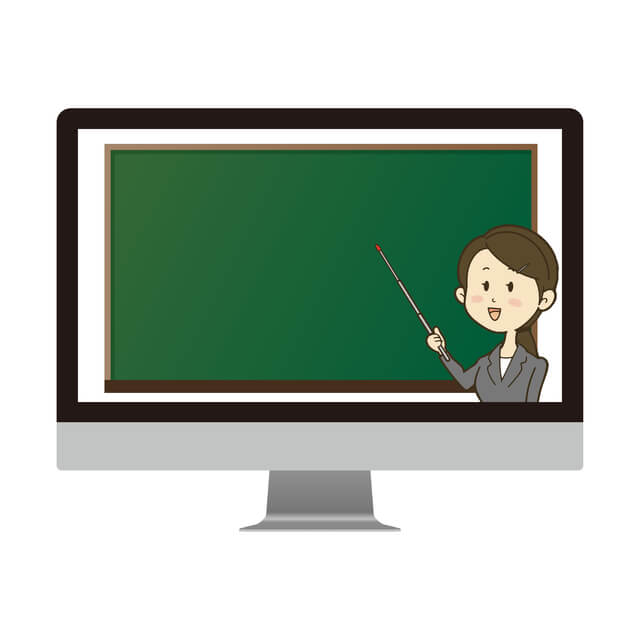



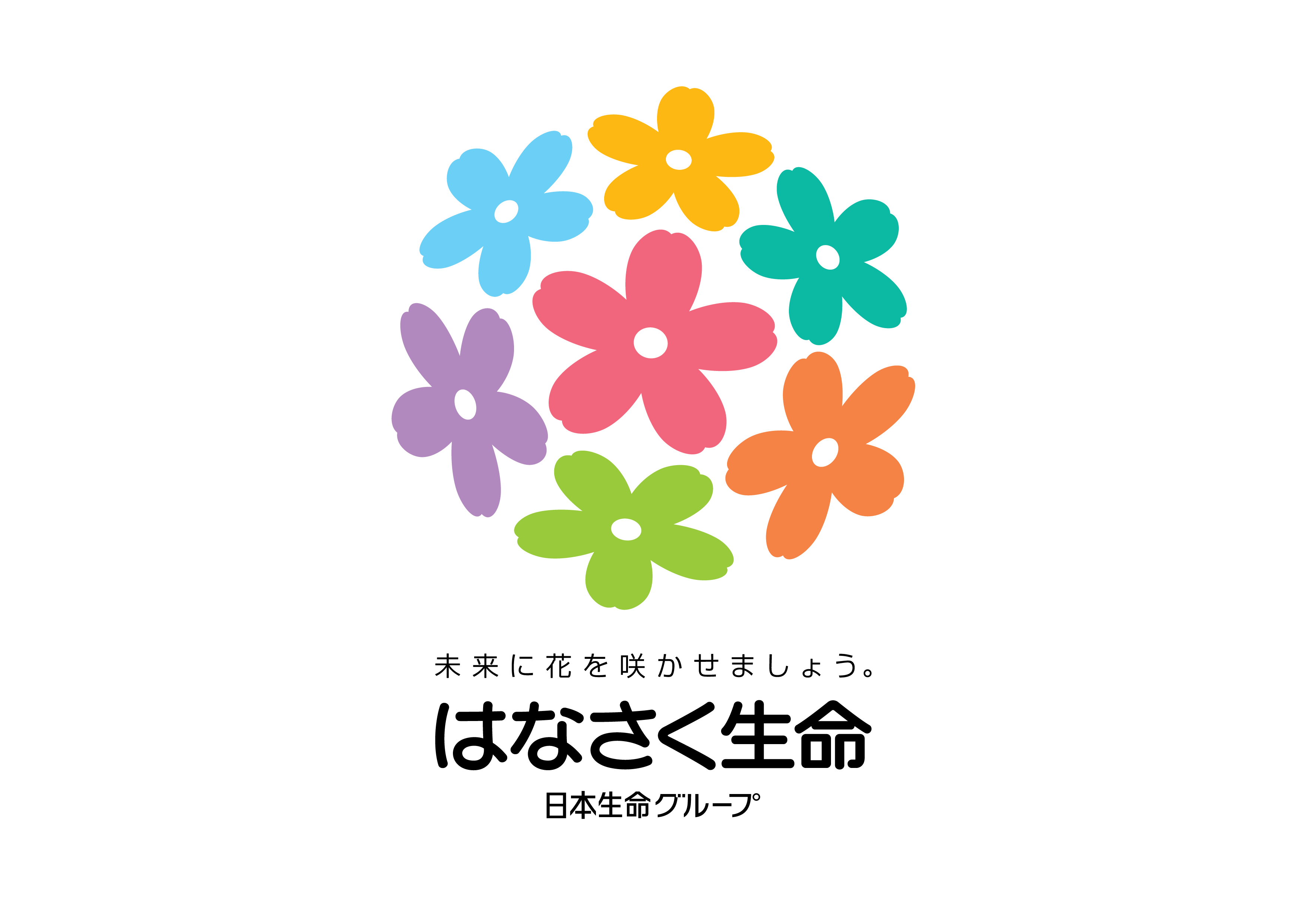
















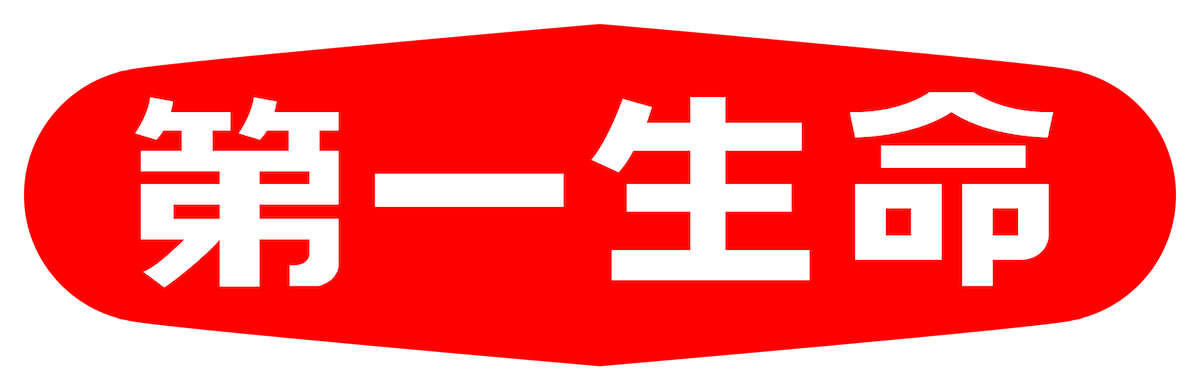
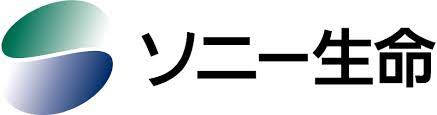

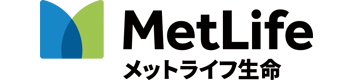












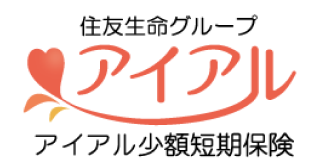
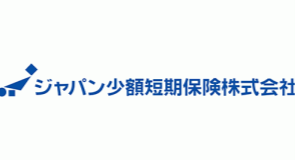










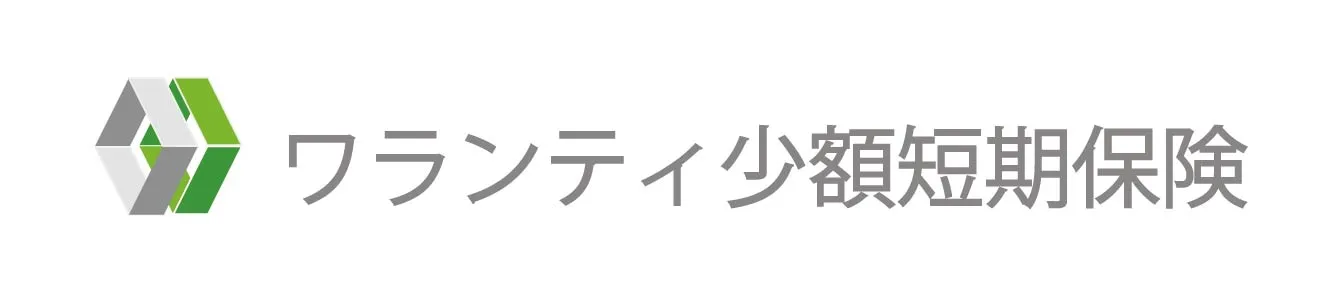

















保険のことをもっと身近に。