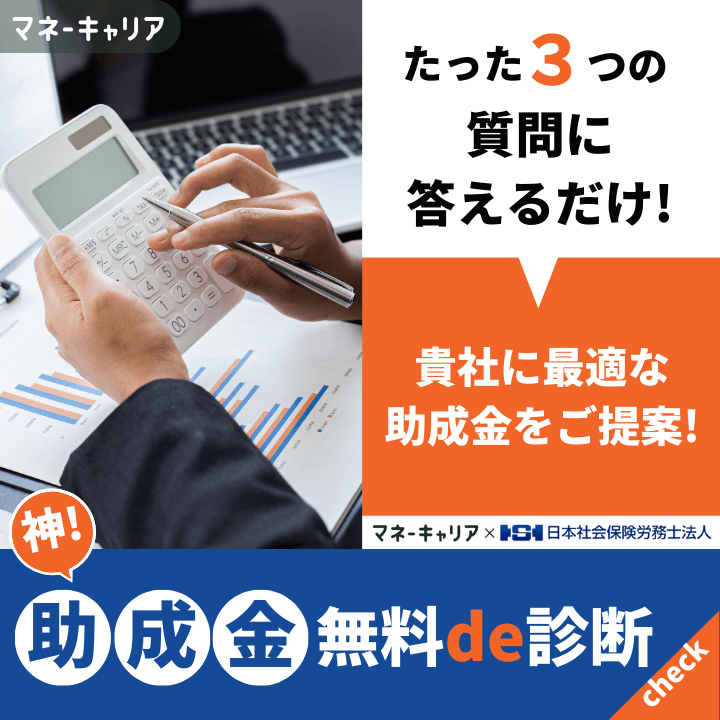法人保険に関する疑問
最適な情報を伝える
法人保険

法人保険のメリットとデメリットとは?活用方法や経営処理を解説!
法人保険とは、契約者が個人ではなく法人関係者(経営者など)として保険に加入することをです。法人保険のメリットについては、経営者に万が一のことがあっても事業を保障してくれる点などがあります。こちらの記事ではその他のメリットやデメリットについても解説しています。
-

損害保険
最終更新日:2025/10/09
建設業総合保険とは、工事遂行中から引渡し後までに損害が発生した場合、一つの保険で漏れなくダブりなく補償することができる保険です。建設業総合保...
-

損害保険
最終更新日:2025/01/30
東京海上日動では、企業が製造・販売した製品や工事や作業の結果により他人の身体の障害または、財物の損壊について法律上の賠償責任を負担することに...
-

損害保険
最終更新日:2025/01/30
請負業者賠償責任保険とは、工事中の事故により、第三者等に損害を与えた際の費用を補償する保険です。東京海上日動でも請負業者賠償責任保険を提供し...
-

損害保険
最終更新日:2025/01/30
動産総合保険とは、各種動産を保険の対象とし、保険対象に生じた損害に対して保険金が支払われる保険で、東京海上日動でも提供されています。こちらの...
-

損害保険
最終更新日:2025/01/30
東京海上日動が提供する超ビジネス保険とは、事業活動のリスクを補償する、事業活動包括保険のことです。こちらの記事では、超ビジネス保険の補償内容...
-

損害保険
最終更新日:2025/01/06
三井住友海上では、保険対象が保管・運送中等に、火災などの事故が発生した場合の損害を補償する動産総合保険の提供をしています。こちらの記事では、...
-
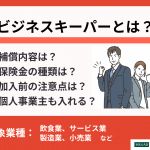
損害保険
最終更新日:2025/01/06
三井住友海上では、事業を取り巻くリスクによる損害を補償する、ビジネスキーパーを提供しています。三井住友海上のビジネスキーパーの基本的な補償内...
-
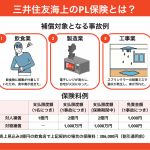
損害保険
最終更新日:2025/01/06
三井住友海上では、企業が製造・販売、工事の結果などにより、第三者にケガをさせた場合などの、損害賠償金や争訟費用などを補償する「PL保険」を提...
-
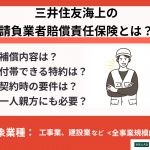
損害保険
最終更新日:2025/01/06
請負業者賠償責任保険とは、作業等の遂行中に第三者にケガをさせた場合などの、損害賠償金や争訟費用などを補償する保険です。三井住友海上でも提供し...
-

損害保険
最終更新日:2024/11/14
本記事では、ベビーシッター事業者向けに、運営に必要な保険の種類や損害事例、注意点などを徹底解説しています。とくに、最適な保険選びに悩むベビー...
-

法人保険
最終更新日:2024/08/31
本記事では小規模企業共済の加入資格や加入できる・できない業種、よくある質問や悩みを解消できる方法を紹介します。小規模企業共済への加入を検討し...
-

法人税対策
最終更新日:2024/08/07
この記事では、借上社宅制度を利用するときに課税されないためのポイントについてご説明します。借上社宅制度は、福利厚生の費用として計上できますが...
-
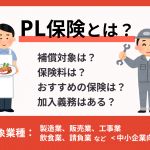
損害保険
最終更新日:2024/08/06
PL保険(生産物賠償責任保険)とは、企業が製造・販売する生産物や工事が結果で起こった事故において、賠償責任により発生した費用を補償してくれる...
-
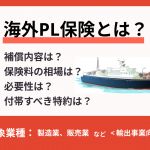
損害保険
最終更新日:2024/08/06
海外PL保険とは、自社で製造、販売した製品が輸出した際に、国外で製品が原因で発生した損害を補償するための保険です。こちらの記事では、海外PL...
-
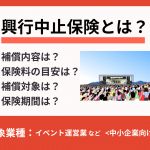
損害保険
最終更新日:2024/08/06
最近はコロナの影響で軒並みイベントが中止や延期となっていますが、興行中止保険という保険が存在するのをご存知でしょうか。興行中止保険は、お祭り...
-
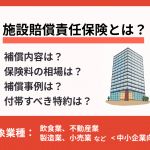
損害保険
最終更新日:2024/08/06
施設の管理者を務める人にとって欠かせない保険、それが施設賠償責任保険です。しかしこの施設賠償責任保険、実際にはどんなときに役立つ保険なのでし...
-
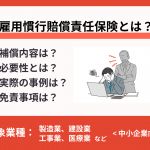
損害保険
最終更新日:2024/08/06
労働者を雇用する企業は、従業員からのパワハラやセクハラ、不当解雇などで訴えられるリスクを常に抱えています。従業員によって損害賠償を請求された...
-
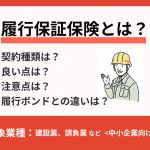
損害保険
最終更新日:2024/08/06
履行保証保険は公共工事を受注した会社が加入する保険で、基本的には「金銭的保証」をしてくれます。しかし、法人向け履行保証保険は履行ボンドと似て...
-

損害保険
最終更新日:2024/08/06
船客傷害賠償責任保険とは、乗客の運送中に事故が起こった際の損害費用を補償する損害保険です。知床での遊覧船事故では、船客傷害賠償責任保険を使い...
-
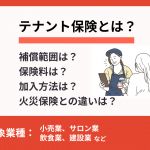
損害保険
最終更新日:2024/08/06
オフィスなどの目的でテナントを借りる際「火災保険」への加入が必須となりますが、実は「テナント保険」というより補償が充実した保険へ加入すること...
-

損害保険
最終更新日:2024/08/06
中古車販売事業には、自動車の整備ミスや労働災害などの事故に関するリスクなどがあります。このような中古車販売特有のリスクに対応するために、自動...
-

損害保険
最終更新日:2024/08/06
トリミングサロンでは、ペットの脱走やトリミング中に耳を誤って切るなどのリスクがあります。トリミングサロンを個人で営業するとなると、責任を全て...
-

損害保険
最終更新日:2024/08/06
サウナ、銭湯など公衆浴場施設経営者には火災や第三者の事故など、様々なリスクがあります。自身が経営している施設のリスクの理解と、それをカバーす...
-
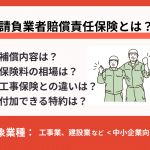
損害保険
最終更新日:2024/08/06
建設業者や工事業者の方であれば加入していると思われる請負業者賠償責任保険ですが、実際に保険の内容などは把握されているでしょうか。この記事では...
-
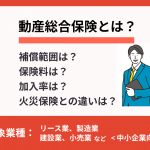
損害保険
最終更新日:2024/08/06
法人向けの動産総合保険とは「保管中・運送中・展示中」の事故のように補償範囲が広い法人保険です。しかし補償できる「動産」や「災害」に制限があり...
-

法人税対策
最終更新日:2024/08/06
法人税の支払い時期は「事業年度終了日の翌日から2カ月以内」です。法人税の支払時期を1日でも遅れると「延滞税・加算税」を支払わなければなりませ...
-

損害保険
最終更新日:2024/08/06
パーソナルトレーナーの運営には、施設の管理不足による損害やクライアントのもしもの事故などのリスクがあります。クライアントが怪我を負った場合の...
-

損害保険
最終更新日:2024/08/06
塾の総合保険とは、塾の教室内などで発生したトラブルを補償してくれる保険のことです。塾の総合保険は、具体的にどのような補償をしてくれるのか気に...
-
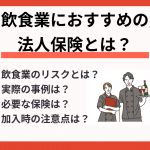
損害保険
最終更新日:2024/08/06
飲食店を経営する上で、様々なリスクに対応できる保険への加入は必須と言えるでしょう。しかし、いまいちどんな保険に加入すればいいのか分からない、...
-

損害保険
最終更新日:2024/08/06
個人事業主にはは、全ての責任を自身で負わなければなりません。本記事では、もしものリスクに対応するため、個人事業主向け損害保険の概要を解説して...