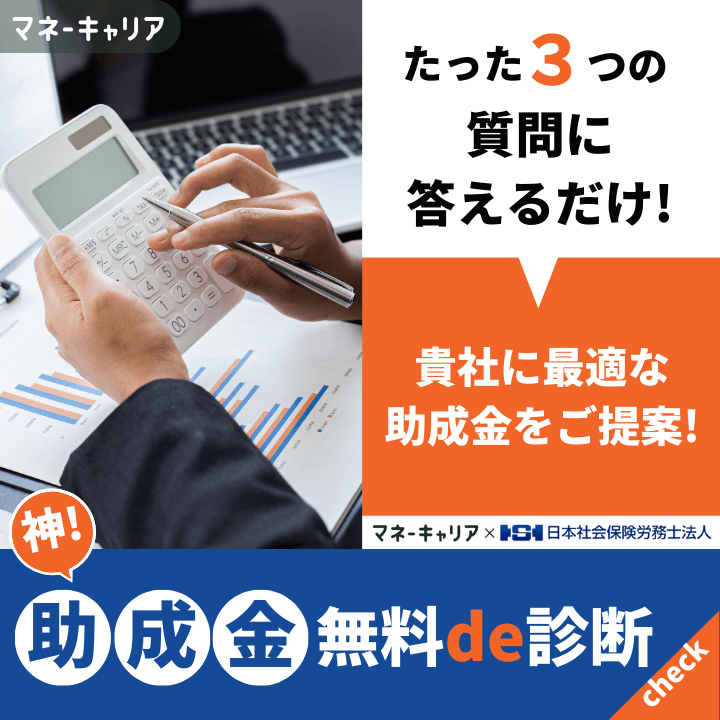法人保険に関する疑問
最適な情報を伝える
法人保険

法人保険のメリットとデメリットとは?活用方法や経営処理を解説!
法人保険とは、契約者が個人ではなく法人関係者(経営者など)として保険に加入することをです。法人保険のメリットについては、経営者に万が一のことがあっても事業を保障してくれる点などがあります。こちらの記事ではその他のメリットやデメリットについても解説しています。
-

損害保険
最終更新日:2026/01/09
請負業者賠償責任保険とは、工事中の事故により、第三者等に損害を与えた際の費用を補償する保険です。東京海上日動でも請負業者賠償責任保険を提供し...
-

損害保険
最終更新日:2026/01/08
動産総合保険とは、各種動産を保険の対象とし、保険対象に生じた損害に対して保険金が支払われる保険で、東京海上日動でも提供されています。こちらの...
-

損害保険
最終更新日:2026/01/08
東京海上日動では、企業が製造・販売した製品や工事や作業の結果により他人の身体の障害または、財物の損壊について法律上の賠償責任を負担することに...
-

損害保険
最終更新日:2026/01/08
東京海上日動が提供する超ビジネス保険とは、事業活動のリスクを補償する、事業活動包括保険のことです。こちらの記事では、超ビジネス保険の補償内容...
-

損害保険
最終更新日:2025/01/06
三井住友海上では、保険対象が保管・運送中等に、火災などの事故が発生した場合の損害を補償する動産総合保険の提供をしています。こちらの記事では、...
-
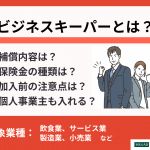
損害保険
最終更新日:2025/01/06
三井住友海上では、事業を取り巻くリスクによる損害を補償する、ビジネスキーパーを提供しています。三井住友海上のビジネスキーパーの基本的な補償内...
-
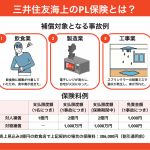
損害保険
最終更新日:2025/01/06
三井住友海上では、企業が製造・販売、工事の結果などにより、第三者にケガをさせた場合などの、損害賠償金や争訟費用などを補償する「PL保険」を提...
-
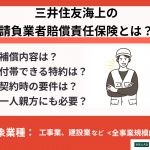
損害保険
最終更新日:2025/01/06
請負業者賠償責任保険とは、作業等の遂行中に第三者にケガをさせた場合などの、損害賠償金や争訟費用などを補償する保険です。三井住友海上でも提供し...
-

損害保険
最終更新日:2024/11/14
本記事では、ベビーシッター事業者向けに、運営に必要な保険の種類や損害事例、注意点などを徹底解説しています。とくに、最適な保険選びに悩むベビー...
-

法人保険
最終更新日:2024/08/31
本記事では小規模企業共済の加入資格や加入できる・できない業種、よくある質問や悩みを解消できる方法を紹介します。小規模企業共済への加入を検討し...
-
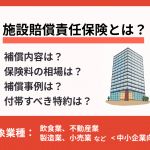
損害保険
最終更新日:2024/08/06
施設の管理者を務める人にとって欠かせない保険、それが施設賠償責任保険です。しかしこの施設賠償責任保険、実際にはどんなときに役立つ保険なのでし...
-
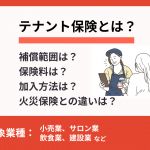
損害保険
最終更新日:2024/08/06
オフィスなどの目的でテナントを借りる際「火災保険」への加入が必須となりますが、実は「テナント保険」というより補償が充実した保険へ加入すること...
-

損害保険
最終更新日:2024/08/06
中古車販売事業には、自動車の整備ミスや労働災害などの事故に関するリスクなどがあります。このような中古車販売特有のリスクに対応するために、自動...
-
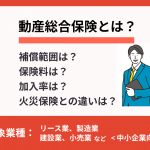
損害保険
最終更新日:2024/08/06
法人向けの動産総合保険とは「保管中・運送中・展示中」の事故のように補償範囲が広い法人保険です。しかし補償できる「動産」や「災害」に制限があり...
-

損害保険
最終更新日:2024/08/06
パーソナルトレーナーの運営には、施設の管理不足による損害やクライアントのもしもの事故などのリスクがあります。クライアントが怪我を負った場合の...
-

損害保険
最終更新日:2024/08/06
塾の総合保険とは、塾の教室内などで発生したトラブルを補償してくれる保険のことです。塾の総合保険は、具体的にどのような補償をしてくれるのか気に...
-

損害保険
最終更新日:2024/08/06
個人事業主にはは、全ての責任を自身で負わなければなりません。本記事では、もしものリスクに対応するため、個人事業主向け損害保険の概要を解説して...
-

損害保険
最終更新日:2023/11/01
保育園では園内行事中の園児のケガや、施設の損傷によるケガだけでなく、保育士も個人情報が漏洩したりするリスクなどが考えられます。そのようなリス...
-

損害保険
最終更新日:2023/09/30
レンタサイクル事業では利用者が第三者に損害を与えたり、自転車が事故に遭い壊れてしまうリスクなどがあります。京都市では平成29年10月からレン...
-

損害保険
最終更新日:2023/09/28
民泊事業では、施設が起因でのゲストの怪我や火災などの被害が予想できます。このような被害に対応するために民泊事業者の方々は、民泊保険などの法人...
-
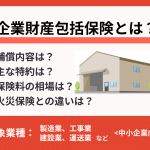
損害保険
最終更新日:2023/09/28
法人向けの保険のなかでも、ほぼすべての企業に必要と言えるのが企業財産保険です。この企業財産保険に加入すれば、いったいどんなリスクに備えられる...