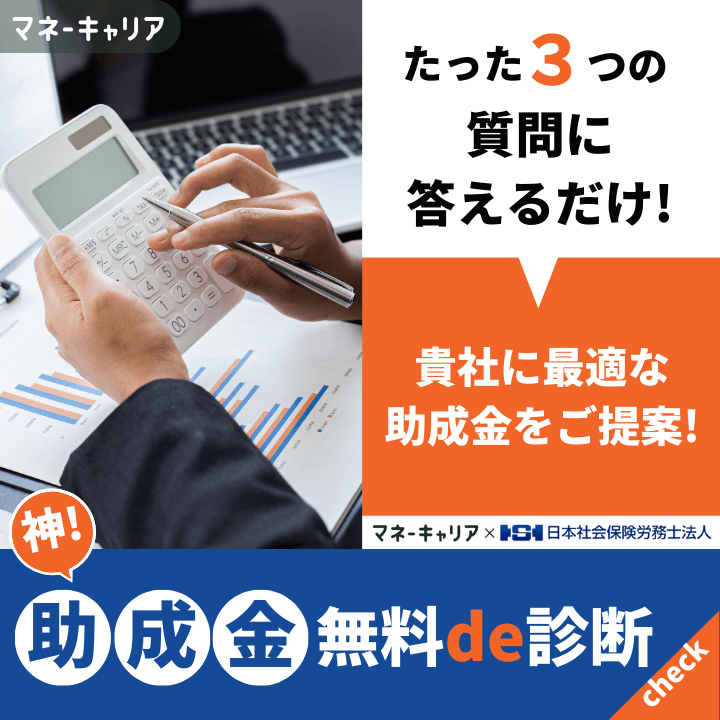更新日:2022/08/15
中小企業におすすめ!11の税金対策と注意点を解説!
中小企業が生き残るためには単純に売り上げを伸ばすだけでなく、しっかりとした税金対策を行うこと、また対策で浮いた費用を有効活用することが重要になります。そこで今回の記事では、中小企業が行うべき税金対策の方法とその他のポイントや注意点について詳しく解説していきます。

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 中小企業が出来る税金対策って何がある?
- まずは節税と脱税の違いをしっかりと抑える
- 中小企業がするべき11個の税金対策を解説
- ①:法人保険に加入する
- ②:役員報酬を適切に設定する
- ③:設備や人材へ投資する
- ④:中小企業向けの共済を利用する
- ⑤:少額減価償却資産を所有しよう
- ⑥:福利厚生を充実させる
- ⑦:別会社を設立する
- ⑧:社長が所有する不動産を貸し付ける
- ⑨:必要のない固定資産の見直しを行う
- ⑩:出張手当を支給する
- ⑪:車両を受け入れる
- 中小企業に税金対策が必要な理由
- 中小企業の方が税負担が重い
- 中小企業は大企業に比べて資金調達が難しい
- 法人税と法人住民税は会社の経費には算入されない
- 中小企業が税金対策をする上で考えるべきポイント
- 税金の繰延の効果は一時的なものである
- いき過ぎた税金対策は行わないようにする
- コラム1:法人向けの節税保険が販売停止に⁉
- コラム2:役員や従業員の退職金準備方法!
- まとめ:税法に則った上で税金対策を行おう!
目次
中小企業が出来る税金対策って何がある?
 経営者なら、少しでも会社に資金を残しておきたいと考えるでしょう。
経営者なら、少しでも会社に資金を残しておきたいと考えるでしょう。
資金繰りの改善にはさまざまな方法があるため、困惑してしまう経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
メリット・デメリットを比較検討し、自分の会社に合った方法を取り入れないと、思わぬ損失を招いてしまう恐れもあります。
ここでは、資金繰り改善を目的とした、税金対策について詳しく説明します!
- 節税と脱税の違い
- 中小企業が取り組める節税方法
- 中小企業に節税が必要な理由
- 中小企業が節税をする上で考えるべきポイント
- 法人保険の規制
- 節税しながら退職金を準備する方法
の4つのポイントについて解説します。
この記事を読み終わる頃には、きっと自分の会社ですぐに取り組める資金繰り改善方法に出会えることでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。
まずは節税と脱税の違いをしっかりと抑える
節税と脱税は一見似ているように感じる言葉ですが、その意味は大きく異なります。
節税は、健全な経営を実現するため、税法に則って税負担を減少しようとする行為です。
一方脱税は、課税される要件があるにも関わらず、意図的に隠し、課税を免れようとする行為で、法律違反となります。
節税は合法的ですが、脱税は違法であり、脱税を犯した人は犯罪者です。
所得税法では、脱税をすると「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金を処し、またはこれを併科する」と定められています。
脱税が立証されるのは悪質な場合に限られるとはいえ、危ない橋は渡らないようくれぐれも注意しましょう。
税法では重加算税などの罰則規定も設けられているため、脱税をしようとすると、かえって税金の負担が大きくなってしまいます。
あくまで法律に従い、正しく税金対策ををすることを心がけましょう。
中小企業がするべき11個の税金対策を解説
①:法人保険に加入する
法人保険の活用は、中小企業ができる代表的な税金対策です。
法人保険の税務対策の中には、結局資金が外部に流出してしまい、法人に資金が残らない方法も少なくありません。
しかし、積み立て型の法人保険を活用すれば、保険料の一部を損金算入しながら法人の外部に資金を積み立てることができます。
一定期間積み立てたうえで解約すれば、解約返戻金を受け取れます。
法人保険加入時に解約返戻金の活用方法等出口戦略を考えた上、法人保険に加入しない場合より法人にとってメリットがある商品も多数あります。
税金対策をしたいけれど、何から始めていいか分からない経営者にとっては必見の方法と言えます。
加入検討時は、ぜひ専門家に相談してから始めてみて下さい!
 法人保険のおすすめ比較ランキング|専門家一押しの法人保険を紹介!
法人保険のおすすめ比較ランキング|専門家一押しの法人保険を紹介! 法人保険は節税効果なし?法人保険の本当の活用法をプロが直伝
法人保険は節税効果なし?法人保険の本当の活用法をプロが直伝 法人保険の損金ルールを簡単にわかりやすく解説!損金算入できない費用まとめ
法人保険の損金ルールを簡単にわかりやすく解説!損金算入できない費用まとめ②:役員報酬を適切に設定する
役員報酬を見直すのも税金対策として効果的です。
役員報酬は、毎月同額を支給するなど一定の要件を満たせば、損金として計上することができます。
また、親族を役員に就任させて所得分散をはかることで、相続税対策をすることもできます。
所得税は累進課税で所得が大きくなるほど高い税率が適用されます。
経営者一人に役員報酬を支給するより、ご家族に分散して支給した方が、トータルで支払う所得税の合計額は少なくなるでしょう。
ただし、業務実態がないまま役員報酬を支払うと税務調査で指摘されるリスクがあるため、役員報酬を支払う場合は一定の業務を担ってもらう必要があります。
③:設備や人材へ投資する
設備投資や人材への投資も、決算対策として一般的に行われます。
これに加えて、設備投資や人材投資をすることで、税額控除が受けられる場合があります。
設備投資に関して、中小企業経営強化税制という特別償却・税額控除の制度があります。
適用できる業者や導入する資産の要件を満たすことができれば、取得価額の7%〜10%の税額控除を受けることができます。
また、人材投資に関しては所得拡大促進税制や雇用促進税制があります。
所得拡大促進税制は、前期に比べて給与の支給額が増加するなど複数の要件を満たすことで、税額控除が受けられる制度です。
雇用促進税制は、一定の計画のもと従業員を採用した場合に税額控除が受けられる制度です。
中小企業経営強化税制や所得拡大促進税制、雇用促進税制などの税制優遇は、期間限定で行われることがほとんどです。
期間を逃すと適用できなかったり、要件が厳しくなってしまったりするので、今年度の税制優遇については「中小企業施策利用ガイドブック」をご確認下さい!
④:中小企業向けの共済を利用する
中小企業が加入できる共済を活用するのもおすすめの節税対策です。
代表的な共済として、中小機構が運営する小規模企業共済と中小企業倒産防止共済があります。
中小機構とは、政府が全額出資して運営している法人なので、民間の生命保険会社と比較して倒産リスクがありません。
小規模企業共済は、従業員数の少ない中小企業の経営者や個人事業主が個人で加入する共済です。
掛金は全額所得控除となり、解散や廃業と同時に解約金を受け取ることができます。
受け取った解約金は受け取り方によって、退職所得や雑所得となります。
一方、中小企業倒産防止共済は、1年以上事業を継続している中小企業の経営者や個人事業主が加入する共済で、掛金は事業の経費として計上します。
受け取った場合は収益の取り扱いとなるため、受け取るタイミングには工夫が必要です。
⑤:少額減価償却資産を所有しよう
通常10万円未満の物は消耗品費として一括で経費にできますが、10万円以上の物は資産として計上し、減価償却をして数年に渡って経費にしなければなりません。
しかし、中小企業が30万円未満の物を購入した場合は、少額償却資産の特例を活用すれば、一括で経費にすることが認められています。
10万円、20万円の物でも一括で経費にできるため、中小企業にとってはありがたい制度です。
決算を迎える前に税金対策をしたいときは、10万円以上30万円未満のもので事業に必要な物がないかを今一度洗い出してみましょう。
少額償却資産の特例を適用するときは、確定申告書や法人税の申告書に明細を添付する必要があります。
明細を添付していないと経費処理が認められないため、注意しましょう。
⑥:福利厚生を充実させる
福利厚生を充実させることは、節税対策だけでなく、従業員の満足度向上にもつながります。
福利厚生を充実させることで、従業員のモチベーションを上げることもできるでしょう。
懇親会や慰安旅行、人間ドックの費用は福利厚生費として経費として損金計上することができます。法人保保険で福利厚生を充実させることもできます。
ただし、誰に対しても機会が平等であることが条件です。
特定の従業員しか参加していない場合は、従業員への給与とみなされ、税務調査で源泉所得税の支払を求められるケースがあります。
 福利厚生のために会社が法人向け保険に加入するメリットとは?
福利厚生のために会社が法人向け保険に加入するメリットとは?⑦:別会社を設立する
本格的な税金対策になりますが、資産管理目的の別会社を作ることも効果的です。
別会社で資産を購入し、会社に貸し付けるといった取引が考えられます。
中小企業では、利益のうち800万円以下の部分には軽減税率15%が適用されます。
別会社を設立することで、軽減税率を適用できる可能性が広がるでしょう。
ただし、別会社に実態がなかったり、取引内容が不自然であれば、税務調査で厳しく指摘されます。
別会社を設立する場合は、税理士などプロに相談したうえで慎重に判断しましょう。
⑧:社長が所有する不動産を貸し付ける
社長が所有する不動産を会社に貸し付けるという方法もあります。
会社としては、社宅や事務所として借りた不動産を活用することとなります。
事業のために不動産を使用すれば、社長に対して支払う家賃は、当然会社の経費として計上できます。
ただし、社長が受け取った不動産収入に対しては所得税がかかるので、注意しましょう。
法人税と所得税のバランスによっては、かえってトータルで支払う税金が高くなってしまうリスクもあります。
全体のバランスを見ながら検討することが大切です。
⑨:必要のない固定資産の見直しを行う
使われていない固定資産があれば、決算前に今一度見直してみましょう。
構築物や機械、車両など、使われていないものや既に廃棄したものが、帳簿上残っている場合があります。
金額や年数にもよりますが、除却損として損金計上できることがあるため、必ず確認しましょう。
また、使われていない資産や廃棄した資産を帳簿から削除することで、償却資産税の負担が少なくなる場合があります。
実態と帳簿を一致させておくことは、実態把握の観点からも大切だといえるでしょう。
⑩:出張手当を支給する
出張が多い業種であれば、役員や従業員に出張手当を支給することを検討するのも選択肢です。
出張手当は会社としては経費にすることができ、受け取った従業員としては所得税や住民税が課税されないというメリットの多い制度です。
ただし、旅費規程を設けて役員にしろ従業員にしろ同じ条件で支給することがポイントです。
税務調査で否認されることがないよう、金額設定にも気を配りましょう。
⑪:車両を受け入れる
個人で所有している車両を法人に売却することで、減価償却費を計上できることがあります。
特に個人から法人に車両を売却する場合は中古車の取り扱いとなるため、新車よりも短い年数で減価償却することができます。
個人で所有している車両を事業用として使用している場合は、法人への売却を検討しましょう。
できれば保険も法人に切り替えるのが望ましいですが、実態として事業用として使っていれば、個人加入の自動車保険料でも経費にすることができます。
中小企業に税金対策が必要な理由

どんな会社でも資金繰り改善のための税金対策は課題ですが中小企業の場合、大企業よりも重要です。
できるだけ税金を抑えることで会社の維持・発展のカギとなります。
大企業よりも対策が重要な理由は
- 大企業と比べると税金の負担が大きい
- お金の調達が厳しい
- 中小企業の場合、法人税・法人住民税は対策にならない
です。
つまり中小企業は大企業と比べて資金繰りの観点において、非常に厳しい経営をしいられます。
そのため対策が重要な理由を把握して適切な税金対策をすることが大切です。
対策をどれだけしっかり行うかで資金繰りがいかに改善するか、ひいては社運が左右されます。
社員の生活を担うためにも理解を深めましょう。
中小企業の方が税負担が重い
中小企業は大企業と比べると会社が出した利益に対し、発生する税金の割合が高いです。
2012年の調査では会社の資本金が1億円を下回る場合の外形標準課税非適用法人の実効税率(法人税、地方法人税、住民税、事業税の合計)は34.59%です。
一方で資本金が1億円を超える会社の外形標準課税適用法人は30.62%ですので資本金が少ない企業のほうが税率が3%ほど高いことがわかります。
社員の数や資本金が違うため安易に比較はできませんが、税率が3%変われば負担が大きいのは理解できるでしょう。
また大企業の場合、海外進出している会社が多いです。
海外進出するほど大きな会社の場合、所得税も大きな違いが生まれます。
なぜなら海外で売り上げたお金の税金はその国に支払うからです。
だから大企業のなかには積極的に海外展開をすることで、税金対策を行える会社もあるのです。
しかし中小企業は所得税も日本の法律が適応されますので負担が上乗せされてしまいます。
その他に社員やその家族の健康を守るために加入する社会保険のお金も必要です。
つまり中小企業の場合、課税につぐ課税で負担額が大企業と比べても多いことがわかるでしょう。
中小企業は大企業に比べて資金調達が難しい
中小企業がお金を調達するのはとても大変です。
大企業は目にする機会が多く、世間からの信用があります。
そのため銀行からも融資を受けやすいです。
また上場企業になれば株や社債も保有していますのであらゆる手段で資金調達が可能です。
しかし中小企業は経営者を中心とした家族が会社を回すお金を確保しています。
経営者のお金が底をついてしまったら途端に経営は行き詰まってしまいます。
中小企業は大企業のように上場していなければ株も保有していません。
そのため第三者から出資を募集すると法律に違反してしまうのでできません。
銀行から融資を受けたいと考えても企業としての功績や成果の他に今までの返済状況を基準として審査します。
中小企業はお金を調達するのがいかに難しいかは理解できるでしょう。
法人税と法人住民税は会社の経費には算入されない
中小企業が税金対策をする上で考えるべきポイント
中小企業が会社を維持・発展する上で大事なのが節税です。
節税は大変ですが、会社の経営状態を良いものにするためには肝心です。
この先、会社を維持するためにもチェックしておいてほしい点があります。
税金対策を検討するにあたって大事なポイントは
- 税金の繰延を行っても効果は一時的だと認識する
- 対策は節度を守った範囲に留め、過剰に行わない
です。
対策をする上で凄く大事なポイントですので理解を深めて経営に活かしてください。
税金の繰延の効果は一時的なものである
税金の繰延は税金の支払いを延ばすことができる制度のことです。
会社からお金が出ていく損益が上乗せされるので税金が安くなったようにみえます。
しかし利益が出た後は税金を納めなくてはなりません。
節税したようにみえて実は税金の支払いを一時的に逃れたにすぎません。
そのため税金の繰延は税金を払わなくて良いことにはなりません。
どうしても対策をしたいなら損益を利益と同じタイミングで捻出し続けなくてはなりません。
しかし損益にあてはまるものは国でも厳しい基準があります。
なかには損益で計上できると思っていたものがあてはまらない場合も考えられます。
繰延を行っても一時しのぎにしかならないことを頭に入れておきましょう。
いき過ぎた税金対策は行わないようにする
中小企業にとって税金対策は会社を維持するために大事なことですが、あまりやり過ぎてしまうのもよくありません。
一例をあげると
- 決算の時期に来年度に必要そうなものをたくさん購入する
- 行き過ぎた交際費を作って計上する
です。
節税対策のつもりが無駄にお金を使ってしまっているケースもあります。
お金を使いすぎてしまえばいくら節税ができたとしても結局は損失につながってしまい、経営を苦しくする原因になります。
方法によっては法律に違反する恐れもあるので節税対策は節度を守って行うことが大切です。
また法律に違反していなくてもいきすぎた節税は税務署が調査に入ったときに指摘されるケースもあります。
法律に違反していなければ問題ないわけではないので、常識の範囲内で節税の対策を講じましょう。
コラム1:法人向けの節税保険が販売停止に⁉
今、金融庁では全額損金タイプの法人保険を規制する動きが出始めています。
全額損金タイプの法人保険でも、保障を目的として加入するなら問題ありません。
金融庁が目をつけているのは、保険料を全額損金にしつつ解約した場合に解約返戻金がもらえるタイプの法人保険です。
法人保険にはさまざまな種類があり、過去にも終身がん保険などに規制が入り、全額損金から半額損金に見直されたという経緯があります。
全額損金タイプの保険にも、同様の規制が入る可能性があるでしょう。
ただし、規制が入ったとしても既に加入している保険については全額損金算入の処理が認められてきました。
今回も、規制が入る前に全額損金タイプの法人保険に加入するのも一つの選択肢かもしれません。
 節税保険を規制した「バレンタインショック」をわかりやすく解説!
節税保険を規制した「バレンタインショック」をわかりやすく解説!コラム2:役員や従業員の退職金準備方法!
役員や従業員の退職金を準備する方法には、いくつかの選択肢があります。
代表的な方法として
- 経営セーフティ共済
- 小規模企業共済
- 法人保険
- 中小企業退職金共済
などがあります。
経営セーフティ共済は、受け取った解約返戻金の使途が限定されていません。
経営者の退職金の原資としてはもちろん、従業員への退職金や取引先への交際費として用いることもできます。
 セーフティ(倒産防止)共済について
セーフティ(倒産防止)共済について小規模企業共済は加入した経営者本人が個人として受け取るため、経営者の退職金を積み立てる制度です。
法人保険は、経営セーフティ共済と同様、使途は自由に決めることができます。
退職金の他に、改装費用や設備投資に利用することもでき、必要なタイミングで必要な分だけを解約することもできます。
中小企業退職金共済は、従業員の退職金を積み立てることに特化した制度です。
掛金は経費として計上することができ、将来的には中小企業退職金共済から従業員へ直接退職金が振り込まれます。
中小企業退職金共済を利用するときは、計画的な積み立てや金額の見直しを行い、金額を管理することが重要です。
まとめ:税法に則った上で税金対策を行おう!
中小企業の11の対策方法を詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは、
- 脱税は犯罪なので、法律の範囲で対策することが大切。
- 法人保険を活用すれば資金を流出させることなく税金対策ができる。
- 優遇税制は期間を過ぎると適用できないため、注意が必要。
- 中小企業が対策を行う主な理由は3つある。
- 繰延は一時しのぎであることを認識する
- 対策はやり過ぎてしまわないように注意する
です。
資金繰りは経営の命綱ともいわれています。
効果的な節税対策を実施することで、会社を成長発展させる原資となる資金を確保しましょう。
また会社を守るためにも法律に違反する行為や違反しなくても限度を超える行為に気をつけてください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい法人保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。