
更新日:2024/08/06
合同会社設立後の社会保険への加入は絶対?3つの注意点を解説!
内容をまとめると
- 合同会社で加入する社会保険には健康保険と厚生年金保険があり、いずれも強制加入である。
- 社会保険に加入しなければ罰則を受けるうえに、2年遡って追徴を受けるので注意。
- 社会保険は合同会社を設立したら5日以内に加入する必要がある。
- 加入手続きをする場合、新規適用届と被保険者資格取得届の2つがある。
- 合同会社は株式会社に比べて設立費用が少なく、ランニングコストも低い。
- しかし、リスク対策が軽視されがちなため、マネーキャリアのように、リスク対策を「無料で何度でも」相談できるサービスを活用する方も急増している。

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 合同会社でも社会保険への加入は必須か
- 社会保険の概要や加入条件とは
- ①健康保険
- ②厚生年金保険
- 例外的に法人でも加入が強制ではないケースとは
- 社会保険に加入しない場合の他の保険制度
- 合同会社を含む法人は労働保険への加入も必要
- 合同会社が社会保険に加入する際の注意点とは
- ①加入しない場合は2年さかのぼって罰則を受ける可能性がある
- ②会社設立から5日以内に加入する必要がある
- ③社会保険への加入を断られる場合もある
- 社会保険の加入手続きの方法
- 社会保険料の計算方法とは
- 社会保険料の基本的な計算式
- 社会保険料は会社側と労働者側で折半する
- 社会保険加入時に合同会社が押さえておくべき例外ケースとは
- 副業などで2社から雇用されている場合
- 社長・代表が1人の合同会社でも生命保険を経費として払えるか
- 合同会社の業務執行社員は従業員向けの保険に加入できるか
- 社会保険と合同会社の事業リスク対策を両立するには
- 合同会社のリスク対策を「無料で何度でも」相談可能:マネーキャリア(丸紅グループ)
- 合同会社の社会保険加入時の注意点や手続きまとめ
目次
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合同会社でも社会保険への加入は必須か
合同会社の社会保険加入は法律で定められており、強制加入となります。
具体的には、健康保険法第3条と厚生年金法第9条によって、以下の2つの場合に該当する場合は強制加入とされています。
- 個人事業主(適用業種で従業員が5人以上)
- 法人(業種や従業員数に関係なく)
合同会社は会社法人なので、業種や従業員数に関係なく法的に加入が義務付けられていることがわかります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
社会保険の概要や加入条件とは
社会保険とは、健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険・介護保険などの公的保険の総称です。
各保険で加入必須条件が異なるため、概要や加入条件は、以下の表のとおりとなります。
| 保険の種類 | 概要 | 加入条件 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 社員とその家族が業務外で、 病気や怪我をした時に、 費用の一部を負担する制度 | 社長、役員、社員は加入必須 アルバイト、パートについては 雇用形態に応じて加入必須 |
| 厚生年金保険 | 公的年金制度(基礎年金・厚生年金) にかかる保険料 | 70歳未満の健康保険加入者 |
| 労災保険 | 従業員が勤務時や通勤時に 病気や怪我をした時に、 費用の一部を負担する制度 | アルバイト、パート含めた 従業員は加入必須 |
| 雇用保険 | 労働者が失業した場合及び労働者について 雇用継続が困難となった場合、 再就職までの生活費を補償 | 1週間の所定労働時間が20時間以上、 31日以上の雇用見込みがある労働者 |
| 介護保険 | 要介護認定を受けた際に介護費用を補償 | 40~65歳の健康保険加入者 |
①健康保険
健康保険には以下の3種類にさらに分類されます。
- 国民健康保険
- 協会けんぽ
- 組合健保
また、「個人事業主や従業員が5人未満の個人事業の従業員」の場合は、国民健康保険に加入することになります。
「法人や従業員5人以上の個人事業の従業員」の場合は、協会けんぽ(全国健康保険協会)の適用事業所であれば協会けんぽに加入し、組合健保(組合鑑賞健康保険)の適用事業所であれば組合健保に加入することになります。
ただし、従業員が5人未満の個人事業であったとしても、任意で協会けんぽの適用事業所になることが可能です。
②厚生年金保険
厚生年金保険とは、国民年金に上乗せされて支給される年金のことで、基礎年金である国民年金に厚生年金の受給額が加算され、その合計が支給されます。
厚生年金保険の適用事業所となるのは、法人と従業員が常時5人以上いる個人事業主の事業所です。
また、適用事業所の条件に当てはまらなくても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、厚生労働大臣の認可を受ければ適用事業所に該当されます。
厚生年金保険への加入の対象となるのは原則として社員のみですが、社員が勤務するべき時間の3/4以上働いている「パート従業員」にも適用することになっています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
例外的に法人でも加入が強制ではないケースとは
健康保険や厚生年金保険は、例外的に法人でも加入が強制ではないケースがあります。
それは、「社長の収入がない、もしくは極めて低いケース」が該当します。
健康保険や厚生年金の保険料は、給料から天引きして納付します。そのため、役員報酬が低すぎて保険料よりも低ければ天引きそのものができません。
経営者が会社の設立時に社会保険の加入申請を行ったとしても、収入がない状態であれば、年金事務所側から加入を断られる可能性があるので注意しましょう。
社会保険に加入しない場合の他の保険制度
仮に収入がない、もしくは極めて低い場合でも、何らかの保険・年金制度には加入しなくてはいけません。
このようなケースの場合、
- 国民健康保険(地方自治体が運営している)
- 国民年金(日本年金機構が運営している)
合同会社を含む法人は労働保険への加入も必要
労災保険法・雇用保険法では、「従業員を雇っている場合、強制加入」となります。
合同会社が社会保険に加入する際の注意点とは
ここでは、合同会社が社会保険に加入する際の注意点を解説します。
合同会社を設立したにもかかわらず、社会保険に加入しなければ、ペナルティや罰則を受けることがあるので、以下の注意点は押さえておくようにしましょう。
- 加入しなかった場合の罰則
- 会社を設立してから加入するまでの期間
- 社会保険への加入を断られてしまう場合
①加入しない場合は2年さかのぼって罰則を受ける可能性がある
合同会社を設立した場合、社会保険への加入は法的に義務付けられており、加入しなかった場合は罰則を受けてしまいます。
社会保険に加入しなかったとしても、ただちに罰則を受けるわけではありません。社会保険に加入していないことを年金事務所が把握すると、文書や電話、会社への訪問によって加入するように勧奨が行われます。
しかし、年金事務所の通知や勧奨を無視すると、会社に立ち入り調査が行われ、強制的に加入することになります。社会保険に加入しないまま時間が経ってしまった場合、社会保険への加入義務が発生してから2年間に遡って追徴を受けることになるので注意しましょう。
健康保険法では、以下に該当する場合は「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処すると定められています。
- 被保険者の資格の取得及び喪失について届け出をせず、または虚偽の届け出をしたとき。
- 被保険者の資格の取得及び喪失について通知をしないとき。
- 督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
- 保険料を納付せず、帳簿を備え付けず、報告せず、もしくは虚偽の報告をしたとき。
- 文書その他の物件の提出もしくは提示をせず、当該職員の質問に答弁せず、もしくは虚偽の答弁をし、もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき。
また、年金事務所から督促をされた後、督促の期限を過ぎると、延滞金が発生してしまいます。延滞金は延滞の期間の日数に応じて、保険料に加算されます。
②会社設立から5日以内に加入する必要がある
社会保険は、合同会社を設立してから「5日以内」に年金事務所に届け出をする必要があります。(「合同会社の設立」とは、法人登記が完了した時を指します。)
合同会社の法人登記をする際は、自分で行う場合はスムーズに進むものの、司法書士に依頼する場合は、司法書士が申請をしてからおおむね3週間程度かかってしまいます。
そのため、司法書士に依頼してから3週間以内に社会保険関係の書類を準備しておくと、スムーズに進みます。
③社会保険への加入を断られる場合もある
合同会社を設立したら社会保険への加入は法的義務ですが、例外的に、社会保険への加入を断られてしまう場合もあるのです。
社会保険への加入を断られるのは「役員報酬がゼロである場合」と「役員報酬が保険料を下回るほど低い場合」が該当します。
また、上記における役員とは「取締役」「会計参与」「監査役」の3つを指します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
社会保険の加入手続きの方法
社会保険への加入手続きをするには、年金事務所に届出を行う必要があります。
社会保険の加入の届出をする際に書類を提出する必要がありますが、以下2つの届出の場合によって提出する書類が異なります。
- 会社設立の際に一度だけ行う届出
- 会社設立後に加入対象者が増えた場合に行う届出
会社設立の際に一度だけ行う「新規適用届」では、以下の書類を提出します。
- 新規適用届
- 登記簿謄本
- 事業所の所在地と登記簿が異なっている場合は、所在地を確認するための公的証明書のコピーなど
そして、会社設立後に加入対象者が増えた場合に行う「被保険者資格取得届」では、以下の書類を提出します。
- 被保険者資格取得届
- 年金手帳
- 加入対象者に被扶養者がいる場合は健康保険者被保険者異動届出
社会保険料の計算方法とは
ここでは、社会保険の計算方法について、「社会保険料の基本的な計算式」や「社会保険料の支払い対象者」に関して解説します。
社会保険料の基本的な計算式
まず、社会保険料の基本的な計算式は、以下になります。
標準報酬月額×保険料率=ひと月当たりの健康保険料
標準報酬月額とは、「毎年4~6月の3か月間の給料の平均額」によって決まる金額のことです。標準報酬月額は、一度等級が決まれば1年間の保険料計算で使われるため、残業でお給料の額が変わっても影響は受けません。
社会保険料は会社側と労働者側で折半する
社会保険料は、会社と労働者側で折半するため、合同会社を設立した場合でも会社側は、社会保険料を半分負担しなくてはなりません。
健康保険料率は、加入する制度によってどれくらい負担するかは変わり、一般的におよそ10%ほど負担します。そして、厚生年金保険料率は18.3%の負担となるため、合計して約30%の半分であるおよそ15%を会社が負担しなくてはならないのです。
社会保険料が高ければ15%の負担も大きくなるので、事前に金額を把握して正しく資金繰りの調整をしておく必要があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
社会保険加入時に合同会社が押さえておくべき例外ケースとは
ここでは、合同会社の社会保険についてより深く知るために、以下の4つの点を解説します。
- 副業などで2社から雇用されている場合に保険はどうなるか
- 社長や代表が1人の場合でも生命保険を経費にできるか
- 合同会社の設立をすると節税になるか
- 合同会社の業務執行社員は従業員向けの保険に加入できるか
副業などで2社から雇用されている場合
社長・代表が1人の合同会社でも生命保険を経費として払えるか
生命保険に加入した時に支払う保険料は、法人契約であれば会社の経費にできます。
1人で合同会社を経営している場合に関しても、一般的な会社法人と変わりなく保険料を経費にできます。
また、1人で合同会社を経営している場合、加入できる保険の種類も一般的な法人と変わりません。
 法人保険のおすすめ比較ランキング|専門家一押しの法人保険を紹介!
法人保険のおすすめ比較ランキング|専門家一押しの法人保険を紹介!合同会社の業務執行社員は従業員向けの保険に加入できるか
合同会社の業務執行社員は、従業員向けの労災保険や雇用保険には加入できません。
合同会社の業務執行社員とは、株式会社で言えば取締役にあたる役員を指すので、従業員向けの保険に加入するには、会社に雇用されていなければなりません。
そのため、合同会社の業務執行社員は、従業員向けの保険には加入できないのです。業務執行社員と会社との関係は、「雇用関係」ではなく「委任関係」となっているからです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
社会保険と合同会社の事業リスク対策を両立するには
以下では、社会保険と合同会社の事業リスク対策を両立するのに最適な方法を紹介します。
合同会社の社会保険加入は必須ですが、法定福利厚生としてのリスク対策だけでは不十分な可能性があります。たとえば、従業員が増えた場合や万が一のケースがあった場合でも、事業運営は滞りなく進めなければなりません。
しかし、社会保険の加入のみでは、上記リスクに対応できないことからも「法人保険」を活用してリスクに備える合同会社も増えているのです。一方、設立直後や創業フェーズの会社では、経営陣がリスク対策に時間を割くことも難しいのが現状です。
そこで、法人保険のプロへ「無料で何度でも」リスク対策を相談できるマネーキャリアを使うのが必須です。
丸紅グループ運営のマネーキャリアは80,000件以上の保険提案の実績から得たノウハウを活かし、自社の状況を総合的に判断したうえで「自社の理想を叶える提案に強み」を持ち、満足度も98.6%を誇ります。
合同会社のリスク対策を「無料で何度でも」相談可能:マネーキャリア(丸紅グループ)
合同会社の社会保険加入時の注意点や手続きまとめ
ここまで、合同会社運営に伴う社会保険への加入や注意点に関して解説しました。
合同会社で加入する社会保険には健康保険と厚生年金保険があり、いずれも強制加入です。また、社会保険に加入しないと罰則を受け、2年遡って追徴を受けるので注意しましょう。
社会保険は合同会社を設立したら5日以内に加入する必要がある一方で、役員報酬が低いと加入を断られる場合もあります。また、加入手続きをする場合、新規適用届と被保険者資格取得届の2つがあります。
合同会社は株式会社に比べて設立費用が少なく、ランニングコストも低い一方で、リスク対策が軽視されがちです。そのため、まずはマネーキャリアのように、リスク対策に関して無料で何度でも相談できるサービスを活用する方も急増しているのです。
無料登録は30秒で完了するので、ぜひマネーキャリアを活用し合同会社の事業リスクに備えられる体制を作りましょう。



















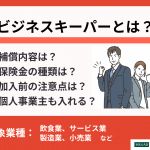
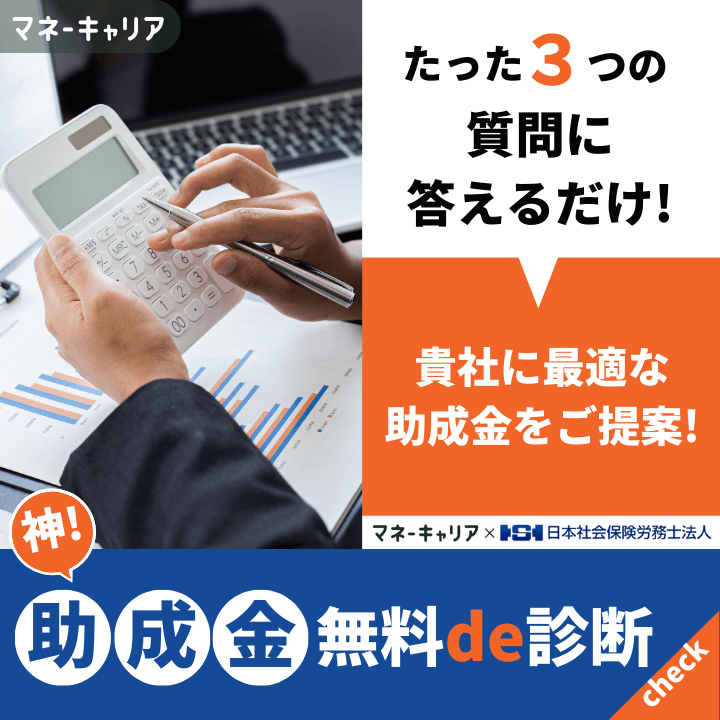
設立費用やランニングコストが低いため、株式会社よりも合同会社を設立したいと考えている方もいます。合同会社を設立した際は社会保険への加入は義務ですが、単に社会保険への加入手続きをすれば済むわけではありません。
実は、会社の状況によっては社会保険への加入を断られる場合があったり、加入しないと懲役や罰金を課せられてしまったりする場合もあるので、上記リスクに備えたい経営者の方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では「合同会社の社会保険加入の概要や3つの注意点、社会保険への加入手続き」を中心に解説します。
・合同会社の経営にあたって社会保険関係の手続きをスムーズに済ませたい
・合同会社の設立や維持ににかかる費用負担を削減しつつ事業運営に集中したい
方は本記事を参考にすると、社会保険関係で手間を取らずにスムーズに合同会社を設立・維持できるうえに、押さえておきたいリスク対策もわかります。