
更新日:2025/09/01
個人年金保険に入らない方がいい・おすすめしない理由は?入るなって本当?
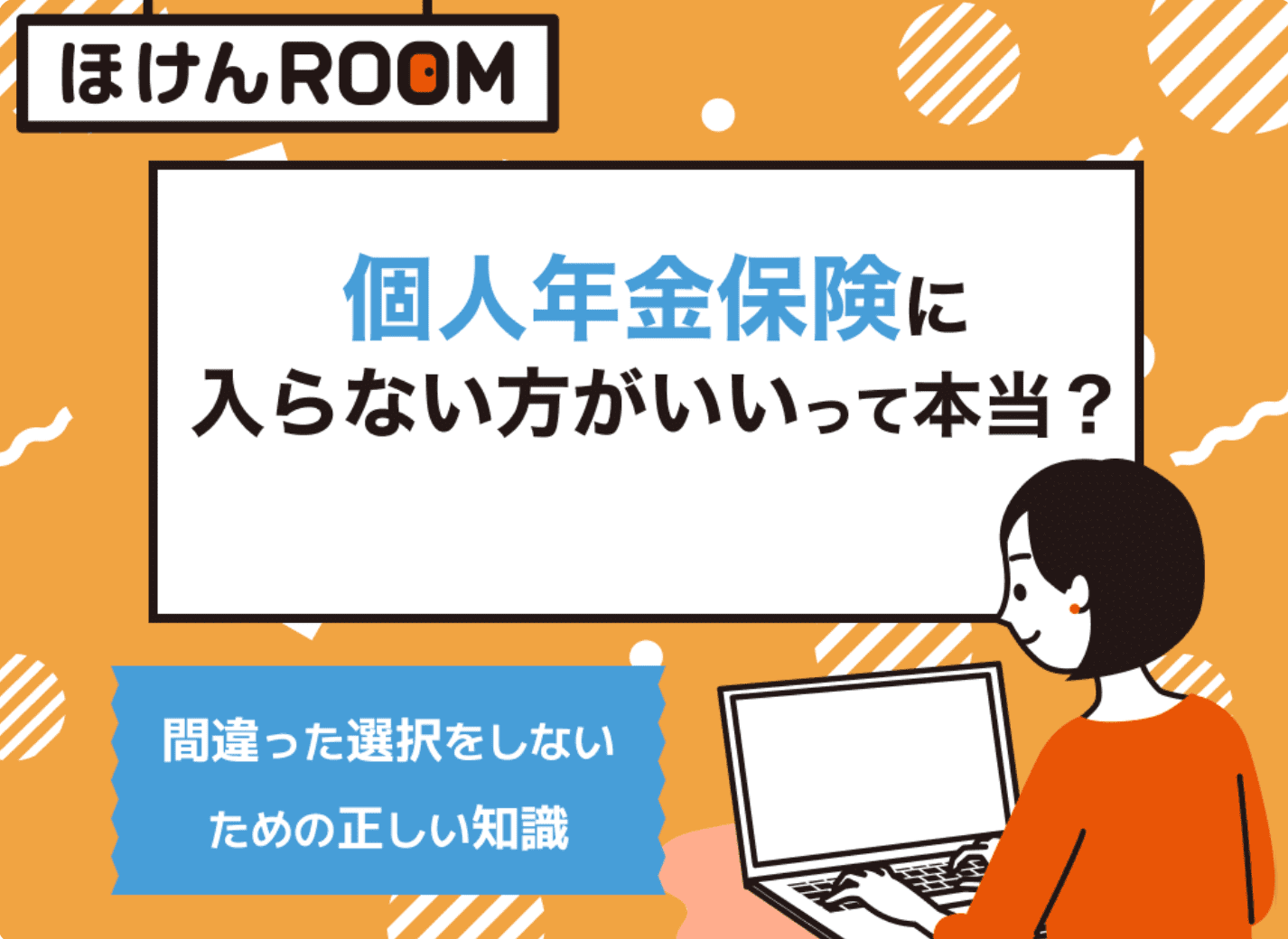
・貯金が少なくて年金だけで老後の生活をしていけるか不安
・個人年金保険は入らないほうがいいって聞いたけど本当?
内容をまとめると
- 個人年金保険に入るなと言われる理由は早期に解約すると元本割れする可能性がある
- 個人年金保険のメリットは保険料控除
- 個人年金保険以外の老後資金の準備方法としてつみたてNISAやiDeCoがある
- マネーキャリアは相談申込40,000件以上、相談満足度93%、在籍FP3,000人以上という国内最大級の保険相談サービス!
個人年金保険とは一定の年齢まで保険料を積み立てて、積立金を元に年金をもらう公的年金の上乗せ補完として利用する保険です。
後半では個人年金保険のメリットやおすすめの資産形成方法について解説しているので、最後までご覧下さい。
▼この記事を読んで欲しい人
- 個人年金保険に入らないほうが良いと言われる理由を知りたい人
- 子供の進学費用や生活費の出費が多く、老後資金が準備できていない人
- 貯金が少なく年金で老後生活を送れるか不安な人

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 個人年金に入らない方がいい・おすすめしないと言われる5つの理由
- ①外貨建て保険の為替リスク
- ②変額個人年金の運用リスク
- ③インフレしたら実質的に損をする
- ④お金が必要になって個人年金保険を解約すると元本割れする
- ⑤亡くなる年齢が若いと元本割れする可能性がある
- 個人年金保険に入らない方がいい・おすすめしない人は?
- ①長期間の積立を好まない人
- ②資産形成やお金全般の知識に詳しくより得するお金の活用ができる人
- ③貯蓄が少ない人
- ④資産を増やしながら老後資金を用意したい人
- ⑤インフレリスクが怖い人
- 個人年金保険を入るな・おすすめしない人は何で資産運用すべき?
- 銀行預金
- iDeCo
- つみたてNISA
- 個人年金保険に入る2つのメリット
- ①保険料控除
- ②貯金が苦手な人は貯金の代わりにできる
- 個人年金保険に入った人の口コミ・評判を紹介
- 個人年金保険の利率を種類ごとに詳しく解説!
- ①円建て個人年金保険
- ②外貨建て個人年金保険
- 個人年金保険に入るならiDeCoの方がおすすめ!
- 自分に合った最適な資産形成方法を知りたいならまずはお金のプロに無料相談!
- 参考:個人年金保険の加入率|実際にどれくらいの人が加入してる?
- 「個人年金に入るな」という意見に対するまとめ
目次
個人年金に入らない方がいい・おすすめしないと言われる5つの理由

個人年金保険に入るなと言われる3つのリスク
- 外貨建て保険の為替リスク
- 変額個人年金の運用リスク
- インフレしたら実質的に損をする
- お金が必要になって個人年金保険を解約すると元本割れする
- 亡くなる年齢が若いと元本割れする可能性がある
①外貨建て保険の為替リスク
外貨建て保険の為替リスクは必ず押さえておきたい点です。
簡単な例を挙げてみましょう。ここでは分かりやすく外貨建ての一時払い保険を契約したとします。
ドルのレートが110円のときに10,000ドルを入れた場合日本円で110万円です。そして10年後の満期時には運用によって11,000ドルになるとします。
もし10年後の為替レートが90円になった場合と130円になった場合をみてみると
- 90円×11,000=99万円
- 130円×11,000=143万円
| 最高値 | 最安値 |
|---|---|
| 125.89円 (2015年6月) | 75.54円 (2011年10月) |
②変額個人年金の運用リスク
変額個人年金は払い込んだ保険料で運用を行い、その運用実績が年金額に直接影響します。
そのため運用実績によっては年金総受取額が払込保険料を下回る可能性があるということが特筆すべきリスクと言えます。
投資先は国内外の株式や債券が主です。そのため投資先で紛争が起きたり災害が起きた場合には運用率が下がります。
最近ではコロナの発症やワクチンの完成などで株式が大きく上下することがありました。
このように投資先の環境によっては利益はでますが、元本割れの可能性があることも知っておかなければいけません。
また保険と運用を同時に行っているため手数料が高めです。
手数料分が引かれるためそもそも元本の復活に時間がかかります。その間に解約してしまうと解約返礼率がぐっと低くなってしまいますので注意しましょう。
③インフレしたら実質的に損をする
④お金が必要になって個人年金保険を解約すると元本割れする
⑤亡くなる年齢が若いと元本割れする可能性がある
個人年金保険に入らない方がいい・おすすめしない人は?

個人年金保険に入らない方がいい・おすすめしない人は以下の通りです。
- 長期間の積立を好まない人
- 資産形成やお金全般の知識に詳しくより得するお金の活用ができる人
- 貯蓄が少ない人
- 資産を増やしながら老後資金を用意したい人
- インフレリスクが怖い人
上記の5点について説明します。
この5点に当てはまる人は、個人年金保険に入らない方がいいかもしれません。
自分に当てはまるかどうか考えながら読んでくださいね。
①長期間の積立を好まない人
長期間の積立を好まない人にはおすすめできません。
契約時に定めた期間積み立てを行い、その資金を保険会社が運用することで満期時100%以上の年金受取ができるようになっているのが個人年金保険です。
このような商品の性質上短くても5年、基本的には10年以上の長期間契約となります。
そのため流動性が低く、使いたいときにすぐ引き出せるような商品ではありませんので注意が必要です。
コツコツ積み立てていくのが基本的な運用方法のため短期間で利益を追求したい人には向いていないでしょう。長期的な目線で資産運用を考える人にはおすすめです。
②資産形成やお金全般の知識に詳しくより得するお金の活用ができる人
資産形成やお金全般の知識に詳しくより得するお金の活用ができる人は加入しない方が良いでしょう。
そもそも知識があるため個人年金保険という選択肢はあまりないかもしれませんが、今の時代に合った資産形成方法は他にもたくさんあります。
例えば下記で詳しく説明しますが、少額で投資可能なiDeCoやNISAなどですね。
個人年金保険は返礼率が期待できなくても、リスクが少なく比較的安定した運用ができるため(特に円建て)金融知識があまりない人やリスクについての許容が難しい人には良いでしょう。
しかし資産形成についての知識がある方にとっては返礼率の低さの方が目立ってしまいます。
③貯蓄が少ない人
④資産を増やしながら老後資金を用意したい人
- 払い込み:25年間(35歳から)毎月2万円
- 受け取り:毎年62.9万円(65歳から10年間)
- 支払った保険料の総額:600万円
- 受け取る年金額:629万円
- 返礼率:104.8%
⑤インフレリスクが怖い人
個人年金保険を入るな・おすすめしない人は何で資産運用すべき?

個人年金保険をおすすめしない・入らないほうがいい人は何で資産運用すべきでしょうか。
この項ではおすすめの資産運用を
- 銀行預金
- iDeCo
- つみたてNISA
上記の3点について説明します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
銀行預金
iDeCo
- iDeCoで掛けたお金は全額が所得控除の対象となり、住民税と所得税が軽減されます。
- iDeCoは運用収益が非課税です。通常、株や投資信託など金融商品を運用した際に出る利益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoの場合はすべて非課税です。
- iDeCoは退職金や年金として控除が適用されます。60歳以降に受給する確定拠出年金を「老齢給付金」といいます。年金の場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」となり、受け取るときもメリットがあります。
つみたてNISA
個人年金保険に入る2つのメリット

個人年金保険に入る2つのメリットについて紹介します。
主な利点は
- 保険料控除
- 貯金が苦手な人は貯金の代わりにできる
①保険料控除
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
②貯金が苦手な人は貯金の代わりにできる
貯蓄が苦手な人はサブ的な貯蓄代わりとして利用すると良いでしょう。
現金を持っていたり、口座にお金があるとついつい使ってしまってなかなか貯蓄ができないという方もいるでしょう。
個人年金保険は
- 中途解約をすると支払保険料を下回る額しか返ってこない
- 保険会社を通しての手続きが必要
という理由から解約に至る可能性が少なくなっています。
個人年金保険という自分の手が届かないところに積み立てをしていくことで貯蓄ができるでしょう。
個人年金保険に入った人の口コミ・評判を紹介
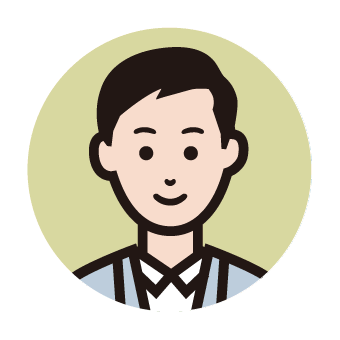
40代男性
日々の節約と将来の楽しみのため
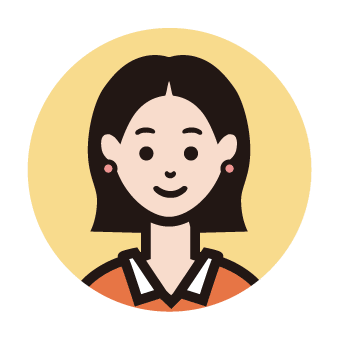
30代女性
外貨建個人年金保険は手数料が高い
保険外交員はこちらが指摘するまで肝心なことはいいませんでした。
1万円引き落としでも実際の積み立てられる保険金は6500円程度。
よって多少見かけの利率が良くても、10年程度の保険期間では100%元本割れします。(大きく円安になれば別ですが。)

40代女性
多様な選択肢があります。
実際支払いが厳しくなってきた事から、満了年齢を60歳から55歳に変更できました。
このようにリスク回避方法を教えてくれるのもありがたいです。
個人年金保険の利率を種類ごとに詳しく解説!
個人年金保険の返礼率を種類ごとにみていきます。
- 円建て個人年金保険→明治安田生命「年金かけはし」
- 外貨建て個人年金保険→住友生命「たのしみグローバル指数連動型」
①円建て個人年金保険
円建て個人年金「年金かけはし」契約例
- 35歳男性
- 月額保険料20,000円
- 据置期間なし
- 10年確定年金
| 年金開始年齢 | 65歳 |
|---|---|
| 振込期間 | 30年 |
| 払込総保険料額 | 720万円 |
| 年受取総額 | 約749万円 |
| 返礼率 | 104% |
| 振込期間 | 25年 |
|---|---|
| 払込総保険料額 | 600万円 |
| 年受取総額 | 約628万円 |
| 返礼率 | 104.8% |
②外貨建て個人年金保険
外貨建て個人年金保険のシミュレーションがネット上でできるものはありませんでした。実際の契約例をみるには保険会社に請求が必要です。
住友生命「たのしみグローバル指数連動型」は積立率が1年間の指数上昇率×連動率(契約時に決定)によって決定される少し特殊な例です。
SGI FIAマルチアセット指数の上昇率に応じて上昇します。商品内容や詳しい説明が気になる方は公式ホームページをチェックしてみてくださいね。
年齢や詳しい受取額等の記載はありませんでしたので過去の返礼率の紹介をします。
| 米ドル | 米国債金利0.5% | 米国債金利1.4% |
|---|---|---|
| 据置期間(保険期間)5年 | 106.2% | 116.4% |
| 据置期間(保険期間)10年 | 115.1% | 144.7% |
| 豪ドル | 豪国債金利0.8% | 豪国債金利0.9% |
|---|---|---|
| 据置期間(保険期間)5年 | 103.5% | 103.6% |
| 据置期間(保険期間)10年 | 113.2% | 114.6% |
返礼率はついては豪ドルよりも米ドルの方が高めになっています。
米国債券10年ものの利回りは1年で1%近く変動することもあるため、為替のリスクと合わせると振れ幅は大きいと言えるでしょう。
円建ての個人年金保険に比べれば高い返礼率ですが、豪ドルの103%や米ドルの116%をみると入るなとは言いませんがリスクの大きさに比例していないように感じます。
個人年金保険に入るならiDeCoの方がおすすめ!
個人年金保険に入るならiDeCoの方がおすすめです。
iDeCoとは自分で決めた額を積立し、運用方法を定め60歳以降に年金を受け取れるよう準備する制度です。
加入条件は20~60歳で
- 国民年金の第1号被保険者(自営業者、フリーランス、学生など)
- 国民年金の第2号被保険者(会社員、公務員など)
- 国民年金の第3号被保険者(専業主婦など)
となっています。
iDeCoの特徴は税制優遇が大きなところです。
個人年金の控除上限は年間で4万円でしたが、iDeCoの場合は第何号の被保険者かによって変わりますが自営業であれば年間で最大81.6万円の控除が可能です。
また利益が非課税で受取にも「退職所得控除」「公的年金等控除」のどちらかが適用されます。
運用についてはリスクがあり、60歳まで引き出せないなどの注意点はありますが検討すべき方法の1つです。
個人年金との比較を表にまとめます。
| iDeCo | 個人年金保険 | |
|---|---|---|
| 加入年齢 | 20~60歳 | 保険会社によって異なる |
| 積み立ての上限 | 月1.2万円~6.8万円(職業による) | 保険会社によって異なるが基本は制限なし |
| 中途解約 | 不可 | 可 |
| 税制優遇 | 小規模企業共済等掛金控除 運用益非課税 退職所得控除or公的年金等控除 | 個人年金保険料控除 |
| 受給開始年齢 | 60歳 | 契約時に設定 |
 個人年金を詳しく比較
個人年金を詳しく比較自分に合った最適な資産形成方法を知りたいならまずはお金のプロに無料相談!
自分に合った最適な資産形成方法を知りたいならまずはお金のプロに相談することをおすすめします。
主観的な視点からは見えなかった提案を客観的に行ってくれます。リスク分散も踏まえたうえで具体案をだしてくれますので一度は利用してみると良いでしょう。
相談箇所がたくさんあって選べないという方は「マネーキャリア」での相談をおすすめします。
全国対応で何度でも相談は無料です。契約件数は12,000件以上にのぼり、顧客満足度は驚きの93%を誇っている信頼できる保険サービスです。
現在コロナの影響もありなかなか外出できないという方もオンライン対応のため自宅から安心して相談できますよ。
「保険の知識がないから不安」「ライフプランもしっかり決まってないけど」という方でも大丈夫。
経験豊富なFPがしっかりサポートしてくれますので、まずは気軽に相談してみましょう。
参考:個人年金保険の加入率|実際にどれくらいの人が加入してる?
個人年金保険の加入率は実際にどのぐらいなのでしょうか。
公益財団法人生命保険文化センターの「2021年度生命保険に関する全国実態調査」によると全体の加入率は21.4%と5人に1人は加入しているようです。
年齢別にみてみましょう。
| 加入割合(%) | |
|---|---|
| 29歳以下 | 14.4 |
| 30~34歳 | 22.4 |
| 35~39歳 | 16.7 |
| 40~44歳 | 17.0 |
| 45~49歳 | 25.1 |
| 50~54歳 | 28.7 |
| 55~59歳 | 29.3 |
| 60~64歳 | 28.1 |
| 65~69歳 | 23.0 |
| 70~74歳 | 16.7 |
| 75~79歳 | 15.6 |
| 80~84歳 | 11.6 |
| 85~89歳 | 12.0 |
| 90歳以上 | 13.0 |
「個人年金に入るな」という意見に対するまとめ
個人年金保険に入るなという意見に対して
- シミュレーション
- リスク
- 口コミ・評判











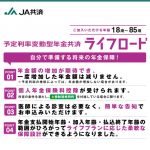











当記事でこのような方に向けて個人年金保険に入らないほうが良い・おすすめしないと言われる理由を解説します。
個人年金に入らない方がいい・おすすめしないと言われる5つの理由をすぐに見る