
更新日:2022/06/10
医療保険・生命保険の違いと必要性は?加入はセットがおすすめ!

「医療保険と生命保険の違いは?」「医療保険と生命保険をセットで加入するのはおすすめ?」このような悩みを抱える人は多いでしょう。そこで本記事では、医療保険と生命保険の違いを解説、世帯別におすすめの保険の組み合わせ方を紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
- 生命保険の種類や医療保険との違いが分からない人
- 保険を一つにまとめるべきか悩んでいる人
- 医療保険・生命保険それぞれの必要性を知りたい人
内容をまとめると
- 医療保険と生命保険の主な違いは対象となるリスクと保険金受取人
- 医療保険は公的制度でカバーしきれずに不足する医療費に対しての備え
- 生命保険は死亡時に家族が困らないようにするための備え
- 保険の加入や選び方で悩みがある場合、マネーキャリアでプロに保険相談がおすすめ
- 今ならスマホひとつで無料保険相談が可能!保険選びのアドバイスをもらいましょう

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 【結論】子持ちは医療保険・生命保険のセット加入がゼッタイ必要!
- 医療保険は「病気やケガでかかる費用」を保障する保険
- 生命保険は「生命」に関わる保障|「死亡保険」を指すこともあり
- 医療保険と生命保険の違いは「何を保障するか」と「誰のためか」
- ①保障内容|「治療費」の保障?それとも「死亡時」に備える?
- ②誰のために加入するか|「自分のため」か「家族のため」か
- 医療保険の加入が必要な人の3つの特徴
- 特徴①自分の病気で家族の生活を圧迫することに不安を感じている
- 特徴②先進医療費に備えたい|先進医療は数百万円する高額な治療
- 特徴③長期治療に備えたい|負担が100万円近くなることもある
- 生命保険の加入が必要な人の2つの特徴
- 特徴①遺された家族の負担を減らしたい|万が一に備える
- 特徴②これから子供の教育費や養育費がかかる人
- 医療保険と生命保険はセット加入を!【おすすめの組み合わせ方】
- ①独身20〜30代:定期医療保険・葬儀費用の定期死亡保険で十分
- ②子持ち20〜40代:手厚い定期医療保険・定期死亡保険に加入
- ③50代:手厚い終身医療保険・最低限の終身死亡保険
- 【参考】医療保険の基礎知識
- 医療保険の保障内容
- 特定条件に特化した医療保険もある|主な種類を紹介
- 【参考】生命保険の基礎知識
- 生命保険の種類
- 死亡保険の種類
- 生命保険には医療保障の特約をつけるメリット・デメリット
- 生命保険に医療保障の特約を付加する3つのメリット
- 生命保険に医療保障の特約を付加する2つのデメリット
- 【注意】医療保険と生命保険に共通:免責事由を確認しよう
- まとめ:医療保険・生命保険選びに迷ったらマネーキャリアで無料相談
目次
【結論】子持ちは医療保険・生命保険のセット加入がゼッタイ必要!
結論から言うと、子どもがいる世帯主の方は、医療保険と生命保険にセットで加入することを強くおすすめします。
また、子持ちの方だけでなく、その他の年代・世帯の方にもおすすめの組み合わせがあります。
- 独身20〜30代:定期医療保険+最低限の定期死亡保険
- 子持ち20〜40代:手厚い定期医療保険+大きな定期死亡保険
- 50代:手厚い終身医療保険+最低限の終身死亡保険
この記事を読むとわかることは以下の通りです。
- 医療保険は「病気やケガでかかる費用」を保障する保険
- 生命保険は「生命」に関わるものを保障|「死亡保険」を指すこともあり
- 医療保険と生命保険の違いは「何を保障するか」と「誰のためか」
- 医療保険と生命保険はセット加入を!年代・世帯別おすすめの組み合わせ方
- 医療保険・生命保険選びに迷ったらマネーキャリアで無料相談
ぜひ最後までご覧いただき、医療保険と生命保険の必要性について確認しましょう。
医療保険は「病気やケガでかかる費用」を保障する保険
医療保険は、病気やケガの治療・入院などの費用を保障する保険です。
日本には医療保険が2種類あります。
- 公的医療保険
- 民間医療保険
公的医療保険は国の制度で、すべての国民が加入しています。普段、私たちが医療費の3割のみを負担しているのは、公的医療制度のおかげです。
公的医療制度には以下のものが含まれます。
- 医療費の自己負担は1割~3割
- 高額療養費制度
- 傷病手当金
- 医療費控除
一方、民間医療保険は民間の保険会社の商品で、希望した人が加入します。一般に「医療保険」といった場合には、この民間医療保険を表すことが多く、この記事では民間医療保険を「医療保険」と呼び、解説していきます。
医療保険は、民間の保険会社が提供しており、公的な医療保障制度ではカバーしきれない医療費への備えとして利用されています。加入すると、 病気やケガなどで入院・通院したときや、手術を受けたときにかかる医療費に対する給付金を受け取ることが可能です。
公的医療制度によって、医療費の自己負担は1割~3割に抑えられますが、実際には「差額ベッド代」「入院中の食事代」「先進医療費」など公的医療保険の対象外のものがあり、さまざまな費用がかかります。
このような公的医療保険ではカバーできない負担分に備えるための保険が医療保険です。
生命保険は「生命」に関わる保障|「死亡保険」を指すこともあり
生命保険は、名前の通り「生命」に関わるさまざまなものを保障する保険です。
生きている中には、「死亡」「生存」「病気」「けが」「介護」など、さまざまなリスクが存在しています。安心して生活するには、死亡や病気の他にも「長生きによるリスク」や「子どもの学費」など、生きていると必要になるさまざまなものに備える必要があります。
生命保険とは以下のような保険です。
- 死亡に備える
- 病気やケガに備える
- 将来に備える
生命保険には、これらすべてのリスクに対するさまざまな保険商品が用意されています。
また、生命保険のうち、死亡に備える保険である「死亡保険」のことを「生命保険」呼ぶこともあるので覚えておきましょう。
医療保険と生命保険の違いは「何を保障するか」と「誰のためか」

生命保険には以下のようなさまざまな種類があります。
- 死亡保険
- 医療保険
- がん保険
- 傷害保険
- 介護保険
- 学資保険
- 個人年金保険
生命保険に含まれるそれぞれの保険は、対象となるリスクに違いがあります。それぞれのリスクに対応した保険がつくられているため、多くの種類があります。
先程紹介した「医療保険」も生命保険のひとつです。
生命保険は様々な保険の総称とも言えますが、「死亡保険」のことを指して「医療保険」と呼ぶ場合も多くあります。ここでは「死亡保険」としての生命保険と、「医療保険」の違いについて解説していきたいと思います。
主な違いは以下の2つです。
- 保障内容
- 誰のために加入するか
どのような違いがあるのか、簡単に表にしたものを見てみましょう。
| 対象となるリスク | 保険金受取人 | |
|---|---|---|
| 生命保険 | 死亡 | 配偶者や子供 |
| 医療保険 | 病気やケガ | 本人 |
これらの違いを理解して、必要な保障を準備できるようにしておきましょう。
①保障内容|「治療費」の保障?それとも「死亡時」に備える?
違いのひとつが保障内容です。
- 医療保険:病気やケガの治療費をカバー
- 生命保険:死亡時への備え
医療保険は病気やケガの治療費に対する備えがメインの保障です。治療にかかる金銭的な負担に対して備えておくことで、治療費を気にすることなく治療に専念できるようになります。特に、高額になる入院や手術に対して備えます。
また、長期入院で働けず、収入が減ってしまうことに備える目的もあります。
生命保険は死亡時の保障を行う保険です。死亡や高度障害時に保険金が支払われることで、今後の家族の生活費などをカバーすることを目的としています。
このように、医療保険と生命保険は対象となるリスクが全く違うため、保障内容も大きく異なります。どちらに加入するか悩んでいる場合には、自分に必要な保障内容を見極めるようにしましょう。
場合によっては、両方加入することも検討が必要です。
②誰のために加入するか|「自分のため」か「家族のため」か
医療保険と生命保険では「誰のために加入するのか」、つまり「保険金の受取人」にも違いが見られます。
主な保険金受取人は以下の通りです。
- 医療保険:本人
- 生命保険:家族
医療保険は、基本的には本人が給付金を受け取ります。
治療を受けたり入院したりした際に請求することで、費用の負担を抑えることができます。治療費がカバーされることで費用を気にすることなく治療に専念ができるようになります。
生命保険の保険金受取人は、家族です。
生命保険に加入することで、自身が死亡した際に遺された家族が生活で困らないよう、ある程度まとまった金額が支払われるようにしておきます。家族構成などによって準備しておく金額はそれぞれです。
このように、「何に対しての保障なのか」「誰のための保障なのか」によって、必要となる保険に違いが出てきます。
医療保険の加入が必要な人の3つの特徴
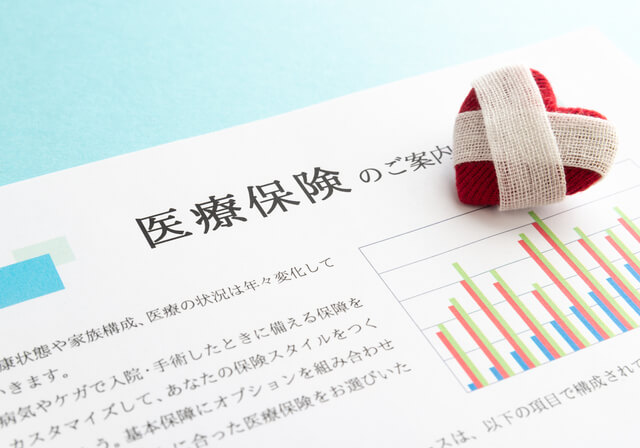
医療保険は公的医療保険ではカバーできない部分を補うために加入するものです。そのため、公的医療保険でどれくらいカバーされるのか、自分の場合どれくらい足りなくなるのかを知っておく必要があります。
たとえば入院をした際、実際の医療費がどれくらいになるのかは、高額療養費制度の限度額を知っておくとある程度想像できます。一般的な年収の方が高額療養費制度を利用する場合、月の上限額は8万円程度です。
(参考:厚生労働省・高額療養費制度)
高額療養費制度の限度額に、食事代や差額ベッド代などの費用を足したものが、必要な医療費となります。この金額を目安に、貯蓄でまかなうことができるのか、保険で準備しておくべきなのかを見極めるようにしましょう。
医療保険の加入を検討するべき人としては、
- 自分の病気で家族の生活を圧迫することに不安を感じている人
- 進医療費に備えたい人
- 長期治療に備えたい人
などが挙げられます。以下でこれらの方の医療保険の必要性について解説していきます。
医療保険の必要性に関してより詳細な知識を得たい方は以下の記事「民間医療保険の必要性【年代別】」が参考になります。
特徴①自分の病気で家族の生活を圧迫することに不安を感じている
まず挙げられるのが、収入や貯蓄に不安があり、自分の病気で家族の生活を苦しめたくない人です。
病気の治療時には治療費を支払う必要があります。公的医療保険で負担は3割まで減少しますが、負担が無くなるわけではありません。
また、入院をすれば差額ベッド代や入院中の食事代もかかり、それらは公的医療保障の対象外です。
家族がいる場合には、家族の生活には通常通りの生活費が発生することになります。そこに医療費が重なると、たとえ少額でも生活費を圧迫する可能性もあります。
入院や治療中には、仕事ができなくなる可能性も忘れてはいけません。
治療や入院に伴う医療費や、働けない間の収入減によって家族の生活を圧迫することに不安を感じている人、特に自由に使える貯蓄が少ない人は、医療保険で備えておきましょう。
特徴②先進医療費に備えたい|先進医療は数百万円する高額な治療
先進医療費の利用を考えている人にも、医療保険への加入をおすすめします。
公的医療保険で医療費を抑えることができますが、あくまで対象になっている事が前提です。
- 先進医療
- 自由診療
これらは公的医療保険の対象外で、かかった費用は全額自己負担となってしまいます。
病気の治療方法には様々なものがあり、なかには先進医療や自由診療に分類されるものもあります。
例えば、がん治療の中で
- 陽子線治療
- 重粒子線治療
といった治療がありますが、これらは先進医療なため200万円〜300万円もの費用がかかります。この先進医療の費用には、医療保険の先進医療特約で対応可能です。もし、医療保険の先進医療特約がなければ、このような高額な医療費を全額負担する必要があります。
費用を気にせず治療方法の選択肢を広げておきたい場合には、医療保険で準備しておくのがおすすめです。
特徴③長期治療に備えたい|負担が100万円近くなることもある
長期の入院となった場合の費用負担に備えるためにも、医療保険は必要です。
入院や治療の際には、公的医療保険の「高額療養費制度」や「傷病手当金」を利用することができます。
高額療養費制度とは、1ヶ月にかかる医療費の自己負担額には上限が設けられており、その上限を超えた金額については後から支給される制度です。一般的な年収(年収約370万円〜770万円)の方で、1ヶ月の自己負担の上限額は8万円程度となります。
傷病手当金とは、病気やケガで働けなくなった場合に給料のおよそ3分の2の金額が、最長1年半の間支給される制度です。
しかし、数ヶ月以上の長期入院となった場合には、これらの公的保障を利用したとしても、自己負担額はかなり大きいものとなります。
一般的に、給料の6割くらいが生活費に充てられているといわれています。その場合、傷病手当金として給料の3分の2が支給されたとしても、そのほとんどは生活費に回ってしまい、医療費の支払いにはなかなか充てられない可能性があります。
また、自営業などの人が加入する国民健康保険には、傷病手当金の仕組み自体がありません。自営業やフリーランスの人は、働けなければ収入がなくなってしまう可能性があります。
高額療養費制度を利用すれば、1ヶ月の医療費の負担は8万円程度で済みますが、その対象とならない費用も存在します。
具体的には、
- 入院中の差額ベッド代
- 入院中の食事代
- 入院中の日用品費
- 先進医療費
- 医師の診断書の費用
1ヶ月に必要となる費用を計算してみると、
日額5,000円 × 30日 + 約8万円(医療費の自己負担額の上限) = 約23万円
となり、入院で月25万円前後の金額が必要となることがわかります。仮に4ヶ月以上の長期入院となれば、100万円以上の費用負担となる可能性もあるのです。がんや生活習慣病は、他の病気と比べて治療が長期化・再発しやすい傾向にあります。場合によっては数年以上の入院となる可能性もゼロではありません。
このような長期の入院となった場合の高額な費用負担には、医療保険で備えておくのが一番です。
生命保険の加入が必要な人の2つの特徴
生命保険の加入を検討するべき人としては、
- 万一の時に遺された家族の負担を減らしたい人
- これから子供の教育費や養育費がかかる人
が挙げられます。
生命保険は自分に万一のことがあった際に、遺された家族が生活に困ることが無いように準備しておくものです。
そのため、独身の場合には必要性や必要額が低くなりますが、家族がいる場合には必要性はかなり高いでしょう。特に、家族が多い人や小さい子供がいる人には必要性が高いと言えます。
以下では検討するべき人について詳しく解説していきます。
特徴①遺された家族の負担を減らしたい|万が一に備える
万一の際に遺された家族の負担を減らしたい人は、生命保険への加入をおすすめします。
どれくらいの金額があれば生活していけるのか考えてみましょう。
65歳以上になると年金の支給が開始されますが、もし夫が亡くなった場合、妻の年金額だけで生活ができるのかを計算してみます。
まずは生活費についてです。
「家計調査年報(平成28年)」では、65歳以上の単身者の消費支出額が
- 月額:143,460円
- 非消費支出:12,085円
とされています。合計で15万円以上の支出となり、さらに医療費や介護費がかかることを考えると、これ以上の出費が考えられます。
しかし、妻だけの年金として受け取れるのは12万円程度と言われており、3万円以上の不足が出てきてしまいます。
仮に妻が65歳で夫が亡くなり、90歳までこの状態が続くことを考えると、900万円の不足と計算できます。
貯蓄で900万円を準備しておくのもひとつの方法ですが、介護などでこれ以上の金額となることも予想されるため、保険でしっかりと確保しておくのがおすすめです。
特徴②これから子供の教育費や養育費がかかる人
これから子供の教育費や養育費がかかる人も生命保険への加入が必要と言えます。
一般に、子供の教育費としてかかる金額は約944万円です。これは小・中・高校を公立で、大学を私立にした場合にかかる費用です。全て私立を希望する場合には、さらに高額な教育費が必要となります。
小さな子どもがいる人の場合、万一の際に教育費の心配がないように、生命保険を活用し準備しておく必要があります。
一方で、子供が独立してからはこれほど高額な備えは必要ないと言えます。
ある程度の貯蓄があるのならば、葬儀費用が賄える程度の最小限の保険に見直すことで、毎月の保険料を抑えることが可能です。
子供が小さい間だけ「定期タイプの生命保険」で手厚い保障をしておくなど、ライフステージや家計と照らし合わせて過不足の無い生命保険になるようにしましょう。
医療保険・生命保険に関してより詳細な知識を得たい方は、以下の記事「医療保険・生命保険の種類をわかりやすく解説!必要性を公的保険と比較」が参考になります。
医療保険と生命保険はセット加入を!【おすすめの組み合わせ方】
生命保険や医療保険には様々な種類があります。保障内容も商品ごとに違い、さらに保険期間のことを考えると多数の組み合わせ方があることが分かります。
どのような組み合わせをすればよいのかはライフステージや家族構成などにより違います。
医療保険は必要なのか、生命保険の保障額はどれくらいが適当なのか、などをしっかりと考えてなくてはなりません。
自分に何が必要なのかを把握するためにも、結婚や子供の有無で必要保障がどのように違うのかを確認していきましょう。
以下では、
- 独身20〜30代
- 子持ち20〜40代
- 50代
の場合に必要性が高くなる保障についてご紹介していきたいと思います。
①独身20〜30代:定期医療保険・葬儀費用の定期死亡保険で十分
医療保険
独身の方であれば家族がいる人に比べて生活費はあまりかからないので、長期入院などで働けなくて収入が入らなくても、公的保障である傷病手当金で大部分はまかなうことができます。
したがって医療保険による保障は最低限で良いでしょう。具体的には、給付金の日額は3,000円〜5,000円程度で十分です。
気を付けておきたいのが、終身型ではなく定期型の医療保険を選択することです。
20代〜30代と若いうちから終身型に加入してしまうと、最も医療保険が必要となる高齢となった時期に、「保障内容が時代に合わず必要な保障が十分に受けられない」という事態になりかねません。
若いうちは定期的に保障の見直しができるよう、定期型の医療保険に加入することをおすすめします。
生命保険
独身の方が万一の場合に備えておかなければならないものは、自分の葬儀にかかる費用です。葬儀費用の備えを自らしておくことで、親族に金銭的な負担をかける心配がなくなります。
子どもや妻(夫)がいる人の場合とは違って、遺された家族が生活していくためのお金を用意しておく必要はありませんので、そこまで大きな死亡保障の金額は必要ありません。
葬儀費用について定期死亡保険で備えておきましょう。
具体的には、死亡保険金の金額は200万円〜500万円程度で十分です。
仮に30代後半〜40代になって独身である場合には、保険の見直しをして終身死亡保険への加入を検討しましょう。
結婚して家族が増える場合にも、保険の見直しは必要です。定期保険で保障を上乗せするなどしておくと安心でしょう。
②子持ち20〜40代:手厚い定期医療保険・定期死亡保険に加入
医療保険
子どもがいる家庭は生活費にかかるお金が多いので、給料のうちの生活費が占める割合は比較的大きくなります。
したがって長期入院などで働けなくて収入が入らない場合、公的保障である傷病手当金が支給されても、それだけでは生活費をまかないきれない可能性もあります。
それを補うためにも、医療保険の給付金の日額は1万円程度と手厚くしておくことをおすすめします。
生命保険
毎月の保険料が高くなり生活を圧迫してしまうことを避けるためにも、生命保険も定期型に加入するのがおすすめです。
万一のことがあったときには、子どもが18歳になるまでは妻の年齢にかかわらず遺族基礎年金を受給することができます。さらに会社員の場合には、これに加えて遺族厚生年金も受給できます。
遺された家族が生活していくのに、これらの公的保障で足りない分について生命保険で補うようにしましょう。
③50代:手厚い終身医療保険・最低限の終身死亡保険
医療保険
一般的に年齢を重ねると病気の罹患率は上がりますので、医療保険がより重要となります。
50代の方であれば、一生涯の保障を得られる終身型の医療保険に加入しましょう。
さらに生活習慣病や認知症など、自分にとってリスクが高いと思われるものに対して保障をプラスするとより一層安心です。
日頃の生活習慣において、食生活の乱れや運動不足、喫煙習慣がある人などは、がん保険や三大疾病保険を検討しましょう。
認知症や三大疾病において遺伝によって罹患するリスクが気になる方も同様に備えておきましょう。
また、認知症や脳卒中、心筋梗塞などに罹患した場合は、要介護状態となったりリハビリが必要となるケースもあります。
そういったケースに備えて、併せて民介護保険についても加入しておくと、家族にとって介護による負担が少なくなるのでさらに安心でしょう。
生命保険
50代の方であれば、子どもがいる場合でも独立している頃でしょう。
したがって高額な死亡保険金は必要ありませんので、葬儀費用分くらいの最低限の金額で、終身死亡保険に加入しておきましょう。
それぞれの年代や家族構成によって最適な保険の選び方があります。自分の場合はどうなのか、迷ったときには保険のプロに相談してみましょう。
顧客満足度93%のマネーキャリアなら、無料でオンライン相談ができます。
【参考】医療保険の基礎知識
医療保険は公的医療保険制度を利用しても不足してしまう医療費に対して備えておく保険です。
健康保険などを利用することで、医療費の支払額はかなり抑えられます。高額療養費制度では支払金額に限度が設定されるようになるため、公的医療保険の対象となる治療の負担額は一定金額までです。
貯蓄が多い人など、まとまった金額を治療に割ける人ならば、保険を利用せずとも問題なく治療が受けられると考えるかもしれません。
しかし実際には、差額ベッド代や先進医療など、公的医療保険の対象外の費用が多くかかります。
このような「公的医療保険ではカバーしきれない医療費」に対し、医療保険はとても有効です。
ここでは以下の2点について詳しく解説していきます。
- 医療保険の保障内容
- 医療保険の主な種類
医療保険の保障内容
主な保障内容としては、
- 入院給付金:入院に対して保険金が支払われる
- 手術給付金:手術に対して一定額が支給される
があります。
どちらも入院日額を基準に計算することがほとんどです。
- 入院給付金:入院日額×日数
- 手術給付金:入院日額×給付倍率
給付倍率は一定の場合と、手術の種類によって倍率に違いがあるものがあります。商品ごとに倍率が違うため、しっかりと確認するようにしましょう。
その他にも以下のような特約を付帯することで、自分に必要な保障をカスタマイズすることができます。
- 通院給付金:通院治療に対しての保障
- 先進医療給付金:先進医療での治療費が保障
- 入院一時金:入院することでまとまった金額が支給される保障
特約を付加する際は、家計の負担にならない保険料になるよう、保険料・家計・補償のバランスが取れているかに注意しましょう。
特定条件に特化した医療保険もある|主な種類を紹介
医療保険はさまざまな特徴によって複数の種類に分類されますが、ここでは特定の条件によって保障がなされる以下の3つの商品タイプを紹介します。
- 女性向け医療保険
- 引受基準緩和型医療保険
- 無選択型医療保険
などが挙げられます。
「引受基準緩和型医療保険」や「無選択型の医療保険」は、保険に加入した人の生活費を大きく圧迫しかねない為、本当に必要か検討する必要があります。
医療保険①女性向け医療保険
女性特有の病気に対する保障が手厚くなる医療保険です。妊娠時の病気や子宮や卵巣に関する病気などに対して保障が厚いという特徴があります。通常の医療保険に特約を付帯することでも、女性特有の疾病に対して手厚く備えておくことが可能です。
医療保険②引受基準緩和型医療保険
契約時の審査がゆるいため、既往歴などがあっても加入しやすい保険です。
通常の保険は健康な方を対象にしているため、経験した病院の有無や種類によっては加入を断られてしまいます。このような方には保険料が多少高くなってしまいますが、審査のゆるい引受基準緩和型がおすすめです。
医療保険③無選択型医療保険
契約時に審査が無いタイプの保険です。誰でも加入することができるため、どのタイプにも加入できなかった場合に最終手段として活用する医療保険です。保険料はかなり高額に設定されています。
【参考】生命保険の基礎知識
生命保険は自分に万一のことがあった場合、遺される家族が金銭的に困ることが無いように備えておく保険です。
家族構成などにより必要な金額が変わるため、契約時にはどれくらい必要になるのかをしっかりと計算する必要があります。
配偶者の有無や子供の有無で金額が大きく変わります。独身の場合には葬儀代程度の金額を準備しておけば良いですが、配偶者がおり子供が小さい間は生活費の他教育費に対しても備えをしておく必要があります。
また、死亡時に対して備えつつ、資産を増やせるタイプの生命保険もあります。通常の死亡保険とは違い、貯蓄性を重視した商品も出されています。
以下では、以下の2つのポイントから生命保険の基礎知識を理解しましょう。
- 生命保険の種類
- 死亡保険の種類
生命保険の種類
生命保険にはおもに、以下の3つの種類があります。
- 死亡保険
- 生存保険
- 生死混合保険
死亡保険
死亡・高度障害時が対象です。遺された家族が金銭的な不安を感じないように準備しておく保険です。自分のためではなく家族に対して準備しておくものです。
ex.定期死亡保険・終身死亡保険
生存保険
一定期間生存時が対象です。保障の為ではなく老後資金の準備に利用されることが一般的ですが、最近では利率が低いため特に加入の理由がない場合はおすすめはしません。
ex.個人年金保険・学資保険など
生死混合保険
死亡・生存の両タイプが合わさっているような保険です。死亡時などの万一の際に受け取れるのはもちろん、生存して満期が来た場合にも受け取ることができます。
ex.養老保険
死亡保険の種類
生命保険のうち代表的なのが「死亡保険」です。この「死亡保険」のことを指して「生命保険」と呼ぶことがあるほど、生命保険の中ではメジャーな保険です。
この死亡保険の4つのタイプについて説明します。
- 定期死亡保険
- 終身死亡保険
- 養老保険
- 収入保障保険
定期死亡保険
保険期間が5年や10年と区切られているタイプです。継続するためには更新が必要になり、その都度保険料が上がります。
終身死亡保険
保険期間は一生涯です。定期保険と違い更新を行う必要はありません。保険料も契約時のものが生涯続くため、若いうちに加入しておくことで安い保険料をキープすることができます。養老保険
資産形成しつつ万一の際に備えておく保険です。満期になるタイミングを自由に設定することができるため、老後資金だけでなく子供の教育資金の準備など様々な利用方法があります。
収入保障保険
被保険者が死亡した場合、受取人に保険金が支払われる保険です。通常の生命保険と同じように感じるかもしれませんが、支払われる金額が時間経過とともに減っていくという点が大きな違いです。死亡すると毎月支払いが開始されますが、保険期間の終了と共に支給も終わるため、受取開始が遅いとその分支給額は減ってしまいます。
貯蓄型の保険には積立金運用方法によっても以下のような種類に違いがあります・
- 定額保険
- 変額保険
- 外貨建て保険
ただし、保険はあくまで保障のために加入するものであることは忘れずに、それでも必要と判断した場合にのみ加入するようにしましょう。
定額保険
保険金額に変動がないタイプです。リスクはありませんが利率は低いため、保険料は高めに設定されています。
変額保険
運用成績によって保険金額が上下する保険です。運用次第では保険金額が高くなる・保険料が安いなどのメリットはありますが、反対に保険金額などが減少するリスクがあります。万一のためというよりは、資産を増やすことを目的にしています。外貨建て保険
保険料を外貨で運用する保険です。予定利率が高いため、円建ての商品よりも多く増える可能性のある保険です。しかし、為替リスクが付いて回るため、運用利益が出ていても為替次第で損をしてしまうリスクがあります。生命保険には医療保障の特約をつけるメリット・デメリット
生命保険の特約には医療保険のような保障内容を含んだものがあります。
以下では生命保険に医療保障を特約として付加するメリットとデメリットについて解説していきます。
生命保険に医療保障の特約を付加する3つのメリット
生命保険に医療保障を特約として付帯した場合のメリットは主に以下の3つです。
- 管理がしやすい
- 保険料が安い
- 保障のダブりに気付きやすい
メリット①管理がしやすい
ひとつにまとめて契約を行っているため、管理がしやすくなります。保険金などを請求する際には同じ担当者へ連絡すればよいため請求しやすく、加入相談などにもまとめて行ってもらえることがメリットの一つです。
メリット②保険料が安い
ひとつにまとめることで契約などの手続きが省けるため、事務手数料などがかからないことになります。その分保険料は安めに設定されています。
メリット③保障のダブりに気付きやすい
保障内容も把握しやすくなり、保障に重複があることに気付きやすくなります。無駄が無くなるため、保険料で損をすることもありません。
保険を一つにまとめることで上記のようなメリットがあります。しかし、通常の医療保険と特約の医療保障ではカバーされる内容に若干違いがある場合も多いため、しっかりと内容を把握してから特約を付帯するようにしてください。
生命保険に医療保障の特約を付加する2つのデメリット
デメリットとしては、以下の2つがあげられます。
- 主契約を解約すると特約もなくなる
- 最適な保障を組み合わせることができない
デメリット①主契約を解約すると特約もなくなる
生命保険に付帯しているため、この主契約を解約してしまうと医療保障も同時に解約となってしまいます。医療保障が気に入っている場合には主契約を継続しなくてはいけないため、保険の見直しがしにくくなってしまう事がデメリットのひとつです。
デメリット②最適な保障を組み合わせることができない
通常の医療保険を選ぶ際には、自分が必要と感じる商品を選ぶこともできますし、カスタマイズ性の高い商品であれば自由に保障を組み合わせることも可能です。しかし特約の医療保障ではあまりカスタマイズ性はなく、保障を組み合わせて自信に有利な形に変えることはできません。
自身にぴったりの保障内容にしたい方には、保険の一本化はあまりおすすめできないと言えます。
医療保険と生命(死亡)保険を組み合わせたセット加入がおすすめです。
【注意】医療保険と生命保険に共通:免責事由を確認しよう
医療保険と生命保険に共通する注意点として、免責事由に当てはまる場合には保険金が支給されないということが挙げられます。
せっかく保険に加入していても、免責事由に当てはまってしまうと保険金を受け取ることができません。
- 自殺
- 泥酔による死亡事故
- 告知義務違反
などが当てはまります。これらが当てはまる場合には保険金が受け取れないということをしっかりと覚えておきましょう。
特に告知義務違反はうっかり記入ミスをしてしまった場合でも保険金の支払対象外となってしまう可能性があります。
万一の時のために加入していても、実際に利用できなくては意味がありません。契約時にはうそをつかないことはもちろん、記入ミスや記入漏れがないかどうかもしっかりと確認してから提出するようにしましょう。
まとめ:医療保険・生命保険選びに迷ったらマネーキャリアで無料相談

いかがでしたか?ここでは医療保険と生命保険の違いについてご紹介しました。
医療保険は病気の治療など自分のための備え、生命保険は死亡時など遺された家族への備えという違いがありました。
それぞれ保障内容や保険金受取人に大きな違いがありますが、どちらも必要性の高い保険と言えます。
しかし、どのような保障内容が必要なのか、保険金額をどれくらいにすればよいのかは個人ごとに違います。加入自体を悩んだり、商品で迷う場合には、相談満足度93%のマネーキャリアの利用がおすすめです。
無料で何度でも相談が可能で、さらに相談相手はMDRTやFPなどの資格を持った保険の専門家です。しっかりとその人に合った保障内容を選んでくれるため、加入前にぜひ相談してみてください。

















