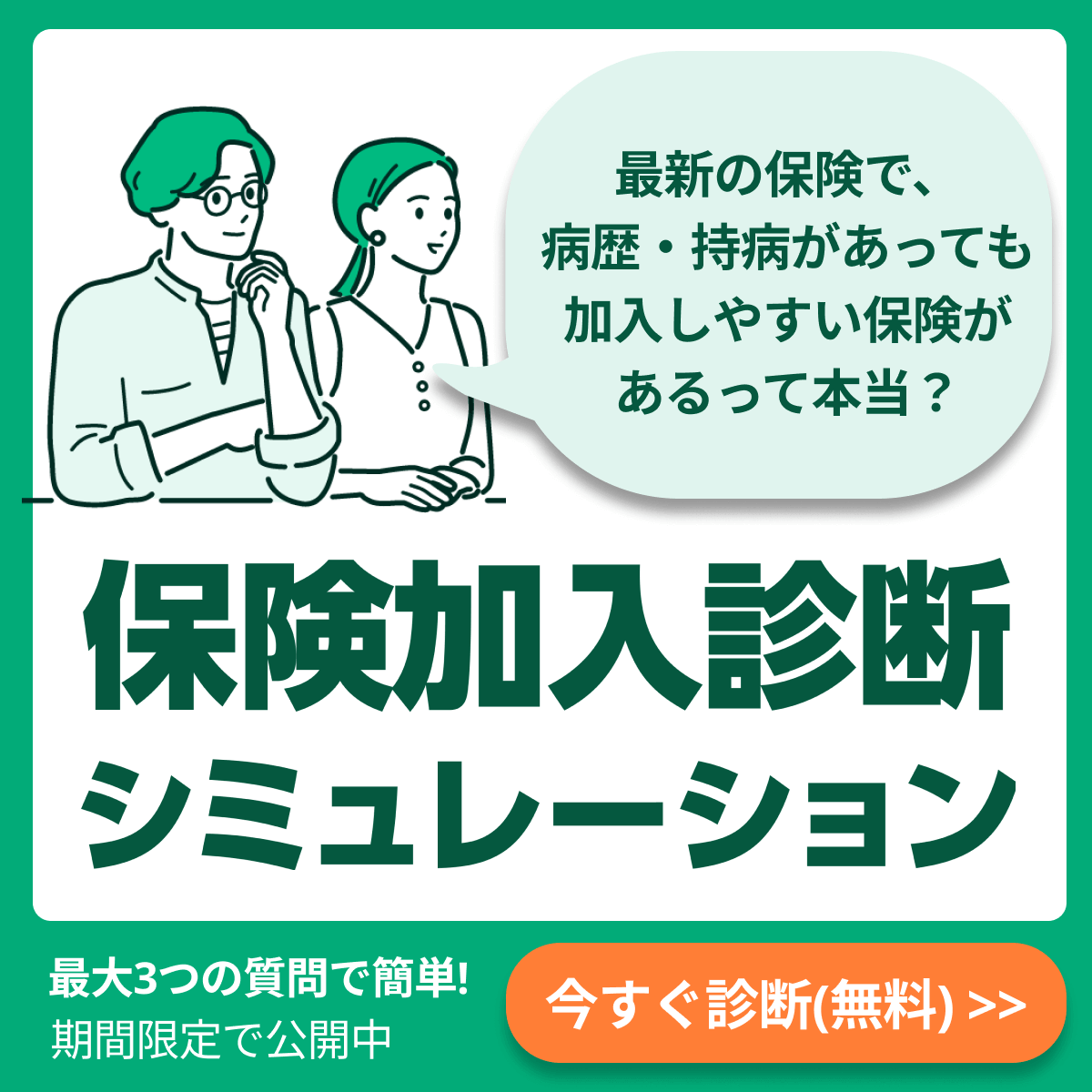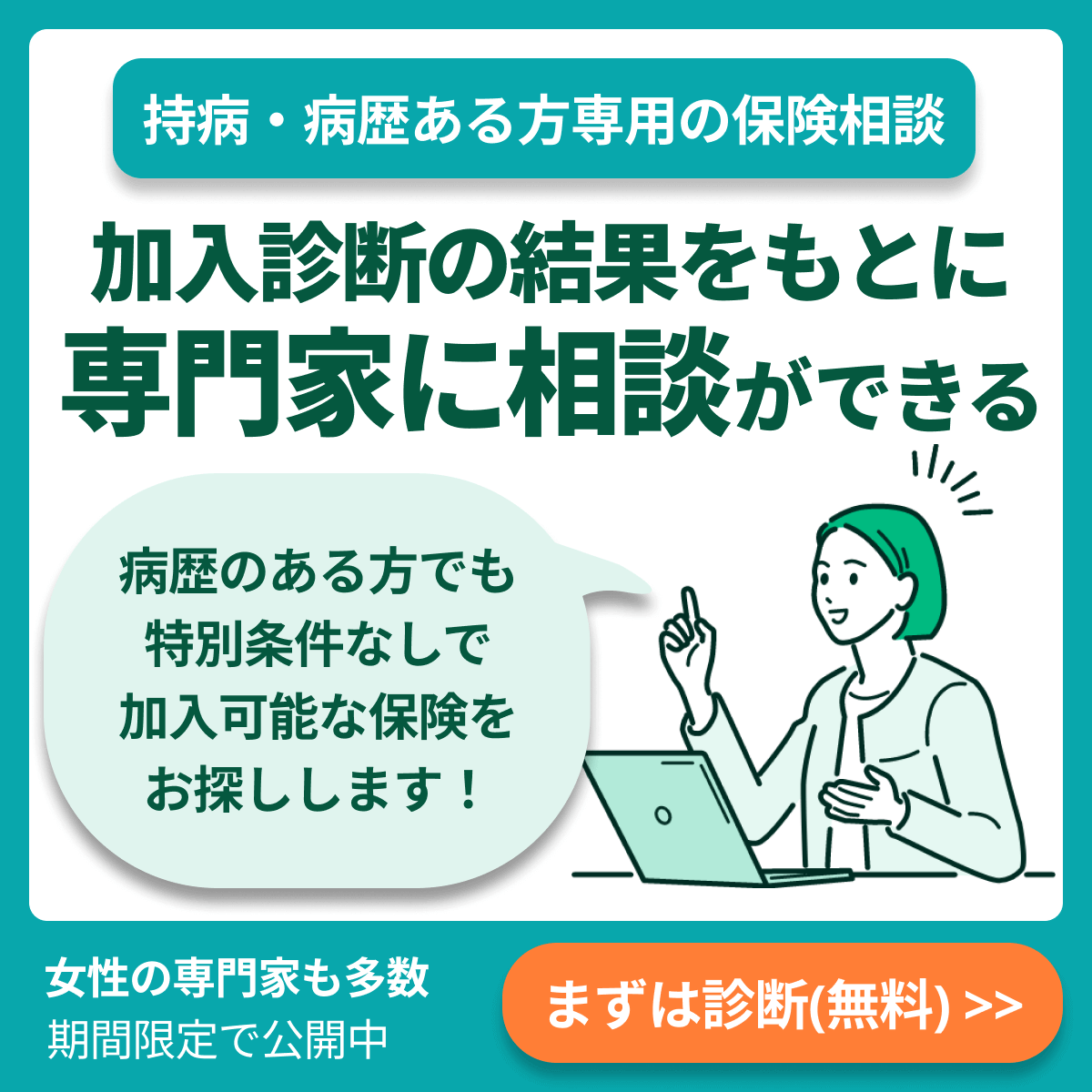更新日:2023/03/24
妊娠中でも医療保険には加入できるのか?注意点も含めて解説!
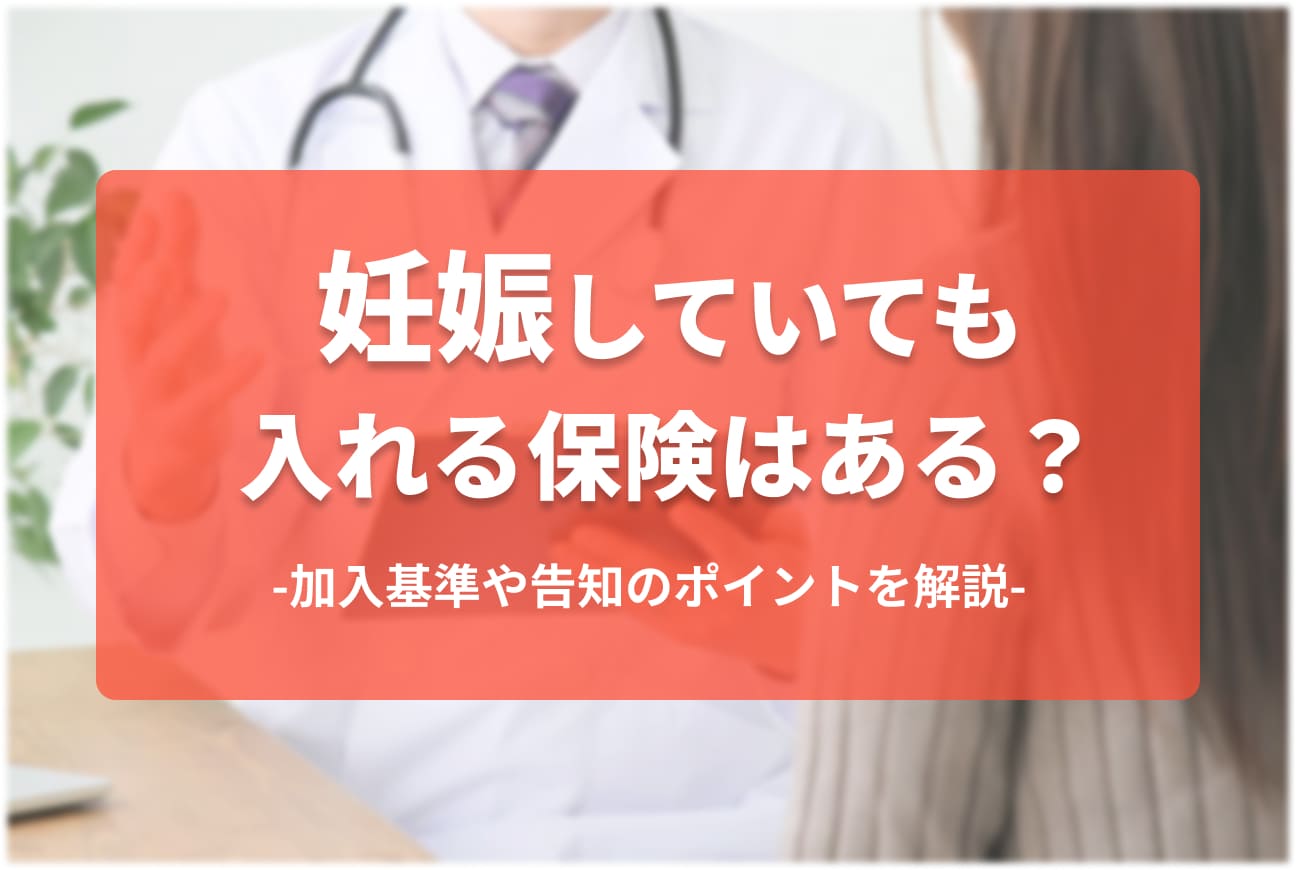
妊娠中でも保険に加入できるのか?妊婦や赤ちゃんの医療費や出産費用がかかり妊娠中の保険加入について知りたい人向けに解説していきます。妊娠中の保険には妊娠には保障範囲に様々な種類があるため今回は妊娠中に加入できる保険や妊娠保険の比較、妊娠中の医療費保障のある保険について解説します。
内容をまとめると
- 妊娠中でも保険に加入はできる!
- 妊娠前から病気を抱えていた人や妊娠中に合併症が発生した人は保険に加入できない場合がある
- 妊娠中に保険加入する際は、妊娠中の健康状態を告知することが必要になる
- 妊娠中の保険でお悩みの方は妊娠保険専門のマネーキャリアを有効活用することがおすすめ!

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 妊娠中の保険はプロに相談した方がいい理由
- 妊娠中でも保険に加入できますか?
- 妊娠中で保険に加入できない場合も解説
- 妊娠中でも入れる保険の種類
- 妊娠中でも医療保険には加入できる?注意点と共に解説!
- 医療保険の対象期間に注意
- 医療保険の保障範囲に注意
- 出産に必要な費用はどのくらいか
- 自然分娩の出産費用
- 異常分娩の出産費用
- マタニティ・ベビー用品
- 妊娠中でも医療保険に加入すべき理由
- 入院費用に備える
- 帝王切開・切迫早産に備える
- 出産後の赤ちゃんのために
- 公的医療保険制度の対象外に備える
- 妊娠中の医療保険選びで知っておくべきポイント
- 解約のタイミングの制限
- 医療保険選びに迷ったらプロに相談する
- 告知義務に注意する
- 妊娠・出産時に公的医療保険を利用できる2つのケース
- ケース①:異常分娩・異常妊娠による出産
- ケース②:高血圧・糖尿病・貧血などの病気に罹患
- 自然分娩の場合でも利用できる4つの公的制度
- 制度①:出産育児一時金
- 制度②:出産手当金
- 制度③:傷病手当金
- 制度④:医療費控除
- まとめ:妊娠中の医療保険選びに迷ったらプロに相談!
目次
妊娠中の保険はプロに相談した方がいい理由
妊娠は病気ではありませんが、女性の身体に大きなダメージを与えることに違いはなく、絶対に安心して出産を終えることができると断言することはできません。
妊娠で不安になる理由には身体への負担だけでなく、経済的なことも理由として挙げられます。
経済的なリスクとして考えられるものに医療費があり、妊娠を原因として発症してしまった場合の治療費負担を軽減するのため保険に加入しようとする妊婦は少なくありません。
近年では妊娠27週を超えても加入できる民間の保険が販売されていますが、妊娠前と妊娠中では加入した保険による保障内容には違いが出るケースもあるのです。
| どんなリスクに備えるか | 必要となる保障内容 |
|---|---|
| 妊娠中の病気に対するリスク | 切迫流産うや切迫早産、妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症) |
| 出産に対するリスク | 帝王切開 |
| 出産後のリスク | がんや病気、怪我に対する保障 |
保険商品を比較してニーズに合った保険選びをすることが必要となりますが、約款を読んだり保障されない場合などを保険種類ごとに調べることは大変な労力になることでしょう。
妊娠中の自分にとって、どのような保険が必要なのかと悩んだときには保険のプロに相談してみると簡単に解決することができるのでおすすめです。
保険の無料相談が可能なマネーキャリアなら、妊娠の経過状況や必要保障額などを踏まえて保険種類を比較しながらFPが一緒に考えてくれるので、ぴったりの保険を見つけることができるようになりますよ。
妊娠中でも保険に加入できますか?
一般的に妊娠中でも保険に加入することは可能ですが、3つのことは十分理解しておくことが重要です。
- 定期健診で、帝王切開の予定や異常を指摘されている場合は加入が難しい
- 妊娠周期が27週を超えて妊娠後期に入ると、保険加入は不利になる
- 保険種類によっては
妊娠中に加入しようとする保険種類によっては、特定部位不担保などが付加されてしまい、ニーズに合った保険へ加入できない可能性があるので注意が必要です。
子宮や卵巣、卵管などが部位不担保となってしまった場合には、妊娠中における病気や出産に対して保障されないことがあるので覚えておきましょう。
- 切迫流産や切迫早産に対する入院や手術は保障されない
- 妊娠中毒症による入院などは保障されない
- 帝王切開になっても、入院や手術の保障はされない
保険種類ごとに審査基準の違いがあり不担保が付加されるかどうかが決まるため、保険種類の比較をすることは非常に重要となるのです。
すべての人が加入しなければならない公的保険の社会健康保険や国民健康保険は、妊娠中でも加入手続きが可能で、妊娠中に異常が発見された場合は健康保険の対象となり医療費を軽減することができます。
ただし加入する健康保険の種類によって、保障内容や制度に違いがあるためよく確認しておくようにしてくださいね。
妊娠中で保険に加入できない場合も解説
妊娠中でも加入できる保険は多数販売されていますが、保険に加入する際には健康に関する告知が必要となります。
- 所定の疾病について過去5年以内の病歴や診断内容、入通院歴や手術など
- 2年以内の病歴や診断内容、入通院歴や手術など
- 2年以内の健康診断などにおける指摘の有無
- 3ヶ月以内における医師の診察歴
もちろん妊娠中に保険へ加入しようとするなら、妊娠中であることも告知をする必要があるので忘れないようにしておきましょう。
妊娠周期が27週を超えていると加入できない保険が一般的となっており、妊娠後期になると加入できない保険があるので保険選びでは加入条件を良く確認しておくことが大切です。
また、妊娠に関する異常や持病や既往症を告知することにより、保障を引き受けできない保険会社は加入を断るケースがあります。
告知内容をもとに保険会社は審査をおこないますが、保険種類によって引受基準が異なるため1種類の保険で断られたからといって、すべての保険に加入できないとは限りません。
持病や既往症が原因で保険加入を断られてしまった場合は、加入しやすい保険を探すか引受基準緩和型や無告知型の保険を検討してみましょう。
保障内容の良い保険に加入したいからといって持病や既往症の事実を隠して加入すると告知義務違反となり、発覚するとペナルティが課せられてしまうため絶対に告知義務違反は避けてくださいね。
妊娠中でも入れる保険の種類
健康状態や加入条件さえクリアしていれば妊娠中でも加入できる保険はありますが、必要となる保障がどのようなものかによって選択する保険種類が大きく違ってくるため、それぞれの保障内容の違いをよく理解しておくようにしましょう。
| 保険種類 | 保障内容 |
|---|---|
| 妊娠・出産保険 | 妊娠中の医療保障や帝王切開への保障 |
| 妊娠合併症保険 | 妊娠中の合併症や難産への保障 |
| 子ども医療保険 | 生まれたばかりの子供の医療保障 |
| がん保険 | がんに対する保障 |
| 障害保険 | 事故による怪我の保障 |
がん保険や傷害保険は、妊娠とは大きな関係性を持たないため妊娠中であっても加入しやすい保険だといえますが、保険種類や保障内容によっては保障されないケースに該当してしまう恐れがあることも覚えておいてください。
妊娠中は経過周期によって加入できる保険に限りが出る場合もあり、比較するために必要な保険種類を見つけることが難しいため、加入する保険を探すときは保険のプロに相談してみることをおすすめします。
マネーキャリアなら無料で保険のプロに相談することができます。
- 何度相談しても無料
- 提携しているFPは3,000人以上
- 累計相談数は4万件を超え、相談満足度は93%以上
- 取り扱い保険会社は40社以上で、豊富な保険種類から比較できる
妊娠中の保険選びで悩んだときには、40社以上の保険会社と提携し豊富な保険商品を取り扱っているマネーキャリアを、ぜひ利用してみてくださいね。
妊娠中でも医療保険には加入できる?注意点と共に解説!

妊娠中だと医療保険に加入できないと思われている方もいるかもしれません。
妊娠中で医療保険に加入していない方は、妊娠・出産に伴う入院・手術などの治療費の備えがないことに不安を感じるでしょう。
実は、妊娠中でも医療保険に加入することは可能です。
ただし、妊娠中に医療保険に加入するにあたっては、以下の注意点があります。
- 医療保険の対象期間
- 医療保険の保障範囲
医療保険の対象期間に注意
妊娠中に医療保険に加入する際の注意点1つ目は、医療保険の対象期間です。
医療保険に加入するときには健康状態の告知があり、妊娠中であることも回答しなければなりません。
保険会社からみると、妊娠中の方については異常妊娠・異常分娩による給付金支払の確率が高いため、加入から一定期間は「部位不担保」という条件がつくことがあります。
部位不担保については後述しますが、多くの保険会社では医療保険の加入後1年間は異常妊娠・異常分娩による給付金支払を免除するという条件が付加されます。
この条件が適用される期間は保険会社により異なるため、事前に確認しましょう。
また妊娠中でも医療保険に加入できるのは、妊娠27週目までとする保険会社が多いです。
妊娠後期は母体や胎児の病気が発症するリスクが高まるため、さらに生命保険の加入が不利になる場合があります。
医療保険の保障範囲に注意
妊娠中に医療保険に加入する際の注意点2つ目は、医療保険の保障範囲です。
そもそも正常な妊娠・出産は病気ではないので、医療保険が適用されません。
公的保険制度と同様、医療保険が適用されるのは子宮外妊娠や早産・流産、帝王切開など、異常妊娠・異常分娩と呼ばれるものに限られます。
さらに、妊娠中に医療保険に加入すると、「部位不担保」という条件が付く場合あるとご説明しました。
「部位不担保」とは、特定の身体の部位については、一定期間あるいは全期間、医療保険の適用対象外となることです。
妊娠中の場合は、子宮・卵巣・卵管などの部位が対象となることが多く、それによって、切迫流産・切迫早産・妊娠高血圧症候群・帝王切開での分娩などについては給付金が支払われなくなります。
出産に必要な費用はどのくらいか

注意点はあるものの、妊娠中でも医療保険に加入できるとご説明しました。
とはいえ、そもそも医療保険に加入すべきかどうか、実感できない方もいるかもしれません。
医療保険は入院・手術といった治療費に備えるものです。
出産にかかる治療費がどれくらいかを知ることによって、医療保険が必要かどうかの参考になるでしょう。
出産方法ごとにどれくらいの費用がかかるのか、
- 自然分娩
- 異常分娩
- その他(マタニティ・ベビー用品)
以上の費用について解説します。
自然分娩の出産費用
自然分娩での出産は公的保険制度や民間の医療保険の対象外となるため、基本的に全額自己負担となります。
自然分娩の場合どれくらいの費用となるのか、国民健康保険中央会の「正常分娩分の平均的な出産費用について(平成28年度)」に掲載されている費用(平均値)をご覧ください。
| 費用項目 | 病院・診療所・助産所 |
|---|---|
| 入院料 | 112,726円 |
| 室料差額 | 16,580円 |
| 分娩料 | 254,180円 |
| 新生児管理保険料 | 50,621円 |
| 検査・薬剤料 | 13,124円 |
| 処置・手当料 | 14,563円 |
| 産科医療補償制度 | 15,581円 |
| その他 | 28,085円 |
上記の費用を合計した平均額は「505,759」円となっています。
費用の中で分娩料がもっとも高いのは多くの人が納得できるところですが、見逃しがちなのは、検査費用や室料差額(差額ベッド代)などの細々と発生するコストです。
あらかじめ資金の準備をしていなければ、1回の妊娠・出産に伴い約50万円を家計から負担しなければならないため、一定の貯蓄がない世帯の場合は特に重い負担となるでしょう。
異常分娩の出産費用
異常分娩の場合は、自然分娩の場合と異なり公的保険制度および医療保険の保障対象となります。では何も費用面の準備をする必要がないのかというと、決してそうではありません。
その理由として、
- 異常分娩は自然分娩と比較して入院日数が長くなる
- 帝王切開の場合は8日前後、切迫早産の場合は2カ月以上入院する場合がある
- 異常分娩は入院費の他に手術費が発生する
以上の点が挙げられます。
まず、異常分娩は正常分娩の費用(平均50万円)プラス手術費用がかかるため、目安として総額「60〜70万円」がかかるとされています。そのうち自己負担となるのは3割、単純計算ではおよそ「18〜21万円」程度となります。
切迫早産などで入院が長期化した場合、たとえ3割負担であっても自己負担となる費用は日ごとに増えていきます。自己負担費用には公的保険制度がまったく適用されない「食事代」や「差額ベッド代」も含まれるからです。
異常分娩の場合は、月間の医療費が一定額以上となった場合に払い戻しを受けられる「高額療養費制度」が利用できますが、この制度はあくまで後日申請であるため、どれだけ高額になっても一時的に費用を建て替えておく必要があります。
マタニティ・ベビー用品
最後に医療費以外にも発生する費用にも注目しましょう。いわゆる「マタニティ・ベビー用品」のことであり、「出産準備費用」とひとくくりにされることもあります。
具体的にどのような費用が出産準備費用として発生するかというと、
- マタニティーウェア
- マタニティー下着
- 産褥ショーツ
- 妊娠線予防クリーム
- 新生児用ウェア・おむつ・お尻拭き等
- ベビーカー
あくまで一例ですが、以上のマタニティ・ベビー用品の購入費用はすべて自己負担となります。
少なくとも妊娠から出産後の0歳育児まで必要であることを考えると、消耗品も含めて「10〜20万円」かかると想定しておいた方が良いでしょう。
妊娠中でも医療保険に加入すべき理由

妊娠中の場合、医療保険に加入する際に条件が付く場合がありますが、それでも医療保険に加入するべきといえます。
なぜ妊娠中でも医療保険に加入するべきか、主な4つの理由について解説していきます。
- 入院費用に備える
- 帝王切開・切迫早産に備える
- 出産後の赤ちゃんのために
- 公的医療保険制度の対象外に備える
入院費用に備える
妊娠中でも医療保険に加入すべき理由1つ目は、「入院費用に備える」です。
妊娠中に医療保険に加入した場合は、部位不担保の条件が付き、異常妊娠・異常分娩に伴う入院については給付金支払の対象外となる可能性があります。
ただし、このような条件は妊娠・出産にかかわる身体の部位のみを対象にしたものなので、妊娠・出産にかかわらない病気やケガの入院・手術などは時期を問わず保障されます。
出産後は生活の変化に適応するのに忙しく、ゆっくり保険を検討することもままならなくなるかもしれません。
また、育児にかかる費用が追加されることで、急な入院による出費はこれまで以上の痛手となることもあります。
思わぬ病気で長期の入院となったときのためにも、早めに医療保険を検討するのがよいです。
帝王切開・切迫早産に備える
出産後の赤ちゃんのために
妊娠中でも医療保険に加入すべき理由3つ目は、「出産後の赤ちゃんのために」です。
厚生労働省の調査「患者調査の概況」によれば、成人までの年代別で入院患者数をみたとき、1歳になるまでの赤ちゃんが最も多いことが分かります。
出産時は母体だけでなく、新生児の健康リスクもあることに注意してください。
出産時、お母さんの保険でカバーできるのはあくまでお母さんの治療費だけです。
ただ、出産後に思いがけない出費がかさむ可能性があることをあらかじめ考慮して準備することが重要です。
公的医療保険制度の対象外に備える
妊娠中の医療保険選びで知っておくべきポイント

妊娠中でも医療保険に加入するべき理由について、ご理解いただけたでしょうか。
これから医療保険を検討しようという方は、ここまでご説明した注意点などをぜひ参考にしてください。
しかし、実際に医療保険を検討しようとしたとき、数ある保険のなかからどれを選べばいいのか迷うかもしれません。
妊娠中に医療保険を選ぶ際には、以下の2つのポイントを押さえるようにしてください。
- 解約のタイミングの制限
- 医療保険選びに迷ったら誰かに相談する
解約のタイミングの制限
医療保険選びに迷ったらプロに相談する
妊娠中の医療保険選びで知っておくべきポイント2つ目は、「医療保険選びに迷ったら誰かに相談する」です。
ここまでのご説明で、妊娠中に自力で保険を選ぶのは大変そうと感じるかもしれません。
確かに、保険商品によって保障内容が異なるのに加え、条件の有無や内容も違います。自分で保険を比較検討するのは大変でしょう。
妊娠中は自身の体調に気を遣わなければならず、また検診などで忙しいなかで、保険について調べる余裕はないかもしれません。
そこでおすすめなのは、保険のプロに相談することです。
保険の知識がある人に相談すれば、条件も含めてぴったりの保険を提案してくれるので、効率的に保険選びができます。
告知義務に注意する
最後に注意したい点は、告知義務に関する点です。
告知義務とは保険の申込時に自分自身の健康状態や既往歴などについて正確に申告する義務のことであり、持病の有無や既往歴を正しく申告しないなど「告知義務違反」に該当し、発覚すると契約が解除となります。
告知義務違反は加入後すぐに発覚するケースだけでなく、加入から数年してから告知義務違反が判明し、突然保険会社から解約されるリスクもあります。
このため、
- 直近3カ月以内に検査・治療・投薬を行っているか
- 直近5年以内に入院・手術を行ったり7日以上の投薬を行ったりしているか
- がんの罹患歴があるか
- 直近1年の間に喫煙を行っているか
- 健康診断や人間ドックで要検査と診断されたか
- (申告時時点で)妊娠しているか
以上のような告知事項に関して、必ず正確に告知しましょう。
妊娠が発覚してから、医療保険に加入したいがために妊娠中であることを隠すのも当然ながら告知義務違反となります。告知義務違反を隠し通すことは難しくデメリットしかないため、必ず正確に正直に告知しましょう。
妊娠・出産時に公的医療保険を利用できる2つのケース
妊娠・出産に伴う費用を賄うために公的保障はフル活用したいですが、実際のところ公的保障を受けるためには一定の条件があります。
そこで次からは、妊娠・出産時に公的医療保険を利用できるケースについて、
- 異常分娩や異常妊娠
- 高血圧・糖尿病・貧血など
以上2つのケースを解説していきます。
ケース①:異常分娩・異常妊娠による出産
公的保険制度の対象となる1つ目のケースは異常分娩による出産です。異常分娩とは、簡単にいえば「正常分娩」に属さない分娩方法のことです。
異常分娩には、
- 帝王切開:子宮切開手術により胎児を取り出す分娩方法
- 吸引分娩:カップを用いて胎児を吸引する分娩方法
- 鉗子分娩:「鉗子」という器具で頭部を挟んで胎児を取り出す分娩方法
- 早産分娩:妊娠から37週未満で出産すること
- 骨盤位分娩:胎児の頭が上を向いたまま出産すること
以上の分娩方法が分類され、これら異常分娩での出産を行った場合に公的保険制度の保障対象となります。
上記以外に分娩に伴って外科手術や子宮収縮剤を用いた場合なども異常分娩とみなされ保障される場合があります。
ケース②:高血圧・糖尿病・貧血などの病気に罹患
2つ目のケースは、ケース①で挙げた異常分娩に伴って、
- 高血圧
- 糖尿病
- 貧血
以上の症状が発生して治療を行った場合です。
具体例の一つに「妊娠高血圧症候群」があります。以前は「妊娠中毒症」と呼ばれていた病気ですが、これは元々高血圧ではない妊婦が妊娠20週から12週の間に高血圧となる病気です。
妊娠高血圧症候群は、
- 子癇:妊婦の手足のむくみ、けいれんを引き起こす
- HELLP症候群:主に「溶血」「肝酵素上昇」「血小板減少」を引き起こす
- 急性妊娠脂肪肝:黄疸・嘔吐・乏尿症状から、肝不全や腎不全を発病する
- 常位胎盤早期剥離:出産前に胎盤が子宮壁から剥離する
- 胎盤機能不全:胎児に栄養や酸素が十分に供給されなくなる
主にこのような合併症を引き起こし、最悪の場合胎内で胎児が死亡する危険もあるため治療が必要な病気です。
治療のために降下剤を投与したり帝王切開を行うケースもありますが、そのような異常分娩に伴う病気の治療であれば公的保険制度の保障対象となります。
自然分娩の場合でも利用できる4つの公的制度
今解説したように「自然分娩」は公的医療保険制度の対象外です。
しかし、自然分娩でも利用できる公的制度があり、それらを利用することで出産に伴う費用をいくらかカバーすることができます。
次からは自然分娩でも利用できる公的制度について、
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 傷病手当金
- 医療費控除
以上4つの制度を解説していきます。
制度①:出産育児一時金
出産育児一時金とは、妊娠4カ月以上で出産した場合に、
- 産科医療補償制度対象の医療機関で出産:42万円
- 産科医療補償制度対象外の医療機関で出産:40.8万円
以上いずれかの一時金が支給される制度です。
出産育児一時金は公的保険制度に加入している方、または夫の被扶養者となっている妻が支給対象です。
一時金の受け取り方には主に2種類あり、
- 直接支払制度
- 受取代理制度
どちらかを選択することになります。
便利なのが「直接支払制度」であり、こちらは対応する医療機関で直接申請すれば、健康保険組合により直接医療機関に医療費が支払われます。もしも医療費が42万円以下の場合は後日差額請求をすることで差額を受け取れますが、逆に超過した場合は退院時に支払います。
直接支払制度に対応していない医療機関の場合は「受取代理制度」を利用できます。こちらはあらかじめ健康保険組合に申請書を提出することで、出産後に医療機関より健康保険組合に請求が行われ、支払われます。
制度②:出産手当金
出産手当金とは、社会保険加入者が妊娠・出産した場合に勤務先の会社より一定額が支給されるしくみです。
女性が育休を取得し働けない期間の生活を確保するための出産手当金は、出産日(出産予定日)42日から出産後56日の期間で給付されます。
出産手当金の支給額は、
直近の継続した12カ月間の平均標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3
以上の計算式により計算されます。
勤務期間が12カ月未満である場合は、
- 直近の継続した各月の平均標準報酬月額
- 標準報酬月額の平均額(28万円または30万円)
上記のうちいずれか金額が低い方が計算に適用されます。
制度③:傷病手当金
会社に勤めており社会保険に加入している方は、仕事以外の原因で病気・ケガで入院したとき「傷病手当金」を受け取ることができます。
傷病手当金は基本的に病気・ケガで入院し一時的にでも休職しなければならなくなった人が対象となりますが、妊婦が異常分娩により治療を受ける場合も「仕事以外を原因とする休職」となるため傷病手当金の対象となります。
傷病手当金の1日あたりの給付額は、
直近の継続した12カ月間の平均標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3
以上の計算式で計算し、勤務期間が12カ月に満たない場合は、
- 直近の継続した各月の平均標準報酬月額
- 標準報酬月額の平均額(30万円)
このうちいずれか低い金額を計算に適用します。
ただし傷病手当金を受給するためには、
- 原因が仕事以外であること
- 仕事ができる状態ではないこと
- 3日間の待機期間を含め4日以上仕事できない日が続くこと
以上の条件をクリアする必要があります。
制度④:医療費控除
最後に解説する制度は「医療費控除」です。これは医療費そのものを賄う制度ではなく、医療費として支払った分が所得金額から差し引かれることで、税金を安くできる仕組みです。
医療費が戻ってくるものだと勘違いされやすいこの仕組みですが、会社員の場合は還付、個人事業主は確定申告を行うことで所得税が安くなるため、該当者は必ず申請するべきです。
控除額の計算方法は、
(年間の医療費総額 ー 保険金等) ー 10万円(または5万円)
以上のとおりで、最高で200万円まで控除を受けることが可能です。
ここまで挙げた制度と異なる点は、異常分娩だけでなく正常分娩での検査・出産費用や不妊治療費なども対象になるという点です。入院中の食費や医療機関への交通費なども含めることができます。
医療費控除は世帯で合算した医療費で計算できるため、必ずしも妊婦(妻)が申告するのではなく、世帯の中でもっとも収入が高い人が申告するのが望ましいです。
まとめ:妊娠中の医療保険選びに迷ったらプロに相談!
- 妊娠中でも医療保険に加入できる
- 妊娠中に医療保険に加入する場合は、部位不担保の条件が付く場合がある
- 医療保険に加入すれば、妊娠・出産にかかわらない病気なども保障される
- 医療保険は自分で選ぶよりもプロに相談したほうが効率的