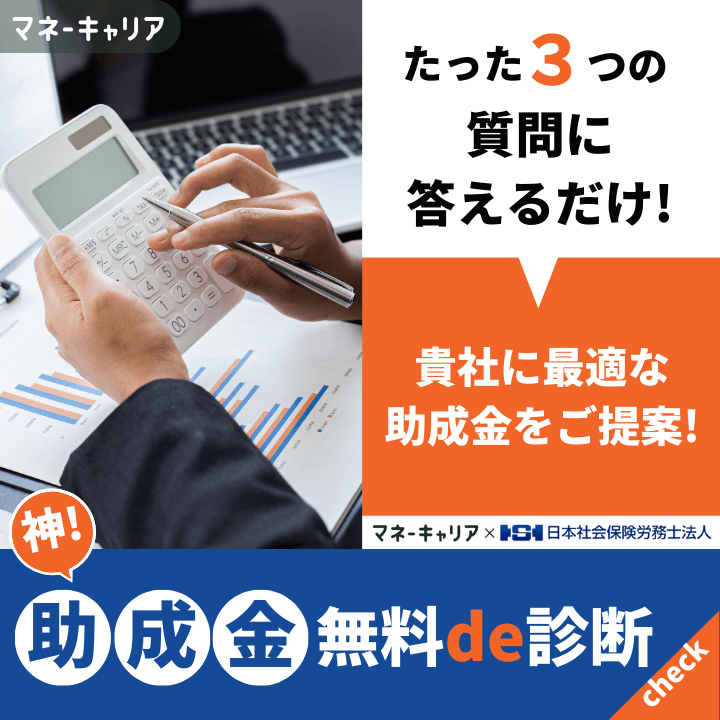更新日:2024/08/06
ギフト券・商品券の経費処理の方法をパターン別にくわしく解説!
内容をまとめると
- 贈答目的で商品券やギフト券を購入したときは「接待交際費」で仕訳。
- 自社で使用する消耗品を購入する目的で商品券・ギフト券を購入したときは「他社商品券」・消耗品を購入したときは「消耗品費」で仕訳をする。
- キャンペーン等で商品券・ギフト券を顧客に送る場合は「広告宣伝費」または「交際費」で仕訳する。
- 公私兼用の物を商品券・ギフト券で購入したときは按分計上する。
- 経費計上の主な注意点は「明細を記しておく」・「業務とプライベートを切り分ける」・「余った商品券は在庫として処理する」・
- 基本的にギフト券の購入だけでは節税対策にならないものの、リスク対策や節税対策に関してマネーキャリアのような「リスク対策のプロへ無料で何度でも相談できるサービス」を活用する会社が急増している。

目次を使って気になるところから読みましょう!
- ギフト券・商品券が経費になるパターン
- ①商品券・ギフト券を贈答用に購入した場合は交際費
- ②自社で使用する場合は消耗品費
- ③キャンペーン等で顧客に送る場合は広告宣伝費か交際費
- ④公私兼用の物を商品券・ギフト券で購入した場合は按分計上する
- 注意:忘年会などの景品・報酬としてのギフト券は経費にならない
- 商品券を経費処理するときの3つの注意点
- ①脱税を疑われないように明細を記しておく
- ②業務とプライベートを正しく切り分ける
- ③余った商品券は在庫として処理しなければならない
- 自社に最適な節税対策が無料で簡単にわかる方法とは
- 自社でできる節税方法がすぐにわかる:マネーキャリア(丸紅グループ)
- 商品券・ギフト券における経費処理方法のまとめ
目次
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ギフト券・商品券が経費になるパターン

以下では、ギフト券・商品券が経費になるケースの場合分けについて解説します。
全国百貨店共通商品券や図書カード、amazonギフト券など、ギフト券や商品券には多くの種類があります。顧客への贈答用にしたり、会社の備品購入に利用したり、さまざまなビジネスシーンで活躍してくれます。
しかし、ギフト券や商品券は現金に近い感覚で使える一方、経費になるかや会計上の取り扱いには違いがあります。
①商品券・ギフト券を贈答用に購入した場合は交際費
贈答目的で商品券やギフト券を購入した場合は、「接待交際費」の勘定科目を利用して経費処理ができます。
お世話になっているクライアントに対して、商品券やギフト券を贈ることもあります。そこで、以下では具体的な例を使って、仕訳をご紹介します。
たとえば、クライアントへの贈答目的で3万円のギフト券を購入したケースの仕訳は、次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 接待交際費 | 30,000 | 現金 | 30,000 |
贈答用の商品券・ギフト券の場合、消費税はかからず「非課税」となります。この点は間違えやすいポイントであるため、注意が必要です。
なお、商品券・ギフト券を「贈答したとき」の経費処理は、必要ありません。
②自社で使用する場合は消耗品費
自分の会社の備品を購入するためなど、自社用に商品券・ギフト券を購入するケースもあります。
自分の会社で使用する目的で商品券・ギフト券を購入した場合、「他社商品券」の勘定科目を利用して経費処理します。
たとえば、自社用に3万円分の商品券を現金購入したときの仕訳は、次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 他社商品券 | 30,000 | 現金 | 30,000 |
消費税は非課税なので、経費処理の必要はありません。
次に、自社用として購入した商品券で3万円の消耗品を購入したときの仕訳は、次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 27,273 | 商品券 | 30,000 |
| 仮払消費税 | 2,727 |
商品券の使用は「課税」となり、税抜経理の場合は、上記のように仮払消費税を計上する必要があります。
上記のように、商品券の「購入時」とは消費税の区分が異なるため、注意が必要です。
③キャンペーン等で顧客に送る場合は広告宣伝費か交際費
顧客へキャンペーンとしてギフト券や商品券を送る場合は、広告宣伝費、もしくは交際費で仕分します。
商品やサービスの売り上げに影響を与えることから、事業に必要な費用とみなされるためです。
ビジネス上のキャンペーン企画などで、顧客に対して商品券・ギフト券を配るケースもあります。具体的には、「商品に関するアンケートにお答えいただいた方に、1,000円分のギフト券をプレゼント」といったケースです。
不特定多数の一般消費者を対象にしている場合、「広告宣伝費(不特定多数を対象に広告や宣伝する際にかかる経費)」の勘定科目を利用できます。
ただし、1件あたりの金額が大きい場合は「交際費」とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
④公私兼用の物を商品券・ギフト券で購入した場合は按分計上する
仕事とプライベートの両方で使用するものを、商品券やギフト券を使って購入した場合、仕事とプライベートの利用比率の割合で按分して計上します。
自宅が事務所を兼ねている場合の家賃などと同様の考え方で、仕事で使う分のみを経費にできます。
たとえば、仕事で4割・プライベートでは6割利用する1万円のプリンターを商品券やギフト券で購入する場合、経費計上が可能なのは「仕事で利用する4割分」です。
したがって、経費として計上できるのは、仕事で利用する「4割分にあたる4千円」になります。
注意:忘年会などの景品・報酬としてのギフト券は経費にならない
ギフト券を会社の忘年会や新年会の景品とする場合は、注意が必要です。
会社で忘年会や新年会を開催する際にかかる費用は、「福利厚生費」として全額を経費にすることが可能な一方、現金は福利厚生費の対象にはなりません。
この考え方は、実質的にお金として取り扱うことのできるギフト券にもあてはまります。もし、忘年会や新年会の景品としてギフト券を渡した場合、それは給料と同様とみなされます。
給与は、所得税や住民税の課税対象なため、前述のケースでは、ギフト券も給与という経費の形にはなるものの、源泉徴収の対象になるのです。
なお、源泉徴収の計算方法は国税庁HPで確認できます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
商品券を経費処理するときの3つの注意点

ここではさらに、商品券を経費処理するときに気を付けるべき3つの注意点について解説します。
- 明細を記しておく
- 業務とプライベートをしっかり切り分ける
- 余った商品券は在庫として処理する必要がある
①脱税を疑われないように明細を記しておく
税務調査の場面において、経費計上した商品券について「利用方法は明確かどうか」という点を確認されることは、少なくありません。
したがって、脱税を疑われることのないよう、商品券の購入・配布と事業との関連性を明確にしておく必要があります。
そのため、商品券の使用状況がわかる明細(配布先リスト)書類を作成し、正しく記録を残しておきましょう。
記録にあたっては、次のポイントをおさえておくべきです。
- いつ
- 誰に
- いくら
- どのような目的で(なぜ)
日頃取引機会のない企業に商品券を配布した場合は、「自社との関係性」などもあわせて記録しておくとよいでしょう。
また、上記のほかに、商品券を受け取った人から「受領書」をもらい、保管しておくことをおすすめします。
このような明細は都度、作成するようにしましょう。「受入」・「払出」・「残高」を合わせて記録しておけば、在庫管理にも役立てることができます。
②業務とプライベートを正しく切り分ける
商品券を経費処理する際は、業務とプライベートを正しく切り分けることが非常に重要です。
事業に関係のない人に商品券を渡した場合や、商品券でプライベートで着るための洋服を買った場合は、もちろん経費にすることはできません。
また、先に説明したとおり、公私兼用の物品を商品券で購入した、というようなケースにおいては、仕事とプライベートの利用比率で按分計上する必要があります。
ただし、税務調査により、プライベートな贈り物が混ざっているという指摘を受けた実例が存在します。そのため、あまりにも法外な金額の商品券を贈答している場合は、プライベート目的の使用ではないか、疑われるので注意が必要です。
経費にすることができるのは、あくまでも「売り上げに紐づくもののみ」であることを意識して、仕分しましょう。
③余った商品券は在庫として処理しなければならない
余ってしまった商品券については、決算時に経費から除外し在庫として処理する必要があります。
贈答用として商品券を購入したものの、すべてを使いきることができず、未使用の商品券が余ってしまった、というケースもあります。
税金対策のために商品券を一括購入して損金算入する、という会計処理は認められていないため、注意が必要です。
贈答用の商品券の購入したときは「接待交際費」として経費計上することをご紹介しましたが、余った商品券を期末に在庫として計上するときは「貯蔵品」の勘定科目を利用します。
処理方法の具体例は、次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵品 | 5,000 | 接待交際費 | 5,000 |
このように、贈答用の商品券が余ってしまった場合は、忘れずに在庫として処理するようにしましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」
業態業種問わず、法人保険のプロに無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」
▼マネーキャリア(丸紅グループ)の公式サイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自社に最適な節税対策が無料で簡単にわかる方法とは
以下では、自社に最適な節税対策が無料で簡単にわかる方法を解説します。
商品券などを従業員への福利厚生や取引先へのギフトとして活用する企業は多いですが、経費計上の可否は状況によって異なります。
また、賢い経費処理のやり方として、ギフト券の経理処理企業全体の節税対策を総合的に考える必要があります。しかし、節税対策は法改正などによって変化するため、専門的な知識が必要です。
加えて、節税対策だけでなく、事業リスクへの備えも同時に考慮しなければなりません。そこで、マネーキャリアのように、法人保険の専門家へ事業リスクや最適な節税対策に関して「無料で何度でも」相談できるサービスを使い会社が急増しています。
丸紅グループが運営するマネーキャリアは、「80,000件以上の相談実績を持ち、98.6%の高い満足度」を誇ります。経営者の事業内容や課題に合わせて、適切な節税対策とリスク管理の方法を提案してくれるので、経費処理はもちろん節税対策全般の悩みを解消できます。
自社でできる節税方法がすぐにわかる:マネーキャリア(丸紅グループ)

法人保険に関する全ての悩みにオンラインで相談できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、法人保険のプロのみを厳選しています。
・保険だけではなく、総合的な事業リスクへの対策を踏まえて「自社の理想の状態を叶える」提案が可能です。
・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も80,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに 「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。