
更新日:2025/09/01
扶養内でも年末調整で生命保険料控除の対象!【103万以下のパート主婦(妻)必見】

- 少しでも生命保険料控除を活用したいと思っている
▼この記事がおすすめな人
- パート主婦でも生命保険料控除をしたい人
- これを機に生命保険のプランを見直したい人
- 将来のために生命保険を上手く活用してお金をやりくりしたい人
内容をまとめると
- 扶養内でのパート主婦も、生命保険料控除ができる!
- 年収103万円以上は所得税の対象、生命保険料控除を活用できる
- 自分で支払っている保険料なら年末調整や確定申告で保険料控除が可能
- 生命保険料控除で迷ったら、マネーキャリアへ相談しよう
- マネーキャリアは何度でも相談が無料、LINEでらくらく相談予約できる

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 扶養内のパート主婦(妻)の生命保険料控除を全解説!
- 年末調整・確定申告時の所得控除の種類
- パートの妻に関わる「103万円の壁」(配偶者控除)のメリット
- 年末調整の生命保険料控除は「誰の」税金を控除したいか考えよう
- 実際に保険料を支払っている人が生命保険料控除の対象となる
- パート主婦(妻)の年末調整の手続きに関わる疑問点
- 源泉徴収票をもらっていない場合の年末調整の手続きは?
- 年末調整がない会社の場合は確定申告が必要?
- パート掛け持ちの主婦の年末調整の注意点を確認
- パート掛け持ち主婦で年末調整が必要な条件とは
- パート掛け持ちの場合は所得税の他に社会保険にも注意
- 妻名義で妻の口座から支払えば夫婦で生命保険料控除を受けられる
- パート主婦(妻)が対象の生命保険料控除を受ける場合の注意点
- 115万円までのアルバイトなら所得控除で同じ扶養を受けられる
- 実は所得税が0のパート主婦(妻)でも住民税がかかる
- まとめ:パート主婦(妻)と生命保険料控除
目次
扶養内のパート主婦(妻)の生命保険料控除を全解説!

- 年末調整・確定申告時の所得控除の種類
- パートの妻に関わる「103万円の壁」(配偶者控除)のメリット
- パート主婦が生命保険料控除を申請する場合の注意点

マネーキャリアでは、生命保険や生命保険料控除の活用に関するオンライン無料相談サービスを行っています。
生命保険は、万が一に備えるための役割だけでなく、お金のやりくりにも役立ちますが、知識がなく十分に活用できていない人も多くいます。
そのため、マネーキャリアのお金や保険に詳しい専門家(FP)に相談することで、ネット上ではわかりにくい生命保険に関する控除・貯蓄について学ぶことがおすすめです。
年末調整・確定申告時の所得控除の種類
まずは、年末調整や確定申告時の所得控除の種類を確認しましょう。
年末調整や確定申告でパート主婦の方が気にしなくてはいけない税金は、以下の2つです。
- 所得税
- 住民税
これらの税金の支払い方法は、以下の通りです。
- 所得税…源泉徴収で給与から天引きして、勤務先が代わりに納税
- 住民税…収入が確定してから、翌年に支払い
上記のようになっており、所得税は給与を振り込むときに先に引かれています。
それぞれの税金と、所得控除の種類や手続きの流れなどは以下の通りです。
所得税については、あらかじめ予想される税額を会社が天引きし、納めてくれます。
もちろん、実際の収入は予想とずれることがあるので、年末調整で申請された控除や、確定申告での申請によって計算しなおし、払いすぎていれば還付金として返ってきます。
住民税の支払いは、年末に収入が確定した後、6月に納税通知書が発行され、自分で納めるか会社から天引きされます。
前年分を払うため、申請された控除を引いた金額となっています。
年末調整や確定申告で申請できる所得控除の種類は、全部で14種類とたくさんありますが、今回お話しするパート主婦の方に関係するのは、以下の3つです。
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 生命保険料金控除
パートの妻に関わる「103万円の壁」(配偶者控除)のメリット
まずは、パートの妻に関わる「103万円の壁」(配偶者控除)をおさらいしましょう。
「103万円の壁」とはいわゆる年収の壁のひとつです。
年収が103万円を越えると扶養控除と配偶者控除から外れてしまうというもので、これを気にしてパートの労働時間を調整して年収が103万円を超えないようにしている人もいます。
年収を103万円におさめるメリットは以下の3つです。
- 夫は配偶者控除を受けられる
- 夫の会社の配偶者手当などを受けられる
- 自分は所得税を払わなくてよい
1.夫は配偶者控除を受けられる
配偶者控除とは以下の通りです。
- 一定の条件をみたす配偶者を持つ夫が、所得税と住民税で受けられる控除
さらに、配偶者が下記の3つの条件を満たしていると、夫が自分の収入から一定の金額を差し引くことができます。
- 民法上の配偶者であること
- 納税者と生計を同じにしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみ103万円以下)
3の合計所得金額というのは、給与以外の所得も合算したもので、配当所得や不動産所得、事業所得がある人はそれも含めます。
収入が給与だけの人は、103万円以上になると、所得として本人の税金の対象になり、夫は配偶者控除を申請できなくなります。
ただ、夫が年収1,000万円以下の場合、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除を受けられます。
2.夫の会社から配偶者手当を受けられる
配偶者手当は、大企業などの手当のひとつで、扶養手当や家族手当など、名称や金額の基準は企業によって違います。
給付の制限を、妻の収入が所得税の基準103万円、もしくは社会保険の扶養を外れる130万円以下であることとしている企業が多くみられます。
つまり夫にとっては、妻が103万円の壁を超えないことで、所得控除が減ることと、会社からの配偶者手当がなくなることを回避できる、ということになります。
3.自分は所得税を払わなくてよい
年末調整の生命保険料控除は「誰の」税金を控除したいか考えよう
- 契約者
- 被保険人
- 受取人
- 夫の年末調整で、妻を契約者とした保険料を控除申請できるか
- パート妻の年末調整で、妻を契約者とした保険料を控除申請できるのか

「生命保険料控除を活用したい」
「控除が使えるなら他の保険も検討しようか迷っている」
そんな方はマネーキャリアのお金と保険の専門家(FP)にご相談ください。
年末調整を機に控除に使える保険について検討・見直しをする方は多いです。
ただし、控除額の上限や毎月の保険料を踏まえる必要があるため、賢く保険に加入したい場合はぜひマネーキャリアに一度ご相談ください。
何度でも無料で相談できて、オンラインでの相談も対応可能です。
実際に保険料を支払っている人が生命保険料控除の対象となる
- 妻が払っている保険料…妻が控除を申請できる
- 夫が払っている保険料…夫の控除の対象になる
パート主婦(妻)の年末調整の手続きに関わる疑問点
扶養内のパートで、年末調整をする場合の疑問でよく耳にするのは以下の2つです。
- 源泉徴収票をもらっていない場合
- 年末調整がない会社の場合
源泉徴収票をもらっていない場合の年末調整の手続きは?
源泉徴収票をもらっていない場合の年末調整の手続き以下の通りです。
- 勤務先の経理担当に再発行を依頼する
- 請求ができない場合や請求してももらえない場合は、税務署で「源泉徴収票不交付の届出書」の提出をすること
困るのは、2で請求しても源泉徴収票を作成してもらえない場合や、すでに会社が倒産している場合です。
その場合はまず、管轄の税務署で源泉徴収票不交付の届出書を提出します。
そうすると、税務署から勤め先に指導が入るので、発行してくれることがほとんどです。
税務署に行くときは、給与が支払われていた証明として、給与明細など支払われた金額のわかる書類を持参しましょう。
毎月の給与明細表は大切に保管しておくことも大切です。
デジタル給与明細の場合も、PDF化しておくなどして、念のために手元で保管をすることをおすすめします。
年末調整を受けられない場合は、自分で確定申告をすることになりますが、その場合も給与明細が必要です。
年末調整がない会社の場合は確定申告が必要?
会社が年末調整をしてくれない、あるいは退職して年末調整が受けられない…という方は、自分で確定申告をすることになります。
確定申告は義務となっており、しないと不申告ということになってしまいます。
面倒くさいという気持ちもあるかと思いますが、今は電子申告システムe-Taxを使ってのスマホ申告もできるようになっています。
年末調整の期限は1月31日、確定申告は2月16日から3月15日までなので、この期間内に手続きをしましょう。
このとき必要なものは、以下の2点です。
- 年末調整未済の源泉徴収票:単純に1年間の給与額合計や源泉徴収額の合計が記載されたもの
- 年末調整済みの源泉徴収票:会社が年末調整後に税務署に提出するもの
パート掛け持ちの主婦の年末調整の注意点を確認
次に、パートを2か所以上掛け持ちで働いている主婦の方の年末調整についてです。
1か所なら勤務先の年末調整で済みますが、2か所以上の場合はどうしたらいいのかわからない方のために、下記の2点についてまとめました。
- パート掛け持ちで年末調整が必要な条件
- パートの場合社会保険にも注意が必要
パート掛け持ち主婦で年末調整が必要な条件とは
パート掛け持ち主婦で年末調整が必要な条件は以下です。
- 2ヶ所以上の勤務先から収入がある
- 年末調整をしない職場の給与と、他の所得の合計が20万円をこえるとき
パート先が1か所で、年間の収入が103万円以下の場合、年末調整をおこなうと所得税の対象にはなりません。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書という書類が勤務先から配られ、それを提出するだけで済みます。
しかしこの書類は、1ケ所にしか提出できません。
2ヶ所目以降の職場の給与は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出ができないため、所得税が差し引かれます。
この場合、自分で確定申告をして、払い過ぎている所得税を還付してもらうことができます。
還付のしかたは、税務署に問い合わせるか、マネーキャリアなどのファイナンシャルプランナーの相談窓口にご相談ください。
パート掛け持ちの場合は所得税の他に社会保険にも注意
パート掛け持ちの場合は所得税の他に社会保険の扶養をはずれる年収額にも注意が必要です。
いわゆる「106万円と130万円の壁」です。
以下のように、年収と所属している会社の規模により条件が異なります。
| 条件 | 変わること | |
|---|---|---|
| 106万円の壁 | 従業員51人以上の会社で 働いている人 | 勤め先の社会保険への 加入義務が生じる |
| 130万円の壁 | 従業員50人以下の会社で 働いている人 | 夫の会社の社会保険から外れ 社会保険へ加入しないといけなくなる |
自分の勤める会社がどちらの壁に相当するのか、確認しておくことが必要です。
いずれにしても、この年収帯で働く人はメリットとデメリットを押さえ、生命保険料控除などの活用をしていくのがよいでしょう。
妻名義で妻の口座から支払えば夫婦で生命保険料控除を受けられる
- 一般生命保険
- 介護医療保険
- 個人年金保険
また、住民税でも生命保険料控除を活用できるため、夫婦で最大14万円の控除が受けられます。
そうすると、夫婦それぞれでうまく生命保険料控除を利用できれば、所得税と住民税で最大38万円の控除が受けられることになります。
パート主婦(妻)が対象の生命保険料控除を受ける場合の注意点
1.夫の受ける配偶者控除
配偶者控除については、妻の年収が103万円を超えても、配偶者特別控除を受けることができます。
ただし、配偶者控除と違う点は、夫の所得が1,000万円以下である場合にのみ受けられるという点です。
さらに、妻の年収が同じでも、夫の所得によって控除の金額が変わります。
妻の年収が201万円に達すると、完全に0になります。
夫の所得が、所得税の税率の境目に近い場合は、夫の税金が大きく関わってくるので、一度確認しておくとよいでしょう。
2.妻の所得税の金額
パート主婦が所得税を払う場合、税額はいくらくらいになるのか気になる方は多いでしょう。
例えば、以下の場合は所得税がいくらになるか計算してみましょう。
- パート主婦まなみさん
- パートの年間収入125万円
125万円−(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)=課税対象額22万円
所得税は、所得が1,000円から1,949,000円までは5%なので、220,000円×5%=11,000円 まなみさんの所得税額は11,000円
まなみさんの払う所得税は、年額で11,000円です。115万円までのアルバイトなら所得控除で同じ扶養を受けられる
その場合、103万円+12万円の計115万円までのアルバイトであれば、所得税はかかりません。
夫が受けられる所得税の配偶者特別控除の額はその分減ってしまいますが、夫の所得に対して考えると、その分の税金の差額はわずかなものです。
それよりも、115万円までパートで働ける金額の方が大きくなるでしょう。
もしも以下のように考えている人は、ぜひ申請しましょう。
- 103万円で扶養をはずれそう…なんとかならないかな…
ギリギリで困っている方で、自分の名義で払っている保険があるなら、ぜひ申請することをおすすめします。
ただこの場合、満額の12万円を受けるためには、それだけの保険料を自分で払うことになるため、生命保険料控除のために無理をして出費することのないようにしましょう。
実は所得税が0のパート主婦(妻)でも住民税がかかる
- 所得税は上限12万円
- 住民税は7万円
そういったことも考慮に入れ、自分で払っている生命保険があったら、ぜひ年末調整や確定申告で控除を申請しましょう。
税金と控除のしくみを知って、使える制度はどんどん活用していきましょう。
まとめ:パート主婦(妻)と生命保険料控除

今回は、パート主婦と生命保険料控除について解説してきました。
- パート主婦でも、年収103万円を超えたら所得税を払っているので、生命保険料控除を申請する方が得
- 年収が103万円に達していなくても、住民税は払っていることがあるので、生命保険料控除を活用できる












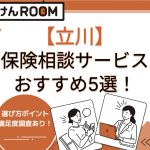
「扶養内のパート主婦でも生命保険料控除は使える?」
「パート主婦でも生命保険料控除で税金を減らしたい」
と思っている人も多いのではないでしょうか?
結論からいうと、扶養内で働くパート主婦でも生命保険料控除はできます。
この記事では、パート主婦が使える生命保険料控除について解説します。
「103万円の壁」と所得税の関係についてもお話しますのでぜひ参考にしてください。