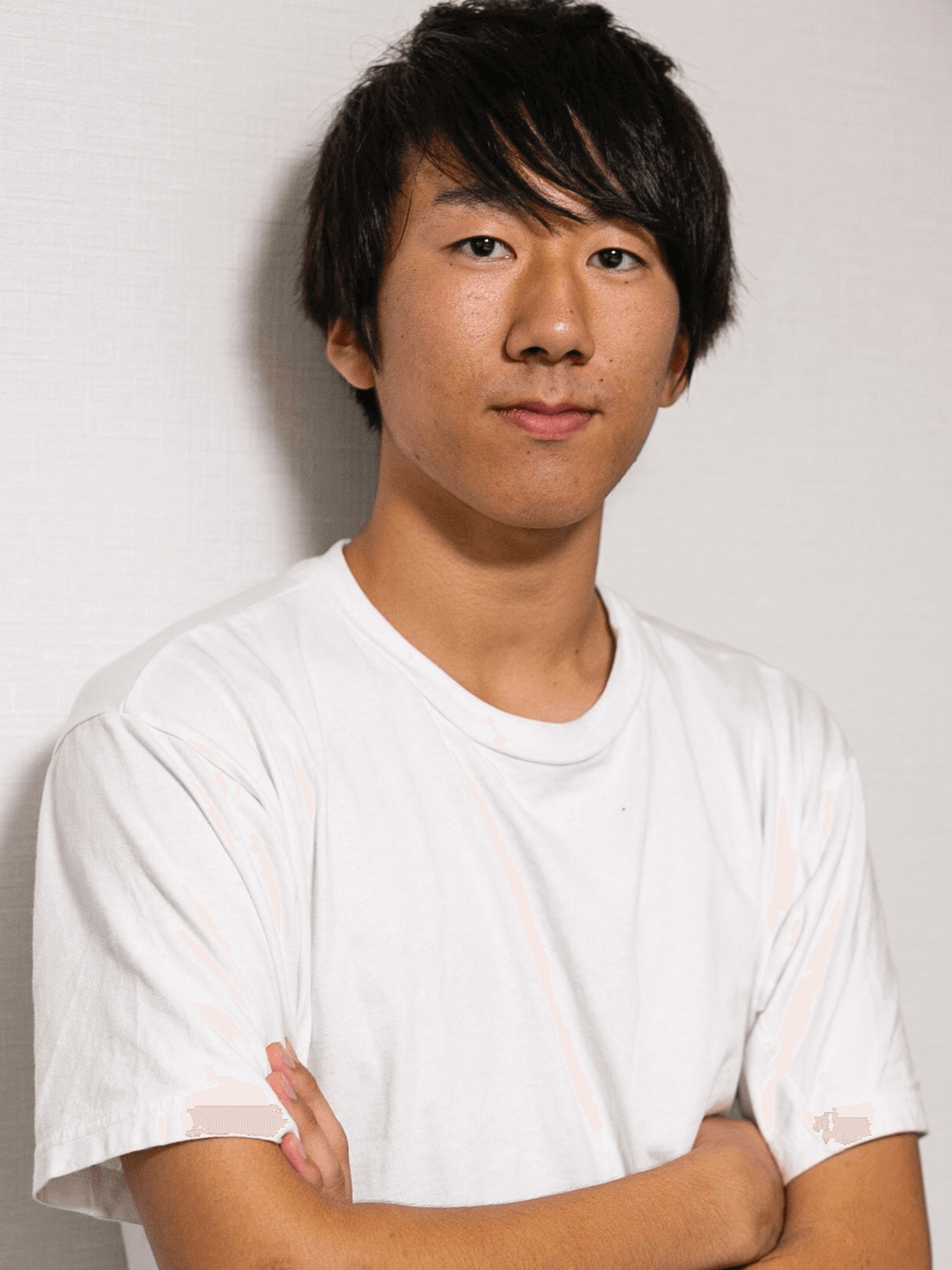更新日:2023/02/23
火災保険料の相場は?保険料の仕組みと保険料を抑える方法も解説
火災保険の保険料の相場は戸建てやマンションなどの建物の構造、所在地、築年数などによって変わります。保険料は補償内容によっても変わるので、火災保険の内容を理解して最適な火災保険に加入しましょう。保険料をできるだけ安く抑える方法も解説しています。

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 火災保険の保険料相場はいくら?料金の平均と目安を紹介
- 火災保険の保険料の相場をケースごとに紹介
- 火災保険の保険料相場①一戸建ての場合
- 火災保険の保険料相場②マンションの場合
- 火災保険の保険料相場③賃貸アパートの場合
- そもそも火災保険とは
- 火災保険って必要なの?
- 火災保険の補償対象には何があるの?
- 火災保険の補償内容って何があるの?
- 火災保険の保険料が算出される仕組み
- 火災保険の保険料の決め方
- 火災保険の保険料の決め方①建物の構造
- 火災保険の保険料の決め方②建物の所在地
- 火災保険の保険料の決め方③建物の延べ床面積
- 火災保険の保険料の決め方④建物の築年数
- 火災保険の保険料の決め方④火災保険の補償内容
- 火災保険の保険料相場を安くする方法
- 火災保険の保険料相場を安くする方法①不要な補償・特約を外す
- 火災保険の保険料相場を安くする方法②長期契約にする
- 火災保険の保険料相場を安くする方法③複数の会社で見積もり比較
- 火災保険の保険料相場を安くする方法④免責金額を設定する
- 火災保険加入時の注意点
- 火災保険で補償されないケースを把握しておこう
- 保険金の払い方について理解しておこう
- 火災保険とセットで入る「地震保険」の保険料相場
- 地震保険の基本料率
- 地震保険の割引率
- 地震保険の長期係数によっても価格相場は変化する
- まとめ:一括見積りをして保険料の相場をみてみよう!
目次
火災保険の保険料相場はいくら?料金の平均と目安を紹介

一戸建てを購入した時や賃貸でマンションを借りた時など、火災保険の加入を検討する機会は多いです。
火災保険の保険料はどのようにして決定されるかご存じでしょうか。
保険会社によっても補償内容やサービスはまちまちで、保険料も同じではありません。
そこで、今回は
- 火災保険料の相場
- 火災保険料の相場の仕組み
- 火災保険料を決める要素
- 火災保険料を安くするコツ
火災保険の保険料の相場をケースごとに紹介
「火災保険の保険料は〇〇円になる」と明確にお伝えすることはできません。
火災保険料は建物の構造や所在地、築年数、補償内容によって変わります。
また、保険会社によって保険料の算出方法も異なります。
そこで今回は、以下の条件で比較してみましょう。
- 所在地/東京都
- 物件/住宅
- 面積/100㎡
- 建物補償額/1,500万円
- 保険開始日/2022年7月1日
- 契約年数/5年
- 保険料支払い方法/一括
なお、今回は建物のみの場合であり、火災と風災、水災及び破損汚損を補償内容としています。
火災保険の保険料相場①一戸建ての場合
一戸建ての場合、保険料の相場はこのようになっています。
なお、保険料の金額は5年契約を一括で支払った場合の金額となっています。
| 新築 | 築10年 | |
|---|---|---|
| 木造(H構造) | 約8万円~約12万円 | 約10万円~約14万円 |
| 鉄筋造り(T構造) | 約4万円~約7万円 | 約6万円~約9万円 |
一般に、火に弱い木造の保険料がかなりの高額になっていますが、耐火基準(耐火構造建築物や耐火建築物である等)を満たしている建物であれば、木造だとしても表に記した金額より低くなる可能性があります。
また、築年数が経つにつれて火災が発生した際の損害が大きいと判断されるため、新築よりも中古の方が保険料が高い傾向にあります。
火災保険の保険料相場②マンションの場合
マンションの場合、保険料の相場はこのようになっています。
なお、保険料の金額は5年契約を一括で支払った場合の金額となっています。
| 新築 | 築10年 | |
|---|---|---|
| マンション(M構造) | 約3万円~約5万円 | 約4万円~約6万円 |
上記は、鉄筋コンクリートのマンションの場合になります。
アパートもマンションの場合に含まれますが、アパートの場合は、軽量鉄骨や非耐火建物の場合もあるため、注意しましょう。
また、マンションの何階かによって災害に見舞われるリスクが変わります。
マンションの上階であれば水災のリスクも下がると考えられるため、補償内容の見直しをすれば保険料も下がるでしょう。
火災保険の保険料相場③賃貸アパートの場合
アパートなどの賃貸契約の場合、火災保険料の相場は1年契約で約7,000円~約1.5万円になります。
賃貸物件の場合、建物全体に火災保険をかける必要はないため、火災保険料の相場は低くなります。
賃貸では引っ越す可能性があるので契約期間も1年とする場合が多いです。
そもそも火災保険とは
火災保険とは、火災や自然災害などが原因で建物や家財が損害を受けた場合に、その損害を補償するための損害保険です。
火災保険に加入する前に、
- 火災保険の必要性
- 火災保険の補償の対象
- 火災保険の補償内容
火災保険って必要なの?
火災保険の加入に法律上の義務はありませんが、加入することをおすすめします。
なぜなら、もし火災が起こった際に多大なる損害が予想されるためです。
もし火災保険に加入しておらず、火災で建物が全焼してしまった場合、建物を再び建築する費用も家財道具の購入費用も自己負担になります。
住宅ローンがある方は、再建築費用や家財購入費用に加えて住宅ローンの支払いも重なり、大きな負担となってしまいます。
賃貸の場合、建物自体は貸主の所有物であり、貸主が火災保険に加入しています。
しかし、入居者は原状回復の義務を負っているため、もし火災を起こしてしまった場合には、入居者が元の状態に戻す必要があります。
そのため、賃貸の場合は「借家人賠償責任補償」が付いた火災保険に加入するのが一般的です。
火災保険の補償対象には何があるの?
火災保険の補償の対象には、「建物」と「家財」があります。
- 建物:建物本体、建物に備え付けの冷暖房、お風呂、洗面台など
- 家財:家具、冷蔵庫、洗濯機、テレビなど
火災保険の補償内容って何があるの?
火災保険の補償内容は火災だけでなく、自然災害や盗難における損害に対しても補償されます。
火災保険の補償内容は以下になります。
- 火災(失火、もらい火などによる火災)
- 落雷(落雷して室外機が破損)
- 風災(台風で窓ガラスが割れる)
- 水漏れ(給排水設備の故障により水漏れ)
- 水災(ゲリラ豪雨で床下浸水)
- 破裂や爆発(ガスが漏れて爆発)
- 盗難(泥棒に入られカギを壊された)
- 騒擾(紛争に巻き込まれ家が崩壊)
- 建物外部からの物体の落下や飛来、衝突(車が家に突っ込んできた)
火災保険の保険料が算出される仕組み
保険料は、「純保険料」と「付加保険料」とで成立しています。
「純保険料」とは、保険の受取人に支払うための資金源のことをいい、純保険料率(過去に起きた事故の発生頻度や損害額のデータに基づいた率)を用いて計算されます。
この純保険料率は、参考純率を元に法律に基づいて各保険会社が独自に決めます。
しかし、過去のデータだけでは将来に起こる災害の予測が困難なのでシミュレーションも行って決定されています。
「付加保険料」は、保険会社の運営に必要な経費や利益から成り立っています。
その算出方法は法律(料率三原則)に従って算出されますが、各保険会社によって異なります。
※料率三原則とは、合理的である、妥当である、不当に差別的でないという3つの要件のことであり、それら全てを満たしていなければいけない法律のことです。
火災保険の保険料の決め方
火災保険の保険料はどのように決定されるのでしょうか。
一般的な火災保険は、
- 建物の構造
- 建物の所在地
- 建物の延べ床面積
- 建物の築年数
- 火災保険の補償内容
火災保険料を決める要素について詳しくみていきましょう。
火災保険の保険料の決め方①建物の構造
火災保険では、建物の構造によって保険料が変わります。
建物の構造は下記の3つに分けられます。
- 非耐火構造(H構造):木造や土蔵づくりなどの一軒家
- 耐火構造(T構造):鉄骨造りなどの一軒家
- マンション構造(M構造):鉄筋コンクリートなどのマンションやアパート
上記の構造のどれに当てはまるかによって保険料が決定されます。
木造よりも鉄骨造りの方が保険料が安いというように、一般的に、耐火性が高いほど保険料は安くなります。
火災保険の保険料の決め方②建物の所在地
建物の所在地も保険料を決定する重要な要素になります。
地域によって、自然災害のリスクが異なるためです。
たとえば、沖縄や九州は台風の被害が多い傾向にありますが、北海道は台風の被害は少ない傾向にあります。
また、住宅が密集している地域で火災が発生した際には、近隣の建物へ火災が広がるリスクが高くなるでしょう。
このように、建物の所在地のリスクが高ければ高いほど、保険料は高くなります。
火災保険の保険料の決め方③建物の延べ床面積
延べ床面積が広くなれば、火災保険料は高くなります。
延べ床面積とは、建物の各階の床の面積を合計したもので、建物の評価額を算出する際に重要になってきます。
たとえば、建物が2階建ての場合、1階と2階の床の面積を合計したものが、その建物の延べ床面積になります。
延べ床面積が広ければ建物の評価額は高くなり、補償額が高くなるため、火災保険料が高くなります。
火災保険の保険料の決め方④建物の築年数
建物の築年数が古いほど、火災保険料は高くなります。
古い建物は電気や給排水設備の老朽化により、火災や水漏れのリスク、台風や大雪などによるリスクが高くなります。
古い建物の場合、火災保険料は高くなりますが、火災や自然災害による損害を受けてしまった際の費用に不安がある方は、火災保険に加入しておくとよいでしょう。
火災保険の保険料の決め方④火災保険の補償内容
補償内容によって火災保険料は変わります。
多くの火災保険の補償内容では、火災や落雷、風災等の自然災害に備えています。
一方、水漏れや水災、 盗難などの補償は、必要なものを選ぶのが一般的です。
一般的に補償内容が広くなるほど、保険料は高くなります。
補償内容を検討する際には、起こりやすい災害を把握しておくことが重要です。
地域によって災害の頻度や程度は異なるため、保険対象の建物がある地域のハザードマップなどを利用して補償内容を検討するとよいでしょう。
また、他に加入している保険の補償内容と重複しないようにすると無駄も省けます。
火災保険の保険料相場を安くする方法
ここまで、火災保険の保険料について説明してきました。
住んでいる建物の構造などによって保険料は変わりますが、特に一戸建ての場合は火災保険だけでも年間10万円ほどかかることも多く、大きな出費ですよね。
また、一般的には建物だけでなく家財にも保険をかけるため、保険料はさらに上がります。
毎月支払う家賃や住宅ローンに加えて資金を準備しておかなくてはならないので、保険料の負担を少しでも節約したいと考える方は多いと思います。
そこで、火災保険の保険料を安くするために
- 不要な補償・特約を外す
- 5年契約などの長期契約にする
- 複数の会社で保険料の見積もりをとって比較する
- 免責金額を設定する
の4つの方法を詳しく説明していきます。
火災保険の保険料相場を安くする方法①不要な補償・特約を外す
補償内容の見直しをすると保険料を抑えられます。
たとえば、高台にあり水害の被害を受けにくいと判断できたら、水災補償を外すと保険料が安くなります。
補償内容を見直す際には、洪水ハザードマップや各都道府県が公開している土砂災害警戒区域などの情報で確認をし、損害リスクを考えて補償を検討しましょう。
しかし、最近では、水災のリスクの低い地域とされていても、洪水や土砂災害が起こるケースも少なくありません。
都市部であっても、突然のゲリラ豪雨で下水や河川が溢れて洪水の被害も多くなっています。
また、台風の場合でも、近年の温暖化の影響で台風の進路も予想できない状況が多々あります。
そのため、災害の可能性が低い地域であったとしても、様々なリスクの予想をして火災保険の補償内容を考える必要があります。
その上で、無駄だと思う補償は入れず、よく検討をして火災保険の補償内容を決定しましょう。
また、他の保険と重複しているものや不要と思われる特約を見直して補償から外すことも大切です。
火災保険には、事故再発防止等費用特約や携行品損害特約などの特約があります。
これらの特約が必要かどうかを考えて見直してみましょう。
火災保険の保険料相場を安くする方法②長期契約にする
火災保険は一般的に契約期間を長期にし、一括で支払うことで保険料が安くなります。
毎年保険料を支払っている方は、長期契約へ変更するだけで保険料が安くなるでしょう。
火災保険の契約期間の最長10年になります。
ただし、保険会社によりますが、2022年10月以降に契約期間の最長は5年に変わる見込みなので、注意しましょう。
火災保険の保険料相場を安くする方法③複数の会社で見積もり比較
一社のみで保険料の見積もりをとって検討するより、複数の保険会社からの見積もりをとって比較すると節約に繋がります。
保険料は保険会社によって独自に計算されたものなので、保険料も異なります。
同じ補償内容や保険金額で設定をして数社から見積もりをとれば、どの火災保険会社が得か分かります。
ただ、サービス内容(ネットから申し込むと割引、オール電化割引など)が各保険会社に設定されている場合があります。
それらを比較するためにも、便利な一括見積をしてくれるサイトを利用すると良いでしょう。
火災保険の保険料相場を安くする方法④免責金額を設定する
火災保険の契約時に免責金額を設定することが出来ます。
免責金額とは自己負担額のことであり、損害が発生して保険金が支払われる際に免責金額を差し引いた金額が給付されます。
この免責金額を設定すると、保険料を安く抑えることが出来ます。
免責金額を高くするほど保険料を抑えられますが、それには注意が必要です。
万が一、災害に見舞われ損害が生じた時、免責金額を設定していない場合では保険金は満額(保険会社の判定によります)支払われます。
しかし、免責金額を設定していた場合、支払われるであろう金額からその免責金額が差し引かれてしまうので、自己負担が大きくなってしまいます。
免責金額を設定すれば保険料は下がりますが、しっかりと考えた上で設定することをおすすめします。
火災保険加入時の注意点
火災保険では火災だけでなく、様々な自然災害にも備えることができるので非常に心強い保険といえますが、契約する際に注意すべき点があります。
ここでは、火災保険加入時に注意すべき点についてご紹介します。
火災保険で補償されないケースを把握しておこう
下記のような場合、火災保険の補償の対象となりません。
- 地震や噴火(火災保険のみ加入の場合)
- 経年劣化
- 故意による過失、重大な過失、法令違反による損害
- ドアや窓の隙間からの雨などの吹込み
- 免責金額以下の損害
保険金の払い方について理解しておこう
- 新価(再調達価格):同じ建物を建築または購入する際に必要な金額
- 時価:建物の現在の価値。新価から時間経過による価値の低下分を引いた金額
の2つがあります。
現在では、「新価」で契約することが一般的ですが、昔に契約した火災保険の中には「時価」で契約されているものがあります。
時価の場合、損害を受けた際に損害額の100%を受け取れない可能性もあるので注意が必要です。
また、時価の場合には保険料が安く設定されています。
契約する際は、「再調達価格」なのか「時価」なのかを確認するようにしましょう。
火災保険とセットで入る「地震保険」の保険料相場
火災保険を契約する際に、地震保険についても検討することが多いです。
そのため、地震保険についても少しご紹介します。
地震保険とは、地震や噴火、それらが原因となって発生した津波による損害を補償する保険です。
火災保険では、地震や噴火、津波による損害は補償対象外となっているため、地震や噴火、津波による損害に備えるためには地震保険が必要となります。
地震保険は単独で加入することはできず、火災保険とセットで加入する仕組みです。
地震保険は損害保険会社と国が共同で運営している性質上、保険会社が違っても保険料は変わりません。
保険料を決める要素は、住んでいる都道府県と建物の構造の2つです。
地震保険の保険料は基準料率(保険金額1,000円に対する年間の保険料の割合)を用いて、以下の計算式で求められます。
保険料=保険金額×基準料率÷1,000
また、基準料率は以下のように計算されます。
基準料率=基本料率×所要の割引率×長期係数(契約が2~5年の場合)
地震保険の基本料率
基本料率は、都道府県と建物の構造によって分けられています。
等地区分
都道府県は、地震の発生リスクに応じて1等地から3等地まで、3つの区分に分けられます。
東京や静岡などの太平洋側の地域は最も地震発生リスクの高い3等地、北海道や日本海側の地域は1等地に分類されています。
構造区分
建物の構造は、耐火建築物・準耐火建築物などの耐火構造の建物はイ構造、それ以外の非耐火構造の建物はロ構造に分類されます。
基本料率
以下の表は、現行の基本料率の一例です。
等地区分が同じでも、基本料率は府県によって微妙に違いがあります。
| イ構造(耐火) | ロ構造(非耐火) | |
|---|---|---|
| 東京(3等地) | 2.75 | 4.11 |
| 大阪(2等地) | 1.16 | 1.95 |
| 北海道(1等地) | 0.73 | 1.12 |
この表を見ると、1等地と3等地で基本料率にかなり大きな差があることがわかりますね。
後で説明する割引率などの適用がない場合、木造などの非耐火構造で比較すると、保険金額1,000万円の地震保険の年間保険料は、東京で41,100円、北海道で11,200円と、実に29,000円以上もの差があります。
地震保険の割引率
地震保険は、建物の耐震性能が優れていれば割引を受けられる仕組みになっています。
割引には4種類あり、条件を満たす場合10~50%の割引が受けられます。
| 条件 | 割引率 | |
|---|---|---|
| 免震建築物割引率 | 住宅性能表示制度の「免震建築物」である | 50% |
| 耐震等級割引率 | 評価方法基準に定められた耐震等級、または国土交通省の定める耐震等級の1~3級に該当する | 3級:50% 2級:30% 1級:10% |
| 耐震診断割引率 | 耐震診断または耐震改修の結果、現行の国が定める耐震基準を満たしている | 10% |
| 建築年割引率 | 1981年6月1日以降に新築された建物である | 10% |
これらの割引は重複して受けることはできず、最も高い割引率のものを適用します。
それぞれの条件を満たしていることを証明する書類については、保険会社に確認して提出しましょう。
地震保険の長期係数によっても価格相場は変化する
地震保険の保険期間は最長5年です。
2~5年の長期契約をした場合の保険料は、保険期間1年の保険料をそのまま2~5倍にするのではなく、下記の長期係数をかけて計算します。
| 保険期間 | 長期係数 |
|---|---|
| 2年 | 1.90 |
| 3年 | 2.85 |
| 4年 | 3.75 |
| 5年 | 4.65 |
そのため、1年ごとに契約するより長期で契約するほうが、保険料はお得になります。
まとめ:一括見積りをして保険料の相場をみてみよう!
火災保険料の相場や補償内容などを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは
- 火災保険料は建物の構造や所在地、補償内容などによって決まる
- 補償内容の見直しや長期契約にすると保険料は安くなる
- 補償内容を検討する際は、所在地の損害リスクを考慮する
- 複数の保険会社の見積もりで比較することが重要