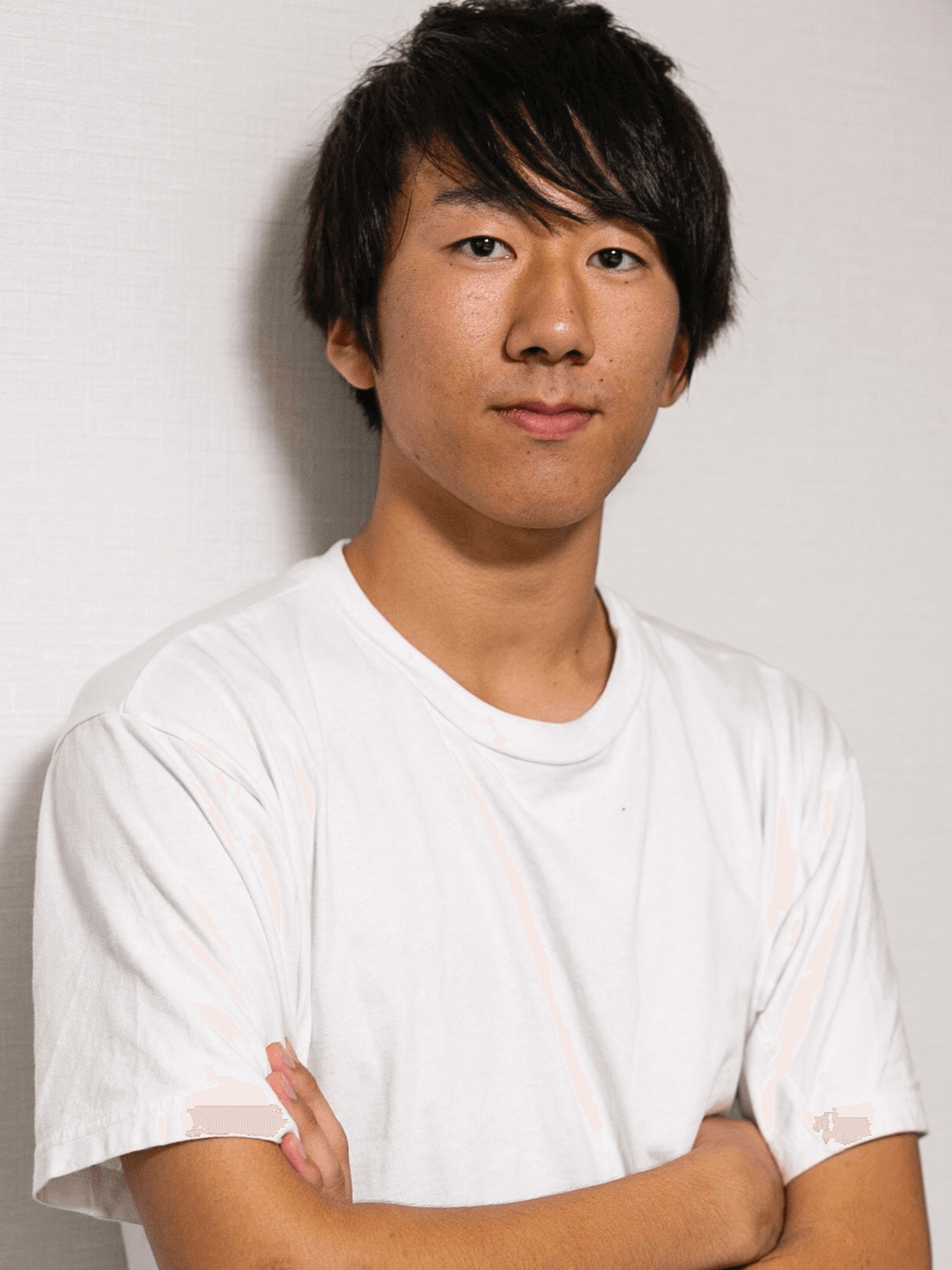更新日:2022/07/07
木造住宅は構造によって火災保険の保険料が変わる?仕組みと相場を解説
木造住宅は一般的に火災保険料が割高に設定されています。しかし同じ木造でも、構造によって保険料が変わり、長期にわたって支払う保険料に大きな影響をおよぼします。今回は構造による保険料の違い、保険料の相場、保険料をおさえるポイントなどを中心に解説します。

目次を使って気になるところから読みましょう!
木造住宅は構造によって火災保険の保険料が変わる!

火災保険の保険料を決める要因のひとつに、建物の構造があります。
一般的に、燃えやすい構造の木造住宅は鉄筋造の住宅よりも保険料が割高です。
しかし、同じ木造住宅のなかでも保険料に差があることをご存じでしょうか?一定の基準を満たせば、木造でも鉄筋造の住宅と同等の保険料になります。
とくに現在木造住宅の購入や新築・改築を検討している人にとっては、長期にわたって支払う保険料にかかわる重要な内容です。
そこで今回の記事では、以下の3点を中心に解説します。
- 木造住宅の構造による保険料の違い
- 省令準耐火構造について
- 木造住宅の保険料をおさえるポイント
この記事を読んでいただければ、木造住宅の保険料の仕組みを理解し、より割安な火災保険を選ぶことができるようになります。
ぜひ最後までご覧ください。
火災保険における木造住宅の2つの構造 | T構造とH構造の特徴
木造住宅の構造は、大きく以下の2つに分類されます。
- T構造:耐火構造
- H構造:非耐火構造
T構造は耐火性がある建物で保険料が割安
T構造は耐火性がある一戸建てが分類される構造です。
おもに以下のような住宅が該当します。
- 柱がコンクリート、れんが、石、鉄骨などでできている一戸建て
- 耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物に該当する一戸建て
H構造は耐火性が低い建物で保険料が割高
H構造はT構造以外の木造住宅が分類される、耐火性の低い構造です。
火災がおきた際の損害が大きくなりがちなため、比較的割高な保険料が設定されています。
増築や改築によってT構造に区分が変わることがあるので、木造住宅の増改築の際は必ず火災保険の見直しを実施しましょう。
木造住宅の火災保険料の相場
火災保険の保険料は築年数や所在地、補償の範囲などで大きく異なります。
ですから、いちがいに相場を算出することは難しいですが、年間の保険料の目安は以下のとおりです。
- T構造:3~6万円程度
- H構造:6~12万円程度
このようにH構造はT構造のおおむね2倍程度の保険料になります。
なお、保険会社によっても保険料は異なるので、火災保険を選ぶ際は必ず複数の保険会社に見積りを依頼するようにしましょう。
省令準耐火構造の木造住宅のメリットとデメリット
省令準耐火構造は、T構造に分類される木造住宅の代表例です。
住宅金融支援機構が定める一定の基準を満たす住宅が分類され、以下の3つの特徴を持ちます。
- 外部からの延焼防止:隣家などから火をもらいにくくする
- 各室防火:火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない
- 他室への延焼遅延:建物内部での延焼をできるだけ遅らせる
木造住宅の火災保険料をおさえる3つのポイント
木造住宅は火災保険料が割高になりがちなので、保険料をおさえることが比較的重要です。
耐火構造を選ぶ以外に、以下のような方法があります。
- 長期契約にして、保険料を一括払いにする
- 不要な補償や特約を外す
- 複数の保険会社に見積りを依頼する
①長期契約にして、保険料を一括払いにする
火災保険料は契約期間が長いほど割安です。
最長の10年契約にした場合の保険料は、1年契約の場合の80%ほどになります。保険料は値上げ傾向にありますが、値上げ以前に契約した保険料は契約終了まで変わりません。
また、保険料は一括払いがもっとも安く、年払い、月払いの順に高くなります。予算が許すのであれば一括払いを選択しましょう。
②不要な補償や特約を外す
火災保険は不要な補償や特約を外すことで保険料をおさえることが可能です。
たとえば高台や賃貸マンションの高層階などに住んでいる場合、水災補償の必要性は低いといえます。家財に対して必要以上に高額な補償をつけていないかも確認しましょう。
火災保険は補償の範囲が比較的広いため、本当に必要な補償のみを選ぶことが肝心です。
③複数の保険会社に見積りを依頼する
火災保険は保険会社によって補償の範囲や保険料が異なります。
ですから加入を検討する際は必ず複数の保険会社に見積りを依頼しましょう。同じ補償内容でより保険料が低い保険会社や、選択肢が多く必要な補償のみを選びやすい保険会社が見つかることも少なくありません。
なお、個々の保険会社に依頼をするのは現実的ではないため、一括で複数社に見積りを依頼できるサービスを利用することをおすすめします。
まとめ:木造住宅の火災保険を選ぶならまずは無料で見積り依頼を!
木造住宅の火災保険について解説してきましたが、いかがでしたか?
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
- 木造住宅は耐火性によってT構造とH構造に分類される
- 耐火性の低いH構造の火災保険料はT構造の2倍程度
- 省令準耐火建物はT構造の代表例
- 木造住宅は火災保険料が高くなりがちなので、本当に必要な補償のみを選ぼう
基本的に耐火性のあるT構造を選んだうえで、必要な補償のみを付加することをおすすめします。
なお、火災保険料は上昇傾向にあり、2022年10月には保険料の大規模な値上げがなされる見込みです。加入と見直しはなるべく早めに検討しましょう。
下部のボタンから利用できる見積りサイトは顧客満足度94%で、最大26商品から比較できます。
保険アドバイザーに何度でも無料で相談が可能ですので、ぜひご活用ください。