学資保険おすすめ人気比較ランキング【2024年版】返戻率が高い学資保険・安い保険をプロが解説!
- 子どもの学費や教育資金が心配な人
- 返戻率が高いおすすめの学資保険が知りたい人
- 学資保険についてよくわかっていないから加入していない人
内容をまとめると
- 学資保険には、元本割れやインフレリスクなどのデメリットも存在する
- 学資保険のメリットは貯蓄と保障を同時に行えるところ
- 自分にぴったりの学資保険を見つけたいという方は、保険のプロに無料相談するのがおすすめ!
- マネーキャリアなら、40社以上の保険商品を一括比較して、あなたにとって1番返戻率の高いおすすめの学資保険を提案してくれる!

- 返戻率だけじゃない?学資保険は専門家に相談がおすすめな理由
- 学資保険のデメリットを4つで解説
- ①学資保険は返戻率が低い!元本割れリスクもある
- ②満期まで引き出すことができない
- ③インフレリスクがある
- ④満期保険金を受け取ると贈与税がかかる
- 学資保険のメリットを3つで解説
- ①教育資金を強制的に貯蓄できる
- ②投資よりも比較的安全にお金を増やせる
- ③所得税と住民税の負担を軽くできる
- 学資保険の選び方
- 選び方①返戻率
- 選び方②保障内容
- 選び方③保険金の受取時期
- 選び方④支払期間と加入期間
- 学資保険の返戻率を高くする方法
- ①払戻開始時期・完了時期が遅いプランにする
- ②保険料の支払い方法を短期払い・年払いにする
- ③学資保険に不要な特約をつけない
- ④早いタイミングで学資保険に加入する
- 学資保険の代わりに教育資金を準備できるおすすめの方法
- おすすめの学資保険に関してよくある質問
- Q1. 学資保険の保険料は毎月いくらくらい?
- Q2. 学資保険は何割くらいの人が入ってる?
- Q3. 学資保険は払込期間は何歳まで?
- Q4. 子供の教育費はいくら必要?
- まとめ:最適な学資保険の相談はマネーキャリアがおすすめ!
目次
返戻率だけじゃない?学資保険は専門家に相談がおすすめな理由
ここまで、2024年最新版の返戻率が高い学資保険おすすめ比較ランキングについてご紹介いたしました。上記の保険会社で保険相談しようと考えた人もいるのではないでしょうか。
保険会社で保険相談する際には、以下のような注意点があります。
- 取扱っている保険商品が自社の商品のみ
- 保険商品数が少ないため比較しにくい
保険会社で保険相談を受けた場合にはあなたにぴったりの保険商品でないとして保険会社の利益のために自社の保険商品をおすすめされる場合があります。
そのため、学資保険に加入する前にはまず無料の保険相談窓口でFPに相談するのがおすすめです。
FPに相談するメリットは以下です。
- 家計やライフプランを踏まえた上で自分にぴったりの学資保険に加入できる
- 保険の専門家であるFPという立場からアドバイスがもらえる
- 多数の保険会社の保険商品を一括比較できる
無料保険相談窓口の中にはオンラインで相談可能な窓口も存在します。時間や場所を選ばず、優秀なFPと相談できるため、おすすめの相談方法となっています。
学資保険への加入を考えている方は、まず無料保険相談窓口で相談してみましょう。

無料保険相談窓口で迷った場合にはマネーキャリアがおすすめです!
国内最大級の保険相談窓口であるマネーキャリアには、学資保険に強い女性FPが多く在籍しているため、あなたの悩みに寄り添った提案をしてくれます!
学資保険のデメリットを4つで解説

おすすめの学資保険について解説してきましたが、そもそも教育資金の準備方法として学資保険を選ぶべきなのか悩んでいる人もいるでしょう。
教育資金の準備方法として有用な学資保険ですが、いくつかのデメリットも存在します。そのため、中には学資保険をおすすめできない人もいるのです。
学資保険への加入を検討中の場合には、それらのデメリットもしっかりと認識された上で加入することをおすすめします。
認識しないまま加入すると、思わぬ損失を被る場合もあるため注意が必要です。
では実際に学資保険にはどんなデメリットがあるのか、注意点と合わせてみていきましょう。

自分に学資保険がおすすめかどうか見極めたい方はこちらの記事もおすすめです!
①学資保険は返戻率が低い!元本割れリスクもある
時代の流れとともに学資保険返戻率が高い商品は少なくなってきています。
おすすめの学資保険を見ていただいてわかる通り、一番高い返戻率が明治安田生命のつみたて学資で109%程度です。
返戻率120%超えをしていた時代もありましたが、現在では、マイナス金利政策によってそこまで高い返戻率をもつ学資保険は存在しなくなってしまったのです。
20年間で総額200万円支払って、106%の返戻率だった場合を例にシミュレーションしてみましょう。
200万円×1.09 = 212万円
つまり、受取金額は総額218万円です。20年間で18万円しか増えに計算になります。
18万円という金額は決して小さなお金ではありませんが、20年という期間を考えると少し物足りなさを感じます。
また、学資保険の中には元本割れする商品もあります。
元本割れとは、支払額より受取額が少なくなるということです。増えるどころか減ってしまうのです。 効率よく増やして貯金する目的で学資保険に加入したのに、元本割れするのであれば本末転倒になってしまいます。
学資保険を検討する際、元本割れのリスクについてもしっかりと認識して加入するようにしましょう。
②満期まで引き出すことができない
学資保険の大きなデメリットが、積立金を満期まで引き出すことができないという点です。
預貯金なら必要な額をすぐに降ろすことが出来ますが、学資保険の場合、解約しなければなりません。
もしご自身やご家族に予期せぬことが起こり、急にまとまったお金が必要になったとき、預貯金がない場合は学資保険を解約して現金を確保しなければなりません。
学資保険を途中解約すると、解約返戻金という形で支払ったお金が返って来るのですが、大抵の場合元本割れしてしまいます。
また、満期時にできるだけたくさん受け取りたいからといって支払額を生活費ギリギリに設定したり、契約時とは生活環境が変わったりするなどして保険料を支払えなくなるケースもあります。
そうなると学資保険を解約しなければならなくなるので、はじめから無理のない金額で契約することも大切です。
十分な預貯金が確保できない場合、学資保険で学費を確保するよりも、いつでも引き出し可能な銀行に貯金する方が良いでしょう。
③インフレリスクがある
インフレとは、お金の価値が下がっていくことです。
このインフレにより、学資保険で受け取る満期保険金の金額では教育資金として足りなくなるというリスクがあるのです。
例えば、年収500万円の人が満期保険金200万円の学資保険に加入していた場合を考えてみましょう。
学資保険の契約から満期保険金を受け取るまでの約20年間でインフレが起こった場合、お金の価値は下がります。これにより物価が上がってしまうのです。それに伴い、学費として必要な資金も増加します。
そうなると、契約時に満期で受け取る金額を200万円に設定していた場合、契約時なら学費として十分足しになる金額だったとしても、インフレが起きたあとだと、学費が足りないという状況になる可能性があるのです。
日本は資本主義国家なのでインフレは完全には避けられません。
このようなリスクがあるということも必ず認識しておきましょう。
④満期保険金を受け取ると贈与税がかかる
満期保険金を受け取ると贈与税がかかります。
具体的に以下のような場合には基本的に贈与税がかかります
- 契約者が親などで、満期保険金の受取人を子供にした場合
- 契約者がおじいちゃん、おばあちゃんなどで、満期保険金の受取人を子供や孫にした場合
などです。
このように実際に保険料を支払った人と、満期保険料を受け取る人が違う場合に贈与税がかかります。
これは保険会社を通してるとはいえ、お金を受け渡したとみなされるからです。
ただし、贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。 贈与額から基礎控除を引いてその金額がプラスだった場合、そのプラス分のみが課税対象になります。
また、契約者と受取人が同じ場合には、一時所得という形で処理され、所得税がかかります。
一時所得は収入から、実際にかかった費用を差し引いた金額分が課税対象になります。
そして、一時所得には年間50万円の控除があります。 満期金受取額から保険に支払った総額を引いて、さらに控除額の50万円を差し引きます。
その金額がプラスだった場合、プラス分が課税対象になります。
基本的には、契約者と受取人が同じ場合の方が、受取時にかかる税金は少なくて済みますが、満期保険金の設定額や返戻率によって税金が変わってきます。契約者と受取人は、契約時によく考えて決めましょう。
学資保険のメリットを3つで解説

ここまでデメリットを見てきましたが、
「もしかして、学資保険って入らない方がいいんじゃない?」
「入ると損しかしない気がする」
など、不安に思いはじめている方もいるのではないでしょうか。
ここまではデメリットや注意点に着目してお話しさせていただきましたが、それはあくまでも余計な損失を避けたり、あとで知らなかった!とならない為です。
学資保険へ加入するメリットも、もちろんあります。
メリットとデメリットどちらも認識した上で、自分にとってベストな選択することが大切になってきます。
では、学資保険のメリット3つを見ていきましょう。
①教育資金を強制的に貯蓄できる
満期まで降ろせないことはデメリットにも書きましたが、逆にそれを利用することもできます。
貯金が苦手な人は、降ろせるお金があると、つい使ってしまいがちですが、保険金として支払うことで、そのお金は引き出せなくなり、強制的に教育資金が貯蓄できます。
学資保険は、以下のような方におすすめ
- 知らない間に1ヶ月分の給料がなくなってしまう方
- コツコツ貯金するのが苦手な方
このようなタイプの方は銀行に預けるより、学資保険で貯めることをおすすめします。
ただし次の点には気をつけて下さい
- 預貯金が少ない
- 学資保険を払うと、生活費がギリギリになる
こういった状況下の場合、やむを得なく解約しなければいけないケースも出てくるので注意しましょう。
②投資よりも比較的安全にお金を増やせる
現在は、NISAやiDeCoなどを利用して投資で積み立てる方も少しずつですが増えてきています。
運用がうまくいけば、学資保険よりも高い利益を生み出すことができますが、あくまでも投資なので元本割れのリスクが高くなります。
学資保険は、契約時に返戻率100%以上のものを選べば、途中解約をしない限り元本割れを起こすことはありませんが、投資は売却するまで元本割れのリスクがつきまといます。
| 学資保険 | 投資 | |
|---|---|---|
| 収益性 | 低い | 高い |
| 安全性 | 高い | 低い |
| メリット | ・契約者に万一のことが起きた場合に適用される払込免除など各種保障の付与 | ・自分の好きなタイミングで売買出来る |
| デメリット | ・好きなタイミングでお金を引き出せない ・途中解約の場合元本割れする可能性がある | ・元本割れの可能性がある |
お金を安全に、少しでも増やしたい人には学資保険はおすすめです。
③所得税と住民税の負担を軽くできる
学資保険は、「生命保険料控除」の対象です。
生命保険料控除とは、1年間に支払った生命保険料の金額から一定額が所得から差し引かれる制度のことです。
年末調整で手続きをすると、所得税と住民税の負担を軽くすることができます。
なぜなら所得税と住民税は、収入から各種控除を差し引いて、残った所得に計算されるからです。
ただしここで気をつけてほしいのが、申告できる人は「実際に保険料を支払った人」が行う、ということです。
契約者と保険料を支払う人が同じ場合は問題ないのですが、契約者が妻で、支払いは夫の口座から引き落としてもらっている。
この場合、控除申告できるのは夫になります。
申告できるのは、あくまでも実際に保険料を支払った人になるという点に気をつけましょう。
学資保険の選び方

現在学資保険を取り扱う会社は10社以上あります。
プランをいくつか用意している会社もあります。
その中から、我が家にピッタリ合ったものを見つけるにはどのようなポイントに注目して選べばいいのでしょうか。
以下のポイントに注目して選びましょう。
重要なポイント4つ
- 返戻率
- 保障内容
- 保険金の受け取り時期
- 支払期間と加入期間
それでは、ポイントを1つ1つ確認していきましょう。
選び方①返戻率
学資保険の一番の目的は、効率よく増やして「貯蓄」することです。
貯蓄性に特化した学資保険を「貯蓄型」といいます。
貯蓄性に優れた学資保険を選ぶ上で注目してほしいのが返戻率です。
※返戻率とは、支払う保険料の総額金に対して受け取る保険料の総額金の割合のことです。
返戻率が高いものほど、増えて戻ってくるお金が増えます。
返戻率は
- 受け取る保険料の総額金÷支払う保険料の総額金×100=返戻率(%)
で計算されます。
100%より少なければ、払った金額より受け取る金額が少ない(元本割れ)ということになります。
選ぶ基準として、貯蓄性を重視したいという方は、返戻率が高いものに注目してみてください。
選び方②保障内容
学資保険の一番の目的は、効率よく増やして「貯蓄」することですが、学資保険には「医療保障」「養育年金」がもらえる保障を付与して保険を強化できるものもあります。
このような保障が付与されている学資保険を「保証型」といいます。
保証型学資保険の特徴
- オプションで子供の医療保障をつけることができる
- 契約者(親など)が亡くなったり、重度障害者になるなど万一の事が起きた時、払込免除制度とは別に「養育年金」が受け取れる
万が一の時にしっかりと備えたい方は、このような保障がついているものがおすすめになります。
また、学資保険の他に子供の医療保険の加入を検討しているという場合にも、このような医療保障が付与されたタイプを検討してみるのもいいでしょう。
選び方③保険金の受取時期
学資保険は、会社やプランによって保険金の受け取り方や時期を選べます。
例をあげますと
- 幼稚園、小学校、中学校、高校入学前お祝い金を受け取る
- 大学入学時にまとめて一度に受け取る
- 大学入学後1年毎に、毎年受け取る(計5回)
などがあります。
またお金を受け取れる時期は、子供の誕生日によっても変わってくるので気をつけましょう。
- ○歳満期と表記されている時、○歳になったあとのはじめの契約応当日にお金を受け取ることができます。 ※契約応当日とは、学資保険を契約した月日のことです。
我が家ではどのタイミングでお金が必要になるのかをしっかりと検討して、受け取るタイミングを選びましょう。
選び方④支払期間と加入期間
保険料の支払いをを子供が何歳になるまでに終わらせるか。
この支払い方法が2つあります。
1つ目は短期払い。
これは満期より早めに支払いを終えるケース。
2つ目は、全期払い。
これは、満期まで支払いを継続する場合です。
短期払いのメリットとデメリットを比較してみましょう。
| 短期払い | 全期払い | |
|---|---|---|
| メリット | 返戻率が高くなる | 保険料を抑えられる |
| デメリット | 保険料の負担が高くなる | 返戻率が低め |
- 毎月の支払う保険料があがる
- 返戻率が低くなる
学資保険の返戻率を高くする方法

効率よくお金を増やして貯蓄性を高めるためには、やはり返戻率が高いということが大事になってきます。
返戻率は意識することで上げることができます。
では、どのようなプランを選べば返戻率が高くなるのでしょうか。
4つご紹介させていただきますので、ひとつずつ見ていきましょう。
①払戻開始時期・完了時期が遅いプランにする
払戻開始時期とは、一番最初に祝い金等の形で保険金を受け取る時のことです。
完了時期とは、全ての保険料の受け取りが終了する時のことです。
学資保険の受け取り方は、先程もご紹介したように以下のように受け取る時期を選択できます。
- 幼稚園、小学校、中学校、高校入学前お祝い金を受け取る
大学入学時にまとめて一度に受け取る
大学入学後1年毎に、毎年受け取る(計5回)
この中で一番返戻率が高いプランは、3番の「大学入学後1年毎に、毎年受け取る」です。
保険会社に預けた保険料は、保険会社が預かっているトータルの額を運用して増やしていきます。
このトータルの額が大きいほど利率は増えます。
そのため祝い金などで途中お金を受け取ってしまうと、預けているトータルの額が減ってしまい、返戻率が下がってしまうというわけです。
以上のことから、1つ目の返戻率を高くする方法はできるだけ「払戻開始時期・完了時期が遅いプランにする」ということです。
②保険料の支払い方法を短期払い・年払いにする
支払い方法は満期まで支払い続ける全期払いより、満期より早く支払いを終わらせる「短期払い」の方がおすすめです。
ひとつ前でもお話ししたように、保険会社は預かっているトータルの金額を運用して増やしていきます。
そのため、短期払いを選ぶことによって保険会社は預かるお金が早く増え、長い間運用できます。
ただし注意してほしいのは、短期払いは支払いを終わらせる期間を早める分、全期払いよりも月々の保険料を多く支払わなければなりません。
最後まで無理なく支払い続けられるように、しっかりと資金計画をしましょう。
また以下のように支払い方法を選ぶこともできます。
- 毎月支払う「月払い」
- 半年分をまとめて支払う「半年払い」
- 1年分をまとめて支払う年払い「年払い」
できるだけまとめての支払い方法を選ぶと、保険料が割引きされます。
そうすると受け取る満期金は月払いと変わらないのに、支払う保険料自体は減るので返戻率が高くなります。
可能であれば「年払い」がおすすめです。
③学資保険に不要な特約をつけない
特約(保障)を付けると返戻率は下がってしまいます。
学資保険に付与できる特約の例
- 子供が病気やケガなどで、手術や入院した時に給付金がもらえる「医療特約」
- 契約者(親など)に万が一の時にもらえる「養育年金」(特約)
保障型は、保障が厚いので万が一の時を考えると魅力的ではありますが、保障の部分に保険金が割り当てられてしまうので、返戻率100%を大幅に下回ってしまうものが多いのが特徴です。
そのため、貯蓄性が薄れてしまいます。
貯蓄性を重視するなら、このような特約をつけるのはおすすめできません。
万が一にも備えたい場合は、学資保険とは別に医療保険へ加入も検討するのも一つの手です。
返戻率を重視するなら学資保険に不要な特約は、つけないことをおすすめします。
④早いタイミングで学資保険に加入する
たいていの学資保険は、子供の出生前から加入することが可能です。
保険料の支払い時期は予め決まっています。
そのため早く加入したほうが保険料の運営期間が長く確保することができ、返戻率が高くなります。
加入年齢の条件は保険によって変わってきますが、子供が6歳(小学校入学前)までのものが多いです。
また同じ保険のプランでも契約者(親など)の年齢が若い方が保険料が安くなります。
実際に子供が生まれたら、忙しくて学資保険の加入を後回しにしてしまい、気付いた時には、返戻率の高い保険への加入年齢条件が過ぎていた、ということにもなりかねません。
ですから学資保険への加入は、できるだけ早く加入することをおすすめします。
おすすめは妊娠中の加入です。
妊娠中から契約者の保障がはじまるものもあります。
お腹の赤ちゃんに万が一のことが起き、亡くなったりした場合は契約が無効化され、支払い済みの保険料は返還されます。
出産前の方が時間があり、ゆっくり検討できるのもおすすめのポイントです。
学資保険の代わりに教育資金を準備できるおすすめの方法
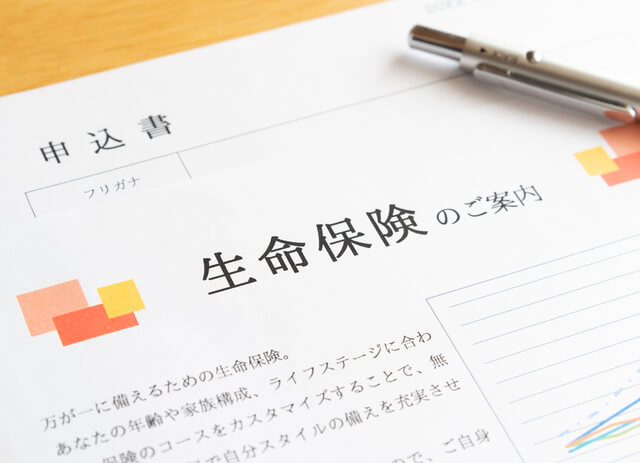
学資保険についてご紹介してきましたが、学資保険以外にもおすすめできる教育資金の準備方法がいくつかあります。
ここでは、学資保険の代わりに教育資金を準備できるおすすめの方法についてご紹介いたします。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 低解約返戻金型終身保険 | ・死亡保障が手厚い ・子どもの年齢に関係なく加入できる ・解約返戻金を受け取るタイミングの自由度が高い | ・途中解約により元本割れする可能性がある ・子どもに保障を付けることができない ・低解約返戻金期間に解約すると返戻率が低くなる |
| 投資(NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA ) | ・学資保険より大きなリターンが見込める ・運用益(運用によって得た利益)が一定期間は非課税になる ・積み立てたお金をいつでも引き出すことができる | ・投資なので元本割れのリスクはある ・運用コストがかかる |
| 外貨建て保険 | ・日本より金利が高いため高い利回りが期待できる ・解約返戻金を受け取るタイミングを自由に決めることができる ・受取時が円安であれば受取額が増える | ・受取時が円高だと受取額が減る ・将来受け取れる金額が読めない ・為替手数料などの諸費用がかかる |
| 個人年金保険 | ・貯蓄が苦手でも計画的に教育資金を積み立てられる ・保険料控除で節税効果がある | ・途中解約によって元本割れする ・積み立てたお金を自由に引き出せない |
| 変額保険 | ・運用成績によっては高い返戻率が期待できる ・インフレに強い ・死亡保険金は最低保障される | ・元本割れのリスクがある ・投資信託より運用コストが高い |
| 貯蓄 | ・元本割れのリスクはない ・いつでも自由に引き出すことができる | ・金利が低いため、お金はほぼ増えない ・インフレにより教育資金が足りなくなる可能性がある ・計画的に貯蓄できる人でないと継続的に貯められない |
| 借入 | ・契約者・返済者は親だから子どもが教育資を負担する必要はない | ・奨学金より比較的金利が高い |
| 奨学金 | 借入より金利が安い、または無利息で借りられる | ・借りたお金は子どもに返済の義務がある |
教育資金の準備方法としては以上のようなものがあります。どの方法にもそれぞれメリット・デメリットが存在するため、目的や性格などに合った方法を選ぶことが大切です。

自分にとってどの準備方法がおすすめか気になった人はこちらの記事も参考にしてください!
おすすめの学資保険に関してよくある質問
ここからは、おすすめの学資保険に関してよくある質問に回答していきます。
- Q1. 学資保険の保険料は毎月いくらくらい?
- Q2. 学資保険は何割くらいの人が入ってる?
- Q3. 学資保険は払込期間は何歳まで?
- Q4. 子供の教育費はいくら必要?
Q1. 学資保険の保険料は毎月いくらくらい?
学資保険の保険料は、子ども1人につき月々1万円程度が適切です。ただし、必要な保険料は、学資保険の加入年齢や教育方針によって異なるため注意が必要です。
学資保険の保険料設定する上では、家計に負担を掛けないようにし、子どもの進学費用を確実に準備できることが大切です。
▼学資保険の保険料の決め方
- 必要な教育資金を確認
- 学資保険の受取額と受取時期を決める
- 保険料の払込期間を決める
以上の手順で保険料を決めるようにしましょう。
また、毎月1万円〜2万円も保険料に掛けたくないという方は、月々2,000円~5,000円程度で加入できる学資保険もあるので検討してみましょう。
Q2. 学資保険は何割くらいの人が入ってる?
アバコミュニケーションズの「『学資保険は必要?』学資保険に関するアンケート」によると、学資保険の加入率は約49%という調査結果になったようです。
学資保険加入していない理由としては、
- 預貯金をしているから
- 元本割れのリスクがあるから
- 利率が低いから
といった回答が見られました。
学資保険のデメリットを学資保険に加入しない理由として挙げた人が多いことが分かります。
Q3. 学資保険は払込期間は何歳まで?
学資保険の払込期間は、18歳満期や22歳満期など長期で保険料を払い続けるタイプの他にも、「10歳まで」「12歳まで」「15歳まで」など短期で払込むタイプもあります。
保険料の払込期間を短くすることで返戻率が上がるというメリットもありますが、将来払うべき保険料を前倒しで払うので月々の保険料が高くなるというデメリットもあります。
そのため、払込期間は保険料が毎月の家計を圧迫しない程度に設定するのがおすすめです。
Q4. 子供の教育費はいくら必要?
子ども1人にかかる教育費がどのくらい必要になるのか文部科学省の調査結果を見てみましょう。
| 子ども1人に必要な教育費 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 165,126円 | 308,909円 |
| 小学校 | 352,566円 | 1,666,949円 |
| 中学校 | 538,799円 | 1,436,353円 |
| 高校 | 512,971円 | 1,054,444円 |
こちらの費用は、学校給食費や学校外活動費など教育費に付随する費用も含んだ学習費です。
大学に進学してから卒業までに必要になる教育費がこちらです。
| 入学料 | 授業料(年間) | 施設設備費(年間) | |
|---|---|---|---|
| 国立大学 | 282,000円 | 535,800円 | - |
| 公立大学 | 394,225円 | 538,294円 | - |
| 私立:文系学部 | 229,997円 | 785,581円 | 151,344円 |
| 私立:理系学部 | 254,309円 | 1,105,616円 | 185,038円 |
| 私立:医歯系学部 | 1,073,083円 | 2,867,802円 | 881,509円 |
出典:文部科学省「平成30年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」
大学に進学した場合、1人暮らしすることが多いため、これらの費用に加えてさらに生活費が必要になります。
以上のように、子どもの教育費としては大学進学時に多額の費用が必要になることが分かります。
子どもの教育費として、大学進学まで考慮しているのであれば、500万円を目安に貯蓄するのが良いでしょう。
まとめ:最適な学資保険の相談はマネーキャリアがおすすめ!
学資保険について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
この記事では、
- 返戻率の比較あり!学資保険おすすめランキング5!
- 学資保険のメリット・デメリット
- 学資保険の選び方のポイント
- 返戻率をできるだけ高くする方法
- 学資保険の代わりに教育資金を準備できるおすすめの方法
を解説いたしました。
学資保険はご自身とお子様の将来のために備えられる大事な保険です。
加入してから失敗した!ということのないようにしっかりと理解しましょう。
自分で調べただけでは理解できたか不安という方は、マネーキャリアの保険のプロに無料相談すると良いですよ。
何度でも無料で相談可能ですので、ぜひご利用ください。






