
更新日:2022/07/14
地震保険の加入率はどのくらい?必要性や補償内容を詳しく解説!
地震保険の加入率は低く、約30%となっています。地震保険の加入率が低い理由として、地震保険の保険料が高いこと、地震保険は補償のみで生活の再建が出来ないことなどが挙げられます。今回の記事では、地震保険の加入率と地震保険加入の必要性について解説します。

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 令和2年度の地震保険加入率は約34%!
- 地震保険の世帯加入率と推移
- 地震保険の付帯率とは
- 共済も含めた地震保険の加入率
- 令和2年度:都道府県別の地震保険加入率
- 地震保険の加入率が低い3つの理由
- ① 地震保険の保険料が高い
- ② 地震保険では十分な保険金がもらえない
- ③ 地震保険の補償のみでは生活の再建が出来ない
- 地震保険の基礎知識
- 地震保険の3つの特徴
- 地震保険の補償対象は「建物」と「家財」
- 地震保険の補償内容
- 地震保険の加入の必要性
- 公的支援制度だけでは地震で受けた損害を補填できない
- 地震保険を付帯すべき人
- 参考:マンションの地震保険の必要性
- 日本で今後30年以内に大地震が起きる確率
- まとめ:地震保険の加入を検討して、いざという時に備えよう
目次
令和2年度の地震保険加入率は約34%!
- 地震保険の世帯加入率について
- 地震保険の加入率や付帯率が低い理由
- 地震保険について
- 地震保険の必要性の高い人とは

地震保険の世帯加入率と推移
| 年度 | 世帯加入率 |
|---|---|
| 2016年度 | 30.5% |
| 2017年度 | 31.2% |
| 2018年度 | 32.2% |
| 2019年度 | 33.1% |
| 2020年度 | 33.9% |
地震保険の付帯率とは
| 年度 | 付帯率 |
|---|---|
| 2016年度 | 62.1% |
| 2017年度 | 63.0% |
| 2018年度 | 65.2% |
| 2019年度 | 66.7% |
| 2020年度 | 68.3% |
共済も含めた地震保険の加入率
火災保険は共済でも取り扱いがあります。
民間の保険と同様に地震保険は火災保険に付帯していますが、損害保険料率算出機構の発表している数値には、各種共済の数値は含まれていません。
そのため、全てを合算した正確な数値は発表されていません。
参考ではありますが、2015年度の内閣府の発表では
- 地震保険の加入率…35%
- 地震共済の加入率…22%
- 両方を併用している分を考慮した合算の加入率…49%
とされています。
また、関西大学による発表では、地震保険の加入率は共済制度と合わせると46.5%となっているので、全体の加入率としては半数弱といえるでしょう。
さらに、地震損害による補填や補償を行う住宅ローンへの保険の非付帯率が37.9%という高い数値も見逃せません。
このように、地震に対する備えは、まだまだ低いと考えられます。
令和2年度:都道府県別の地震保険加入率
| ランキング | 都道府県 | 世帯加入率 |
|---|---|---|
| 1位 | 宮城県 | 51.9% |
| 2位 | 熊本県 | 43.5% |
| 3位 | 愛知県 | 43.3% |
| 4位 | 岐阜県 | 39.1% |
| 5位 | 福岡県 | 38.2% |
| ・・・ | ||
| 45位 | 島根県 | 20.1% |
| 46位 | 長崎県 | 19.6% |
| 47位 | 沖縄県 | 17.2% |
地震保険の加入率が低い3つの理由
「まさか自分の住んでいるところで大きな地震は起こらないだろう」や「うちは大丈夫」といった風に考えてしまいがちですよね。
地震保険は万が一の時に手助けの一部になります。実は世界で発生するマグニチュード6.0以上の地震のうち、20%が日本の周辺で起きています。
地震大国にすむ私たちは、今一度地震保険について真剣に考える必要があるのです。
そんな地震大国日本で、地震保険加入率が低い具体的な理由は、大きく分けて3つあります。
- 都道府県の地域によって地震保険料が割高な点
- 全壊、全焼した場合でも最大火災保険の半額しか補償されない点
- 補償対象が一部損以上でないと補償対象にならない点
保険金で地震により失った建物と同等の家を建て直すことはできません。これらの理由により地震保険の加入を消極的に思う方が少なくないようです。
① 地震保険の保険料が高い
| 都道府県 | 保険金額 |
|---|---|
| 千葉県、東京都、神奈川県、静岡県 | 27,500円 |
| 埼玉県 | 20,400円 |
| 徳島県、高知県 | 17,700円 |
| 宮城県、愛媛県 他 | 11,800円 |
| 京都府・北海道 他 | 7,400円 |
② 地震保険では十分な保険金がもらえない
| 建物 | 5,000万 |
|---|---|
| 家財 | 1,000万 |
③ 地震保険の補償のみでは生活の再建が出来ない
地震保険では、建物は5000万円、家財も1000万円までの補償なので、全てが補償されるわけではありません。
地震保険はさしあたり生活に困らないための補償と考えるのがいいでしょう。
財務省発表の地震保険制度の概要でも、地震保険とは『地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的』としているのです。
しかし、1から自分で再建するよりも、地震保険によってある程度の補償が受けることで、再建が後押しされるのも事実です。
日本に住んでいる以上、地震はいつ起こってもおかしくない物として考え、備えておくべきではないでしょうか。
地震保険の基礎知識
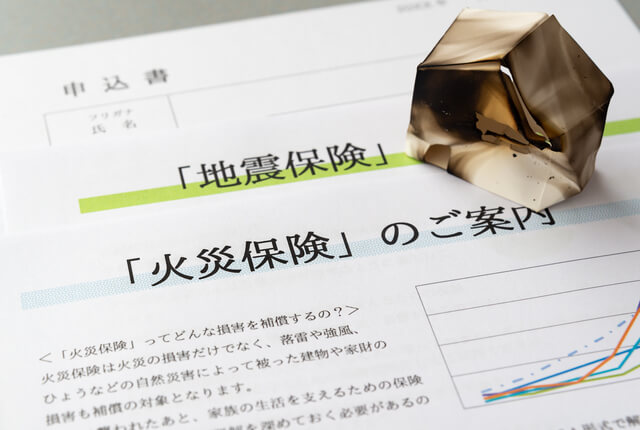
ここまで、地震保険の加入率と付帯率や、加入率が低い理由について解説してきました。
地震保険の加入傾向は、以下のようになっています。
- 世帯加入率は約30%と低い数値を推移しています
- 最近の地震保険付帯率は約3人に2人が契約しているので徐々に広まっています
- 都道府県の地域によって地震保険加入率に差があります
地震保険の3つの特徴
地震保険の特徴について紹介します。
- 火災保険に付帯して加入する必要があります
- 保険会社と政府が補償する仕組みになっています
- 同じ条件であれば、取扱保険会社によって地震保険の保険料に違いはありません
① 単独で地震保険だけの契約をすることはできません。
地震保険に加入するには、必ず火災保険の加入が必要となります。
② 地震保険は政府が保険会社の支払えない部分を補償するので、保険金が受け取れない心配をする必要がありません。
ただし地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき政府による再保険制度が導入されています。
1回の地震による保険金の総支払限度額が11.7兆円(2019年4月現在)と定められ、1回の地震等によって損害保険会社全社の支払うべき地震保険金総額がその額を超える場合、保険金は削減されることがあります。
③ 地震保険は、民間の損害保険会社と国が共同で運営しています。そのため、補償内容と保険料は各社同じ内容となっています。
ですが、耐火(=鉄筋コンクリート造など非木造)・非耐火(=木造)といった建物構造、免震耐震等の建物性能、築年数、建物所在地のある都道府県、一括払いか分割払いかといった支払い方法によって保険金額 保険料は変わります。
すでに火災保険を契約されている方は、契約の途中からでも地震保険に加入できます。
地震保険の補償対象は「建物」と「家財」
地震保険の補償対象は2つあります。
- 住居用に使用される「建物」(店舗併用住宅は可)
- 家具や家電製品などの生活用の動産「家財」
賃貸物件では建物の地震保険は所有者(貸主)がかけます。
そのため、賃貸物件の場合地震保険で補償されるのは「家財」となります。
また、地震保険の補償対象外になるケースがあります。
- 火災保険の対象が建物のみの場合の家財に損害
- 30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物などの美術品
- 自動車、住居用でない事務所や工場建物
- 建物に損害がなかった場合の門、塀、垣の損害
- 地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に発生した損害(状況により火災保険の対象になる可能性があります)
主に上記の条件ですが他にも地震保険の対象外になるケースがありますので、地震保険についてしっかり調べた上で万が一に備える準備が必要です。
地震保険の補償内容
| 分類 | 損傷の程度 | お支払い保険金 |
|---|---|---|
| 全損 | 建物の時価額の50%または延床面積が70%以上 | 保険金額の100% (時価額が限度となる) |
| 大半損 | 建物の時価額の40%以上50%未満 または延床面積が50%以上70%未満 | 保険金額の60% (時価額の60%が限度となる) |
| 小半損 | 建物の時価額の20%以上40%未満 または延床面積が20%以上50%未満 | 保険金額の30% (時価額の30%が限度となる) |
| 一部損 | 建物の時価額の3%以上20%未満 または床上浸水または地盤面から45㎝ | 保険金額の5% (時価額の5%が限度となる) |
地震保険の加入の必要性
火災保険と比較して、加入率や付帯率の低い地震保険ですが、特に加入が必要な人たちがいるのも事実です。
一度被害に遭うと失うものが多く、なにもかもを自分で再生することは極めて難しいのも地震災害の大きな特徴です。
そこで次は、地震保険の加入の必要性について解説します。
これを読んでいただき、改めて、自分が地震被害に遭遇したときは大丈夫かどうかを確認してください。
ちょっと不安かも、と感じるのであれば、地震保険の加入を検討すべきではないでしょうか。
公的支援制度だけでは地震で受けた損害を補填できない
日本は、世界的に見ても地震の発生数が多い地震大国です。
そんな日本の、地震で被害を受けた人に対する公的な支援制度はどんなものがあるのでしょうか。また、公的制度で地震の被害は100%カバーすることができるのでしょうか。
代表的な、地震に対する公的な支援制度は以下の2つです。
被災者生活再建支援制度…住宅が全壊するなどの大きな被害を受けた世帯に最大300万円の支援金が支給される
住宅の応急修理(災害救助法)…住宅が半壊し修理する資力がない世帯に対して、日常生活に必要な最小限度の部分を応急修理するために最大57.4万円の支援金が支給される
ご覧の通り、地震により大きな損害を受けた時の補填として考えるには十分な額とは言えません。
公的な補助制度のみをあてにすることはできないことがわかって頂けたと思います。
では、地震保険を付帯すべき人とはどんな人なのでしょうか。
地震保険を付帯すべき人
地震保険を付帯すべきなのは、以下のような人です。
- 地震被害による、自力再生が難しい
- 住宅ローンがある
- 新築を購入したて
- 地震などの災害リスクの高い地域に住んでいる
参考:マンションの地震保険の必要性
日本で今後30年以内に大地震が起きる確率

まとめ:地震保険の加入を検討して、いざという時に備えよう

地震保険の加入率や、地震保険の必要性などをご紹介いたしましたが、いかがでしたか。
この記事のポイントは、以下の3点でした。
- 地震保険の加入率は全体的に低め
- 被害の全額を補償されるわけではないが、当面の生活を支えたり、自力再生した人が再建するための補償としては有効
- ローンを抱えていたり、地震リスクの高い地域に住んでいる人たちは加入すべき
地震保険の加入率は決して高くありません。しかし、地震による被害は大きくなりやすいため、損害を受けてから後悔しても遅いのです。
住んでいる地域のことや生活状況を考えて、改めて地震保険の必要性を検討してみてはどうでしょうか。
「保険スクウェアbang」では、住んでいる地域の地震保険の必要性や保険の内容について保険アドバイザーが何度でも無料でご相談に乗ります。
無理な勧誘はございませんので、顧客満足度は94%とご評価いただいております。
自然災害の多発で2022年10月から保険料が値上がりします。今のうちに、最大26商品から比較可能の「保険スクウェアbang」をご検討ください。







