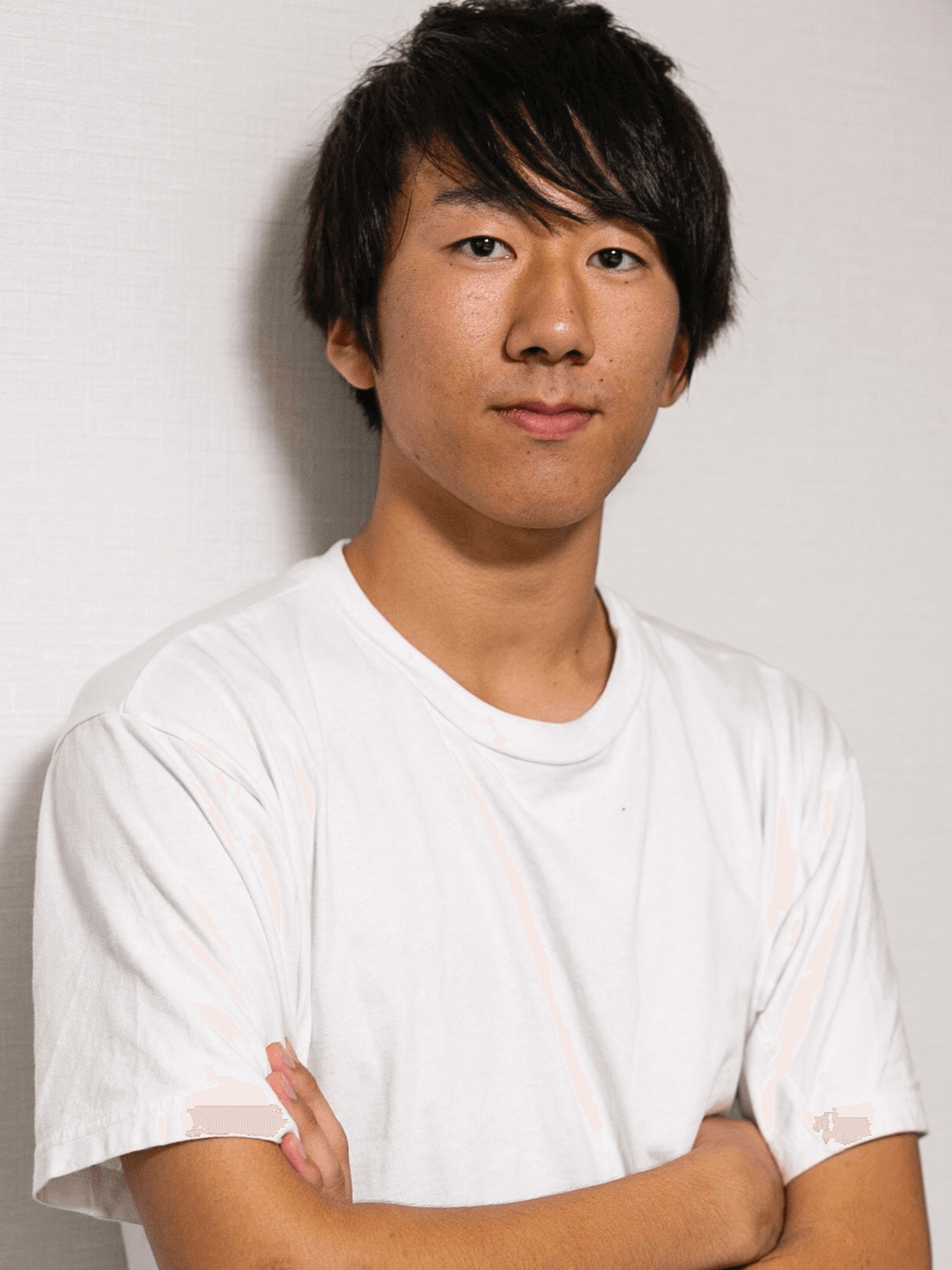更新日:2022/06/25
地震保険は単独で加入できる?仕組みとおすすめの制度を徹底解説!
地震大国の日本で重要な地震保険は基本的に単独では加入できず、火災保険とセットでの加入になります。この記事では、なぜ単独では加入できないのかについてと、単独で加入できる地震補償保険、そしておすすめの割引制度などを中心に解説します。

目次を使って気になるところから読みましょう!
地震保険は基本的に単独では加入できない
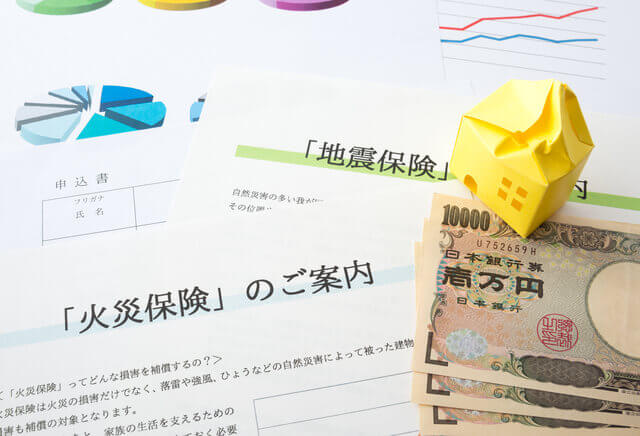
地震大国の日本において、地震保険は知っておくべき制度のひとつです。
地震保険は基本的に単独加入ができず、火災保険とセットでの加入になります。地震が多い国だからこそ、政府主導で加入方法や限度額に制限をかけているからです。
しかし実は、地震保険以外にも地震に備えられる制度が存在します。単独で加入することも可能な制度です。選択肢のひとつとして、理解しておきたい制度といえるでしょう。
そこで今回の記事では、以下の内容を中心に解説します。
- 地震保険にはなぜ単独で加入できないのか
- 地震保険以外の地震に備える制度
- 地震保険の保険料をおさえる方法
この記事を読んでいただければ、地震保険についてを理解し、適切な保険料で地震に備えることができるようになります。
ぜひ最後までご覧ください。
地震保険とは
地震保険とは、地震災害専用の保険のことです。
具体的には「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害を補償する」ものです。(参照:財務省「地震保険制度の概要」)
地震保険には以下のような特徴があります。
- 補償対象は居住用の建物と家財
- 単独での加入はできず、基本的に火災保険とのセット加入になる
- 保険金額の上限は火災保険金額の50%
火災保険では地震による損害が補償されないため、大きな損害に備えて加入を検討することをおすすめします。
地震保険にはなぜ単独で加入できないのか
地震保険は原則として火災保険とのセット加入になります。政府主導の保険で、セット加入についてが法律で定められているからです。
セット加入の仕組みはいずれの保険会社でも変わりません。補償内容が同じであれば保険料も共通です。地震が多い国における公共性の高い保険だといえるでしょう。
単独加入ができず、セット加入を推進している理由は以下のとおりです。
- 火災保険とセットにすることで、地震保険の加入率を高めるため
- 火災保険とセットにすることで、運用コストをおさえるため
- 地震と火災は連動することが多く、セット販売の親和性が高いため
地震補償保険 | 単独で加入できる地震保険
地震補償保険は、単独で加入できる地震保険です。
原則1年で更新となる少額短期保険で、保険金の上限は1,000万円となっています。
この保険に加入するメリットは以下の3点です。
- 火災保険に加入していなくても加入できる
- 損害額と関係なく保険金が支払われる
- 地震保険に上乗せすることができる
それぞれくわしく見ていきましょう。
メリット①火災保険に加入していなくても加入できる
地震補償保険の最大のメリットは単独で加入できることです。
火災保険に加入する必要がないので、自身が本当に必要とする補償のみを選ぶことができます。
ただし、地震補償保険は政府主導の保険ではないため地震保険料控除が受けられません。また、保険会社によっては地震保険とくらべて補償が限定的なことがあるので注意しましょう。
メリット②損害額と関係なく保険金が支払われる
地震補償保険は損害額と関係なく保険金が支払われます。
この点が、損害の程度に応じて保険金が支払われる地震保険との大きな違いです。建物の再建ではなく被災後の生活の再建のための保険ともいえます。
地震補償保険の保険金上限額は世帯人数によって変わる
地震補償保険の保険金は世帯人数によって上限額が変わります。
1人世帯であれば300万円、5人世帯であれば900万円を上限とするプランが主流です。
| 保険金上限 | 月々の保険料(目安) | |
|---|---|---|
| 1人世帯 | 300万円 | 1,000~2,000円 |
| 3人世帯 | 600万円 | 1,500~2,500円 |
| 5人世帯 | 900万円 | 2,000~3,000円 |
なお、地震補償保険の保険料は所在地と建築素材によって大きく変わります。
加入を検討する際は、まずは複数の保険会社に見積りを依頼してみましょう。
メリット③地震保険に上乗せすることができる
地震補償保険には、地震保険に上乗せして補償の不足分を補えるというメリットもあります。
地震保険の保険金は、火災保険の保険金の50%が上限です。ですから、地震保険だけでは建物や家財の実際の損害額に対して保険金が不足することも少なくありません。その不足分をおぎなうのが地震補償保険です。
また、地震保険の申請には現地調査が必要なので、保険会社によって基準が異なります。いっぽう地震補償保険は地方自治体による罹災証明書があれば申請できるので、基準が明確だといえるでしょう。
地震保険の保険料をおさえる2つの方法

地震保険の保険料は所在地と建物の構造によって決まります。
国と保険会社が共同で運営しているため、補償内容が同じであれば保険会社間で保険料に差はありません。
しかし、保険料をおさえる方法はあります。以下の2つです。
- 2~5年の長期契約にする
- 割引制度を利用する
2~5年の長期契約にする
地震保険は1年から5年までの契約ができ、2年以上の長期契約に対して割引がなされる仕組みになっています。
以下の表は、契約年数に応じてどれだけ割引されるかをまとめたものです。
| 期間 | 長期係数 |
|---|---|
| 2年 | 1.90 |
| 3年 | 2.80 |
| 4年 | 3.70 |
| 5年 | 4.60 |
(参照:財務省「地震保険制度の概要」)
1年の契約を更新して2回契約した場合、トータルの保険料は単純に1年の2倍になります。
いっぽう2年契約の場合の保険料は、1年の1.90倍です。5%割引になるということです。
5年契約がもっとも割引率が大きく、8%割引になります。
ただし、火災保険の契約内容によっては地震保険の長期契約ができない場合があるので、保険会社に確認してみましょう。
割引制度を利用する
地震保険の保険料には以下の4つの割引制度があります。
| 内容 | 割引率 | |
|---|---|---|
| 建築年割引 | 1981年6月1に以降に新築された建物 | 10% |
| 耐震等級割引 | 所定の耐震等級を有している建物 | 1級は10% 2級は30% 3級は50% |
| 免震建築物割引 | 所定の免震建築物 | 50% |
| 耐震診断割引 | 耐震診断または耐震改修の結果、 所定の耐震基準を満たす建物 | 10% |
耐震性や築年数など一定の条件を満たした建物に対して割引がなされる制度です。
耐震性のある建物は、そうでない建物にくらべて保険金を受け取る確率がさがるため、保険加入者間の公平性を保つためにこうした割引制度が作られています。
なお、割引制度は重複して利用できないことには注意が必要です。複数の条件に該当する場合は、割引率の高い制度を利用しましょう。
参考:火災保険とは
火災保険は火事による損害を補償する保険です。
以下の3つの加入パターンがあります。
- 建物のみを補償する
- 家財のみを補償する
- 建物と家財のどちらも補償する
- 台風や落雷などの自然災害による破損
- 洪水などの水災
- 排水管の破損などによる水濡れ
- 空き巣や自動車衝突などによる建物の破損
- 家具の移動中におきた壁の破損
まとめ:地震保険に加入するならまずは無料で見積り依頼を!
地震保険について解説してきましたが、いかがでしたか?
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
- 地震保険は基本的に単独では加入できず、火災保険とセット加入になる
- 地震補償保険であれば単独で加入できる
- 地震保険の保険料は長期契約や割引制度の利用でおさえられる
地震保険は単独では加入できないため、実際に加入を検討する際は火災保険や地震補償保険の比較が中心になります。
なお、保険料は上昇傾向にあり、2022年10月には大規模な値上げがなされる見込みです。ですから、加入と見直しはなるべく早めに検討しましょう。
下部のボタンから利用できる見積りサイトは顧客満足度94%で、最大26商品から比較できます。
保険アドバイザーに何度でも無料で相談が可能ですので、ぜひご活用ください。