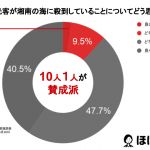マネー・ライフに関する疑問
最適な情報を伝える
マネー・ライフ

-

マネー・ライフ
最終更新日:2025/08/29
お金の相談をする場合、相談内容により相談窓口を選ぶ必要があります。家計全般、住宅ローン、保険に関する相談は、ファイナンシャルプランナーに相談...
-

投資・運用
最終更新日:2025/03/12
お子さんが小さいときから将来の蓄えとして子供用口座に貯金したい親御さんも多いのではないでしょうか。この記事では5つの銀行から金利・メリットと...
-

投資・運用
最終更新日:2025/01/30
ゆうちょ銀行の投資信託やつみたてNISAの評判について気になっている人もいるでしょう。中には騙されたとの評判もあり、これから投資信託や新NI...
-

投資・運用
最終更新日:2025/01/24
PayPay銀行とは2021年4月に誕生したネット銀行(旧ジャパンネット銀行)です。PayPayを使いながらよりおトクに投資を始めたい!そん...
-

投資・運用
最終更新日:2024/11/26
「新NISAで毎月いくら投資すれば得する?」「自分に合った積立額が知りたい」と思っているかたが多いです。実際、毎月積立額は平均60,689円...
-

貯金・節約
最終更新日:2024/11/20
2020年に政府が発表した家計調査によると4人家族の生活費平均額は約37万円です。この記事では、4人家族の1ヶ月の生活費の平均、子供の年齢と...
-

投資・運用
最終更新日:2024/11/11
新NISAは月1万では意味がないと言われることもありますが、実際に月1万円を利回り5%の20年間で積み立てると「約167万円の利益」がシミュ...
-

マネー・ライフ
最終更新日:2024/10/29
一人暮らしの食費を1ヶ月あたり1万円に抑えるための節約レシピや節約のコツを解説しました。食費を抑えるためには、毎日の自炊が基本となるので、安...
-

貯金・節約
最終更新日:2024/10/29
子供2人を育てるのに理想的な世帯年収がいくらかご存知ですか?子供2人の4人家族には、8世帯年収800万が必要だと言われています。ここでは子育...
-

投資・運用
最終更新日:2024/10/29
「新NISAで1,800万円を使い切ったその後、10年・20年後の資産はどれくらい?」と悩む方は多いです。実際、シミュレーションでは20年後...
-

投資・運用
最終更新日:2024/06/12
40代から新NISAを始めることで、資産形成にどのようなメリットがあるのか気になる方も多いのではないでしょうか。本記事では、新NISAの活用...
-

投資・運用
最終更新日:2024/05/11
海外赴任をする前にちょっと待って!多くの証券口座は海外赴任をすると凍結・解約されてしまいます。解約される原因、証券会社に海外赴任がばれる理由...
-

投資・運用
最終更新日:2024/04/04
夫婦で新NISAをつかうと様々なメリットがあり、将来の資産形成を夫婦で一緒に考えている方にとっては押さえておくべき記事になっています。注意点...
-

投資・運用
最終更新日:2024/04/04
「ろうきんの新NISA・投資信託の評判は良いの?デメリットは?」と思っている方も多いのではないでしょうか。この記事ではろうきんの評判、メリッ...
-

投資・運用
最終更新日:2024/03/28
「新NISAで毎月積立するのがむずかしくなってきた」「お金が浮いたのでさらに積立額を増やしたい」と考えている人も多いのではないでしょうか。積...
-

投資・運用
最終更新日:2023/12/19
積立NISAの利益はいつでも引き出し可能です。引き出し方法は銀行口座への振り込みや、専用ATMカードでの引き出し等があります。利益の引き出し...
-

貯金・節約
最終更新日:2022/10/04
小銭貯金がやっと貯まったら使い道に悩みますよね。欲しいものを買ったり、旅行に行ったり...使い道は様々です。そこで今回は小銭貯金をした人の貯...
-

マネー・ライフ
最終更新日:2022/01/15
65歳以上でも収入があると年金がもらえない、働くと満額もらえないと知ってますか?在職老齢年金により年収がある方は厚生年金が減額されるケースが...
-

貯金・節約
最終更新日:2021/02/23
究極の節約術とはなに?貯金が溜まる倹約術が知りたい!という方は多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、究極の節約術について解説します。...
-

貯金・節約
最終更新日:2020/11/20
結婚するとこれから何かとお金がかかってきますよね。新婚夫婦の二人暮らしに向けた無理なく楽しく節約できる方法を解説します。夫婦で協力すれば月1...
-

貯金・節約
最終更新日:2020/11/10
小銭貯金は手軽に誰でも続けることができる節約・貯金方法として有名ですよね。しかし、小銭が大量に貯まった貯金箱を銀行ATMなどで入金するのは迷...
-