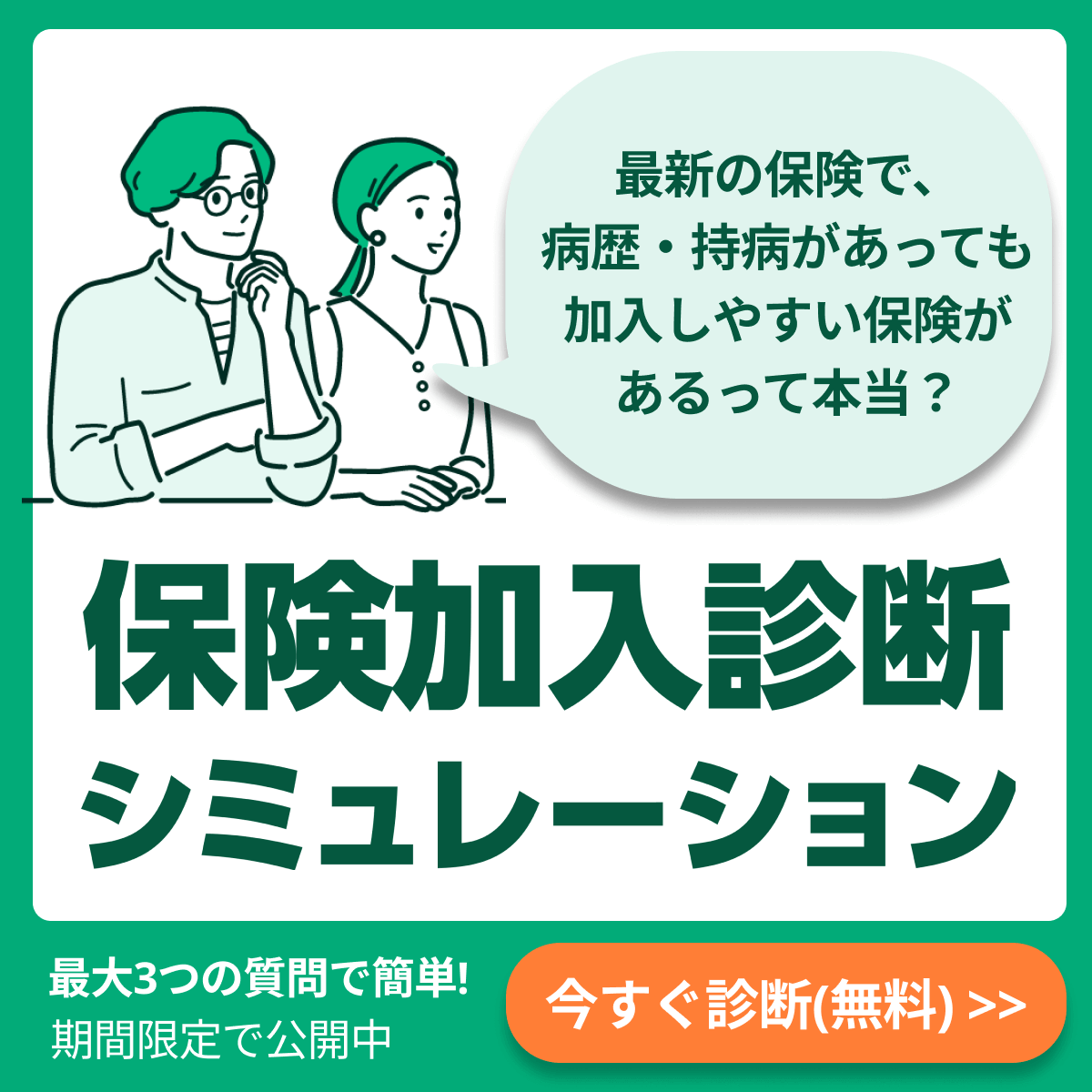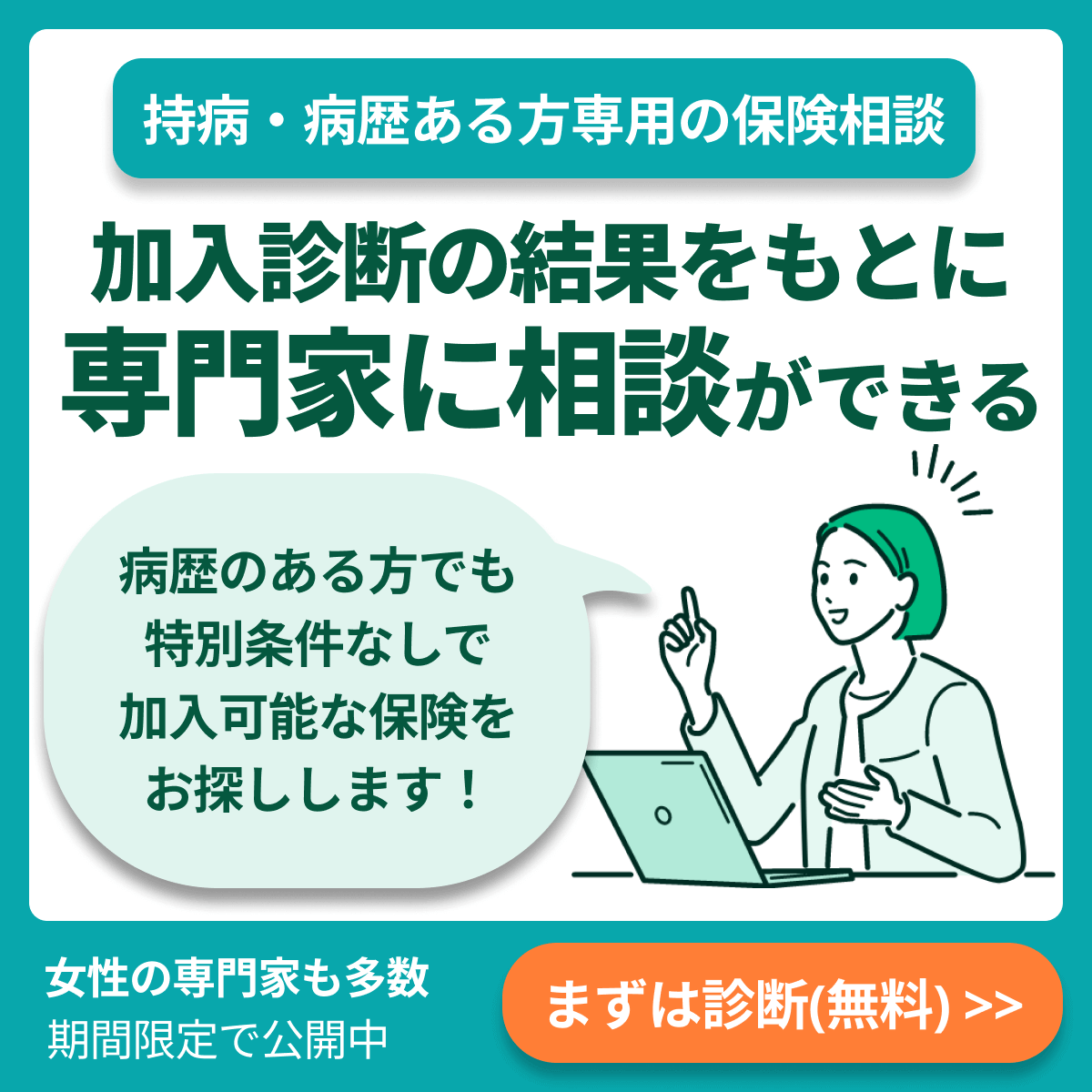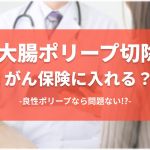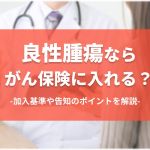更新日:2023/03/21
基底細胞癌はがん保険の対象外になっているのは本当?メラノーマなど皮膚がんの保険をプロが解説!
基底細胞癌は一般的にはがん保険の対象外となっていることが多いため基底細胞癌のがん保険に加入することが難しいケースが大半です。しかし、保険会社によって基底細胞癌のがん保険や特定の疾病保険に基底細胞癌が含まれているケースがあるため取扱保険会社数が多い保険代理店で相談することがおすすめです。
内容をまとめると
- 基底細胞癌は一般的には保障の対象外となっているケースが多い
- 保険会社によっては基底細胞癌のがん保険を取り扱っている場合がある
- 特定疾病保険で基底細胞癌が含まれている場合もある
- 基底細胞癌は加入できる保険や保障対象となる保険の条件が多いため保険商品の内容をよく理解している保険代理店で相談することがおすすめ!
- 基底細胞癌の保険でお悩みの方はがん保険専門のマネーキャリアの保険相談を有効活用しましょう!

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 基底細胞がんの保険についてがん保険のプロが解説します
- 基底細胞がんの保険適用とがん保険についてわかりやすく解説!
- 基底細胞がんが保障対象となるがん保険はあるのか
- 基底細胞がんでも保険加入できる?
- 基底細胞がんの保険適用と健康保険制度について
- 基底細胞がんの保険でお悩みの方はプロに相談がおすすめ!
- 皮膚がん(基底細胞がん、メラノーマ)だとがん保険は保障対象でないって本当?
- 基底細胞がんはがん保険の保障対象外なケースも多い!手術費用は?
- 基底細胞がんとは
- 基底細胞がんの原因
- 基底細胞がんの症状
- 基底細胞がんの治療や手術にかかる費用
- なぜ上皮内新生物はがん保険で保障されないのか
- かかりやすい3つの皮膚がんを紹介
- ①基底細胞がん
- ②有棘細胞がん
- ③悪性黒色腫(メラノーマ)
- 悪性黒色腫以外の皮膚がんはがん保険の対象外である事がある
- 皮膚がんの治療費は相対的に安い
- 重粒子線治療を使う場合もあるので先進医療特約をつけておこう
- 皮膚がんが保障外でないがん保険
- まとめ:皮膚がんはがん保険の対象外なのか
目次
基底細胞がんの保険についてがん保険のプロが解説します
初期のがんには上皮内がんというものがあり、最も罹患しやすいがんとして皮膚がんが存在します。
身体のどこにでも発症する可能性がある皮膚がんには、一番深い表皮の層にできる基底細胞や毛根を包む毛包細胞から発症する腫瘍である基底細胞がんがあり、転移する可能性は低く完治できる可能性は高いといえるのです。
しかし一度でも基底細胞がんと診断されたことがあるひとは、がん保険に加入する際は必ず告知しなければならず、告知することでがん保険に加入できないのではないかと不安になってしまいますよね。
初期に発見して適切な治療を受ければ再発のリスクは少なく『完治と診断された場合は告知しなくても良いのではないか』と考えてしまうひとも多いことでしょう。
またがん保険では、基底細胞がんは保障の対象外になってしまう可能性があることも事実で、初期のがんだと保障されないのではないかという不安を感じることも・・・
この記事では、がん保険のプロが基底細胞がんとがん保険の関係について、わかりやすく解説しています。
- 基底細胞がんになったら、がん保険には入れない?
- そもそも基底細胞がんってなに?
- 上皮内がんといわれる基底細胞がんは、本当にがん保険で保障されないの?
そのような疑問をお持ちのひとは、ぜひ最後までご覧ください。
基底細胞がんは誰でも罹患するリスクがあるため、これからがん保険に加入しやすいと思っているひとにとって、検討する際の参考になるはずです。
また基底細胞がんは保険加入にあたって医師からの治療を推奨された経験や入院歴によって加入できるかできないか大きく変わります。
加入診断も含め最適ながん保険を提案してもらいたい人は無料で加入診断をしてくれるマネーキャリアの保険相談を有効活用してみてください。
基底細胞がんの保険適用とがん保険についてわかりやすく解説!
がん保険なら、どのようながんでも保障されると思っているひとは多くいますが、実は保障されないがんもあるということはご存知でしょうか。
『がんと診断されたら一時金』
そのような保障内容をよく耳にしますが、加入しているがん保険の種類によっては基底細胞がんは保障の対象外となっていたり、給付金額が50%となっていることもしばしば見かけます。
基底細胞がんを保障しているかどうかは、がん保険を販売している保険会社によって異なり、統一化されていないので保障内容についてよく理解しておくことが重要となるのです。
比較的完治しやすい傾向にある基底細胞がんは、誰でも罹患するリスクを持っており、最初はほくろのようなものなので健康状態に関する告知の段階では保険会社が基底細胞がんを罹患する可能性を予測することは非常に困難となっています。
誰にでもリスクがあるということは、保険会社が保険金や給付金を支払わなければならない可能性が高くなり、肺がんや大腸がんなど一般的ながんと同様の保障を基底細胞がんを含む上皮内がんに対して支払うことは通常の保険料では難しくなるのです。
保険料が高くなると加入するひとの負担が大きくなるため、完治しやすく治療が一定期間で完了となる上皮内がんに対しては、がん保険の保障の対象外にしたり、通常の保障内容より給付を少なく設定したりしています。
基底細胞がんが保障対象となるがん保険はあるのか
基底細胞がんを含む上皮内がんは、保険会社の支払いリスクが高くなってしまうため、がん保険の保障対象外としている場合や保障内容を減額して設定されている場合があり保険会社や保険種類によって違いがあるのです。
- 上皮内がんは通常のがん診断給付金の10%
- 上皮内がんも通常のがんと同額のがん診断給付金
がん保険に加入したとき、がんと診断されたときに支払われる一時金を200万円で設定すると、基底細胞がんと診断されたときには10%の20万円や5%の10万円など減額して支払われるケースが一般的です。
なかには上皮内がんは給付金支払いの対象外となっている保険種類もあり、そのようながん保険に加入している場合は基底細胞がんと診断されても保障されません。
特に保険料が比較的安い更新タイプのがん保険は、上皮内がんは保障の対象外であったり、減額による給付であったりする傾向があります。
保険料が高い終身タイプのがん保険は、基底細胞がんを含む上皮内がんでも契約している一時金と同額が給付される傾向がありますが、更新タイプに比べて保障内容が手薄になっているケースもあるので注意が必要です。
ひと昔前のがん保険は上皮内がんは保障の対象外となっていたことが多く、以前から加入しているがん保険では、基底細胞がんに対する保障がないケースもあるので、よく確認しておかなければなりません。
新しいがん保険でも、特約を付加することで基底細胞がんなど上皮内がんに対する保障を持つことができる場合もあるので、保障内容には注意しておくようにしてくださいね。
基底細胞がんでも保険加入できる?
一度でもがんと診断されたことがあれば、加入時の告知で記入する必要があり保険会社の査定によって加入できるかどうかが決まります。
がん保険に加入できるのは、がんを罹患するリスクが少ないひとであり、がんに罹患したことがあるひとは再発や転移の可能性があるため一般的ながん保険に加入することは難しいといわれているのです。
そのため「基底細胞がんと診断されたから、もうがん保険に入ることはできない」と悩んでしまってはいないでしょうか。
基底細胞がんは完治する可能性が高く、一般的に転移や再発のリスクは少ないといわれているため『絶対にがん保険に加入できないのか』といえばそうではないのです。
基底細胞がんと診断され、治療中だったり手術の予定があったりするとがん保険に加入することはできません。
しかし基底細胞がんを完治してから一定期間が経過していて、その後の定期健診でも再発や転移などの指摘を受けていなければ、一般のがん保険に加入できる場合もあります。
完治してからの期間は保険会社や保険種類ごとに異なるため、がん保険Aでは加入できなかったけれどがん保険Bには加入できたというケースもあるのです。
- 基底細胞がんは完治してから一定期間が経過している
- 完治してから定期的に検査を受けている
- 完治後、転移や再発の指摘は受けていない
このような場合はがん保険に加入できる可能性は残されています。
一般のがん保険に加入できなかったとしても、引受基準緩和型や無告知型の保険を選択するという方法もあるので、基底細胞がんと診断されたことがあるからといってがん保険を諦める必要はないのです。
基底細胞がんの保険適用と健康保険制度について
日本は国民皆保険の制度によってすべての国民が健康保険や年金に加入することで、高額な医療費を負担することなく治療を受けられるようになっています。
現役世代は一般的に医療費の3割が自己負担となっており、自己負担額が一定の金額を上回ると高額療養費制度を利用して医療費の自己負担分を減額することが可能なのです。
企業に雇用されている会社員であれば、基底細胞がんを患い治療に専念するため働けなくなってしまったときには健康保険の傷病手当金制度を利用することで、給与の60%程度を最長1年6ヶ月間受給することができます。
年金制度ではがんにより障害を負ってしまった場合は障害年金を受給することができ、国民年金なら障害基礎年金、厚生年金なら障害厚生年金が上乗せとなるので、経済的な負担を軽減することができるようになります。
基底細胞がんと診断されても公的な社会保険制度を利用することで、治療費や生活費の負担を減らすことができるため、必ずしもすべてをがん保険でカバーする必要はないということなのです。
社会保険制度は収入に応じて受給できる金額にも違いがあり、加入している健康保険や年金の種類によっても保障内容に違いがあります。
がん保険に加入する際は、こうした公的な保障をよく理解しておくことが大切で不足する部分をがん保険で補うという考え方が理想ですが、そのためにはどんどん変化する社会保険制度について最新の情報を取り入れておかなければなりません。
代理店や保険会社に確認することもできますが、強く加入をすすめられることを不安に思うなら、お金にまつわる様々な相談が無料でできるマネーキャリアを利用してみると、詳しく教えてくれるのでおすすめですよ。
基底細胞がんの保険でお悩みの方はプロに相談がおすすめ!
がん保険によって基底細胞がんに対する保障内容には違いがあり、保障される保険がどれなのか悩んでしまいますよね。
- がん保険にはどれくらいの保障が必要なのか
- 基底細胞がんでも保障されるがん保険はどれなのか
こうした悩みがあるなら、保険の無料相談を利用することをおすすめします。
相談者の満足度が高く、無料で何度でもファイナンシャルプランナーに相談したいなら国内最大級の無料保険相談となっているマネーキャリアがおすすめです。
ファイナンシャルプランナーに相談することで、がん保険による保障内容だけでなく、公的保障も含めて相談者にとって必要な保障額をもとに、様々な保険から選別して必要ながん保険を教えてもらうことができます。
マネーキャリアでは、対面だけでなくオンライン相談も受け付けているため、都合の良いときに相談することができるので忙しいひとでも安心して利用することが可能です。
もしものときに備えるがん保険は、加入するまえに本当に必要な保障を確認しておかなければなりません。
納得できるまで何度でも相談できるマネーキャリアは利用が無料で、無理に加入をすすめられることはないので、必要がないと感じれば断ることもできるため女性でも安心して相談することができます。
がん保険に対する疑問や悩みがあれば、ぜひマネーキャリアに相談してみてはいかがでしょうか。
皮膚がん(基底細胞がん、メラノーマ)だとがん保険は保障対象でないって本当?

皮膚がんの一種である「基底細胞がん」や「メラノーマ」は、がん保険に加入しても保障されない、と認識されていることが多いですが、本当なのでしょうか。
まず大前提として、皮膚がんは
- 基底細胞がん
- 有棘細胞がん
- 悪性黒色腫(メラノーマ)
- パジェット病
基底細胞がんはがん保険の保障対象外なケースも多い!手術費用は?

なぜ基底細胞がんやメラノーマが、がん保険で保障されない場合があるのか理由を知りたいと思われる方は多いでしょう。
そこでまずは、
- 基底細胞がんとは
- 基底細胞がんの原因
- 基底細胞がんの症状
- 基底細胞がんの治療や手術にかかる費用
これらの解説から基底細胞がんについて詳しく知り、なぜがん保険で保障されないのかを考えてみましょう。
基底細胞がんとは
「基底細胞がん」とは皮膚がんの一種であり、皮膚構造のうち「基底層」からがんが発生する病気です。
ただし必ずしも基底層の細胞ががん化するわけではなく、あくまで基底細胞に似ているがん細胞が発生することから、基底細胞がんという命名となっています。
実は皮膚がんのなかでもっとも罹患する確率が高いのがこの「基底細胞がん」であり、国立がん研究センターによると皮膚がん患者全体の24%を占めています。
日本において皮膚がん自体の死亡率は低く、統計によると2018年の罹患者数が「12,391人」であるのに対し死者数が「848人」となっています。
基底細胞がんの原因
基底細胞がんの主な原因として挙げられるのは、簡単にいえば外で紫外線を浴び続けること、いわば「日光曝露」が原因とされています。
そのほかにも、放射線や火傷などが原因で発病することもあるため、原因を一つに絞ることはできません。
基底細胞がんの症状
基底細胞がんの症状として、一見するとホクロのような皮疹が、主に顔の皮膚表面に現れるというものがあります。
発症からしばらくすると、ホクロのように見えていた部分はかさぶたとなり、出血がみられることもあります。
ただし医者が見れば通常のホクロとは完全に異なるため、皮膚科を受診すればがんが見逃されることはまずありません。
検査は基本的に初回は触診および視診であり、多くの場合受診した時点で症状が顕著であるため皮膚がんであることが医者には分かる場合が多いですが、実際に罹患が確定するのは生検病理診断を行ってからです。
基底細胞がんはその症状によって、
- 結節型
- 表在型
- 湿潤型
- 斑状強皮症型
基底細胞がんの治療や手術にかかる費用
基底細胞がんの治療は、主に腫瘍部分を切除することにより行われますが、場合によっては、
- 放射線治療:患部への放射線の照射
- 化学治療:軟骨などの皮膚患部への塗布
- 凍結治療:液体窒素による細胞の凍結・破壊
- 光線力学的療法:化学治療との併用による細胞へのレーザー治療
- モース顕微鏡手術:切除部位をできるだけ少なくする特別な切除手術
- 顔などのリスクが高い部位に腫瘍ができており大きさが6ミリ以上
- 境界が不明瞭である
- 再発した、または放射線による治療歴がある
- 斑状強皮症型や湿潤型などの「組織型」である
なぜ上皮内新生物はがん保険で保障されないのか

がんはいわゆる「悪性新生物」と「上皮内新生物」に分類され、それは皮膚がんも同様です。
そして「上皮内新生物」はがん保険の保障対象外、または保障されるとしても悪性新生物よりも保障内容が薄い場合があります。
なぜ上皮内新生物は悪性新生物よりも保障されにくいのか、それは病気としての「リスクの低さ」が主な原因として挙げられます。
基本的に上皮内新生物は、がんが「上皮」で留まっている状態であり、転移や再発のリスクが低く、かかる治療費も悪性新生物のときより少ないため、必然的にがん保険での保障も少なくなります。
上皮内新生物への保障が基本保障に含まれているがん保険もありますが、別途特約を付帯する必要があるがん保険もあるため、悪性新生物だけでなく上皮内新生物診断時にも確実に保障を受けたいという方は、加入時に必ず保障の有無を確認しておきましょう。
かかりやすい3つの皮膚がんを紹介

皮膚がんにがん保険で備えた方が良いと実感するための根拠として、それぞれの皮膚がんの種類における違いについて理解しておくことは重要です。
そこで次からは、罹患しやすい皮膚がんについて、
- 基底細胞がん
- 有棘細胞がん
- 悪性黒色腫(メラノーマ)
①基底細胞がん
今回のメインテーマとなっている「基底細胞がん」は、もっとも罹患する割合が高い病気です。
すでに解説したとおり、皮膚構造のうち「基底細胞」ががん化するものであり、日光曝露ややけどが主な原因とされています。
基底細胞がんは再発率・死亡率ともに皮膚がんの中でもっとも低く、完治しやすいとされています。
②有棘細胞がん
「有棘細胞がん」は、皮膚構造のうち「有棘層」にがんが発生します。
基底細胞がんに次いで罹患する割合が高い皮膚がんであり、主な原因と考えられているのは日光曝露ですが、ほとんど日光に当たらない口の中などに発生することもあります。
代表的な初期症状として挙げられるのは「日光角化症」であり、皮膚の一部分がやけどを負ったようになったり、進行すると潰瘍状に肥大化し、臭いを放つようになることもあります。
基本的に皮膚がんは早期に腫瘤の切除ができれば完治する可能性が高いですが、有棘細胞がんの場合、発症からしばらく放置してしまったことによって腫瘤が肥大化していると、他の臓器に転移している可能性も高くなります。
もし転移した場合は切除だけで完治させることはできず、抗がん剤や放射線治療が必要になります。
有棘細胞がんは腫瘤の切除以外にも、必要に応じて凍結治療や光線科学的療法などを用います。
③悪性黒色腫(メラノーマ)
「悪性黒色腫(メラノーマ)」は、メラノサイトという色素細胞から生成されるメラニンという色素が、がん化したものです。
メラノーマは長時間の日光暴露だけでなく、産まれたときからあるホクロが原因となることもあるため、別名「ホクロがん」と呼ばれることもあります。
皮膚がんの中ではもっとも死亡率が高く、他の臓器に転移した場合、5年生存率は1割程度とされています。
ただし日本人の発症率自体はおよそ0.01%と、統計的にメラノーマの発症率・死亡率が高い白人と比べても発症する可能性はかなり低いです。
初期のメラノーマは一見普通のホクロとほとんど見分けが付きませんが、
- ホクロの色にムラがある、変色している
- 明らかに元々のホクロが大きくなっている(目安は6ミリ以上)
- ホクロが円形ではなく、外側が不規則な形になっている
- 30、40歳頃になってから急に新しいホクロができた
悪性黒色腫以外の皮膚がんはがん保険の対象外である事がある
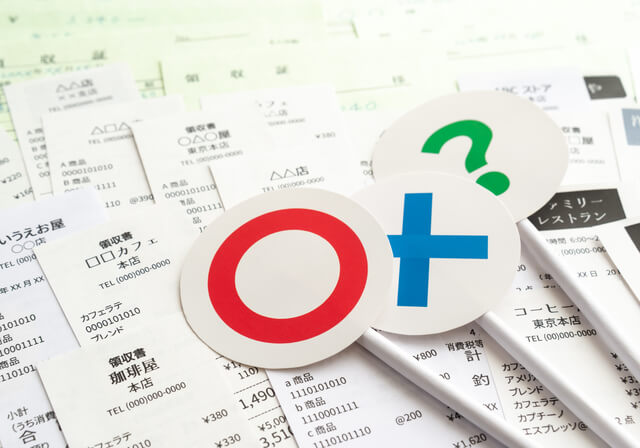
すでに冒頭で説明したとおり、悪性黒色腫(メラノーマ)以外のがんは、がん保険における保障の対象外となっている場合があります。
悪性黒色腫と比較してリスクが低い上皮内新生物が保障の対象外であることが多いのと同様に、基底細胞がんや有棘細胞がんもリスクが低いためです。
ただしすべてのがん保険でメラノーマ以外が対象外なのかというとそうではなく、ある保険会社では次のように定められています。
| 病名 | 保障の可否 | 理由 |
|---|---|---|
| 悪性黒色腫(メラノーマ) | ○ | |
| 上皮内黒色腫 若年性黒色腫 | ✕ | 上皮内新生物に包含されるため |
| 悪性リンパ種 | ○ | |
| 基底細胞腫 | ○ |
※保障の可否が「✕」となっている病気でも、特約を付帯することで保障を受けられる場合があります。
上記のがん保険では、メラノーマのほかに基底細胞がんも保障の対象となっていますが、「上皮内黒色腫」や「若年性黒色腫」は基本保障から外れています。
このように、悪性黒色腫以外の保障の可否に関しては、がん保険によって基準が異なります。
皮膚がんの治療費は相対的に安い

他のがんに比べると比較的にリスクが小さいものの放置すると命にかかわることもある皮膚がんですが、初期の段階であれば腫瘤部分を切除すれば十分完治が可能であり、他のがんと比べて治療費も安く済みます。
ある病院における皮膚がんの治療費(健康保険適用後・概算)は、
- 手術(外来):約4万円
- 入院:約10万円
重粒子線治療を使う場合もあるので先進医療特約をつけておこう
たいていのがん保険には、重粒子線治療などの健康保険が適用されず全額自己負担となる「先進医療」が必要になったときのために、「先進医療特約」が用意されています。
なぜこの特約が必要といえるのか、それは先進医療が必要となるリスク自体は低いものの、もし先進医療を選ばざるを得なくなったときの金銭的負担、リスクが非常に大きいからです。
先進医療特約は、「かかった技術料全額保障・通算2,000万円まで保障」のように設定されていることが多いことからも、通常の治療とは比較できないほど高額になる可能性があることが分かるでしょう。
大きなリスクに備えられる反面、先進医療特約が必要となるケースも少ないため、毎月の保険料に数百円するだけで、大きな金銭的リスクに備えることができます。
中には「先進医療自体、選択されることが少ないのだから加入しておく必要はない」と考える方もいるかもしれませんが、任意自動車保険などと同様に「万が一のときのリスクが非常に大きい」ため、実際多くの人が、がん保険加入時に先進医療特約を付帯しています。
皮膚がんが保障外でないがん保険
多くの方が抱かれる「がん保険で皮膚がんに備えることができるのか」という疑問に対しては、実際のところ現在販売されているほとんどのがん保険において皮膚がんは保障対象となっているため、確かに「備えられる」と回答できます。
しかし重要なのは、今回何度も解説しているようにがん保険それぞれで適用されるがんの種類、いわば保障範囲が大きく異なることです。
あるがん保険ではメラノーマ以外は保障されなかったり、また別の保険では上皮内新生物への保障も基本保障に含まれておらず特約が必要だったりと、保険ごとに異なる「条件」をきちんとチェックしておく必要があります。
また上皮内新生物が基本保障に含まれていても、「悪性新生物の50%」というように、保険金額に制限があることが多い点にも注意が必要です。
現在の皮膚がん治療においては、入院よりも通院治療を重視することが増えつつあることも考え、皮膚がん治療で入院が必要となるリスクがどれくらいなのか、また支払う保険料での負増やしててまで入院保障を充実させる必要があるのか、という点なども慎重に考える必要があります。
まとめ:皮膚がんはがん保険の対象外なのか

今回は基底細胞がんや悪性黒色腫(メラノーマ)といった皮膚がんが、がん保険の対象になるかどうか、という点をさまざまな角度から解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
皮膚がんは他のがんよりもリスクが少ないとはいえ、もし罹患したら確実に治療が必要であり治療費もかかるため、自己負担分を賄えるがん保険に加入しておくことは確かにメリットがあります。
もちろんがん保険は皮膚がんだけでなく胃がんや大腸がん、肺がんや肝臓がんなど、リスクが高いがんの治療費にも備えることができるため、この機会にがん保険への加入について、真剣に考えてみてはいかがでしょうか。
ほけんROOMではこの記事以外にも、役に立つ様々な記事を掲載していますので、ぜひそちらもご覧ください。