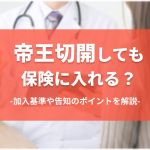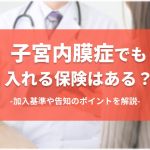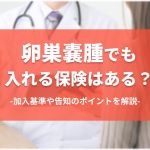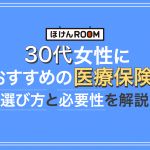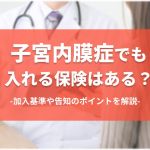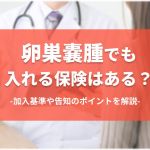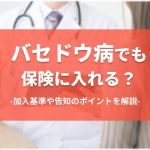【20~40代】おすすめの女性保険!口コミ・ランキングと貯蓄型の必要性
女性保険のランキングを口コミで比較していきます。女性保険も年々増えており商品も多彩になってきました。そこで保障内容の概要とともに実際に加入している人の声を検証することでどの保険がおすすめなのか紹介します。選び方や利点と欠点も紹介していますのでぜひご覧ください。
- 女性保険の口コミランキングを知りたい人
- 医療保険を検討している女性
- 女性保険の選び方や特徴を知りたい人
- 女性保険の口コミランキング
- 女性保険の基礎知識
- 保険を選ぶ際のポイント
- 女性保険のメリットとデメリット
内容をまとめると
- 女性保険は女性特有の疾患に対し通常の医療保険よりも手厚い保障がある
- 選び方のポイント①保障対象や支払限度日数等は各保険会社によって異なるため事前チェックを
- 選び方のポイント②保険料は入院給付金が10,000円あると安心
- 選び方のポイント③保険会社の対応は口コミでチェック
- 選び方のポイント④元気なうちに加入を検討する、またライフスタイルが変化する際には見直しを
- メリットは「女性疾患に対しての保障が割安」「経済的な不安をなくし治療に専念できる」
- デメリットは「妊娠中の加入が難しい」「貯蓄性のあるものはない」
- 保険選びに迷ったらマネーキャリアでプロに無料相談を!

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 女性保険ってどんな商品?女性保険の基礎知識を解説!
- 主な保障内容
- 女性特有の病気リスク
- 医療保険と女性保険の違い
- 女性保険の必要性|治療が長期化したら大金が必要になる
- 女性保険を選ぶ4つのポイント|ゼッタイ損したくない女性必見!
- ①保障内容(手術給付金・入院給付金の条件)
- ②保険料・払込期間
- ③保険金を請求したときの対応
- ④加入条件・タイミング
- 【年代別】20〜50代におすすめの女性保険の選び方を解説!
- 20代女性:帝王切開などの妊娠・出産の負担に備える
- 30代〜50代女性:女性特有がんに万全の対策をする
- 【独身・主婦・子持ち別】おすすめの女性保険の選び方を解説!
- 独身女性:治療が長期化した場合に備える
- 専業主婦:最低限の日額保障で十分!|20〜40代主婦必見!
- 主夫・子持ち女性:手厚い日額保障の女性保険に加入
- 女性保険の良い口コミを紹介!
- 良い口コミ①「乳がんの治療費にコスパ良く備えられる!」
- 良い口コミ②「乳がんの罹患リスクに手厚い保障があって安心!」
- 女性保険の悪い口コミを紹介!
- 悪い口コミ①「他の病気の保障は無いの!?」
- 悪い口コミ②「保障内容のアレンジがしづらい!」
- 【参考】女性保険の2つのメリットをプロが解説!
- メリット①女性特有の病気への保障が割安
- メリット②経済的な不安を無くして治療に専念できる
- 女性保険の2つのデメリット「妊娠中だと入れない保険が多い」
- デメリット①妊娠中だと入れない保険が多い
- デメリット②貯蓄型の商品がない
- まとめ:自分に今必要な保障に迷ったらまずは保険のプロに相談を!
女性保険ってどんな商品?女性保険の基礎知識を解説!

女性保険とは、女性特有の病気に対して手厚い保障がついているものを指します。 帝王切開・子宮頸がんなどの女性特有の手術や病気が対象です。ただし保険会社によって対象の範囲は異なりますので事前に範囲を確認しておくことをおすすめします。
また死亡保障やお祝い金などがある場合もあるため、自分に必要な保障があるものを検討しましょう。
厚生労働省の患者調査によると女性の受療率は人口10万人に対して
| 年代 | 入院 (人数) | 外来 (人数) |
|---|---|---|
| 20代 | 469人 | 6311人 |
| 30代 | 731人 | 8311人 |
| 40代 | 650人 | 8582人 |
| 50代 | 1103人 | 11165人 |
| 60代 | 1878人 | 15149人 |
となっています。 入院については30代は妊娠、出産のための入院が多いため40代よりも受療率が高くなっています。
どちらにも言えることは40代から50代の境目になると受療率がぐっとあがってくるということです。女性特有の病気も同じように増加します。 入院や出産、年齢があがるにつれての疾患リスクに備え女性保険は検討しておくと安心です。
主な保障内容
女性保険の基礎知識についてこちらの項目では
- 主な保障内容
- 女性特有のリスク
- 医療保険との相違点
について概評します。 保障内容や医療保険との違いを知っておくことで今後保険を検討する際に役立つことでしょう。
また保険相談窓口などプロに相談する場合であっても知識を頭に入れておくことで、ただ言われるままになるだけでなく自分の意見もしっかりもてるはずです。
女性の疾患に備えるには女性保険の他に医療保険に女性疾患特約を付けることでカバーが可能です。こちらについては女性特有の疾病を保険で備える必要性とは!女性疾病特約は本当に必要?の記事をご覧ください。
女性特有の病気リスク
女性特有の病気としては
- 子宮がん
- 乳がん
- 卵巣機能障害 乳房の障害
- 卵巣機能障害 妊娠の合併症
- 分娩の合併症 産褥の合併症
- 子宮頚部の異形成
- 月経異常
- 流産
| 部位 | |
|---|---|
| 1位 | 乳がん |
| 2位 | 大腸 |
| 3位 | 肺 |
| 4位 | 胃 |
| 5位 | 子宮がん |
医療保険と女性保険の違い
医療保険と女性保険の違いは形式上はありません。医療保険に比べて女性特有の疾患リスクに手厚く対応しているのが女性保険なのです。
主に入院した際の日額が一般の病気で入院した場合に比べ上乗せ額が3000円~5000円になるものが多いうえに、入院保障日数も長い傾向にあります。 また女性特有の手術の場合も普通の医療保険に比べれば給付金が多くでるものが一般的です。
医療保険にも女性疾患特約を選択できる商品があるので、一般的な疾患も手厚く、なおかつ女性特有の疾患もしっかり準備したいという方は特約での付属も1つの手です。
女性保険の必要性|治療が長期化したら大金が必要になる
治療が長引き働けない期間がそれ以上長期化すると、治療費の負担が重くのしかかってきます。「長期入院することになっても、高額療養費制度や傷病手当金があるんじゃない?」と思った方も多いでしょう。
上記の公的医療保険の2つの制度というのは、以下のようなものです。
| 高額療養費制度 | 傷病手当金 |
|---|---|
| ひと月あたりの医療費の上限を超えた部分は 払い戻しを受けることができる | 病気やケガで働けなくなった場合に およそ給料の3分の2の手当金が支給される |
高額療養費制度を利用すれば、一般的な年収(約370万円~約770万円)の方であれば、1ヶ月に支払う標準医療費は8万円程度が上限となります。
しかし、高額療養費制度の対象となる費用は、保険適用の医療費に限定されています。したがって、 入院中の以下のような費用については、高額療養費制度の対象外となります。
- 差額ベッド代
- 食事代
- 日用品費
上記の高額療養費制度の対象外となる費用が1日に5,000円程度かかった場合には、
5,000円 × 30日 + 8万円程度(高額療養費制度の上限額) = 23万円
となり、1ヶ月の入院でおよそ25万円程度かかることが想定されます。これが数ヶ月、数年となると、かなりの大きな金額の負担となってしまうのです。
また、傷病手当金が受け取れる期間は最長で一年半までと決まっているので、それ以上の長期の入院となる場合の費用についても想定しておくことが必要です。
女性保険を選ぶ4つのポイント|ゼッタイ損したくない女性必見!

損をしないための女性保険の選び方を紹介します。
注目してほしいポイントとしては
- 保障内容
- 保険料・払込期間
- 保険金を請求したときの対応
- 加入条件・タイミング
の4つがあります。 保障内容や月々の支払額についてはもちろんのこと、困った時の対応や給付金の支払いがスムーズだったかも調べておきたい項目です。 いくら安い保険料だったとしても対応が良くなければ満足度は下がってしまいますよね。
また加入の条件やタイミングについても覚えておくと見直し等に役立つためチェックしておきましょう。
①保障内容(手術給付金・入院給付金の条件)
保障内容は以下のポイントをしっかり確認しましょう。
- 入院給付金・手術給付金条件
- 支払限度日数
- 健康祝い金の有無
入院給付金・手術給付金の条件
女性のがん罹患率では乳がんが1番多くなっています。乳がんになった際かかる費用の中に乳房再建手術がありますが、保険によっては対象外になっているものもあります。
またがんと診断された時に一時金がでるのか、保障に上乗せがあるだけなのか、取扱い保険会社によって異なります。思わぬ病気になった際に、「保障がでると思っていたのにでなかった!」とならないようにするためにも事前チェックはきちんとしておきましょう。
支払限度日数
妊娠・出産を予定している女性は入院時の支払限度日数も重要です。 厚生労働省によると日本の帝王切開率は20%を超え30年前と比べると3倍になっています。今後も増加傾向にあるようです。 2割の人が経験する帝王切開は医療保険によってカバーできます。
帝王切開での入院日数は短くて6日、状況によっては2週間以上かかる場合もありますので、支払限度日数は余裕をもって30日はあるものを選びましょう。
健康祝い金
健康祝い金があるかもチェックしましょう。 健康祝い金は加入後一定期間たてば条件によってお祝い金がもらえるというものです。 お祝い金がある分保険料は少し割高になる可能性がありますが、定期的にお祝い金があるのは思いのほか嬉しいものです。
②保険料・払込期間
保険料についてはまず令和元年度生活保障に関する調査の1日の自己負担額平均をみていきましょう。
| 1日の自己負担額 | 割合 |
|---|---|
| 5,000円未満 | 10.6% |
| 5 ,000~7,000円未満 | 7.6% |
| 7,000~10,000円未満 | 11.1% |
| 10,000~15,000円未満 | 24.2% |
| 15,000~20,000円未満 | 9% |
| 20,000~30,000円未満 | 12.8% |
| 30,000~40,000円未満 | 8.7% |
| 40,000円以上 | 16% |
1日の平均は23,300円となっています。10,000~15,000円までの割合が一番高いですが、2番目が40,000円以上なことにも注目しましょう。
医療費自体は公的保証がありますが、差額ベッド代や消耗品費はすべて自己負担です。高額に設定すると保険料が高くなってしまいますが、入院保障額は1日につき10,000円は欲しい所です。
振込期間は終身医療保険であれば「終身払い」もしくは「短期払い」、定期医療保険であれば「保険期間と払込期間が同一」が一般的です。
終身医療保険を選ぶ際に、終身払いと定期払いのどちらを選ぶと良いのかは医療保険は短期払いと終身払いどっちがいい?払込期間の選び方を解説をご参考ください。
③保険金を請求したときの対応
保険金を請求した時の対応も口コミなどで確認しておくと安心です。 保険金を請求するのは自分が病気やけがをした時です。そんな時に相手の対応が悪かったらいくら良い保険でも精神的にがっかりしてしまいますよね。
またできるだけ早く給付金が必要なのになんなかスムーズに手続きがすすまないということがあれば保険会社に対しての信用も落ちるでしょう。 口コミ以外では一度保険内容の確認のため電話をしてみると雰囲気をつかむことができますよ。
④加入条件・タイミング
女性保険の加入条件としては
- 早産・流産・帝王切開の経験
- 不妊治療をしている
- 睡眠薬、精神安定剤等を服用している
- 無職・危険を伴う職業従事者
の場合には加入ができない、または加入できても条件が伴う場合があります。 そのため加入のタイミングの大前提として「健康なうち」がポイントとなります。健康なうちに加入をする場合、保険の選択肢が広がるだけでなく商品によっては保険料が割安になる場合もあるというメリットがあります。
また、以下のような場合が保険の加入や見直しをすべきタイミングです。
- 就職
- 結婚
- 出産・妊娠
- 老後への備え
自分のライフスタイルが大きく変わる際には必要な保障もかわります。転換期には必ず保険の確認を行いましょう。
【年代別】20〜50代におすすめの女性保険の選び方を解説!
それでは今度は年代別におすすめの女性保険の選び方を紹介していきます。
年代ごとに注意したい女性疾病は異なってきますので、それぞれの年代がよりリスクの高い女性疾病に備えておきましょう。まとめると、以下の通りです。
- 20代女性:「帝王切開など妊娠・出産への備え 」
- 30代〜50代女性:「乳がん・子宮がんなどへ万全の備え」
ではくわしく確認していきましょう。
20代女性:帝王切開などの妊娠・出産の負担に備える
20代の女性であれば、女性特有の病気に関わらず、病気への罹患率は比較的低いです。しかし、若い女性ならではのリスクとなるのが、妊娠・出産の際に起きるトラブルや病気です。
妊娠中の保障対象となるもの
妊娠中に起こりうるトラブルには、次のようなものがあります。
| 疾患 | 症状 |
|---|---|
| 重度のつわり | 食事や水分が摂れないほどのひどいつわり |
| 切迫流産・切迫早産 | 食事とトイレ以外は横になって自宅で安静に過す必要がある |
| 子宮外妊娠 | 受精卵が子宮以外に着床しており、薬物療法や手術が必要 |
帝王切開のリスク
帝王切開による出産を経験する人は近年増えています。
厚生労働省によると、およそ5人に1人が帝王切開による分娩を経験しています。
(参照:平成 29 年(2017) 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況 )
増えた要因としては
- 医療技術の進歩により帝王切開の手術がされやすくなった
- 晩婚化や不妊治療で35歳以上の高齢出産が増えた
などの理由があります。帝王切開の出産となった場合の入院期間は7日〜10日程度で、自然分娩の場合と比べ1日〜3日程度長くなります。ただし、入院がそこまで長期となるわけではないので、診断一時金や手術一時金を少し多めに設定しておき、入院給付金は日額3,000円程度にしておくのがおすすめです。
切迫早産のリスク
仮に切迫早産となり入院するよう医師から指示を受けた場合には、入院期間は2,3か月に及ぶ可能性があります。
切迫早産の状態になる確率は、妊娠中の女性の約15%です。そのうち実際に早産に至る確率は、約5%とされています。
では切迫早産になりやすい人にはどのような特徴があるのでしょうか。
- 子宮に何らかの病気がある
- 感染症にかかっている
- 喫煙者
腹部に強い衝撃を受けた場合
上記のような理由で切迫早産になるリスクが高まるといわれています。このような理由に当てはまりそうな人や、切迫早産になった場合に備えておきたい人は、入院給付金日額の保障を優先して手厚くしましょう。 具体的には、日額1万円程度に設定し、その分診断一時金や手術一時金は保障を少なくすることをおすすめします。
30代〜50代女性:女性特有がんに万全の対策をする
30代〜40代の女性は、乳がんや子宮がんなど女性特有のがんにしっかりと備えましょう。前述の通り、特に40代からは乳がんの罹患率が急激に増えます。65歳〜70歳くらいの患者がもっとも多く、もっと高齢になってからかかる人もいます。
日本乳癌学会事務局の「患者さんのための乳癌診療ガイドライン2019年版」によると、妊娠・出産を経験していない女性は発症するリスクが2.2倍ほど高いいと言われています。1970年代から世界中で非常に多くの研究が行われており、出産経験と乳がん発症の関連は強いです。
また、がんの治療は他の病気の治療と比べて長期化しやすい特徴があります。入院・手術をして、退院してからも、通院による治療や経過観察があり、治療期間は数年に及ぶことは少なくありません。こうした理由からがん保険や女性保険などを併用することでしっかりと備えておくことをおすすめします。
がん保険の場合は給付金の支払い日数が無制限となっている商品も多く、保障は手厚いです。女性保険でも併せて備えておくことで、がんの場合にはさらに手厚い保障となりますし、がん以外の女性疾病もしっかりカバーできるのでおすすめです。
がん保険と女性保険の両方で備える場合は、それぞれの給付金日額を3,000円〜5,000円程度にしておくことで、保険のかけ過ぎを防ぎながらもしっかりとした保障を得ることができます。
【独身・主婦・子持ち別】おすすめの女性保険の選び方を解説!

ここまでは女性保険の概要について説明してきました。 本章では世帯別の最適な女性保険の選び方について紹介していきます。
- 独身女性:「日額5,000程度 + 就業不能保険・介護保険など 」
- 専業主婦:「日額3,000円程度 + 一時金は多めに設定 」
- 主夫・子持ち女性:「日額1万円程度 + 生命保険 」
の3パターンに分けて、それぞれくわしく解説します。
独身女性:治療が長期化した場合に備える
治療が長期化した場合のリスク
独先ほど入院が長期化した場合、1カ月あたり25万円程度かかると説明しました。
独身の方であれば、子持ちの方などと比べて、日々の生活費の負担はそこまで大きくはないはずです。したがって逸失収入の負担の大部分を傷病手当金で補えるはずですので、治療費を補うには、入院給付金を日額5,000円程度に設定しておけば大丈夫です。
治療が数年かかる場合にも備える|就業不能保険・介護保険
特に独身である場合は、夫や子どもに金銭的な支援や介護を頼むことができません。治療が数年以上長期化したり要介護状態となるようなケースでは、上記の計算のようにかなりの負担となってしまいます。
貯金で全てまかなうのには限界があります。
女性保険だけでなく、就業不能保険や介護保険などを併用するのも良い方法です。
将来の自分が困らないように、もしもの場合にに備えておくことが大切でしょう。
専業主婦:最低限の日額保障で十分!|20〜40代主婦必見!
給付金日額は最低限の保障
専業主婦の女性の場合は、あまり大きい保障は必要ありません。病気やケガで働けなくなったときに本来なら得られたはずの収入のことを、逸失収入といいます。 専業主婦の方は逸失収入についてはあまり考慮しなくても良いため、最低限の保障があれば十分である可能性が高いです。
しかし、長期の治療となった場合には、次の費用に注意が必要です。
- 家事代行サービスなどの利用費
- スーパーのお惣菜などの中食や外食が増えることでによる食費の負担
- 子どもが小さい場合のベビーシッター代
それらを考慮しても、入院給付金は日額3,000円程度で良いでしょう。
女性疾病への備え
ただし、女性特有の病気への備えはやはりあった方が安心です。 乳がんなど女性特有のがんでは、前述の通り治療費が高額になりやすいです。
入院期間はそれほど長くなくても、手術の費用や術後の通院治療などで費用負担が生じます。
入院給付金日額の保障を抑えた代わりに、診断一時金や手術一時金などを少し高めの金額に設定しておくと安心でしょう。
主夫・子持ち女性:手厚い日額保障の女性保険に加入
稼ぎ頭の女性は逸失収入への備えが重要|日額金を手厚く
家庭の収入を担っている女性の場合は、逸失収入の負担に一番備えたいところです。特に治療が長期化した場合、逸失収入の負担は非常に大きくなります。
日々の生活費だけでなく、治療費の自己負担部分についても出費となるため、貯金が十分になければ非常に厳しい状況となるでしょう。したがって入院給付金は日額1万円程度と手厚くしておくことをおすすめします。
前述したひと月にかかる25万円程度の負担も、日額1万円あれば支払いに余裕をもてます。
日額の保障を高くする代わりに、診断一時金や手術一時金などはそこまで高く設定しておかなくても大丈夫です。 保障のバランスをみて、保険料負担が上がりすぎないように必要な保障のみ選択しましょう。
万一の場合にも備えておくと安心|生命保険
さらに、稼ぎ頭である女性の場合には、やはり万一のときの遺された家族のことを考えておかなければなりません。 自分に万一のことがあれば、遺された家族が生活できなくなってしまったり、子どもの教育が望むところに進まなかったりする可能性が生じます。
そこで、死亡保障付きの医療保険や、もしくは医療保険と生命保険を併用し死亡保障をプラスするのがおすすめです。
女性保険の良い口コミを紹介!
前の章では女性保険の仕組みについて解説しましたが、本章では実際に女性保険が必要なのかを商品を検討している人や購入者の口コミを紹介していきます。具体的には以下のような
- 乳がんの治療費
- 乳がんへの罹患リスク
良い口コミ①「乳がんの治療費にコスパ良く備えられる!」
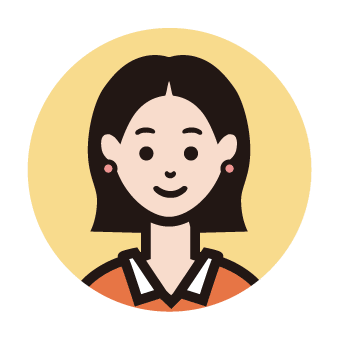
30代女性
「女性特有の病気で一番心配なのは乳がん。乳がんになったら結構治療費がかかるって聞くけど、月数千円の保険料で乳がんに備えられるのはすごいコスパ良いと思う!」
【編集者によるコメント】
乳がんの治療費については、手術や検査の種類、入院期間、治療を受ける施設によって様々ですので一概には言えませんが、一般的には、治療を始めてから1年間で150万円程度(健康保険適用による3割負担の金額)かかるとも言われています。
- 手術前後の抗がん剤・ホルモン療法
- 切除手術と1週間程度の入院
- 5日間×5週間程度の通院による放射線治療
- 乳房再建術
などの治療を行なった場合の一例です。
術後の治療が数年に渡って続く場合もあります。 また抗がん剤治療よってウィッグが必要となったり、乳がん治療用の下着が必要になったりと、何かとお金がかかります。
女性特有の病気に対してしっかりとした保障をつけたい場合、一般の医療保険だとそれだけに特化して保障を増やすことができず全体的に保障が手厚くなるため、その分保険料が高くなってしまいます。
その点、女性保険の場合は女性特有の病気に手厚く備えるような保障内容となっているため、無駄なく必要なところだけ保障を手厚くすることができます。
一般の医療保険で同じように備える場合と比べると、保険料は割安であると言えます。
良い口コミ②「乳がんの罹患リスクに手厚い保障があって安心!」

40代女性
「女性は40代になると、乳がんや子宮がんにかかるリスクが高くなるんですよね。女性特有のがんに手厚い保障があるのはものすごく安心です!」
【編集者によるコメント】
女性が一番多くかかるのが乳がんです。
乳がんの罹患率は20代後半から徐々に増え始め、45歳以降あたりから急激に増えていきます。
65歳〜70歳くらいの患者が最も多く、もっと高齢になってからかかる可能性もあります。
乳がんは、女性ホルモン(エストロゲン)の刺激を受けて乳腺の細胞ががん化することで起きます。
乳がんは閉経後でも発生する可能性があり、高齢者の罹患率も比較的高いです。
罹患率は年々増えている傾向にあります。
女性の社会進出が進み、妊娠・出産を経験しない女性が増えていることが理由のひとつであると考えられています。
(参照: 乳房:[国立がん研究センター がん統計] - がん情報サービス)
ですので、女性特有のがんに対する備えは非常に重要であることがわかります。
がん保険に加入していない方にとっては、女性保険は乳がんへの保障を手厚くできるのでお勧めです。
がん保険に入っていたとしても、がん以外の女性特有の病気にしっかりと備えられるのはやはり女性保険なので、女性疾病全体をカバーしたい人は検討してみましょう。
女性保険の悪い口コミを紹介!
当然どのような商品にも良い口コミだけではなく、悪い口コミがあります。本章では
- 女性疾病以外の病気の保障
- 保障内容の豊富さ
悪い口コミ①「他の病気の保障は無いの!?」
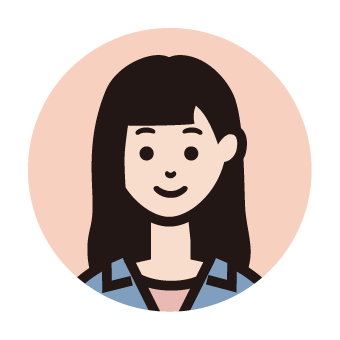
20代女性
「女性保険は女性特有の病気に備えるものでしょ?それ以外の病気が保障されないのが不満!」
【編集者によるコメント】
女性保険は「女性」とついているので、女性特有の病気だけを保障するものと誤解されがちですが、一般的な病気やケガへの保障ももちろんあります。
女性特有の病気の場合に、一般的な病気で支払われる給付金より上乗せされた給付金を受け取ることができるというものです。
仮に「一般的な病気やケガでの保障も手厚くしたい」ということであれば、通常の医療保険の給付金日額を多く設定するなど、保障内容を見直してみましょう。
悪い口コミ②「保障内容のアレンジがしづらい!」
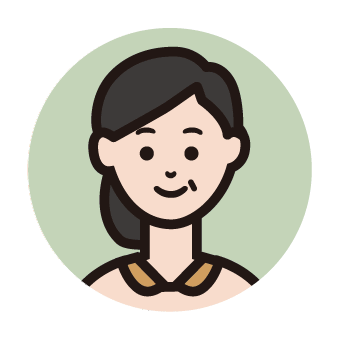
50代女性
「どの女性保険の商品もフルパッケージなものが多い。保障内容を自分に合わせてアレンジできたら良いのに!」
【編集者によるコメント】
女性保険の保障対象となる女性特有の病気で、不要なものを除くということは残念ながら難しい場合がほとんどでしょう。
例えば高齢の女性が、「出産などでの合併症についての保障は必要ない」と思ったとしても、保障を除いてその分保険料を安くするといったことはできません。
そういう意味では「保障内容を自分に合わせてアレンジする」ことはできませんが、必要な保障を加えるという意味でのアレンジは可能です。 具体的には、女性保険で女性特有の病気に備えながら、病気で働けなくなるリスクにも備えるため就業不能保険にも加入するといったものです。
自分に将来必要となる保障は何なのかしっかり検討した上で、必要な保険に加入するようにしましょう。
【参考】女性保険の2つのメリットをプロが解説!

加入するメリットは
- 女性特有の病気への保障が割安
- 経済的な不安を無くして治療に専念できる
が主な点です。 妊娠や出産、女性特有の疾患について経済的補填ができる女性保険は結果的に女性にとっての大きな精神的な支えとなります。
治療時の不安やストレスは回復の大きな敵です。手厚い保障があることは治療への精神的負荷も軽減してくれますよ。
メリット①女性特有の病気への保障が割安
女性保険は女性特有の疾患になると通常の疾患に上乗せして給付金が払われることが一般的です。
通常の医療保険に女性保険と同等の保障を求めると、保障設定金額を上げなければなりません。その点女性保険なら保障額を倍にするよりも割安な保険料で備えることができます。
女性特有のがんや月経関連の病気は年齢があがるにつれてリスクも大きくなるため備えは大切です。また妊娠を希望している方は帝王切開や異常分娩の可能性もありますので活用をおすすめします。
メリット②経済的な不安を無くして治療に専念できる
保険全般にも言えますが、やはり経済的な不安を軽くしてくれる点は大きなメリットです。 3割自己負担で済むこと、公的制度として高額療養制度があることもあり大丈夫と思っている方もいるかもしれません。
しかし乳がんの例をあげると入院は1週間以上で治療費は自己負担が20万円以上を超えます。また入院が長引いた場合や通院や必要な場合はさらに必要です。
切らずにがんを治す陽子線治療は276万円ほどの費用がかかりますが、公的医療の対象外のため全額自己負担となってしまいます。
保険に加入することで最先端の技術や長引く入院にも経済的な保障がしっかりできるため治療に専念することが可能なのです。
女性保険の2つのデメリット「妊娠中だと入れない保険が多い」
女性保険のデメリットは
- 妊娠中だと入れない保険が多い
- 貯蓄性のある商品がない
の点があげられます。 欠点は利点よりも重要と言っても過言ではありません。 欠点を見逃して納得のできない保険に加入してしまった、ということがおきないようにきちんと理解しておきましょう。
デメリット①妊娠中だと入れない保険が多い
妊娠中だと入れない保険が多いのは知っておきたいポイントです。 相互扶助で成り立っているのが保険です。加入者からお金を集め、万が一が起こった人へ支払われるという仕組みです。
女性保険の多くは出産に関しての異常分娩に関して保障をつけています。 妊娠をしている女性はしていない女性に対して支払いのリスクが高くなっているので加入制限がないと不公平になってしまうのです。
妊娠中でも加入できるものはありますが、保障内容が制限されるケースがあります。詳しくは女性保険は妊娠中でも加入できる?妊娠中の保険加入は条件付きに?の記事に記載されていますのでご一読ください。
妊娠を望む方は早めに女性保険への加入を検討しましょう。
デメリット②貯蓄型の商品がない
女性保険には貯蓄性のある商品がありません。 基本的に保険料は掛け捨てです。
貯蓄性の代わりになるものとして強いてあげるならばお祝い金がある程度にとどまります。定期的にお金が入るのは嬉しいことですが、保険料はその分上乗せされているためやはり貯蓄という言葉には合わないでしょう。
どうしても「掛け捨てはもったいない!」と感じる方は女性保険よりも貯蓄性のある終身医療保険を検討することをおすすめします。
まとめ:自分に今必要な保障に迷ったらまずは保険のプロに相談を!
今回は女性保険について
- 口コミランキング
- 女性保険の基礎知識
- 検討の際に注目してほしいポイント
- メリット・デメリット
を中心に解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
ランキングを参考にしても今自分に必要な保障が何か迷ってしまうことがあればプロに相談してみることも1つの手です。
相談窓口でおすすめは「マネーキャリア」です。
全国対応で何度でも相談は無料、スマホ一つで簡単に相談できます。
契約件数は10,000件以上にのぼり、顧客満足度は驚きの93%を誇っている信頼できる保険サービスのため、あなたにぴったりの保険を提案してくれるでしょう。
ほけんROOMでは、保険に関する記事が数多くありますので興味のある方は合わせてご覧ください。