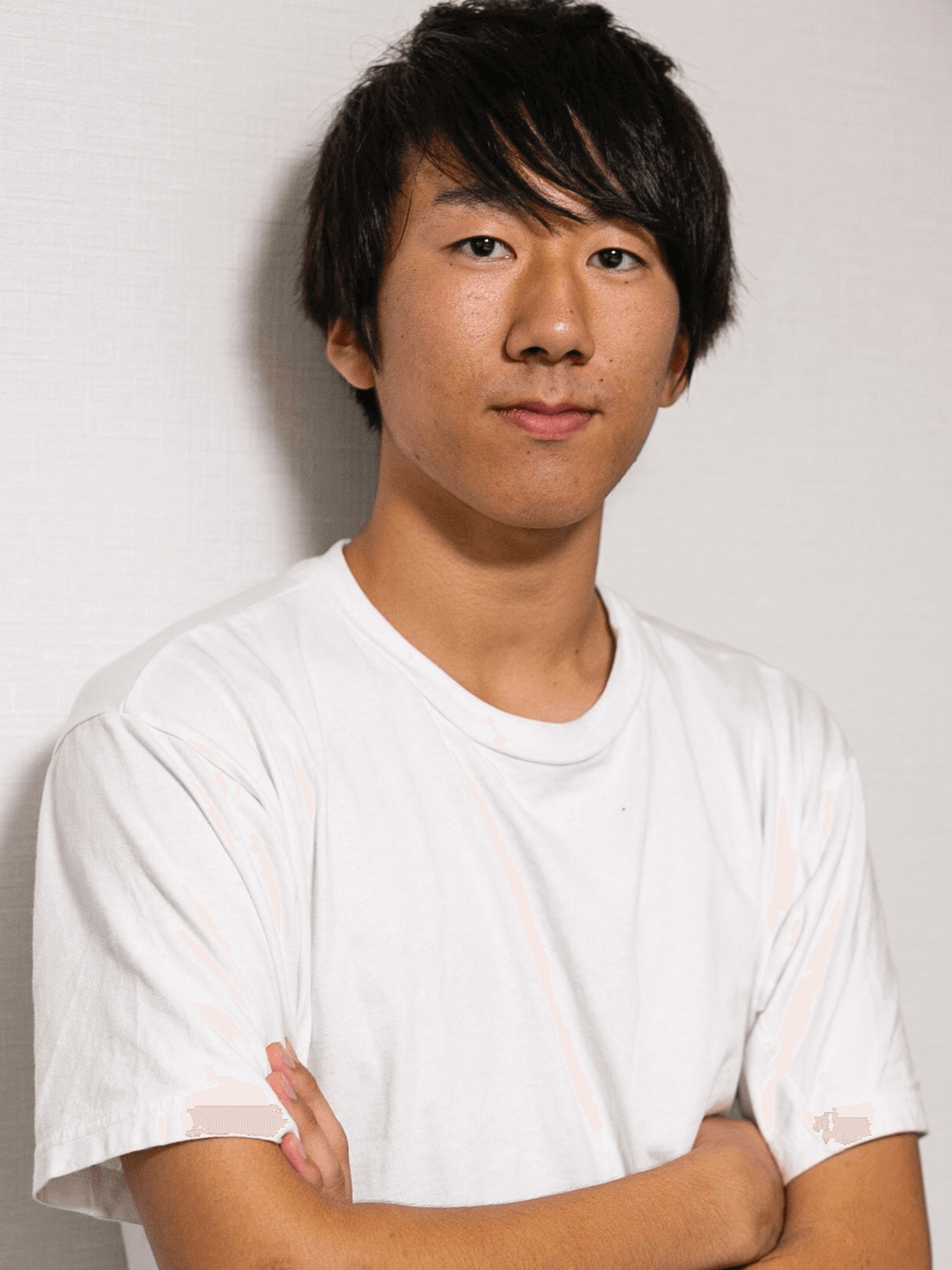更新日:2022/07/14
地震保険の保険金は火災保険の半額?保険金の上乗せ特約や割引も解説
地震保険では、最大でも火災保険の保険金額の半額しか補償されません。地震保険の特殊な仕組みや目的が関わっているためです。この記事では、火災保険の半額に制限されている理由や地震保険をカバーする上乗せ特約、地震保険料が最大半額になる割引制度について解説します。

目次を使って気になるところから読みましょう!
地震保険で設定できる保険金額は、最大でも火災保険金額の50%
地震保険の保険金額は、火災保険金額の30%〜50%、最大でも半額で設定が可能です。
例えば、建物の火災保険金を5,000万円で設定しているなら、建物の地震保険は最大2,500万円。
家財の火災保険2,000万円で設定しているなら、家財の地震保険は最大1,000万円となります。
さらに、上限は建物は5,000万円、家財は1,000万円と定められています(地震保険に関する法律)。
これは法律で定められているので、どの保険会社を選んでも保険料や報償内容に変わりはありません。
では、なぜ地震保険の保険金額は火災保険の最大半分なのか、なぜ補償内容がどの保険会社を選んでも画一的なのでしょうか。
地震保険の保険金額が火災保険の半額なのはなぜ?
地震保険の保険金額が火災保険の半額なのは、損害保険会社の担保力、国の財政にも限度があるからです。
そもそも地震保険は、民間保険会社を国がバックアップ(再保険)することで成り立っており、国と損害保険会社が共同で運営しています。
つまり、民間保険会社のみでは対応しきれないほどの巨大地震が発生した場合は、国が保険金を支払っているのです。
地震は予測ができないだけでなく、一度起こると被害が広範囲に及び、損害額が巨大になる可能性があります。
そのため、火災保険の金額の50%までに制限しているのです。
地震保険は、補償が半額ということと、保険料に割高感があるせいか、加入率が低めです。
損害保険料率算出機構の損害保険料率算出機構統計集2020年度版地震保険統計によると、地震保険の世帯加入率は33.9%です
火災保険の加入率が約82%ですから、比較するとその低さがわかります。
地震保険は被災後の当面の生活を支える保険
家財の地震保険も加入するとより安心
建物の地震保険のみならず、家財の地震保険にも加入するとより安心感が得られます。
地震保険金額は火災保険金額の最大50%。
万が一被災してしまった場合、建物の地震保険だけでは足りず、生活再建が難しくなる可能性があります。
たとえば、㆞震により建物と家財が全損してしまった際の、建物のみに加入の場合と、建物・家財に加入の場合それぞれの受取額例は以下の通りです。
| 建物のみに加入の場合 | 建物・家財に加入の場合 | |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 建物の地震保険金 | 1,000万円 |
| 300万円 | 支援金 | 300万円 |
| 100万円 | 義援金およそ | 100万円 |
| ー | 家財の地震保険金 | 500万円 |
| 1,400万円 | 合計の受取額およそ | 1,900万円 |
※建物の火災保険2,000万円(地震保険1,000万円)、家財の火災保険1,000万円(地震保険500万円)に加入していた場合
※東日本大震災での地震保険金や支援金、義援金等の受け取り例(宮城県で家屋全損・人的被害なしの場合)
このように、建物の地震保険のみならず家財の地震保険も合わせて加入することで、受取金額を増やすことができ、被災してしまったときの経済的な安心を得ることができます。
地震への補償をさらに手厚く!上乗せ補償ができる2つの特約

火災保険には、地震に関連した補償を厚くし、地震被害をカバーできる特約が2つあります。
「地震火災費用特約」と「地震危険等上乗せ補償特約」です。
自然災害での被害は、予想できないほど甚大で、広範囲に及ぶことがあります。
設定した火災保険金額によっては、地震災害時、地震保険のみでは生活再建が苦しくなる可能性もあります。
どれだけ備えればいいかは各家庭によって異なりますが、補償内容を少しでも充実させたいなら、効果的な特約となるでしょう。
そこで次は、それぞれの特約の内容について解説します。
特約①:地震火災費用特約
特約②:地震危険等上乗せ補償特約
地震保険料が最大半額になる4つの割引
地震保険へ加入しやすいように、4つの割引制度が設けられており、建物の免震・耐震性能、建築年月に応じて保険料が10〜50%の割引が適用されます。
なお、重複して割引を適用することはできませんので注意しましょう。
割引制度を利用する場合は、必要書類を保険会社へ提出します。
免震建築物割引
建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律で規定する免震建築物である場合 、保険料の50%割引となります。
必要書類は主に次の通りです。
- 建設(設計)住宅性能評価の写し
- 技術的審査適合証書の写し
- 認定通知書の写し
- 設計内容説明書の写し
など
耐震等級割引
対象物件が、地方公共団体等による耐震診断・耐震改修の結果、建築基準法における耐震基準を満たす場合に適用される割引制度です。
耐震等級3は50%、耐震等級2は30%、耐震等級1は10%割引となります。
必要書類は主に次の通りです。
- 建設(設計)住宅性能評価書の写し
- 耐震性能評価書の写し
- 技術的審査適合証または認定通知書の写し
- 設計内容説明書の写し
など
耐震診断割引
地方自治体等の耐震診断や耐震改修で、耐震基準を満たす場合、保険料が10%割引となります。
必要書類は主に次の通りです。
- 地方公共団体建築士等が証明した書類の写し
- 耐震基準適合証明書または住宅耐震改修証明書等の写し
など
建築年割引
1981年6月1日以降に新築された建物を条件として、保険料が10%割引となります。
必要書類は主に次の通りです。
- 建物登記簿謄本
- 建物登記済権利証
- 建築確認書等
など
参考:地震保険が必要な人と不要な人
「火災保険の半額以下しか補償されない」という理由で、地震保険の加入へ抵抗を感じる人も多いことでしょう。
しかしながら、地震保険の本来の目的は「地震等による被災者の生活の安定に寄与すること」であり、地震保険の保険金の使用用途は限定されていません。
では、地震保険の本来目的、地震保険の必要な人、不要な人はどのような基準で検討するべきでしょうか?
必要な人の基準
地震保険の加入が必要な方々は、次に該当するケースがあげられます。
- 地震で被災した場合、ご自身の世帯だけで生活再建できる貯蓄が無い場合
- 住宅ローンのような借金を返済中である場合
- 子供が独立していない場合
貯蓄に不安があり、借金を返済中の方々は地震保険へ加入することが大切です。
特に住宅ローンを組んでいる場合は、返済が長期にわたることがあります。
たとえ住宅が被災して壊れても、ローンが無くなるわけではなく、原則として完済する義務は残ってしまいます。
また、子供が独立していない場合には、今後の教育資金も当然必要になるでしょう。
地震保険へ加入していれば、下りた保険金で必要な支出を補填することが可能です。
火災保険金の半額以下であっても、頼りになる補償となります。
不要な人の基準
一方、地震保険の加入が不要な方々は、次に該当するケースがあげられます。
- ご自身の世帯だけで生活再建できるほどの貯蓄がある場合
- 借金等がない場合
- 単身またはご夫婦だけの世帯の場合
保険への加入・見直しの際は一括見積もりがオススメ!
火災保険や地震保険は、一度加入するとなかなか見直す機会がなかったり、保険料の高さから加入を躊躇してしまったりしがちです。
「うちの保険はこれで大丈夫かな」と心配なときは、他の保険と比較検討してみてはいかがでしょうか。
火災保険には、さまざまな保険会社について、一括見積できるサービスがあります。
補償額はどこの保険会社でも同じですが、補償範囲や特約、サービス内容は保険会社によって異なります。
また、地震保険はもちろん、火災保険の見直しなども、自分で一社ずつ調べるよりもスピーディで、まとめて比較するほうがわかりやすいですよね。ぜひ利用してみてください。
まとめ:地震保険では火災保険金額の半額しか補償されない

地震保険の仕組みと補償の半額になる理由について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは
- 地震保険では最大でも火災保険金額の半額までしか補償されない
- 地震保険は国と保険会社によって運営され、特殊な仕組みとなっている
- 地震保険金は保険加入者へ適正に配分する必要があるため、半額以下に補償が縮減されるのはやむを得ない
- 地震保険は、被災者の生活を最優先にサポートすることが目的
- 保険金を上乗せする特約がある
- 地震保険料の割引制度を利用すれば、保険料の最大半額が割り引かれる