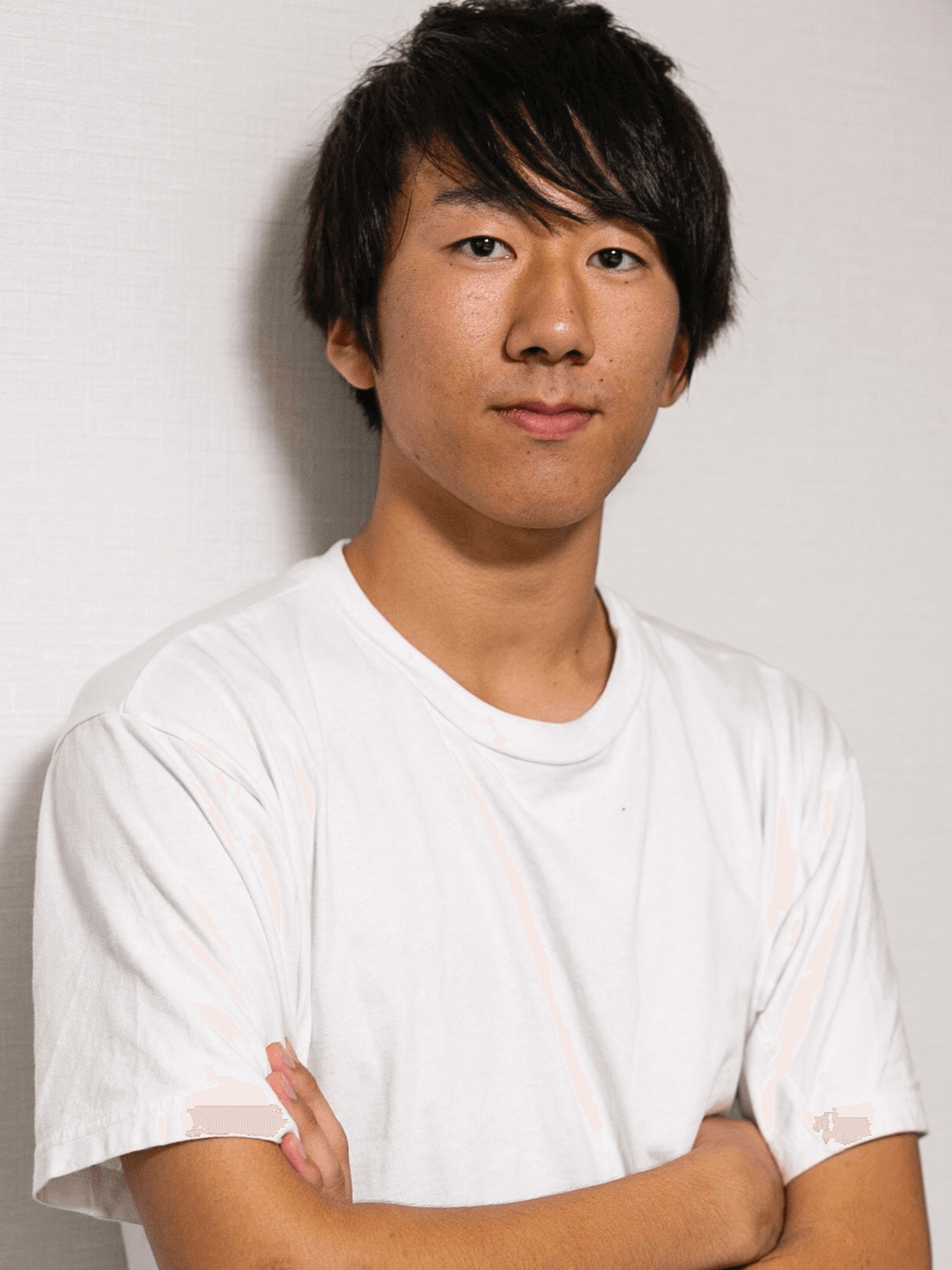更新日:2022/07/12
地震保険で被害の全額補償できない?全額補償する秘策を解説!
みなさんは地震保険で地震被害を全額補償できないことをご存知でしたか?もし地震で家が倒壊した場合、地震保険のみでは元通りに再建することは不可能です。今回は、地震保険で被害を全額補償する方法と地震保険の仕組みについて解説します。

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 地震保険で地震被害を全額補償できる?
- 地震保険のみでは全額補償することはできない
- 地震保険では火災保険の50%が限度
- 補足:地震保険の総支払限度額
- 地震保険金が全額出る場合
- 地震保険で全額補償する3つの方法
- 方法①被災者生活再建支援制度の利用
- 方法②保険会社の地震保険の補償を上乗せする
- 方法③少額短期保険の利用
- 知っておくべき地震保険の仕組み
- 地震保険の補償対象
- 地震保険の補償内容
- 保険料が決まる際の基準
- 地震保険が全額控除される場合
- 地震保険を検討する際のポイントを解説!
- ポイント①地震保険のメリットとデメリットを把握しよう
- ポイント②補償金額と保険料のバランスを考えよう
- ポイント③地震保険の長期契約や割引制度を利用しよう
- ポイント④特約は控除対象外もあるので注意しよう
- 特約を付帯したいけど保険料はどれくらい上がるのか知りたい方は
- まとめ:地震に備えて全額補償を検討しよう
目次
地震保険で地震被害を全額補償できる?

地震保険では地震災害による損害を全額補償されないことを知っていますか。
地震保険は本来、家の再建を目的としたものではなく、被災後の生活の安定を目的としています。
しかし、被災して保険で家が再建できないのでは、保険としての意味が感じられませんよね。
実は、地震保険の保険金を上乗せする方法や地震災害の保険で家を再建する方法もあります。
そこで今回は地震保険の保険金について
- 地震保険のみでは全額補償できない理由
- 地震保険金が全額出る場合
- 地震保険で全額補償する方法
- 地震保険を検討する際のポイント
以上のことを解説します。
この記事を読んで地震保険を正しく理解し、被災後の家の再建や復興へ向けての生活の安定のために、後悔のない備えをしましょう。
是非最後までお読み下さい。
地震保険のみでは全額補償することはできない
地震がひとたび起きればその災害は非常に大規模になり、自助努力だけでは立ち直れないことは、災害の度に政府や自治体が支援に乗り出していることを見ればわかります。
地震災害のこのような特徴から、被災後の社会秩序の維持と生活の安定に向けた社会保障的な制度の必要があるということで、政府がバックアップする形の地震保険が作られました。
地震災害の保険金は巨額にのぼり支払いを確実にするためにも、地震保険は掛けられる保険金額に上限を設け、家の再建よりは被災後の生活の安定を目的とする制度にしています。
それゆえに、地震保険のみでは損害額の全額を補償することはできません。
地震保険では火災保険の50%が限度
上記のような社会的意味を持つ地震保険の主旨から、政府としてはできる限り多くの人に地震保険に加入してもらいたわけです。
そのために地震保険は単独で販売する形を採らずに、広く周知されている火災保険とセットで販売する方式を採用しています。
つまり、地震保険は単独では加入できず、火災保険とセットで加入するか、すでに火災保険に入っている人はそれに追加して地震保険に加入することになります。
火災保険と地震保険では保険金が異なり、火災保険は建物の再取得価格か時価を限度として決められます。
しかし、地震保険の保険金は火災保険の保険金の30%~50%の範囲でしか設定できず、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限となります。
たとえば、3,000万円の家の場合、火災により全焼したときは3,000万円の保険金が支払われますが、地震により全壊もしくは全焼したときは最大1,500万円しか支払われません。
では残りの1,500万円はどうすればよいのでしょうか。ここが地震保険に加入する、もしくは加入を検討する人にとって悩みのタネになります。
補足:地震保険の総支払限度額
前述したように一度地震が起きたときの損害は甚大なものとなり、民間保険会社だけでは補いきれないのみならず、政府にも無尽蔵に資金があるわけではありません。
1つの地震で総損害額が884億円までは全額民間保険会社が負担しますが、884億円を超え1,390億円までの部分は、保険会社と政府が折半の負担をします。
さらに、1,390億円を超えた11.3兆円までの部分は保険会社は0.2%しか負担せず、残りの99.8%は政府が負担するようになっています。
11.3兆円が1つの地震で国と保険会社が支払うことができる限度額になります。
いままでで保険会社と政府の合わせた総支払額がもっとも多かった災害は、平成23年東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で1兆2795億17百万円でした。
では、総損害額が総支払限度額である11.3兆円を超えた更なる大規模地震の場合はどうなるのでしょうか、不安になりますよね。
総支払限度額を超えたときは、超えた割合に応じて個々に支払われる保険金額が減額される仕組みになっています。
地震保険金が全額出る場合
地震保険の損害認定基準は、支払いを迅速にするために4段階に簡略化されています。地震保険の損害認定基準を建物と家財に分けて下表にして示します。
建物の損害認定基準
| 損害の程度 | 損害の基準 |
|---|---|
| 全損 | 主要構造部の損害額が時価の50%以上 または 焼失、流出した床面積が70%以上 |
| 大半損 | 主要構造部の損害額が時価の40%以上50%未満 または 焼失、流出した床面積が50%以上70%未満 |
| 小半損 | 主要構造部の損害額が20%以上40%未満 または 焼失、流出した床面積が20%以上50%未満 |
| 一部損 | 主要構造部の損害額が3%以上20%未満 または 床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受けたとき |
被害を被ってはいるが、主要構造部の損害額が3%未満のときには保険金が支払われないという点が火災保険との違いです。
家財の損害認定基準
| 損害の程度 | 損害の基準 |
|---|---|
| 全損 | 損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上 |
| 大半損 | 損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満 |
| 小半損 | 損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満 |
| 一部損 | 損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満 |
家財の損害額が10%未満の場合は、保険金が支払われないという点が火災保険との違いです。
保険金の支払い額はそれぞれの損害認定の段階に応じて決められており、建物、家財の損害に対する支払額はこのようになっています。
建物、家財の損害に対する支払額
| 支払い額 | |
|---|---|
| 全損 | 地震保険の保険金の100% |
| 大半損 | 地震保険の保険金の60% |
| 小半損 | 地震保険の保険金の30% |
| 一部損 | 地震保険の保険金の5% |
繰り返し注意したいことは、たとえば主要構造部が50%以上の損害を受けたとき、保険金は全額が支払われますが、それは火災保険のそれの最大50%だということです。
火災保険の場合多くは、全焼したときに支払われる保険金で家が再建できるように設定されているでしょう。
地震保険の場合は、保険金が全額支払われても家の再建費用の半分にしかならないことをしっかり認識しておくことが重要です。
地震保険で全額補償する3つの方法
では他に、地震災害による保険金等で家を再建する方法はないのでしょうか。
地震保険はたとえ保険会社を違えても重複して加入することはできません。
また、地震保険の保険金を上げる意味で、火災保険の保険金を再建費用の2倍に設定することもできません。
ここでは地震保険の保険金に上乗せして保険金等を受け取ることができる方法を3つ解説します。
ただ地震保険に加入するときには、被災後の生活を安定させるためか家を再建するためかなどの目的を明確にして、補償と保険料のバランスをとることが大切です。

方法①被災者生活再建支援制度の利用
被災者生活再建支援制度とは、一定規模以上の災害が発生した市町村内または都道府県内において利用できる制度です。
そこで住宅が全壊または半壊し、住宅を建設・購入または賃借した場合、最大300万円から50万円までが支給されます。
支給されるにはさまざまな制限がありますので、各自治体にお問い合わせください。
地震保険の加入時に保険金を設定するときには、被災者生活再建支援制度から支援される支給金も考えに入れておくと良いでしょう。
方法②保険会社の地震保険の補償を上乗せする
前述したように、地震保険ではたとえ家が全壊した場合でも、再建に必要な費用の半分しか補償されないという問題があります。
そこで保険会社によっては、火災保険等の特約として地震保険ではたりない残りの50%の保険金を上乗せするものを販売しています。
このような地震保険の上乗せ補償には、「地震危険等上乗せ補償特約」と「地震火災費用特約」があります。
地震危険等上乗せ補償特約
地震危険等上乗せ補償特約では、被災時に地震保険金と同額の保険金を受け取れます。
被災時には地震保険で火災保険の最大50%が補償され、残り50%が特約で補償されるので、合計で100%、つまり全額補償ができるようになります。
地震火災費用特約
地震火災費用特約では、地震が原因で起こった火災による損害を地震保険と合わせることで全額補償が可能になります。
地震火災費用特約は、地震により発生した火災が原因で起こった損害を補償するものになるので注意しましょう。
しかし、特約を付帯することで補償は手厚くなりますが、
- 地震危険等上乗せ補償特約:地震保険料の約1.3~2.1倍
- 地震火災費用特約:地震保険料の約0.7~0.9倍
方法③少額短期保険の利用
保険料を抑えたいけど、地震への備えとして補償を手厚くしたい方には、「少額短期保険」の利用がおすすめです。。
小回りの利く保険である少額短期保険の一種に地震補償保険があり、これは地震保険を規定している「地震保険に関する法律」の規制を受けません。
したがって、地震補償保険は火災保険とセットで加入する必要がなく、単独でも地震保険の上乗せとしても加入できる保険です。
しかし、名前が示すとおり少額で短期の保険であって、少額とは損保の場合1,000万円(会社によって異なる)まで、短期とは原則1年です。
とはいえ、1,000万円は家の再建費用としては大きいですし、短期であっても更新すれば補償期間は続きます。
ただし、保険料控除が受けられなかったり、保険会社が破綻したときのセーフティネットがなかったりする短所はあります。
知っておくべき地震保険の仕組み
ここまで地震保険の補償金額にするための方法について説明してきました。
地震保険の補償を全額保証にする必要があるのかを検討するにあたって、地震保険の仕組みについて理解しておくことが大切です。
万が一、被災してしまった時に補償されると思っていたのに補償されず、予想よりもはるかに低い保険金しか支払われなかったという事態になるかもしれません。
一方で、貯蓄が十分にあるにも関わらず、特約を付帯することで保険料が上がり、家計を圧迫する可能性もあります。
ぜひ地震保険の仕組みについて理解して、必要な補償について考えてみましょう。
地震保険の補償対象
地震保険の補償対象は、「建物」と「家財」になります。
建物とは居住部分がある建物のこと、家財とは居住用建物に収納されている家財道具のことを指します。
契約する際は、火災保険と同様に
- 建物のみ
- 家財のみ
- 建物+家財
- 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手など
- 自動車
- 1個(または1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物などの美術品
- 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿など
地震保険の補償内容
地震保険では、地震、噴火、津波により
- 住宅や家財が焼けたとき
- 住宅や家財が壊れたとき
- 住宅や家財が流されたとき
- 建物に損害がないが、門、塀、垣が壊れたとき
- 損害の程度が一部損に満たないと判断されたとき
- 故意や重大な過失、法令違反とされる行為によって損害が生じたとき
- 地震の発生から10日以上経った後に損害が発生したとき
- 戦争、内乱などによって損害を受けたとき
- 地震などが発生した際に紛失・盗難にあい、損害を受けたとき
保険料が決まる際の基準
- イ構造:鉄骨やコンクリート造の建物など
- ロ構造:木造など
地震保険の保険料(円)=保険金額(円)×基本料率÷1,000
| 鉄骨造・コンクリート造 (イ構造) | 木造 (ロ構造) | |
|---|---|---|
| 北海道 | 0.73 | 1.12 |
| 大阪 | 1.16 | 1.95 |
| 福岡 | 0.73 | 1.12 |
| 東京 | 2.75 | 4.11 |
| 神奈川 | 2.75 | 4.11 |
| 埼玉 | 2.65 | 4.11 |
| イ構造 | ロ構造 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 7,300円 | 11,200円 |
| 大阪 | 11,600円 | 19,500円 |
| 福岡 | 7,300円 | 11,200円 |
| 東京 | 27,500円 | 41,100円 |
| 神奈川 | 27,500円 | 41,100円 |
| 埼玉 | 26,500円 | 41,100円 |
地震保険が全額控除される場合
地震保険は政府が普及を進めていますから、その手段として確定申告で地震保険料控除が受けられます。
年間保険料が50,000円未満のとき、所得税においては全額が、住民税においては半額が所得から控除されます。
年間保険料が50,000円を超えたときは、所得税においては50,000円が、住民税においては半額の25,000円が所得から控除されます。
地震保険を検討する際のポイントを解説!
日本は地震の発生確率が高く、いつどこで地震が起こっても不思議ではありません。
広範囲での被害が予測されている南海トラフ地震や首都圏を中心に甚大な被害が予想されている首都直下地震の30年以内の発生確率は70%以上といわれています。
そのため、地震保険で地震に備えておくことは重要です。
しかし、保険料が高いため加入を迷っている方もいらっしゃると思います。
ここでは、地震保険を検討する際のポイントについて解説します。ご自身の状況や貯蓄額などを考えながら読んでみてください。
ポイント①地震保険のメリットとデメリットを把握しよう
まずは、地震保険のメリットとデメリットを知っておきましょう。メリットとデメリットを知っておくことで、地震保険に加入する必要があるのか考えるときに役に立ちます。
地震保険にはこのようなメリットがあります。
- 地震などによる損害の補償が受けられる
- 被災した際にまとまったお金を速やかに確保できる
- 保険料の負担が大きい
- 基本的に火災保険に付帯した形でしか加入できない
- 地震保険だけでは再建築費用には不十分である
ポイント②補償金額と保険料のバランスを考えよう
特約を付帯することで地震保険の補償金額を全額にすると、その分保険料は上がってしまいます。
そのため、貯蓄や住宅ローンなどを考慮して補償金額を検討する必要があります。
今回の記事で説明してきた補償について整理してみます。
被災した際には下記のような補償が受けられます。
- 一定規模以上の災害が発生した場合:被災者生活再建支援制度で50万円~300万円
- 地震保険に加入している場合:地震保険の保険金額(火災保険の保険金額の30~50%)
- 地震保険に関する特約を付帯している場合:地震保険金と合わせて最大で全額補償(火災保険の保険金額の最大100%)
ポイント③地震保険の長期契約や割引制度を利用しよう
地震保険は国と民間保険会社が共同で運営しているため、どの保険会社で契約しても保険料は変わりませんが、長期契約や割引制度を利用することで、保険料を少しでも抑えることができます。
契約期間や住宅の耐震基準によって割引率は異なりますが、長期契約や割引制度により保険料を安く抑えられるので、地震保険に加入する際には利用しましょう。
長期契約
地震保険は最長5年契約ができます。契約期間が長くなるほど、保険料の支払総額は安く抑えられます。
2021年1月1日以降の地震保険の長期契約係数はこのようになっています。
| 長期契約係数 | 割引率 | |
|---|---|---|
| 2年 | 1.90 | 5.0% |
| 3年 | 2.85 | 5.0% |
| 4年 | 3.75 | 6.25% |
| 5年 | 4.65 | 7.0% |
| 割引制度の適用条件 | 保険料の割引率 | |
|---|---|---|
| 免震建築物割引 | 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の 「免震建築物」に当てはまる建物 | 50% |
| 耐震等級割引 | 一定の基準を満たし、耐震等級が認められた建物 | 耐震等級3:50% 耐震等級2:30% 耐震等級1:10% |
| 耐震診断割引 | 耐震の診断または改修により 建築基準法の耐震基準を満たした建物 | 10% |
| 建築年割引 | 1981年6月1日以降に建築された建物 | 10% |
ポイント④特約は控除対象外もあるので注意しよう
地震保険の保険料は所得控除の対象となっており、それぞれの控除額はこのようになっています。
| 年間の支払保険料 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 50,000円以下 | 全額 | 年間の支払保険料の半額 |
| 50,000円超 | 一律50,000円 | 一律25,000円 |
特約を付帯したいけど保険料はどれくらい上がるのか知りたい方は
ここまで地震保険について説明してきましたが、「実際に特約を付帯することでどれくらい保険料が上がるのか知りたい」、「実際の保険料をみてみないと判断できない」と思う方がいらっしゃると思います。
そのような方はぜひ一括見積を利用してみてください。
基本的に地震保険は火災保険とセットで加入するため、地震保険を見直す際には火災保険の見直しが必要になります。
火災保険は、建物の構造や所在地、補償内容によって保険料が異なるため、保険会社から見積もりを取り寄せる必要があります。
しかし、保険会社はたくさんあるので一つ一つ問い合わせるのは大変です。
以下のサイトの一括見積りを利用すると、無料で最大26商品を一度に見積もってくれるので、一つ一つ問い合わせる手間がかかりません。
また、「保険に詳しくないから補償内容を自分では選べない」と不安に思っている方でも、保険アドバイザーが何度でも無料で相談にのってくれるので安心です。
もちろん無理な勧誘はありませんので、気軽な気持ちで利用してみてください。
火災保険の一括見積を利用したい方は、こちらのボタンから利用できますのでよろしければ試してみてください。
まとめ:地震に備えて全額補償を検討しよう
地震保険を全額補償にする方法について解説してきました。今回の記事のポイントは
- 地震保険は被災後の生活の安定を目的とする制度のため、全額補償できない
- 全額補償にするためには、「地震危険等上乗せ補償特約」と「地震火災費用特約」を利用する
- 保険料を抑えたい方は「少額短期保険」を検討する
- 保険料と補償金額のバランスを考える