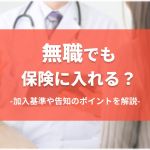更新日:2022/06/28
掛け捨て医療保険に入るべきか?男女別・年代別選び方のポイントを解説

「医療保険に入るべき?」「医療保険選びのポイントは?」このような悩みを抱える人は多いでしょう。そこで本記事では医療保険が必要な理由や年代別に医療保険選びのポイントを解説、医療保険に入るべきおすすめタイミングについても紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
- 医療保険に入るべきかどうか迷っている方
- 自分の年齢で医療保険に加入する必要があるのかわからない方
- 医療保険の不要論を聞いて入るべきか判断しきれない方
内容をまとめると
- 医療保険は入院中の医療費だけでなく入院後の生活もカバーできる
- 医療保険は公的保障で「カバーできない分」の金額を賄うのが定石
- 20代は最低限の保障で良いが高齢になるにつれて手厚い保障や見直しが必要
- 保険に入るべきかどうか迷っている方は「マネーキャリア」の利用がおすすめ!
- 「マネーキャリア」は顧客満足度93%なので、初めて保険相談をする方でも安心!

目次を使って気になるところから読みましょう!
- 医療保険に入るべき?医療保険が必要な5つの理由を解説
- 理由①:公的医療保障だけではまかなえない
- 理由②:逸失収入による家族の経済的困窮
- 理由③:療養中のさまざまな要因による心的負担
- 理由④:完治後の経済的困窮
- 理由⑤:健康なときにしか加入できない
- 医療保険が必要な人と不要な人の特徴を紹介
- 医療保険が必要な人の特徴5選
- 医療保険が不要な人の特徴5選
- 医療保険は公的保障とのバランスが重要
- 医療保険に入る前に絶対に知っておくべき3つの公的制度
- 民間の医療保険は公的医療保険でカバーできない部分を補う保険
- 医療保険に入るべき3つのタイミング
- ①就職するとき
- ②結婚するとき
- ③子どもが生まれるとき
- 【注意】30代〜40代の女性は女性特有がんに備えて入るべき!
- データから見る女性特有がんの危険性
- 女性だけに用意されたコスパ重視の「女性保険」!
- 【注意】男性は高齢になってからがんになりやすい
- 年代別に医療保険選びのポイントを解説
- 20代:病気リスクが少ないため必要最低限の保障で加入する
- 30代:教育費の貯蓄が必要なため手厚い医療保障が重要
- 40代:病気やケガのリスクが高まるため手厚い医療保障が必要
- 50代:加入している医療保険の見直しが必須!
- まとめ:医療保険に入るべきか迷ったらプロに相談するのがおすすめ
目次
医療保険に入るべき?医療保険が必要な5つの理由を解説

医療保険に入るべきかどうか迷っている方は多いですが、そもそも医療保険に加入することで得られるメリットについて、十分に理解できていないという方も多いでしょう。
医療保険は必要・不要の明確な答えがないからこそ、迷われている方が多いのです。ここからはなぜ医療保険が必要かを事実とデータに基づいて解説していきます。
家族が増えたことをきっかけに医療保険に加入すべきか検討している人、医療保険の見直しの時期で医療保険の必要性について考えている人、医療保険はなんとなく必要ないと思っている人に役立つ内容となっています。
医療保険が必要な理由として、下記5つが挙げられます。
- 公的な医療保障だけで不十分なケースもある
- 入院により休職すると「逸失収入」が発生する
- 療養中に金銭的な悩みがあると心的負担になる
- 完治・退院後の生活が保障されていない
- 健康なときにしか加入が難しい
理由①:公的医療保障だけではまかなえない
1つ目の理由は公的な医療保障の不十分さです。
日本では、すべての国民が公的医療保険に入ることが義務付けられており(国民皆保険)、医療保障制度は充実したものと耳にすることが多いでしょう。
事実、健康保険加入者であれば誰でも医療費が3割負担になったり、高額療養費制度によって月々の医療費が一定額を超えた分を負担してくれます。
一方で、直近で入院した人の自己負担額は下記のようになっています。
(出典:令和元年度 生活保障に関する調査 - 公益財団法人生活保険文化センター)
自己負担額が20万円未満である人が63.9%と過半数を占めており、入院1回あたりの自己負担額は「10~20万円」という回答がもっとも多いという結果となっています。
この結果から見て、どのような人には医療保険が必要でどのような人には不要でしょうか。
理由②:逸失収入による家族の経済的困窮
2つ目に挙げられる理由は病気やケガ等による入院で発生する「逸失収入」です。逸失収入とは入院などによって休職することによって、本来得られるはずだった失われた収入のことであり、保険選びの際に見逃してしまうことの多い要素の一つです。
私たちの家計は収入と支出で成り立っており、医療保険に加入することで万が一の時には給付金が受け取れて支出を減らすことができるという点に目がいきがちですが、得られる収入が減少しないかという点にも注意を払う必要があります。
過去5年間で入院歴のある方のうち「21.6%」の人が「逸失収入が発生した」と回答しています
入院で生じる逸失収入の平均については、以下の表をご覧ください。
| 逸失収入額 | 割合 |
|---|---|
| 5万円未満 | 16.8% |
| 5~10万円未満 | 16.8% |
| 10~20万円未満 | 29.4% |
| 20~30万円未満 | 9.2% |
| 30~50万円未満 | 14.3% |
| 50~100万円未満 | 5.0% |
| 100万円以上 | 8.4% |
(出典:令和元年度 生活保障に関する調査 - 公益財団法人生活保険文化センター)
統計によると「10~20万円」がもっとも多くなっており、「32万円」が逸失収入の平均となっています。
たとえば、病気やケガで入院したことで20万円もあったはずの収入が突然ゼロになると、自分だけではなく家族の生活にも大きな影響を及ぼします。蓄えがないと、光熱費や食費、子供の教育費でさえも払えないような事態に陥りかねません。
では、医療保険が必要な人、不要な人はどんな人でしょうか。
医療保険が必要な人
逸失収入が発生した場合に、生活が困窮してしまうという人には医療保険が必ず必要でしょう。具体的には毎月の収入が途絶えた時点で生活が立ち行かなくなるのであれば、医療保険で備えておく必要があります。
医療保険が不要な人
逸失収入が発生した場合でも、慌てる必要がない程度に、貯蓄がある人については医療保険は不要と言えるでしょう。また、病気やケガがなければ入ってきた30万円程度のお金が惜しいとは思わないのであれば、医療保険で備えておかなくても問題ないでしょう。
理由③:療養中のさまざまな要因による心的負担
入院中にはさまざまな要因により、心的ストレスがかかることが考えられます。
たとえば、入院中の生活を考えると
- 慣れない病院での寝泊まりや食事
- (大部屋の場合)他人とのスペースの共有
- 日々の検査や治療
- 入院による収入の減少
- 復職後の収入
- 家族の生活費
社会保険に加入している会社員であれば1年半にわたって「傷病手当金」を受け取ることができますが、個人事業主は対象外です。個人事業主の方は会社員と比較して手厚い備えが必要といえそうです。
もし医療保険に加入していて給付金を受け取ることができれば、金銭的な心的負担について軽減することができます。
入院中や退院後に無収入となるリスクに重点的に備えたい方は、逸失収入をカバーできる「所得補償保険」や「就業不能保険」に加入することも可能です。
入院中の生活にかかるストレスは軽減することは難しいですが、金銭的な面での心的負担は医療保険によってカバーすることができます。
また、医療保険での給付金を個室の費用にあてることができれば入院生活でのストレスも多少は減らすことができそうですね。
理由④:完治後の経済的困窮
入院によって仕事を失った場合に、退院後に経済的に困窮してしまうリスクに備えるためにも医療保険は有用です。
多くの人は病気やケガで入院しても退院後に復職しますが、例外もあります。治療がうまくいき、無事に退院ができた場合でも下記のようなことが考えられます。
- 会社都合で解雇される
- 復職後の収入が減少する
- 体調の問題で仕事の継続が難しい
会社都合で解雇される
職場によっては退院後も復職できるかどうかわからない、まれに退院後復職してすぐ退職を言い渡される、というケースもあります。
就業規則で正当な理由があれば解雇が認められている場合、入院の長期化によってまったく業務に復帰できなければ、解雇されるような事態に陥る可能性もあります。
もし解雇されるとしても、労働基準法に則り解雇の30日前以上に通達されなければなりませんが、入院していた場合は再就職しようとしてもすぐに新しい仕事を探すのが難しい場合が多いでしょう。
復職後の収入が減少する
入院前と同じ職場に復職したとしても、体調によっては以前より残業を減らさなければならなかったり、降給や降格したりすることもあるでしょう。その場合でも生活するのに十分な給与であれば、日々の生活に困ることはないでしょうが、入院前よりも倹約する必要が出てくるかもしれません。生活の水準を落とすことはなかなか難しいものです。
体調の問題で仕事の継続が難しい
また、復職が可能であったとしても、自分の体調によって入院前と同じ仕事を継続することが困難なことも考えられます。
会社は入院前と変わらない待遇で受け入れてくれることももちろんあると思いますが、自分自身が入院前と同じ働き方ができない可能性も考えておくべきでしょう。
精神的にも体力的にもストレスが多い仕事であればあるほど、病気から復帰したばかりの状態で同じ仕事をしていくことは難しいはずです。
上記のような場合に備えて「就業不能保険」も活用できます。
- 就業不能給付金
- 入院見舞金
- 復帰支援一時金
理由⑤:健康なときにしか加入できない
医療保険に加入する際には一般的に「告知」をする必要があります。告知とは、自身の健康状態について加入する保険会社へ申告することをいいます。
健康状態について何かしら告知事項がある場合には、
- 医療保険へ加入ができない
- 健康な人よりも悪い条件での加入となる
医療保険が必要な人と不要な人の特徴を紹介
医療保険が必要な理由についてさまざまなデータをもとに解説してきました。
以上を踏まえて、医療保険が必要な人と不要な人の特徴をそれぞれ紹介していきます。自分に医療保険が必要なのか迷っている人はぜひ読み進めてください。
医療保険が必要な人の特徴5選
医療保険が必要な人の特徴を5つ紹介していきます。
- 今手元に貯金がない人
- 逸失収入を惜しいと思う人
- 不安になることが多い人
- 保険適用外の先進医療を受けたい人
- 健康状態に自信がない人
今手元に貯金がない人
逸失収入を惜しいと思う人
入院しなければ得ていたはずの収入のことを逸失収入と呼ぶことは既に紹介しました。また、逸失収入の平均は32万円と説明しました。
生活できる程度の貯金はあるものの、入院をしたことによって発生した逸失収入(およそ30万円程度)を惜しいと思ってしまう人は貯金の有無にかかわらず、医療保険に加入しておくべきでしょう。
不安になることが多い人
保険適用外の先進医療を受けたい人
健康状態に自信がない人
医療保険が不要な人の特徴5選
では、医療保険が不要な人の特徴にはどんなものがあるでしょうか。5つご紹介します。
- 余裕資金が100万程度ある人
- 逸失収入があっても問題ないと思える人
- 精神的ストレスに強い人
- 先進医療を受けないと思っている人
- 自分の健康に自信がある人
余裕資金が100万程度ある人
精神的ストレスに強い人
先進医療を受けないと思っている人
自分の健康に自信がある人
先のことは分からないものですが、自分自身の健康に自信を持っている人にも医療保険は不要でしょう。
病気をしようと思ってする人はほぼいないといえそうですが、それでも医療保険は必要ない、健康でいる自信があるという人は必ずしも医療保険に加入する必要はありません。
医療保険は公的保障とのバランスが重要
医療保険というのは第一に公的医療保険制度が根底にあり、それだけでは保障がされない部分を補填する目的で、第二に民間の医療保険に加入するという順番で考える必要があります。
そのため民間の医療保険に加入するにあたって、公的医療保険制度で医療費をどれだけカバーできるのかを知っておくことは重要です。
公的医療保険制度でカバーできない部分を補うのが民間の医療保険の役割となります。
この章では
- 3つの公的医療保障制度
- 民間の医療保険の役割
について説明していきます。
医療保険に入る前に絶対に知っておくべき3つの公的制度
医療保険に加入する前に、必ず知っておくべき公的制度は、以下の3つです。
- 傷病手当金
- 高額療養費制度
- 国民健康保険
傷病手当金
支給開始日前(12カ月)の標準報酬月額平均 ÷ 30日 × 2/3
また、傷病手当金を受給するためには、以下の条件をクリアする必要があります。- 業務に関係のない病気やケガで入院している
- まったく就業ができない状態である
- 4日以上就業していない
- 休業期間の給与が支払われていない
- 社会保険加入者(自営
業者や個人事業主などは対象外)
167,400円+(医療費-558,000)×1%
民間の医療保険は公的医療保険でカバーできない部分を補う保険
ここまで挙げた3つの代表的な公的医療保険制度でカバーできない分が、入院や通院に伴って確実に自己負担となる分です。そのため、民間の医療保険でどれだけ自己負担分をカバーする必要があるかを保険料とのバランスを考慮して保障内容を決める必要があります。
公的医療保障制度をみてみると、年齢や収入によって公的医療保険でカバーできる医療費が異なることがわかります。生活スタイルや資産状況に応じて必要な保障額も変わってくるでしょう。
また、年齢や収入によって公的医療保険でカバーできる医療費が異なるということは、医療保険は一度加入して終わりではなく、ライフステージに合わせた見直しも必要ということです。
たとえば、入院給付金や手術給付金を高く設定すると、万が一のときも手厚い保障が受けられますが、毎月の保険料がかさみ家計が圧迫されて生活が苦しくなる可能性もあります。
逆に、保険料の安さだけにとらわれて本当に必要最低限の保障内容にしてしまうと、いざ病気になってしまった場合に受け取れる給付金が思っていたよりも少なく、医療費がカバーできないということも考えられます。
このように、医療保険を検討する際には年齢や収入、家族構成、資産状況など考慮すべき観点が多くあります。
無料の保険サービスを活用することで、納得できるまで何度もシミュレーションを重ねて、あなたにぴったりのプランを作成できます。
マネーキャリアではオンラインでも対面でも、ご要望に合わせた方法での面談が可能です。ぜひ一度、プロと一緒にあなたに合った保険をシミュレーションしてみましょう。
医療保険に入るべき3つのタイミング

人によって医療保険の必要性を実感したり、必要に迫られたりするタイミングは異なります。「身近な人が病気になった」「健康診断の結果の数値が気になる」「周りの友人はみんな入っていた」など、医療保険を検討するきっかけはさまざまです。
医療保険への加入や見直しをライフイベントのタイミングで考えてみることをおすすめします。
ここでは主に以下の3つのタイミングで保険の加入を検討するべき理由を解説していきます。
- 就職するとき
- 結婚するとき
- 子どもが生まれるとき
①就職するとき
高校・大学を卒業してはじめて就職するときは、以下の理由から医療保険に入るべきかどうかを考える絶好のタイミングだといえます。
- 貯蓄がほとんどないため緊急時に対応できない
- 無収入状態になるのは精神的・経済的に厳しい
- 環境が変わることで病気になることも考えられる
②結婚するとき
結婚するときも医療保険への加入を考える良いタイミングです。家計の見直しを考える夫婦も多いですが、あわせて保険も見直すチャンスです。
独身のときに医療保険に加入していなくても、加入する必要が出てきたり、独身のときに加入していたものでは不十分であったりと加入や見直しをすべきタイミングといえるでしょう。
共働き夫婦で収入が同程度の場合
収入源が分散されていることはメリットですが、どちらかが病気になった場合は、通常時の半分近くの収入が減少することになります。
どちらか片方の収入のみで生活ができるのか、独身であれば自分一人の生活ですが、2人の生活を考えたうえで検討する必要があるでしょう。
どちらか片方が働いている夫婦の場合
また、万が一扶養者が死亡してしまった場合は、とりわけ片方が主婦・主夫である場合は大きな精神的・経済的痛手となります。医療保険に加入することで、そのようなパートナーがいるからこそのリスクに対して対応できます。
女性特有の妊娠・出産への備え
また、女性であれば妊娠・出産に伴うリスクに備えられるというメリットもあります。
厚生労働省の令和2(2020)年医療施設調査・病院報告によると、一般病院におけるすべての分娩のうち、帝王切開娩出術の割合は27.4%、一般診療所における割合は14.7%となっており、年々増加傾向にあります。
医療保険の中には、乳がんがや子宮筋腫などの女性特有疾病、また出産に伴い帝王切開手術を行った場合に、手厚い保障を受けられるものがあります。
妊娠してからでも加入できる医療保険は増えていますが、条件付きとなったり、割高になったりすることもあるので、医療保険を検討する場合にはなるべく早く対応しましょう。
③子どもが生まれるとき
子どもが生まれて家族が増えたときも、医療保険に入るべきか考えるべきでしょう。
理由としては下記が挙げられます。
- 子どもの教育にはお金がかかる
- 万が一のときのリスクに備える必要がある
子どもの教育にかかるお金は一人当たりおよそ1,000万円
| 公立 | 私立 | |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 223,647円 | 527,916円 |
| 小学校 | 321,281円 | 1,598,691円 |
| 中学校 | 488,397円 | 1,406,433円 |
| 高等学校 | 457,380円 | 969,911円 |
| 国立 | 私立 | |
|---|---|---|
| 入学料 | 282,000円 | 245,951円 |
| 授業料 | 535,800円 | 930,943円 |
| 施設設備費 | - | 180,186円 |
万が一のときのリスクが高い
万が一両親に何かあった場合には、パートナーであるお互いの生活のみならず、子どもの生活にも大きな影響があります。夫婦だけの家庭よりも子どものいる家庭のほうがリスクに備えておく必要性は高いといえます。一方で、厚生労働省の「国民生活基礎調査の概況(2019年)」によると、29歳以下の1世帯あたりの平均貯蓄額は「179.8万円」となっており、この金額は30代の約3分の1です。
とりわけ年齢が若くして結婚・出産を経験している夫婦は、たとえ共働きであっても貯蓄が十分でないことが多く、突然どちらかが入院するような突発的なリスクに対応できません。
医療保険に加入しておくことで、子どもの大学入学時など教育費にもっともお金のかかる時期に万が一のことがあった場合でも、子どもの食費・教育費が払えなくなるなどの、金銭的な問題を抱えないで済みます。
また、病気での療養中に亡くなってしまった場合、残された家族に大きな経済的負担が生じる可能性があれば、医療保険だけではなく生命保険(死亡保険)への加入も検討した方が良いでしょう。
20代・30代は医療保険・生命保険のどちらもまだ保険料が安く済むため、少ないコストで大きなリスクに備えられます。
【注意】30代〜40代の女性は女性特有がんに備えて入るべき!
30代〜40代の女性が特に備えておきたい病気が、乳がんや子宮がんなどの女性特有のがんです。
以下では、その理由や女性保険で備える方法についてくわしく解説していきます。
データから見る女性特有がんの危険性
50代前半までは男性より女性の方ががんの罹患数が多いことはご存知でしょうか。
特に女性の患者数は、30代では男性の約4倍、40代では男性の約3倍となっており、大きく上回っていることがわかります。
(出典:平成30年 全国がん登録 罹患数・率 報告 - 厚生労働省)
女性のがん罹患数の順位(2019年)は、下記のようになっています。
- 乳房
- 大腸
- 肺
- 胃
- 子宮
(出典:最新がん統計 -がん情報サービス)
ここではとりわけ女性特有のがんである「乳がん」と「子宮頸がん」について解説していきます。
乳がん
女性がかかるがんのうち第1位が乳がんで、30代から40代後半にかけての患者数が多いことがわかります。総数は93,858人で、一例として2018年の年代別のデータが下記です。
| 年代 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 25~29歳 | 260 | 0.2% |
| 30~34歳 | 933 | 0.9% |
| 35~39歳 | 2,561 | 2.7% |
| 40~44歳 | 6,518 | 6.9% |
| 45歳~49歳 | 10,756 | 11.4% |
| 50~54歳 | 9,369 | 9.9% |
罹患率についても30代から40代後半にかけて急激に上昇する傾向があります。
60代後半が一番罹患率が高く、その後さらに高齢になっても比較的罹患率が高いのが特徴です。
(出典:
乳房:[国立がん研究センター がん統計] - がん情報サービス)
子宮頸がん
乳がんと比較すると、子宮頸がんはより若い年代の患者数が多いのが特徴です。
2018年の患者総数は10,978人で、年代別の患者数は下記のとおりです。
| 年代 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 25~29歳 | 157 | 1.4% |
| 30~34歳 | 617 | 5.6% |
| 35~39歳 | 1,001 | 9.1% |
| 40~44歳 | 1,246 | 11.3% |
| 45歳~49歳 | 1,397 | 12.7% |
| 50~54歳 | 1,099 | 10% |
(出典:
子宮頸部:[国立がん研究センター がん統計] - がん情報サービス)
罹患率についても、子宮頸がんは乳がんと比較して若い女性のほうが高い傾向にあります。
20代後半から30代後半にかけて急激に罹患率が増加し、40代後半で罹患率がピークとなります。
女性だけに用意されたコスパ重視の「女性保険」!
女性特有の病気への対策として、「女性保険」で備えるという方法があります。
女性保険とは、通常の医療保険として一般的な病気にも備えつつ、女性特有の病気に対しては通常の保障に上乗せした保障が得られる保険のことをいいます。
例えば、通常の病気での入院給付金が日額5,000円である場合、女性疾病での入院給付金の日額は5,000円上乗せされて日額1万円の保障となる、という商品があります。
女性保険に加入する際は、通常の医療保険の部分の保障は大きくしすぎず、女性特有の病気へ備える部分の保障を重視することをおすすめします。
例えば、子宮体がんにおいて、
- 手術を受けたが再発リスクが高い
- 手術ができないほど進行している
これらの場合は、通院での化学療法(抗がん剤治療)が半年程度続く可能性があります。
抗がん剤治療にかかる費用は病状によって様々です。
仮に高額療養費制度を利用して医療費が月に8万円程度で済んだとしても、それが半年続いたとすると、
約8万円 × 6ヶ月 = 約48万円
と計算できます。
交通費などの保険適用外の費用も考えると、半年で50万円程度の費用負担となる可能性もあります。
このように女性特有のがんで通院での治療が長期化する場合であっても、女性保険で備えておけば手厚い保障が受けられるので安心です。
【注意】男性は高齢になってからがんになりやすい
年齢が若いうちは、男性よりも女性の方ががん患者数が多いのですが、50代後半くらいから男性の患者数が女性を上回ってくる傾向にあります。
また一生のうちに、がんと診断される人数は女性と比べて男性の方が多いのが現状です。
2018年の全部位のがん患者数を見てみましょう。男性の総数は558,874人、女性の総数は421,964人です。
| 年代 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 25~29歳 | 1,038 | 1,744 |
| 30~34歳 | 1,772 | 3,733 |
| 35~39歳 | 2,867 | 7,159 |
| 40~44歳 | 5,487 | 14,260 |
| 45歳~49歳 | 9,631 | 22,413 |
| 50~54歳 | 15,005 | 24,017 |
| 55~59歳 | 26,466 | 26,258 |
| 60~64歳 | 45,994 | 32,098 |
| 65~69歳 | 89,439 | 50,577 |
(出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」 -全国がん登録)
このようなデータがあることも一因として、男性においては年齢が上がるとがんの保障にかかる保険料は高くなります。
若いうちに医療保険に加入しておいた方が、払い込む総額の保険料が安くなることもあるので早めに検討するのが良いでしょう。
年代別に医療保険選びのポイントを解説

医療保険を選ぶときには、加入者の年齢や家族構成、資産状況などさまざまな観点から総合的に検討していく必要があります。
ここでは年代別に医療保険選びのポイントを解説していきます。20代と50代では、病気になる確率も異なりますし、ライフステージも大きく異なる段階にいると考えられます。備えなければならないリスクの種類も大きさも変わってきます。
ではそれぞれの年代においてどのように医療保険を選べば良いのかについて、以下の年代毎に解説していきます。
- 20代:病気リスクが少ないため必要最低限の保障で加入する
- 30代:教育費の貯蓄が必要なため手厚い医療保障が重要
- 40代:病気やケガのリスクが高まるため手厚い医療保障が必要
- 50代:加入している医療保険の見直しが必須!
20代:病気リスクが少ないため必要最低限の保障で加入する
20代における医療保険選びのポイントを3つご紹介します。
- 病気にかかるリスクは比較的小さい
- 収入に見合った保険料に抑える
- 女性は妊娠・出産も考慮する
それぞれ以下で詳細を見ていきましょう。
病気にかかるリスクは比較的小さい
20代は、病気やケガで入院するリスクがもっとも少ない年代であるため、必要最低限の保障で、非常に安く医療保険に加入できます。
医療保険は病気になった場合の入院・手術に備えるためのものであるという前提にもとづけば、そもそも病気にかかるリスクが小さいので、保障もリスクに合わせたミニマルなもので済ませてよいでしょう。
収入に見合った保険料に抑える
一般的に20代のうちは収入もそこまで多くはないでしょうし、貯蓄もまだまだできている人が少ない場合が多いです。必要以上の保障のために保険料が高くなってしまい、日常生活が圧迫されてしまうようなことがないように、注意しましょう。
ただ、若いうちに終身型の保険に加入しておけば、一生涯保険料が上がることはなく、保障がずっと受けられるというメリットはあります。
女性は妊娠・出産も考慮する
女性で妊娠・出産に伴うリスクに備えたいという方は、「必要最低限」を重視するのではなく、リスクにピンポイントで備えられる女性専用の医療保険に加入する方が良いでしょう。
一般的に女性専用の医療保険は通常の医療保険に必要最低限の保障で加入した場合よりも保険料が高くなるため、保障内容と保険料のバランスを考える必要があります。
30代:教育費の貯蓄が必要なため手厚い医療保障が重要
30代における医療保険選びのポイントとして下記2つを解説します。
- 生活習慣病などのリスクが高まってくる
- 家族構成に変化が出てくる
生活習慣病などのリスクが高まってくる
30代は20代と比較して、健康リスクが高まってくる年代です。喫煙や飲酒、食事の欧米化などにより、生活習慣病のリスクは上昇傾向にあります。
健康診断の結果によっては医療保険の加入が難しくなったり条件付きでの加入となってしまう可能性も出てくるので、その前に一度医療保険の加入について検討しておくべきでしょう。
家族構成に変化が出てくる
結婚やそれに伴い子どもができて家族構成に変化が現れだすのも30代という年代の特徴といえるでしょう。働き盛りで20代と比べると収入も増えている一方で、家族をもつことによる支出の増加も考えられます。家族の生活を守るための保障は考えておく必要があります。
また、30代になると貯蓄型の保険に興味を持つ方がいますが基本的には不要です。将来のためにお金を貯めたいのであればまずは支出をしっかり削って貯金や資産形成をしていくべきです。
病気やケガの場合に出ていくお金に備える保険と、子どもの教育費などの貯蓄についてはそれぞれ分けて考えましょう。
あくまで保険は保障のためであり、貯蓄のために活用するには優れている手段ではありません。なぜなら、貯蓄型の保険は早期解約すれば返戻率は100%を下回ることが多く利率もそこまで高いわけではないため、流動性に欠けた貯蓄に過ぎないからです。
保険は万が一のときに自身の生活や家族の将来を困らせないためですので、全体の家計の負担にならない範囲で保障のことだけを考えて加入しましょう。
40代:病気やケガのリスクが高まるため手厚い医療保障が必要
40代の医療保険選びのポイントは、
- 健康面のリスクがさらに高まる
- 子どもの教育費の負担が大きい
- 保険の見直し
健康面のリスクがさらに高まる
収入、家庭環境ともに安定してくる40代から医療保険に加入する場合は、健康面のリスクが20代・30代と比較して高くなることに注目して、保険選びを行いましょう。
国立がんセンターの統計によると、2018年におけるがんの年齢別罹患者数は次のとおりです。
| 年齢 | 男性・罹患数 (全部位) | 女性・罹患数 (全部位) |
|---|---|---|
| 20〜24歳 | 672 | 871 |
| 25〜29歳 | 1,038 | 1,744 |
| 30〜34歳 | 1,772 | 3,733 |
| 35〜39歳 | 2,867 | 7,159 |
| 40〜44歳 | 5,487 | 14,260 |
| 45〜49歳 | 9,631 | 22,413 |
| 50〜54歳 | 15,005 | 24,017 |
| 55〜59歳 | 26,466 | 26,258 |
| 60〜64歳 | 45,994 | 32,098 |
このように、40代以降から罹患者数は高くなっていることがわかります。患者数だけだとわかりにくいですが、30〜34歳での罹患率(人口10万人対)が「79.4」であるのに対して、40〜44歳は「217.2」と急増しています。
高まる病気のリスクに備えて医療保険への加入を検討することは合理的だといえるでしょう。
子どもの教育費の負担が大きい
また、多くの家庭において親が40代になっていると、ちょうど子どもが高校・大学を迎える年齢です。教育費も大きく負担となってくる時期でしょう。突発的な病気や入院のリスクに備えておくことが必要です。
保険の見直し
20代の時に医療保険には入っているから安心だという人も、保険の見直しを検討する年齢だといえます。病気のリスクも高まっていますし、加入してから年数がたっていると医療の現状にも変化があるはずです。現状に合わせた保険に加入していないと、いざというときに保障が不十分であったり、最悪の場合は何の役にもたたなかったりします。
医療保険は一度加入して終わりではないため、定期的な見直しが必要であることを覚えておきましょう。
50代:加入している医療保険の見直しが必須!
50代での医療保険の選び方のポイントは40代とも似通っていますが、さらに老後を見据えて選ぶべきでしょう。
- 保険の見直しは必須
- 家族構成の変化
保険の見直しは必須
50代では保険加入の有無だけでなく、保険をどのように活用すれば老後に備えることができるか、という点を真剣に考える必要があります。
50代は医療保険に新規加入するには少し遅い年齢であり、病気やケガのリスクも高いため、新規加入する場合は生命保険全般の保険料が割高になっています。
50代から医療保険に加入したい方は、
- 必要最低限の保障で、可能な限り安く備える
- 保険料がある程度高くなっても、老後にまとまったお金を受け取れる保険にする
上記のうちどちらを重視するかを決めておきましょう。
また、持病を持っている方、または過去に特定の病歴がある方は保険への加入は、保険そのものに加入できない可能性も高くなります。
ただし、通常の医療保険に加入できない場合でも、審査に通りやすい「引受基準緩和型医療保険」や、告知の必要がない「無選択型保険」といった選択肢もあるため、保険加入自体を諦める必要はありません。
まとめ:医療保険に入るべきか迷ったらプロに相談するのがおすすめ
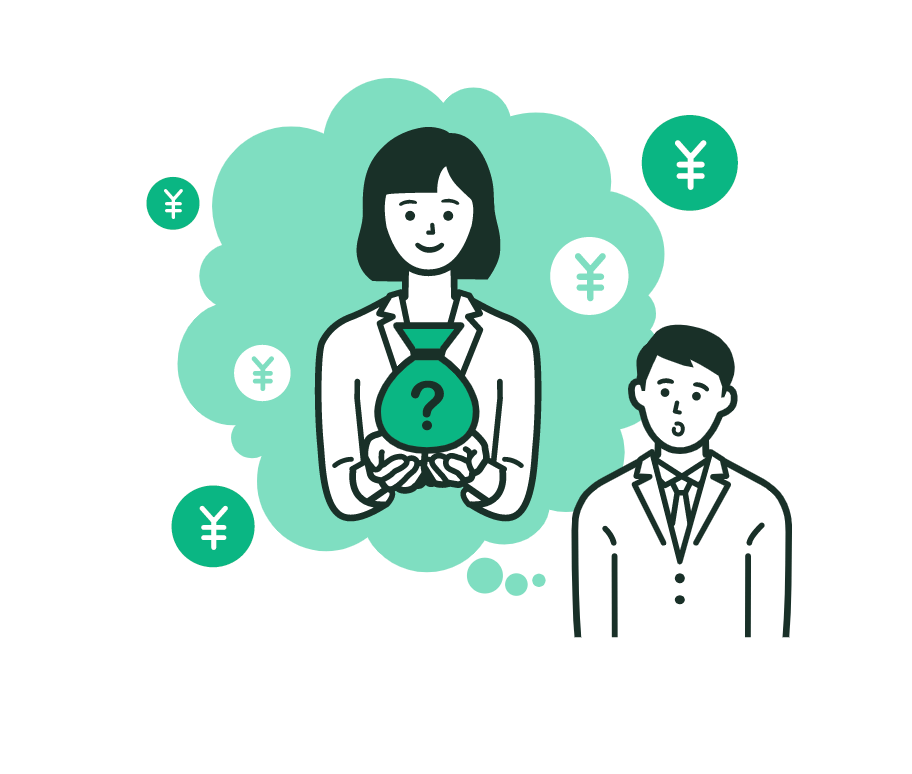
今回は医療保険に入るべき理由や医療保険選びのポイントを、さまざまな目線から解説してきました。
ご自身に医療保険が必要なのか、また年齢や家族構成に応じてどのような保障があればあんしんなのか、また不要になった保障がないのか、いろいろな角度から考える必要があります。
たしかに、突然の医療費に備えるという意味で医療保険に入るべきであるということも大事ですが、もっとも重要なのはそれぞれの経済状況やライフプランに合わせて、加入の有無や保障内容を決めることです。
マネーキャリアでは「医療保険がそもそも必要なのか分からない」「保険の見直しをしたいけれど、やり方が分からない」などの疑問にお答えします。顧客満足度93%と、多くのお客様にご評価いただいております。
オンラインでも対面でもご自分に合わせた面談のスタイルを選択できますので、初めての方でも安心してご相談いただけます。
ご相談は無料なので、ぜひ一度この機会に保険のプロの話を聞いてみませんか。ぜひお申し込みください。

医療保険の必要性が知りたい方はこちらの記事もご覧ください